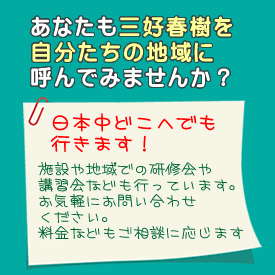●「投降のススメ」
経済優先、いじめ蔓延の日本社会よ / 君たちは包囲されている / 悪業非道を悔いて投降する者は /
経済よりいのち、弱者最優先の / 介護の現場に集合せよ
(三好春樹)
●「武漢日記」より
「一つの国が文明国家であるかどうかの基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である」
(方方)
● 介護夜汰話
- List
介護夜駄話 フーコーから介護世界が見えてきた
介護夜駄話 流れに逆らう根拠
介護夜駄話 大井シゲの「福の神」
介護夜駄話 江藤淳の自死について ~決して強さとは言いたくないね~
地下水脈 最終回 「介護の時代」のほんとうの意味
地下水脈 地下水脈 遊びリテーションは近代を越える〈下〉
地下水脈 久しぶりに映画を観た
地下水脈 遊びリテーションは近代を越える〈上〉
地下水脈 チューブ外しとアインシュタイン
地下水脈 国は滅びても商売は残る
地下水脈 羊飼いの使命感
地下水脈 意識の高みからではなく無意識の深みから
地下水脈 介護保険を逆手にとる
地下水脈 『歯は老化ではなくならない』 ~ひと月遅れの「私の一冊~
地下水脈 『仁ちゃん』のタバコ ~『じいさん・ばあさんの愛しかた』より抜粋~
地下水脈 老人につきあわされるケアを
地下水脈(番外地) 投稿と質問に答えて
地下水脈 介護保険・現場の見方、使い方
地下水脈 差別告発者が好きじゃない訳
地下水脈 怒れる老人が少なくなった訳 ~個人主義は排他主義~
地下水脈 「人間」が具体性を取りもどす場
地下水脈 暗順応していく目
地下水脈 徳永進◆三好春樹 対談
地下水脈 “入りたいホーム”という欺瞞
- 1999 ~ 1998
-
- 1999.12月 介護夜駄話 フーコーから介護世界が見えてきた
客人 11月も忙しかったようだな。
三好 秋田に2日いて沖縄、宮古島、石垣島と、久しぶりに6泊のツアーだった。
客人 今年を振り返って何か一言。
三好 1988年に広島でオムツ外し学会を開いたときは、夢が実現した!と思ったものだ。それが今年は北は稚内で10月に、11月は石垣島でと、北と南の果てでオムツ外し学会を開けたなんて感激ものだよ。
客人 もう行くところがなくなったな(笑)。
三好 石垣よりもっと西の西表でどうだという話はある。北から南まで、一文になるわけでもないのに学会を開くため、いいケアのために活動してくれる人がいっぱいいるというのがありがたい。
客人 来年の抱負は?まさか樺太と台湾で、なんて言わないだろうな。
三好 抱負なんてないよ。俺はもうピークは過ぎたから、あとは下り坂を重力に逆らわないでちゃんと下っていこうと思ってる。
客人 なにを気弱なことを。まだ君に期待してる現場はいっぱいあるぜ。
三好 50歳にもなって「いつまでも前向きに、若々しく」なんて気持ち悪いじゃないか。「年相応」でいいよ。
客人 でも「いつまでも若々しく」なんてのが高齢社会のスローガンみたいになってるぜ。
三好 そりゃ、老いに対する恐怖感の表れだよ。老いと向き合いたくないんだな。
客人 誰だって年とりゃ近代的主体が崩壊するんだけど、それを認めたくないんだろうか。
三好 秋田でも沖縄でもこんな話を聞いた。特養ホームに個室がいくつかあるんだが、老人はそこに入りたがらないというんだ。「さみしいから4人部屋に入れてくれ」と訴える。家族も怒ってくるそうだ。「なんでうちの婆さんだけ1人ぼっちにするんだ」と言って。
客人 都会では完全に個室指向だけどな。
三好 でもプライバシーばかりを気にする近代的主体なんて老化と共に崩壊するから、都会でも個室は「独房」になるだけだよ。いま関わってる新設予定の特養も、全室個室の壁を取り外しできるよう変更するのに苦労したものさ。
客人 秋田県といえば全室個室を売り物にしてる有名な施設があるじゃないか。
三好 うん。行ったことはないけど、とても老人のニーズでつくったとは思えない。進歩的ジャーナリストや評論家がアドバイザーなんかになって、老人のニーズより自分たちの理念を大事にしてつくった結果だよ。
客人 その理念が“近代的主体よ、永遠なれ”というものだな。
三好 そう。老いても死ぬまで“主体”であることを強制する。一種の近代の暴力だね、、これは。
客人 そうか。毎月ミッシェル・フーコーの勉強会をやっていると聞いたけど、その理由がわかってきたよ。フーコーは、“近代的主体¨は近代がつくりあげた幻想だと言ってるものな。
三好 そう。テキストとして使っている「フーコー・知と権力」(講談社)は、フーコー関連書としてはわかりやすいと評判だが、それでも我々には難解。でも印象に残る文章がいくつもあったのでその一部を挙げておく。
人間はすばらしい、人間ばんざい、人間らしくあれ、われらの社会は、人間に関するあらゆるスローガンに満ちている。だが、そのすばらしい人間が、なぜ、戦争で大量殺戮をし、強制収容所で虐殺をし、拷問をするのだろうか。
人はそれを機械のせいにし、制度のせいにするが、人間という存在がこの機械を作り、制度を生み出してきたのではないだろうか。人間はすばらしい存在だとしながら、ヒューマニズムは、異なる生き物の運命には無関心ではないのか。ヒューマニズムという人間中心主義は、自然環境の破壊を肯定し続けてきたのではないのか。
近代のすべての学問の中心に「人間」という価値がインプットされ、自然界のなかで、「支配者としての人間」を中心とする傲慢な思想が生み出されてきたのではないか。そして、現在の野蛮な状況は、その「人間」によって、人間の近代的理性によって生み出されたものではなかったのか。
われわれは、他者との関係の網目のなかに生きているのであって、時代や社会関係に応じて「自己」は、そのつど作りあげられているにすぎない。普遍的で固有な「自己」という名前の主体は存在しないのだ。「なにものにも依存せず自立した主体」などというものは存在しない。
われわれは、いかなる時でも、生きている時代や属している社会の無意識的な構造(儀礼、慣習、イデオロギー)によって、あるいは社会関係、人間関係によって規定されたうえで判断を下し、行動しているのだ。日本でも、ドイツでもフランスでも、「お前はどうするのだ」という告白を迫ったのも、そうした最後の「主体」信仰のなせるわざだったといっていい。
社会関係のなかに人が存在して、そのなかで動かされていることを認めず、自律的な存在として自分をコントロールできると思い込むことは、他人をも簡単にコントロールできると思い込むことにつながる。
全体主義というのは、そうした自己コントロールの思想の延長上にあると考えるべきである。自己開発だの、自己啓発だのという心理的コントロールが、全体主義的テクニックだというのは、そういう意味である。 「フーコー・知と権力」(講談社)より抜粋
客人 そうか。“自立した個人”といった主体万能論が全体主義とつなかっていたんだ。どおりで「人権」を叫ぶ人たちがどうしてあんなに強迫的なのか不思議だったのだが、全体主義と通底していたんだな。
三好 フーコーの勉強会は、「人間という概念の崩壊」から「権力と処罰」、さらに「牧人権力」というところへ入っていく。君も来てみないか。
客人 そりゃおもしろそうだけど、難しそうだもんな。構造主義でもっとわかりやすい本があったら紹介してくれよ。
三好 じゃ季節にぴったしの本を1冊。『サンタクロースの秘密』(せりか書房2,000円)はどうだい。レヴイ=ストロースの「火あぶりにされたサンタクロース」に、訳者でもある中沢新一が「幸福の贈与」という解説文を加えて1冊の本にしたものだ。
じつは1951年のクリスマスに、サンタクロース(の人形)が火刑にあっている。カソリック教会が、アメリカナイズされた商業主義だとしてサンタクロースを異端だと審判し“火刑”にしたのだそうだ。にもかかわらず、サンタクロースが全世界に急速に広まったのはなぜか、ということを論じた本なんだ。これで構造主義がわかるわけじゃないけど、これは優れた「子ども論」であり「贈与論」だよ。


客人 ということは「子ども論」を「老人論」に、「贈与論」を「介護論」に置き換えて読めということなんだろうな。
三好 そう。介護保険なんかで語られているのとはまったく違ったところから、老いと介護の意味が見えてくるかもしれんよ。
------------------------------------------
「サンタクロースの秘密」
著者:クロード・レヴィ=ストロース
版型:四六判・112頁
定価:2,000円+税
発行:せりか書房
「フーコー・知と権力」
著者:桜井哲夫
版型:A5判・340頁
定価:2,524円十税
発行:講談社
--------------------------------------------
- 1999.11月 介護夜駄話 流れに逆らう根拠
客人 介護保険の施行が近いということで、新聞もテレビも介護問題を大々的に取り上げているけど、老人福祉月間もあったというのに、君にはどこからも声はかからないんだな。
三好 そうでもないんだけど、4日後にスタジオに来いなんて話じゃとても無理だよ。それに介護保険についてのこちらの話は現場向けのオフレコの内容ばかりだからテレビには出せないだろう。
客人 そりゃそうだな。「客観的に評価するな。ニーズで評価しろ」とか「介護拒否で認定額が上がるぞ」なんて話だもんな。
三好「認定作業ができることが介護だと思ってるヤツがいる。あんなのは保険の査定屋でしかない。しかもコンピュータの使い走り」とか、「MDSは”問題だらけ、センスなし”の略だ」なんてことも言ってるからなあ。
客人 なんでそんな憎まれ口ばかりをたたくんだね(笑)。
三好 だって介護を巡る今の流れはすごいもんだよ。アメリカの会社と提携した企業が訪問介護の会社のフランチャイズを募集して、説明会に人が押しかけてる様子をNHKの特集番組でやってただろう。
客人 ああ。最後に訪問を受けているお婆さんが、毎日何人ものケアスタッフが入れ替わりでオムツ交換に来るんで「名前も覚えられなくて…」と笑ってたな。
三好 「介護の社会化」それ自体はいいスローガンだが、実は介護の「企業化」「マニュアル化」へと急速に向かっているんだよな。
客人 でも考えてみりゃしょうがないよな。社会なんてとっくに企業社会化、マニュアル社会化してるんだものな。でもその歯止めとしてNPOがあるんだろう。
三好 でも大部分のNPOは「ケアを知らないNPO」だから、形態だけは企業化を免れても、ケアの中身となると結局大企業のつくったマニュアルを追っかけるしかないだろうと俺は見ている。ある民間会社に勤めていたヘルパーの話だが、訪問に行ったケースのオムツを換えようとして肛門をのぞくと、肛門括約筋が開いていた。つまり排便反射が起きているんだ。
そこですぐにトイレに誘導して座ってもらうとちゃんと便が出たというんだ。でもそれで時間が余分にかかって会社に帰るのが遅れたらしい。訳を話したら、誉めてくれるかと思ったら「あなたの仕事はオムツ交換だから、トイレに座らせちゃいけない」と叱られたというんだよ。彼女はすぐにそこを辞めたというけどね。
客人 そりゃひどいな。ケアを知らない。
三好 そこだって、民間会社とはいえちゃんとした理念をもってるところで、代表は講演なんかしてるんだぜ。

客人『まちの雑誌』の連載で君が2号と3号に「よい施設の見分け方」を書いていたけど、東京都の特養で全員特殊浴槽に入れてるなんてところがあるとのことだが、施設だってケアを知らないところがあるんだものな。
三好 歩ける老人は自分で着物と靴を脱いでストレッチャーに横になってる。呆けてる人はストレッチャーの上で動くからというので、ひもで身体を縛って風呂に入れているそうだよ。これじや、寝たきりは寝たきりのまま、寝たきりでない人まで寝たきりにするというとんでもないケアだ。
客人 で、施設のパンフレットには「やさしさとまごころ」なんて書いてあったりするんだよな(笑)。
三好 そのとおり。この施設も住民運動がつくったとかいって、その代表は有名な人だというんだからあきれちまう。こうした市民運動とか住民運動をやってるおばさんたちは「老人問題」には興味をもっても「老人介護」には興味を示さない連中なんだ。だからこんなことになる。
客人 そんな人に限って「人権を守れ」なんて言うんだよな。
三好 そう。俺は「人権」を声高に叫ぶ人がどうして「プライバシー」と「言葉使い」しか言わないのか不思議でたまらない(笑)。それは「人権」というものの表面をなぞってるだけだよ。どんな入浴ケアをするのか、どんな排泄ケアをするのか、どんな生活づくり、関係づくりをするのかこそが「人権」じゃないか。
でも彼らはそういった具体的な内容を何も提案できないから、「プライバシー」と「言葉使い」しか言えないのさ。だいたい「人権」と言う人は入浴ケアや排泄ケアなんかしないもんな。
客人 しててもすぐに大学の先生なんかに出世してる。
三好 いや成り下がってるんだよ。介護現場じゃ誰も相手にしてくれないから、弱い立場の学生なら影響力を与えられるだろうと考えているんじゃないの。かくして、またまた、介護を知らない介護福祉士なんてのが大量につくられる。
客人 介護がこんなに語られているのに、どこにも介護がないという皮肉な時代になりつつあるというわけか。
三好 ヘルパー養成講座なんてのもひどいもんだ。食事ケアというとすぐにスプーンで食べさせるやり方を教えるんだから。「介助しなくてもいい方法」を教えなくちゃいけないんだ。「老人が1人で食べるための工夫を10考えなさい」なんて教え方こそケアの教育のはずだよ。
客人 排泄ケアというといきなりオムツの当て方だもんな。三好「オムツをしなくていい工夫を10考えなさい」という教育が必要なんだ。現場はそんなことを毎日のようにやってきている。その個別的でマニュアル化なんかできない工夫のおもしろさのわからないヤツが先生に成り下かってないか。
客人 また憎まれ口だな。介護保険に立ち向かうドンキホーテみたいでいいけどな。
三好 おい、サンチョパンサ、後に続け(笑)。
- 1999.10月 介護夜駄話 大井シゲの「福の神」
客人 先月号の江藤淳の自死についての話はおもしろかった。こんなことを話題にできるのもブリコラージュがちゃんとした雑誌じゃないおかげだよ。
三好 ちゃんとしてないとは聞き捨てならんな。デザイナーの石原さんのおかげで立派にリニューアルしたじゃないか。表紙だって『ブルータス』か『サライ』とまちがえそうだ。
客人 それは認める。でもたとえば『月刊総合ケア』や『おはよう21』じゃこんな話は出てこないだろう。ついでにブリコラージュでしかできない君のプライバシーについて聞いてみよう。今年の夏は広島へ帰ったそうだが、恒例の車イス阿波踊りにも行ったのかい?
三好 行った。でも今年はボランティアとしてじゃなくて家族6人で観覧席で応援するという形の参加だった。一度阿波踊りの雰囲気を味あわせたかったんでね。
客人 踊ってるのと、見てるのとじゃ違いがあったかね。
三好 初めていろんな連(グループ)の踊りを通して見たんだけどある発見があったね。おっと思わず引き込まれる連というのがあるんだがそんな連には共通した特徴があるんだ。一見してヤクザばかりじゃないかというようなグループとか、暴走族の兄ちゃん、姉ちゃんのグループなんてのが魅力的なんだよね。
客人 なんとなくわかるような気がするな。
三好 迫力とか踊りにかける意気込みみたいなものが違うんだよね。自己主張があるんだ。
客人 非行や暴走に向かうエネルギーを踊りにぶつけてるんだな。
三好 そう。古くからあるいい祭りというのはそうした連中を取り込むだけの魅力があるんだと思う。
客人 博多の山笠なんかもそうだよ。ふだんは社会ののけ者や役立たずがここぞとばかりに張り切って回りから拍手を受ける。
三好 熊本のボシタ祭りもすごいよ。何か月も前から練習して祭りの当日は早朝から夜まで馬を引きずり回して踊り歩く。9月15日が祭りなんだけど、毎年のように暴れる馬に蹴られて頚部骨折する老人が出る。とんだ敬老の日だ(笑)。でも茶髪の姉ちゃんも老人もみな特有のリズムで踊りまくる。
客人 昔の祭りはそうした社会の不適応者たちを、年に一度共同体の中に迎え入れてやるという機能を持っていたんだろうな。祭りという非日常によって秩序を壊すことで、日常の秩序を守ろうとしたんだろうな。
三好 それに比べると新しくつくられた祭りはまったくダメだな。そういう知恵を持ってないから魅力も何にもない。私の地元、広島のフラワーフェスティバルなんて、明るくて整然としていて、はぐれ者を取り込む力なんて少しもないね。
客人 札幌の「YOSAKOIソーラン祭り」もあまりおもしろくなかったなあ。
三好 老人施設の行事もそんな魅力が必要だと思うんだよね。日頃「問題老人」なんて言われている老人が夢中になってみんなから拍手を受けるような¨祭り¨がね。
客人 なるほど、そう結びつくか。

三好「遊びと人間」を書いた哲学者のカイヨワは、遊びの要素を4つ挙げている。「競争」と「運」、それに「めまい」と「仮装」の4つだ。この本で俺が一番感心して納得したのは、仮装、つまり演劇とか祭りでお面をつけたりする遊びは、ほっとくと犯罪や暴力に走るタイプに適応があるというところだ。つまり、仮装という遊びによって、そいつの持っている反社会性を抑止する機能を持っているというんだ。
客人 元演劇部の君としては思い当たるところがあるだろう。
三好 あるある。カイヨワはどこでこんなことを発見したんだろう。特養ホームの問題老人だった大井シゲはボスとして君臨して回りから嫌がられてたけど、節分の時に面をつけて鬼や福の神の役をやらせると喜々として演じて、しばらくは機嫌がよかったのを覚えているよ。どこかに人から注目されたいとか、自分以外のものになりたいという願望があるんだろうな。
客人「めまい」はどんなタイプにいいんだね?
三好 カイヨワによれば、輪になって踊ったりするのは、放っておくとヒステリーになるタイプだと言っている。これも当たってるなあ。俺は生活指導員の時に、ヒステリータイプの婆さんに芝居の主役をやらせようとして失敗したことがある。前夜から体調をこわしたといって出てこなかった。あの婆さんは今思うとヒステリーになるタイプだから、もっと単純な動きのある遊びを用意すべきだったことになる。
客人 そうか。よく老人ホームごと演劇をやってるなんて実践が紹介されたりして感心してたんだけど、演劇なんてのが合う老人と合わない老人がいるんだな。
三好 そう。ダンスでイキイキしてストレスを発散する人もいれば、芝居をすることで充実感を得る人もいる。反対に、ダンスが苦痛だったり、芝居がストレスになる人もいるはずだ。1つの施設みんなで1つのことをやってるなんてのは考えものだよな。
客人 やっと出た『遊びリテーション学』(雲母書房刊)の中にも「めまい」や「仮装」の要素がたくさん入ってるよな。
三好「めまい」はもちろんだけどスゴロクで誰かに変身したり罰ゲームで何かを演じたりという形で「仮装」もあるね。こうした昔の人が持っていた共同体秩序を守るための祭りの中にある知恵を老人ケアに生かしたいもんだ。
客人 いつから秩序を守る側になったんだろうね(笑)。- 1999.09月 介護夜駄話 江藤淳の自死について
~決して強さとは言いたくないね~ 客人 今日は江藤淳の自死について聞こうと思ってきた。
三好 そうくると思った。君は江藤の代表作「成熟と喪失」が気に入っていたものな。でも俺は彼の熱心な読者というわけではなかったから、その思想も人柄もそれほど知ってはいない。だから、少し距離を置いた場所からの発言でよければ語ってみたい。
客人 いいとも。
三好 まず、遺書で脳梗塞になった自分を「形骸(ぬけがら)」と表現しているのが俺にはどうしてもひっかかる。 5年前にも梗塞があって今度が2回めらしい。右マヒか左マヒかはどこにも記されていないけれど、「文藝春秋」9月号の姪の書かれた文章から推測すると、どうも右マヒのようだ。意識もあって歩行が少しおぼつかなかったというんだけど、多くの脳卒中後遺症者と関わっている者としては「形骸」にはあえてひっかかりたいなあ。
客人 コトバや理念に生きた者にとっては、軽いマヒとはいえ、その落差が大きすぎたんだろうな。お前も本を書いてるくらいだからその気持ちはわかるんじゃないかね。
三好 うーん。確かに文章というのはどこか、いいカッコするところはあるけどなあ。でも自分の理念のために身体のほうを“処決”するというのは、他人にもそれを強要することにつながるような気がして、少なくとも“潔し”とする気はないなあ。
客人 彼は保守の論客だったけど、そういう意味ではマルクス主義と同じような体質をもっていたということになるのかな。
三好 左右を問わずインテリの弱さじゃないかなあ。決して強さとは言いたくないね。強さというなら、障害をもって生きているこれまで会った大勢の老人のほうが強いと思うもの。
客人 そうか、老人介護の現場の人間にはそういう判断基準があるか。僕なんかは、あの遺書の「……江藤淳は形骸に過ぎず。自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ」という文を読むと、思わず「諒」と言いたくなってしまうけど。でも君の中にも江藤淳的な部分はあるだろう。
三好 あるね。同じ状況になったらどうするかはわからん。でも願望を言わせてもらえば、「老化は進み、以降物忘れや失禁で回りに多大の迷惑をかけ、老醜をさらして生きていくこととなると思う。乞う、諸君よ、それを諒とせられよ」と書いて筆を置く、というふうにいきたいものだ。

客人 老いや障害を肯定しようとしてきた君らしい言い方だな。だが自分の老いや障害となるとどうかな。
三好 その辺りを「文學界」(文藝春秋発行)9月号の吉本隆明の追悼文がさすがにうまく書いていた。吉本は、自分なら自殺しないとは確信できない、しかし、自殺するとも言えない、と書いている。
江藤はそのあいまいさを嫌って最後まで自己決定したがったのではないか、という主旨だったように思う。俺なら「江藤淳」は[形骸]でも、本名の「江頭淳夫」で生きていけばよかったじゃないか、と思うけど、彼はやはり「江藤淳」でしか生きられなかったんだろうな。回帰できなかったんだと思うよ。
客人 文章で表現するということのなかにはそういう退路を断つみたいなものがあるんじゃないかなあ。文章だけじゃなくて芸術とか、芸人の芸なんかにも。
三好 人間にとって表現って何なのかと考えさせられるよなあ。
客人 文芸誌が追悼特集を次々に出しているけど、そのなかで印象に残ったものがあれば最後に挙げてほしい。
三好 前出の「文學界」の吉本隆明よりおもしろかったのが、同じ雑誌に載った西部邁の追悼文だ。「自死は精神の自然である」と題されていて、江藤の死を「諒」としているかに見えるが、内容はかなり辛らつなものだ。「喪失ゆえの弱さを克服して成熟せよ」という江藤に対して西部は「喪失そのものが成熟である、ととらえる精神の回路」が必要だと言うんだ。刺激的だよ。
客人 「妻と私」それに遺筆となった「幼年期」は読んだかね。
三好 読んだ。でもいずれも俺はピンとこなかったね。論理と意志の力で評論し発言してきた人がなんでこんな私的なことを書かなきゃいけなかったのか、という戸惑いを覚えたなあ。
客人 それは僕も同感だ。上流家庭に生まれたエリートに対する反発みたいなものまで感じるんだよ。
三好 西部の批判にもそんなところがあるのかもしれない。西部の論は一歩問違うと「正義のために積極的に死ね」なんてことになりそうな恐さがあって是とはしにくいけれど、なんとなく共感したのはそこだったのかなあ。下流階級としては(笑)。
なんで「幼年期」なのか、と思うに、論理と意志の力でやってきたと思ってきたけれど、じつはそれは宿命だったんじゃないか、と思い始めたんじゃないかな。それは江藤淳にとっては自己否定だよね。俺は吉本と西部がどう老いを迎えていくのかに興味があるなあ。
客人 俺はお前の老い方に興味があるけどね。
---------------------------------------
江藤 淳
本名・江頭淳夫。昭和7年12月25日東京生まれ。慶応大学在学中から文芸評論を書き始める。『夏目漱石』が有名だが、文学の世界のみならず、世相全般に対しても積極的に発言してきた文芸評論家。7月21日、自宅にて自死。享年66歳。
---------------------------------------
- 1999.08-7月 地下水脈 最終回 「介護の時代」のほんとうの意味
「介護の時代」と言われ始めている。新聞やテレビが介護保険の問題を取りあげない日がないくらいだし、書店には介護関係の本がズラリと並ぶようになった。ヘルパー養成講座の受講者を募集すれば、テキスト代と諸費用を入れると10万円近くもかかるというのに、若い人から定年を過ぎた人まで申し込みがくる、そんな時代になった。
介護の専門職を養成する学校も続々新設されているし、介護保険の施行に伴って必要になるケアマネジャーの試験には、看護婦や理学療法士といった専門職はもちろん、医師までが殺到した。どうしてこんなに介護が注目され、介護に関わる人が必要とされるようになったのか。高齢社会が到来し、老人、特に寝たきりや痴呆性老人が増えてきたし、これからも増えるから、と説明されている。
たしかにそのとおりである。しかし、ではなぜ医師や看護婦、保健婦といった従来の専門職を増やすというやり方をとらないのだろうか。医師の数はすでに過剰になっているし、看護婦は毎年のように大量の資格者を送りだしている。保健婦も市町村にはほぽ配置されており、保健所ではむしろ整理統合で余っているくらいである。
新たに学校をつくって設備を整え、教官をそろえるよりも、今ある専門職を増やしたり活用したりするほうがはるかに効率がいいはずなのに、それをしないで、なぜわざわざ“介護福祉士”や、1級から3級までのヘルパーを養成しようとするのか。
じつはここには、高齢者が増えて、看護、介護するものの人手が足りない、という単なる数の問題では捉えきれない問題が起こっているのだ。その問題とは、医師、看護婦を中心とした医療・看護という専門家によっては、現代の老人と家族が抱えている問題を解決できなかったことなのである。いや、解決するどころか、問題をつくりだし、その問題をもっと難しくしてきたのだと言っていい。
かつて私は「病院の専門職が寝たきりと呆けをつくりだしている。だからシロウトの介護職こそが寝たきりを起こし、呆けを落ちつかせよう」と訴えて、同業の理学療法士をはじめ、医師や看護婦から猛反発を受けたものである。「あいつは医療職のくせに病院の悪口を言っている」「理学療法士の専門性を否定するつもりか」などなど。
しかし、それから15年たって、世の中の認識は大きく変わってきた。従来の専門性の限界と弊害について、老人を入院させた家族の側からだけではなく、医療の内部からも批判と反省の声があがるようになってきた。そもそも既得権を守ることには異常に熱心な医師会や看護協会が、新しい「介護福祉士」といった資格制度の新設を認めざるをえなくなり、医師や看護職がケアマネジャーの試験にまで殺到することが、そのことの一つの表れでもある。
ではなぜ従来の専門性が、高齢社会と呼ばれる現代の人々のニーズに適応できなくなり、逆に寝たきりや呆けをつくり出すに至って結果的に「介護」の台頭を許すことになってしまったのか。その最大の原因は皮肉なことにも近代医療の発達なのである。そもそも病院のはじまりは野戦病院である。
抗生物質のない時代に、病人とケガ人は、感染の予防も治療もできず、死に至った。医師にできることはわずかの治療、それも現在では全く効果はないことが判明している“治療”だけであった。しかし看護には有効な方法があった。安静を保ち、栄養を捕給することである。安静と栄養と、“治療”を受けたという暗示によって、回復力のある運のいい若い患者は治癒することができた。
だから看護職は、安静の技術を持っていればよかった。栄養を補給することを考えればよかった。だから、いまだに老人に鼻からチューブで栄養を入れようとし、そのチューブを抜いてしまうから、と手を縛って安静を強制してしまうのだが、そういった方法論のみならず問題なのは、医師、看護職の頭の中に「安静を必要とする病人」というイメージが固定されてしまったことにある。
医師、看護職が対象とするのは「病人」なのだ。そんなことは当たり前ではないか、と思うかもしれないが、人間を〈元気ー病気〉という2種類に分類して見てしまうまなざしが動かしがたくできあかってしまったのである。この、人間を〈元気ー病気〉という二元論で見るまなざしは、医療、看護教育の中で強化され体系化されるに至る。
生か死かが問われる野戦病院や、かつての結核療養所ではこの二元論は通用した。〈病気〉の人を戦闘や日常の労働から解放して安静を保障することで、〈元気〉に戻っていったからだ。ところが、近代医療の飛躍的発達が、この二元論を崩し始める。かつては死に至った病気が治療できるようになったのだ。〈病気〉から〈元気〉に戻る人は増えた。
しかし、治ったとはいっても〈元気〉というわけではない、という人たちも飛躍的に増えたのだ。その典型が脳出血や脳梗塞といった脳血管障害である。 CTスキャンといった検査技術と治療法の発達によって死亡率は驚くほど低下した。しかし発症者数は変化していないから。手足に障害をもって生活していく人が増えてきたのだ。
死に至る病が、治癒、またはコントロールできるようになって平均寿命は伸び、老人、つまり老いと共に生活していく人が増えてきたこともご承知のとおりである。
わかりやすく図に表してみよう。
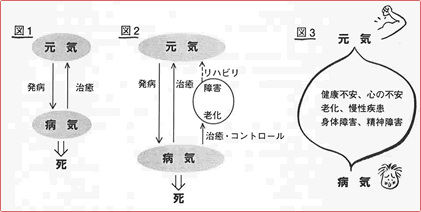
従来は、図1のように、人間を〈元気〉と〈病気〉の二つに分けて考えればよかった。〈元気〉から〈病気〉に至るのが発病であり、その逆が治癒で、治癒しないケースの大量の死が存在した。近代医療の発達によるこの構造の変化を示したのが図2である。
死に至ることは少なくなり、病気を、治癒、コントロールできるようになったが、〈病気〉と〈元気〉の間に、脳血管障害による手足のマヒといった身体障害や、老化をもった人たちが生まれてきたことを示している。
この〈病気〉と〈元気〉の間の人たちに対して、医療も看護も無力であった。治癒を目的としてつくられてきた医療体系は、もうこれ以上は治らない、となると興味を失うし、安静を目的としてつくられた看護体系は、自らの体系を守るために、すでに患者ではない障害老人を安静の中に閉じこめようとして手足を縛ったのだった。
そこに救世主が登場する。リハビリテーションである。私か理学療法士(PT)の養成校に入学した頃、PTやOT(作業療法士)は希望の星であった。リハビリさえやれば、手足のマヒは治り、寝たきり老人は立ち上がり、老人問題などすぐにでも解決するかのように期待されていた。
ある病院では、PTがまだ少なかったこともあったが、医師住宅を明け渡してまでPTを迎え入れたものである。もちろんそれが幻想にすぎないことはすぐに判明してしまう。もちろんリハビリテーションを受けたほうが良いことは間違いのない事実だが、脳細胞の損傷を原因とする手足のマヒが完全に治ることなどありえないし、まして何年も寝ていた寝たきり老人が歩きだすはずもない。もちろん老化を止められるリハビリテーションがあろうはずもない。
あのリハビリへの強い期待の裏にあったものは、じつは、医療の側の〈元気ー病気〉の二元論をリハビリによって守れるのではないか、という手前勝手な願望なのではなかったろうか。図2を見てほしい。〈元気〉と〈病気〉の間にあってどう関わっていいか判らぬ障害と老化を、リハビリによって〈元気〉に戻してくれるなら、従来の自分たちの人間像と、治癒・安静という方法論は安泰だからである。
つまり、図2に点線で示した「リハビリ」とは、医療と看護の古い構造を守るための最後の希望としての“幻想のリハビリ”なのである。いくらリハビリテーションを充実しても、〈元気〉と〈病気〉の間に存在する人たちは増え続けてきた。病気も突然発病して、ある日完治するといった一時的なものではなくて、慢性疾患と呼ばれる、病態へと変化してきた。

たとえば、糖尿病患者の多くはかつて死に至らねばならなかった。しかしインシュリンの発明によって事態は変わった。インシュリンは糖尿病を治癒するわけではない。コントロールできるようになったのである。こうして、糖尿病を患った人たちは、〈元気〉と〈病気〉の中間で生活していくことになったのだ。
興味深いことに、精神障害の分野でも病態の変化が起こっている。かつては激しい妄想や暴力を示した精神分裂病は、最近では静かで自閉的な症状を示すようになってきたという。かつての激しい症状は薬物療法によって治癒することもあったが、最近の静かな病者は治癒に至ることが難しいという。ここでも〈元気ー病気〉の二元論は崩れ、その中問に存在する人たちが増えているのだ。
さらに興味深いと思うのは、老人でもなく、身体障害も精神障害はもちろん、慢性疾患をもっているわけでもない人たち、つまり、図1、2でいえば〈元気〉に入ると思われる人たちまで、“中間化”していることである。自分のことを、元気だ、と胸を張って言える人がいなくなっているのだ。みんな自分の健康に不安を持っていて、病気ではないか、病気になるのではないか、とヒヤヒヤしているように見える。
昼間のテレビのワイドショーで毎日紹介される健康法をみんな競って見て、ある食品が健康にいいと言えば、その日のスーパーマーケットの棚からその食品が消えてしまうといったことがそれを象徴しているではないか。健康診断に行って「どこも悪くない」と言われると残念がって、逆に、隠しているのではないかと半信半疑になるなんて話もよくあるらしい。
現代人は、少なくとも主観的には、自分を元気だと思っている人はほんの一握りにすぎなくなっていて、その人も回りからは「なんて単純な人だろう。病気じゃないか」と思われている、そんな時代なのである。
これは一種の神経症ではないだろうか。名付けるとしたら、健康神経症だろうか。健康のためにこれをしなければならぬ、健康のためにこれを食べちやダメ、と神経をすりへらすというきわめて不健康な生活が蔓延している。元気で長生きしている老人は例外なく、そんなことを考えもしなかった人ばかりだけれど。
心の領域でもそうである。アダルトチルドレンなんてコトバが流行したのはまだ記憶に新しい。子どもの頃、親から虐待を受けたために精神的外傷をもっている大人という意味だが、アメリカでは「私も」「私も」と。アダルトチルドレンを自称する人が続出したという。ある調査では対象者の80%以上が「自分はアダルトチルドレンだ」と思っているという。
実際に虐待を受けたかどうかは別にして、少なくとも多くの現代人がそういう物語を必要としているのだということがポイントであるだろう。少なくとも主観的には多くの人が、自分の精神が傷ついており、これまたはやりの言葉でいえば、癒しを求めているのである。
さあ、そうなると、図1の〈元気ー病気〉に、その問を付け加えた図2といったパターンではとても現在の医療・看護と介護を巡る状況を説明できなくなってくる。 現代では、元気と病気はそれぞれの極として存在するにすぎず、その間が大きくふくれあがっている。それを図3で示してみた。
かつて、発病と治癒によって通過するにすぎなかった〈元気〉と〈病気〉の間に、大部分の人が含まれるに至った。だがこの図の膨らみは単に量的なものを示すものではない。抱えている問題の多様性、個別性をも表している。一人の人が身体障害と慢性疾患を併せもっていたりもする。老人となればなおさらでここに書いたいくつもの問題を抱えているのである。

この多様性と個別性をもった人たちのニーズに、安静看護という画一的な方法が通じるはずがない。安静看護は、病気という、しかも急性期という一時的な時期と病院のICU(集中治療室)という特殊な空問でのみ通用するものになったのだ。
さあ、そこで介護が登場した。つまり。介護とは、単に高齢者が増えたから必要とされるようになったのではなくて、人々の抱える問題が多様化、個別化した現代に、その多様で個別のニーズに応えるために必要とされているのである。
となると画一的なやり方は通用しない。なにしろ一人ひとりの抱える問題は多様であり、さらにそれに一人ひとりの家族まで含めた生活習慣や人生観までが交錯したところにニーズがあるからである。
つまり、介護とは一人ひとりの個別の状態を把握し、個別のニーズをつかんで、マニュアルなんかに頼らない個別のアプローチを創り出していくものなのである。私が介護に必要なのは二つのソーゾーリョク、つまり想像力と創造力だ、と言い続けてきたことの理由はここにある。
ところが世の中では介護に想像力と創造力が必要とは思っていないらしい。単なる介護力か、それに心が優しければいい、くらいにしか思っていないのだ。残念ながら介護職までもそんな介護像しかもっていないのが現実である。私の目的はそんな介護像を打ち破り、介護の時代にふさわしい新しい介護のイメージと方法論を提出することにある。
この文章は2000年1月に新潮社から刊行予定の『老人介護常識の誤り』(仮題)の巻頭の文章として書かれたものです。
●ご好評いただきました「地下水脈」は今回で終了します。
長い間のご愛読ありがとうございました。
9月号からは、三好春樹による新連載『介護夜汰話』が始まります。
どうぞご期待<ださい。
●ブリコラージュ1号から続いてきたこの『地下水脈』は、それぞれの時期に三好春樹の単行本の中に収められてきました。
専門バカにつける薬(1992年発行)
正義の味方につける薬(1995年発行)
老人介護問題発言(1998年発行)
- 1999.06月 地下水脈 遊びリテーションは近代を越える〈下〉
人間とは無意識的存在である
私は人間というものを、意識的存在としてよりも、はるかに大きく無意識的な存在であると考えています。それは現実的存在である、生活的存在であると言ってもいいわけです。ですから介護を変えていこうとする時も意識を変えていくというやり方ではなくて、もちろんそれが有効な場合もあるのですけれども、それはほんの一部のインテリだけに有効な方法だろうと思います。
ほとんどの介護職にとっては、無意識の部分、あるいは現実を変えていく中で、まず感じ方、まなざし、見方とか、そういうものが変わって、意識が変るのは最後だと思うのです。いわば、氷山の一角のようなものであろう、目に見える所だけの意識だけを変えたと思っても、実はその下にある広大な無意識が変っていなければ何の役にも立たない。むしろ、そんな理念的意識は邪魔になるような気がします。
これは痴呆性老人への関わり方でもそうですね。私たちは、ひじょうに勉強して意識的に関わっていこうという関わり方が、痴呆性老人に対して全くの無効であるという経験をしています。この人は何型の痴呆だからこういうアプローチ、たとえばバイステックの7原理、受容の原理、自己決定の原理なんてのを頭に入れて老人に関わろうとしますと、老人は全然反応してこないということがあります。
そういう時にはむしろ私たちは頭をからっぽにして、老人の前にちゃんと現われて、同じ目線に立って二コッとする。そうすると向こうも二コッとしてくれる。そこに私と痴呆性老人との間に醸し出された雰囲気みたいなものに自分が動かされていくというようなやり方をした時に、老人との共感的世界が生まれるという経験を、みなさんもしているだろうと思います。
もちろん、意識的にやることで効果があるということもいっぱいありますから、私はそれが意味がないと言っているわけではないのですが、痴呆が深くなればなるほど、どうも意識的なアプローチというのは、老人にとっては何か意図的な関わり方に思えるのではないでしょうか。彼らはその場の空気にひじょうに敏感ですから、わざとらしさみたいなものを感じ取るのではないかなという気がします。
呆けというのは、人間が意識的存在から無意識的存在になっていくことだと私は思うのですけれども、われわれもまた同じように無意識的な世界に入って、そこで何か関係のいちばんの基礎になっているところを作り上げていく方がはるかに有効だと思います。
@“意識的”は暴力を含んでいる
これは子どもとの関わりも一緒だと思うのです。インテリが子育てに失敗していることが多いというのも、そういうことではないのかという気がします。ひじょうに意識的に関わろうとするのですね。東大を出た進歩主義者のお父さん、かなり倫理主義的な人だったと思いますけれども、この人が子どもの家庭内暴力に耐え切れなくて精神科医に相談しに行っているわけですね。
この精神科医もおそらく同じような思想を持った人だろうと思いますけれども、どんなに暴力を振るわれても非暴力を貫け、じっと耐えろという指導をするわけです。それをその通りやって、けっきよく耐え切れなくバットで息子を殴り殺してしまうという事件がありました。
新聞なんかは、お父さんに対して大変同情的なのですけれども、私は子どもの方に同情的です。この子どもはアルバイト先ではちゃんと人問関係をもっていましたね。親に対してだけ暴力を振るっていた、特に父親に対してだけ暴力を振るっていたわけです。自分がいくら暴力を振るっても相手が非暴力でじっと耐えているというのは、父親が自分より高い所にいて何か自分を変えてやろうという意図を感じたのだろうと思います。僕は、そこに子どもの方がムカついたのだろうという気がします。
私は殴られたら殴り返せばいいじゃないかと思います。一方的に殴るのは全然良くないと思いますけれども、殴り合うのは構わないじゃないですか。そりゃ暴力はいけないですよ。殴らないですむのにこしたことはないけれども、理不尽に殴られたら殴り返す方が自然だという気がします。このお父さんはそういう自然さみたいなものを失っていたという気がするのですね。
暴力はいけないと思っていたかも知れないけれども、人間って存在そのものが暴力的であるということがあるのですね。特に東大なんか出ているとそれだけで暴力的存在だと私は思いますね。頭の良い人が一口しゃべると周囲の人間って黙るでしょう。回りを沈黙させる力というのはすごい暴力ですよね。
あるいは専門家というのもそれだけで暴力的存在だったりするわけでしょう。そういう事に対してひじょうに無自覚だったのではないかな、という気がするのです。ですから、もともと人間は暴力的存在で、特にインテリで東大を出ていれば暴力そのものなのですから、殴らないということで非暴力的になれるなんて思っているのが、私は幻想だという気がするのですよね。
大事なのは無意識の関わり方だと思うのです。無意識はフロイトが発見しました。人間観が大きく変わったすごい発見ですね。では、人間の無意識はどこで形成されるのでしょうか。だいたい胎児、お母さんのお腹の中にいる時と、せいぜい2歳ぐらいまでの間に形成されると言われています。
無意識にトラウマ、つまり精神的な傷があって、自分も自覚していない、抑圧している、忘れよう忘れようとしている傷がある時には、これを意識化することによってその問題を乗り越えていこうという方法論が精神分析というやり方です。私はこれはフロイトが精神科医だったために、無意識をいわば意識化されるべき対象として捉えてしまったという気がします。
私は無意識とは、単に“意識に従属していて、これから意識化されて明らかにされるべき対象”ではないと思っています。そうやって対象化されたものが果たしてほんとうに無意識かどうかは実証もできないし、曖昧で、不確かなものです。たとえば親からのこういう什打ちを受けて私はこういう問題を抱えたのだ、というふうに催眠療法なども使って無意識を意識化していく作業をするわけですけれども、これはフロイト自身も言っているのですが、それの大半は物語であるという言い方をしていますね。つまり事実ではないことが多いということです。
@無意識を豊かにする
私もそう思うのですが、事実であるか事実でないかは別にして、問題は、そういう物語をその人がいま必要としているということだろうという気がします。問題老人がいっぱいいる時に、胎児とか2歳まで戻って対象化しろというのは全く無理な話です。特に痴呆性老人にとっては無理な話で、私はそういう意味では精神分析という方法論は具体的にも本質的にも問題があると生意気にも考えているのです。
私は無意識を変えていくのは過去を対象化・意識化しなくてもできると思っています。それは、たとえ2歳を過ぎていても日常的な生活自体が無意識を作っていったり、無意識を変えていくと考えるからです。というのは、生活というのは大半が無意識に行われ繰り返されているものですから、その蓄積の中で無意識というものは変化していく、つまり無意識の世界とは、小さい頃の過去の世界ではなくて、現実の世界であり、刻々と生活によって変わっていくものだと思っています。
そうすると無意識を変えていく、無意識を豊かにしようと思えば、生活そのものをまず変える、つまり、現実を変えていけばいいわけですね。ですから、その方法としては、お年寄りの意識を変えようとかいうアプローチをするのではなくて、老人の無意識が変化していって、固い表情が柔らかくなり、笑顔が出てくるような生活をどう作るかということをやっていくことが必要になります。
ですから、当然ですけれども回想法をやって回想させようというやり方では全然ないわけで、遊びリテーションをやって、憎い嫁のことも嫌な寮母のことも忘れて、その場でパッと笑顔が出てくることの方がはるかに大きな効果があるだろうと思っています。無意識が変われば、、日ごろ抱えている問題も解決はしないまでも、我慢できるところまでいくということです。
これが大事なんですね。解決できるような問題はたいした問題ではないです。誰でもみんな、人生にいっぱい問題を抱え込んで生きているわけで、解決しようというのではなくて、何とか我慢できるところまで持っていくことで、日常、人生をやってきているわけです。ですから、老人もそれができればいいのですね。その意味では遊びリテーションは大変有効な方法論だろうと思います。
@介護職の意識変化
そして、実は遊びリテーションによって、そこに関わっている介護職そのものの無意識が変っていくのですね。これがもう一つの大変大事なところだろうと思います。つまりベッドに寝ている老人の排泄ケア、食事ケアをするという、そういう関わり方のなかで捉えている老人像みたいなものと、遊びリテーションをやって、ワーワーキャーキャーと笑顔が出ている老人と関わっている人の老人像とは違ってくるわけです。
老人の見方が現実的に変っていくのです。そうすると「あっ、あの人はああいう表情をするのだ」ということを見ただけで、どうしてお風呂に入った時にそういう表情が出ないのだろう、食事はほんらい楽しいはずなのに、なんであんなにイヤそうな顔で食欲も出ていないのだろう、とそういうことを感じ始めるわけです。感じていけば、次に「これは変わるはずだ、他の方法があるはずだ」と考えられるわけです。
その意味では、意識の部分だけが人間であるという狭い人間観から、無意識、生き物というところまで含めて、広い幅で人間を捉えていく方法論が必要とされていると思います。人間を意識だけで捉えるというのは、これも医療が近代医療と言われたように、極めて近代的な人間の見方なのですね。その枠をとっぱらわなくてはならない、ということになっているのだろうと思います。
ですから、遊びリテーションというやり方に対して批判し、意識を変えなくてはいけないと言っている人は、実はこれまた古い枠の中にいた専門職と同じように、古い人間像の枠に捕われているのだろうと思います。その中でちょっと悲鳴をあげているというか、それが私たちの新しさへの批判になって出てきているのだろうと思います。
ですから、こういう代表的な遊びリテーションヘの二つの批判というのは、実は遊びリテーションが切り開いている新しい方法論、その背後にある新しい人間観というものに対し、ひじょうに敏感にそれを感じとって悲鳴を上げているのではないかと私は思っています。ですからこういう批判はありかたいですね。批判に答えることで自分たちのやっていることの意味が、実はどんどん明らかになっていくと思っています。- 1999.06月 地下水脈 久しぶりに映画を観た
客人:ゴールデンウィークまで仕事とはご苦労なことだな。
三好:うん。でも半日大阪で暇があったので映画館をはしごしたりした。
客人:それは珍しい。映画なんてあまり見るほうじゃないだろう。
三好:特にハリウッドの大作には嫌気がさしている。『タイタニック』なんか金もらっても見ないつもりだ。
客人:相変わらずひねくれ者だな。で、何を見たんだね。
三好:一つは『虹の岬』。三國連太郎と原田美枝子の不倫もの。二つめがよかった。『バージンフライト』という題だ。
客人:ああ、映画評で見た。難病患者とボランティアの話だろ。ボランティア嫌いのお前がなんでそんな映画を見る気になったんだ。
三好:言っておくが俺はボランティア嫌いじゃない。同じ老人介護をやってても、ボランティアでやるのと仕事としてやるのは全然意味が違うから同列に論じるべきじゃない、と言ってるだけだ。そして俺は仕事としてやってる立場から発言するぜ、ということさ。
この主人公はボランティアつたって、ボランティア刑なんだ。ちょっと変人でノイローゼ気味の男が世間を騒がせた罪で奉仕刑を受ける。だからこれは仕事に近い。
客人:なるほど。
三好:さすがはイギリス映画だけあって、担当させられた難病の女性患者がパンク風なんだ。髪型もそうだし電動車イスで万引きはするし、インターネットでポルノを見てる。
客人:そりゃおもしろそうだ。
三好:本当におもしろい。ノイローゼ男と死に至る難病女性の深刻だが心温まる月並みの物語だと思ったら大違い。俺は終始ゲラゲラ笑って見た。この女性が18歳で発病して今は25歳なんだけど、「処女のまま死ぬのは嫌だ」と言い始めるんだ。それで、”リチャード・ギアみたいな”ジゴロを探しに行くんだが、一晩2000ポンドだと言われて、金がないんで銀行強盗することになる、というハチャメチャなストーリーになっていく。邦題は『バージンフライト』だが、原題は『The theory of flight』。“プライト”は生きていくことのメタファだろう。
客人:日本じゃ、とてもこんな映画はつくれないな。
三好:そう思った。日本で難病とか老人をテーマにした映画をつくると、気恥ずかしくなるような臭いセリフをしゃべらせて、バックに情緒的な音楽を流し観客を泣かせようとする。老人介護をテーマにした『一本の手』なんてのはその典型で、これを見せられた福岡の宅老所よりあいのスタッフは口を揃えて、「偽善だ!」「大嘘だ!」と怒りまくっていた。
客人:ああ、あの田中美里主演のやつね。あれはひどかった。舞台のときはまだ良かったんだけどなあ。
三好:『バージンフライト』には、“臭い”セリフは全然出てこない。最後のセリフ、これは女性の遺言みたいなもんだが、それは言語障害が進行していて自動音声器の音で語られるんだ。意図的に情緒的にしないように抑制されている。バックの音楽もロック調。それに比べて日本じゃ、『一本の手』みたいな欺隔の集大成みたいな映画か、あとは、意識を高めてやろうなんて意図がミエミエの退屈極まりない啓もう的な記録映画くらいしかないのが日本の情けない現状さ。
客人:羽田澄子の映画のことだな。
三好:判るか。
客人:判るよ(笑)。これはもう日本とイギリスの文化のレベルの差だろうな。日本があちら並みになるには20年くらいかかるんじゃないかな。
三好:いや俺はそうは思いたくない。それじゃ、日本はダメ、西欧は進んでるというこれまでの図式になるだけだ。
客人:そうか、君は日本主義だったな。
三好:日本主義じゃない。文化を一本の評価軸で捉えて優劣を比べるのが間違っているんだ。赤と青と緑のどちらが上かなんてのに意味はないだろう?日本には日本の文化があるんだよ。俺は日本文化が遅れているんじゃなくて、日本で映画をつくってるインテリたちが日本の観客をとことんバカにしてるんだと思う。彼らは二言めには「日本人は個人として自立していない」とか言うくせに、じつは彼らが日本人の涙もろい情緒性に依存し迎合する形でしか作品をつくれないんだよ。自立してないのは映画人や評論家のほうさ。
客人:そうかもしれん。ついでにお前の好きな映画ベスト10を並べてみないか。読者も知りたがってるかもしれん。
三好:そんなに見てないけれど、じゃ順不同で。『ナイトオンザプラネット』『マンハッタン』『アニーホール』『Uボート』『ブリキの太鼓』。うーん、10にはならんなあ。あと日本映画で『竜二』と『七人の侍』で7つがやっとかな。あっ『バージンフライト』で8つだ。
客人:よっぽど気に入ったんだな。- 1999.05月 地下水脈 遊びリテーションは近代を越える〈上〉
◇10年目の遊びリテーション
『遊びリテーション』を竹内孝仁先生たちと一緒に出させていただいてから、今年で10年になります。 1989年出版ですから、今年でちょうど10年です。この間、遊びリテーションというのは老人介護の現場に大変広がりました。先日テレビを見ておりましたら、ニュースで天皇夫妻が老人施設を訪問しているのですけれども、そこでちょうど風船バレーボールをやっているところでした。それぐらい社会に認知されたのかと思いました。
ここまで広まりますと、「単に遊びリテーションをやっていればいいというものではないよ」と逆に言いたくなったりするわけですけれども、今日はどうして遊びリテーションがこんなに広がったのかという理由を探っていくことで、遊びリテーションの意味について再確認をしていきたいと思っています。
なぜこんなに広がったのか。1つはこれを普及する人たちがどんどん出てきたことにあるでしょう。私も以前は「生活リハビリ講座」で遊びリテーションの実技をやってたりしていましたけれども、そのうちに上野文規さんや下山名月さんがやり始めました。それから坂本宗久さんも全国で実技教室を開いています。
この人たちは、私よりもはるかに上手なのですね。それで私の役割はもう終ったなと思って、あまり遊びリテーション実技はやらなくなりました。さらに小松丈祐さんという人が一座を率いて全国を巡業して回るというのも出てきましたし、最近では作業療法士の松林さんあたりも実技指導をして歩いています。
もちろん普及する人が増えたからといって、現場の人がこれに共感をしなければ現場に定着していくということはないわけです。じゃあ、なぜ現場の人たちの共感を得たのでしょう。私たちはこの間ずっと、「介護とは何か」ということを訴えてきました。介護の介とは媒介の介である。
つまり、きっかけになることだ。老人が主人公になるために私たちの知識や技術、われわれの存在そのものを媒介にしていくことが介護です。それは急性期の治療や看護から始まった方法論、つまり、老人が医療や看護の受け身的な対象になっているやり方とは違うものなのですよということです。
食事を食べさせられるのではなくて、食事を老人自身が楽しんで食べる。排泄をさせられるのではなくて、自ら排便・排尿をする。お風呂に入れられるのではなくて、お風呂に入って良かった、と思えるような介護をしようと訴えてきたわけです。それで「オムツ外し学会」などを開いてきたりしました。お風呂も、機械に頼ることをできるだけやめて、ふつうの生活的な、家庭的なお風呂に入っていただこうよ、ということをやってきたわけです。
しかし、オムツ外しなんて言いましても、職場のチームワークがなかなか取れないところでは取り組みが難しいわけですし、入浴を変えていこうと思いますと、風呂場の改造が不可欠であるということもありまして、なかなか難しいわけですね。
ところが遊びリテーションをやってみますと、いとも簡単にと言ってもいいと思うのですけれども、老人がその場で主体として登場してくる場面に出会うわけです。そういう経験を現場の人たちがするわけですから、それで“これはおもしろい”ということになります。しかも改造も何も要りません。われわれがやる気があって、場所があって、老人が集まってくればできるわけですから、そういうことでどんどん全国に広がっていったのだろうと思います。
◇遊びは自発性である
カイヨワという人が『遊びと人間』という本を書いていますけれども、このなかで「遊びの本質とは何か。それは自発性である」ということをはっきりと言い切っています。自発的にやるから遊びなので、させられるというのは遊びではないわけです。ですから逆に言うと、遊びということを通して自発性はいちばん引き出しやすい、ということでもあると思います。
ところが、遊びリテーションを始めた頃は、いくつかの批判が私たちに寄せられてきました。今日はその批判を大きく2つに分けて、それに反論するかたちで私たちがやってきている遊びリテーションの意味をもう一度考えていきたいと思っています。

まず、PTやOTとかいった専門家からの批判が、最初かなり多くありました。たとえばPTからは「PTが遊びリテーションをやるというのは、PTとしての専門性を放棄するものである。専門家というのはPTにしかできないことをやるべきであって、誰にでもできるようなレクリエーションに手を出すというのは自らの専門性の放棄である」という批判が出てきました。私たちはこういう批判に対して2つの回答を用意しています。
ひとつは大変オーソドックスな回答の仕方で、「PTやOTが遊びリテーションをやるということは専門性を豊かにすることであって、決して専門性を放棄することでも、ないがしろにすることでもない」という回答です。困っている人のニーズがあるから制度とか専門家を作ったわけですね。ところが制度ができてしまうと専門家が専門家のニーズで仕事をし始めて、そのニーズに合う対象者を選んでしまうということになりかねません。
たとえばリハビリテーションの効果を士。げよう、学会で発表するために治癒率を高めようと思いますと、最初から年寄りを除外する方向に走ってしまう。重度の大は除外、ボケている大は対象外、若くてやる気のある人だけを相手にやっていれば治癒率は高められて学会では認められるという、そういう倒錯が起こってきます。
実は齢とってボケて重度な人ほどニーズは強いわけで、そういう人のために専門家を作って身分を保証しているわけですから、そういう人にこそ実は専門家が積極的に関わらなくてはいけないはずです。もちろん学校ではボケの人に訓練する方法などは習っていないわけですから大変なのですが、それをやらないと専門性はどんどん衰退していくばっかりではないか、という言い方をしてきたわけです。
2つ目の回答は、ちょっと過激というか、開き直りの反論を用意しています。「遊びリテーションに手を出すのは専門性の放棄であるというのは、まったくそのとおりである。その批判は正しい」という回答の仕方です。どうしてかと言うと、医学とその医学の中にあるリハビリテーションという体系は、人間を人体として見る、あるいは個体として見るというところで成立をしてきました。
たとえば1人の身体の中のどこに問題点があって、それを見つけ出してそこヘアプローチをしていこうというやり方ですね。それによって老人を元気にしようとしてきたわけですけれども、確かに治癒が可能なもの、あるいは治癒が可能な時期には、それは大変有効なわけです。しかし慢性期、私たちはこれを生活期と呼んでいますが、つまりこれ以上治らないとなった時には、それは通用しないんです。老人も生きいきしてこない。老人がもう1回、生活の主体として登場してくるために一番良い方法は、人体とか個体へのアプローチじゃないんですね。
◇関係を見ない専門家の限界
実は人間は、個体として存在するのではなくて人間関係の中で生きいきしたり、あるいはダメになったりしているわけです。つまり人間を個体として捉えるのではなく関係的存在として捉えなくてはいけないわけですね。みんなで一緒にわいわい、がやがやとひとつの目的をもってやるということの中で、個体だけにアプローチしてやっていた訓練では出なかった機能が、いくらでも出てくるという経験を私たちはしてきました。これは人間を関係的存在として捉えれば当り前のことなわけです。
そこでわれわれは、痛くて苦しい訓練をしかめっ面してやるよりも、笑顔が出てくるような楽しい方法のほうが効果があるよ、という言い方をしてきたわけです。もちろんそれは数量化なんてできませんから、「笑顔があればいいという表現は専門家ではない」と批判されてきました。ですが、笑顔というのは自分が共感的世界にいるということの象徴のひとつなわけですね。
人間というのは人問関係の中に自分が位置づけられている、みんなと一緒にいるんだ、みんなと一緒に生きていこうとしているんだということで、初めて心身共に落ち着きますし機能が発揮されるわけです。これは当然ですが、身体機能だけではなくて、精神機能も全くそのとおりでありまして、どんな状態でも人間は人と一緒にいたい、共感的世界を持ちたいと思っています。
ただ、その世界は共感も得られるけれども傷つけられることもあったりするものですから、時には閉じこもって1人になりたい時問もあります。私にもありますし、みなさんにもあるでしょう。 1人になる時間という`のは、もう一度そこで自分というものを確認して、再び関係的世界の中に出て行こう、自ら関係づけをしていこうことの準備の時間です。関係的世界と1人でいる世界は、裏表として一体になっているような気がします。
長い問ひとり暮らしをしてきて、人間関係が希薄になっていったおばあさんが、91歳で特別養護老人ホームに入って来ました。この人は4人部屋のベッドにいたのですが、長い間誰とも会話をしない生活をしていたためにどうなっていたかというと、ほかの3人と話すのではなく、自分で自分と会話をするのですね。
自分で自分の名前を呼びます。「今田トワさん、今田トワさん」と言って「はい、私か今田トワです」と返事をする。「あなたが今田トワですか。さすがですな、ワアハッハッハ」とか言って、1人で笑ったりしているわけです。どうも大変気持ちの悪い世界に入っていくわけですが、そこまで追い込められた時でも、自分の内的世界で話し相手を作り出しているんです。共感してくれる人を自分の心の中に作り上げなくてはいけないぐらい、人間はそういう世界を求めているわけです。
ですから、専門家が個体だけを見てアプローチするよりも、みんなと一緒にワイワイ、ガヤガヤやったほうが、はるかに機能も良くなりますし精神的にも落ち着きますし、生活そのものが変わってしまうことすらあるわけです。 つまりPTやOTの側の方が、「専門性を放棄するものだ」と言ったのは大変正しい洞察でありまして、人間を目に見える個体としてしか見ないという近代科学の狭い枠の中にいる専門家が、いわば自分の限界を自ら告白しているという気がするのですね。その意味では、「おおいに専門性を放棄して解体していけばいいじゃないか」という過激な回答を用意しているんです。

◇人権を抽象的理念でしか語れない人々
近代科学の発達のおかげでみんな長生きをして治らない病気も治るようになったわけですけれども、一方でその限界が明らかになってきていて、それが実は老人問題なわけです。大袈裟な言い方になりますけれども、遊びリテーションというのは、その意味では近代の限界みたいなものを超えていこうという方法論として出てきた気がします。
もうひとつの批判は、ひじょうに真面目な社会福祉をやっている人たちから出てきました。この人たちは人権を大事にしようよ、ということを声高く言う人たちです。「現場の人たちは人権意識が低い」と言って、人権意識を強く啓蒙してくれる人たちなわけです。
私はこういう人たちずっと論争してきまして、その論争が『正義の味方につける薬』(筒井書房刊)という、ちょっと皮肉な題の本になっているわけですけれども、どうも彼らは目の前にいる老人の人権が大事なのではなくて、自分の持っている人権という理念が大事なだけなのではないか、という気がしています。
というのは、こういう言い方をするのですね。「遊びリテーションなんか一生懸命にやっているけれども、一方では、お風呂に入れるのに老人を丸裸にしてタオル1枚かけただけで廊下にズラッと待たせて、人権をないがしろにするようなことをやっている」というかたちで遊びリテーションを批判するのです。私は何を言っているのだろう、と思うのですね。間違っているというなら、入浴の仕方をちゃんと具体的に提起すればいいわけでしょう。
私たちが言ってきたように、家庭用のお風呂にほとんどの人が入れるわけで、そうすると職員にも余裕ができます。老人にとっても、これまで70年80年やってきたのと同じお風呂に入ればいいわけですから、たいへん自立していきます。具体的な方法があるわけですから、それをどう実現するかという問題を立てるべきで「遊びリテーションなんかやっていないで、もっと人権意識を持つべきだ」なんていうのは全くおかしな話です。
私は人権が大事ではないとは全く思いませんけれども、人権を大事にするということはもっと具体的なことなのですね。たとえば“ベッドが高すぎるために足を降ろせなくなって、立てる人でも立てなくなっている”というのが実は人権の侵害ですから、人権を守るためにはまずベッドの足を切るべきです。脳卒中になっても片手で起き上がれない人はいないはずですから、ベッドの幅さえ広くすればいい。広くと言ってもふつうのベッドの幅でいいのです。
病院で使われているベッドがあまりにも狭すぎることが、起き上がれる人を起き上がらせなくし、寝たきりにしているわけですから、これはどの人権侵害はないわけです。広いベッドにしようよ、と具体的、現実的に老人の生活を変えていくという提案ができなければ、「人権意識を」と100回言っても、老人はちっとも生きいきしてこないわけです。
ここに私は、大変大きな方法論の違いというものを感じました。私たちが倫理主義者と呼んでいる人たちは、まず意識を変えようとするわけです。つまり人間というのを意識的存在として捉えている気がします。ですから、もっと意識を高くしなくてはいけないので、意識の高い者が低い者を啓蒙する、教えてあげるという態度が出てくる。
これはどうも差別的構造ではないかと私は思うのですが、そういう構造を強く持っています。ですからこういう人たちが政治の世界で政権を取ったりしますと、ひじょうに抑圧的な政治になるというのも実は歴史の教えるところだろうと思うのですけれども。(次号につづく)- 1999.04月 地下水脈 チューブ外しとアインシュタイン
私が呼びかけ人になって開いている「チューブ外し学会」が、医師の一部で評判が悪いそうである。特に、非経口的栄養摂取、つまり、口から食べるのではなくて鼻からのチューブや、胃ろう(胃にあけた孔)からの栄養補給の方法を研究している人たちからは非難さえ起こっているという。
「命にかかわることなのに“チューブ外し”とは何ごとか」というのである。球マヒや仮性球マヒによって嚥下反射が消失してしまったケースや、重篤な症状のときに、こうした非経口的方法を一時的に使うことを否定する人はいないだろう。その技術の開発によって命が助かる人もたくさんいるはずである。
また、終末期と思われるケースにこうした方法をすべきかどうか、また、いつまで続けるのかの判断は、その人と家族の人生観によって変わるだろうけれど、本人や家族が少しでも延命したいと願っているのなら、そのときにもこれらの技術が必要であることはいうまでもない。
しかし問題は、彼らが、患者と家族のためにと思って開発してきた方法と技術が、老人看護・介護の現場でどう使われているかということなのである。デイサービスセンターに通っていた人の話である。脳梗塞による右片マヒで失語症があったが体調を崩して検査のために入院することになった。
車イスで病院に行ったとはいえ、自分で立ちあがってベッドに移ったくらいで、食欲は落ちていたが、左手でスプーンとフォークで自分で食べていた人である。ところが、病棟婦長の家族への第一声は「鼻にしますか、胃にしますか。胃のほうが楽ですよ」であった。
家族には最初なんのことかわからなかったが、勧められるままに手術で胃に孔をあけられ、ここから栄養を流されることになった。彼はなによりも、急に手術されたことでショックを受け、目が虚ろになった。腹部の痛みと違和感のため、無意識に左手で胃ろうに触ろうとするので手を抑制された。
そして1週間後には、尿道カテーテルやモニターを身体中につけられ“重体”になっていたのである。胃ろう形成術が簡単にできるようになった。そこに装着される器具も便利なものである。そうした方法と技術の開発が、食欲低下というだけの老人を、“主体の死”に追いやっているのである。
胃に送り込まれる“カロリー”の代償として。「そんなことのために技術を開発したのではない」と彼らは言うだろう。でも研究室や大学病院から出て、老人病院の看護・介護現場に行ってみるがいい。こんな話はいくらでもあるのだ。核物理学の研究者たちももちろん、人間を大量殺りくしようなどと思っていたわけではなかった。
だから、「戦争終結のため」という大義があるとはいえ、多くの科学者が原爆を製造するための「マンハッタン計画」への参加を拒否した。参加した人たちも、ヒロシマ、ナガサキの惨状を知らされるにつれて、良心の痛みを感じ、科学の成果とその使われ方について深刻に悩み始めるのである。
そして、アインシュタインをはじめとする多くの科学者が、反核運動、平和運動に参画していくのである。開発された非経口的栄養摂取法は、自分の手で口から食べるための工夫と努力を現場から奪いつつある。「生活障害論」で示した、姿勢や時という、どこでも誰にでもできるふつうの介護を試みようともしないまま、老人はベッドに縛られることになった。
だから当然ながら、チューブの人の大半がチューブを外せるのである。そもそもチューブをすべきでない人を、看護・介護の不在によってチューブにさせているのを外してどこに問題があろうか。それを非難する理由があろうはずがないではないか。
それどころか、自分が開発した技術が老人を“主体の死”に追い込んでいることに良心の痛みを覚えて、「チューブ外し学会」に馳せ参じるのが人間の道ではないか、と言いたくなるのだが、彼らにアインシュタインのような倫理観を要求するのはよそう。私は、無いものねだりはしない主義だから。
彼らがいくら批判しようが、現場の人たちは「でも、外れるものは外れるのよねえ」なんて言っている。体験で知っているから、現場を知らない人から何を言われても影響はない。影響があるのは、「チューブ外し学会」を取材にきたジャーナリストが、専門家の言い分も聞こうと研究室へ行って「チューブ外しなんてとんでもない」と説教され、結局、どっちつかずの“バランスのとれだ記事を書いてしまうくらいのことである。
「原爆は悪いという人もいるけれど、一生懸命開発した人もいるんだから、まあ、ケースバイケースで」なんて立場がバランスのとれたものでないことは言うまでもない。被爆の実態を少しでも知ってればそんなバランスはとるまい。研究者にもジャーナリストにも、もっと現場を知れ、とだけ言っておこう。「チューブ外し学会」はもちろん今後もやる。- 1999.03月 地下水脈 国は滅びても商売は残る
「15年間、どんな戦略でやってきたんですか」と聞かれたことがある。「これから、どんな計画があるんですか」ともよく聞かれる。ところが、戦略も計画もないのである。生活とリハビリ研究所を名乗ってからの15年間で、今の事務所が7軒めだというのが計画性のないことを何より示している。
現場に伝えたいことがあって、それを語っているうちに、向こうからいろんな依頼が来てそれを受けているうちに「オムツ外し学会」も「チューブ外し学会」も生まれてきた、そんな感じである。
本だってそうだ。初めて人前で呆けについてしゃべったら、それを聞いていた医学書院の編集者が面白がって連載を書かせてくれて最初の本になった。(『老人の生活ケア』)
講演のテープがすでに活字になっていて「これを本にしたいんだけど」と言われたのが、筒井書房で出た最初の本だ。(『生活リハビリとはなにか』)
だから、戦略どころか、こちらの予想だにしない形で新しいケアとリハビリは広まっていった。もっとも予想を外れたというか、予想だにしなかったのが、民間デイサービスが全国に生まれたことである。これも最初の本で下山名月さんと出会ったことがきっかけである。
もうひとつ予想が外れたのが、各職種から同じように新しいケアを訴える人たちが続々登場したことである。私一人が何を言おうが、「ひねくれ者が変なこと言ってる」くらいにしか思ってくれなくても、安永道生さんが話せばうなずく人がいるのだ。
フリーの怪しげなPTだけじゃなくて県庁のPTまで言うのなら正しいのかもしれん、なんて思うのだろう。さらに上野文規さんが訴えれば若い女性はうなずくし、下山さんが語れば社協のおじさんが納得する、といった具合だ。
私が安静介護を批判すればムッとする看護職も、永田則子さんや松下明美さんが言えばむしろ“看護職の誇り”にまでなってしまうのである。私が「ふつうの家庭用の風呂に入れよう」と訴えても「そんな理想論が通用するもんか」と反発する人が、村上廣夫さんが施設長の立場から説明すれば身を乗り出してくるのである。
いくら新しい発想の介護法が広まったとはいえ、まだ全体の9割以上は古い体質のケアのままだし、老人施設も地域ケアに関わる人もどんどん増えている。だとしたら、新しいケアを訴える人がもっともっと増えて、彼や彼女らの発言力、影響力が大きくなるようにしなければ、とてもこの世界を変えていくことはできないだろう。
だから数年前から、私と下山、上野がいっしょにセミナーをする機会は少なくしている。同じ日に、同じ会場にいるなんてもったいないからだ。私が札幌で上野が大阪、下山は鹿児島という具合だ。
それに村上さんが施設連盟の会で発言していて、フリーになった坂本宗久さんが名古屋にいて、中田光彦さんは東京で話してる、朝倉義子さんは山田ゆたかさんと生活リハビリ研修センター松露庵でジジババ体験をやっている、というふうにいろんな人が、いろんな場でいろんな人を対象に張り切ってる、という状況が、最近の Bricolage を見ると起こっているのである。すごい情報量ですものねえ。
フリーになったOTの松林誠志さんも、本誌の情報欄を占拠するくらいの巡業ぶりである。彼がフリーでメシを食えるようになればまた後に続く人も出てくるだろう。読者のみなさん、応援をよろしく。
「三好は金もうけのためにやってるんだから」なんて陰で言っている人がいる。それが国立大学のリハの教官だというのだから笑ってしまう。国が徴収した税金を再分配してもらっている身で、しかもPTやOTで「教授」なんて肩書きをつくっで”アカデミズムごっご”をしている人がよくもそんなことを言うもんである。
一度そんな肩書きなんかなしで、つまり自分の語る内容だけでセミナーを開いて何人が金を出して来てくれるかやってみればいいのだ。公的な立場なるものが商売よりも価値が高いなんて思っているようなセンスでよく地域リハビリとか言えるものである。
地域とは生活の場であり、健全な生活者ほど、公的なものに頼ったりぶらさがったりせず、自分の才にだけ頼った商売でメシを食っているのである。ニーズに応えられなければ食えない、とい引刀実さこそが、老人ケアと世の中を変えていくエネルギーなのだ。
もちろん民間デイも私も松林さんも、その危機感で仕事をしているのは同じだ。「国は滅びても商売は残る」。私の好きなコトバの1つである。国家より商売のほうが歴史的にもずっと古い。つまり人間にとって普遍的なのである。
さて私の戦略。もっと金もうけして、「三好でもあれだけできるんだから自分も」という人をもっとつくること、とでもしておきましょうか。- 1999.02月 地下水脈 羊飼いの使命感
「精神科の先生って変な人が多いですよね。変だから精神科へ行ったのか、行ったから変になったのか知りませんが」。などと、唐突に長谷川式の検査を始め、老人が答えないでいると「こりゃ相当呆けてますなあ」なんて目の前で言う精神科医への皮肉を含んだいつもの話を私はしていた。イ山台での集中セミナーでのことである。
それを二コニコして聞いていた医者が、じつは病院で「物忘れ外来」を担当している精神科医だと知ったのは、セミナーの後の懇親会でのことである。山崎英樹先生という方で、現在、仙台市内にデイケアを準備中とのことだが、医者が私なんぞの話を聞きに1日やってくるだけでも、この人、ただ者ではない、と思うではないか。
それもそのはずで、発表原稿の要約のコピーをいただいたのだが、その最初のスライドに「牧人権力・フーコー」と出てくるのである。フーコーとは、私が「関係障害論」のなかで「一方的に見ることが権力の発生根拠」と言った人として紹介している哲学者である。
牧人(ぽくじん)とは羊飼いのことである。羊を人間に見たてて、キリスト教の司祭の意味に転じた。迷える子羊の群を導ぐ牧師”ということである。
フーコーは「かつては君主が民衆の身体を拘束し、切り刻む実権を持っていた」が「近代では、君主の名ではなく、国民の名のもとに、すべての人々が、身体をソフトに管理される時代となった」と指摘している。それを「牧人権力」と名付けた。
羊飼いは親切で責任感が強い。羊の群れに対してはとくに献身的で専門的知識や技術を身につけようとする。羊飼いがいないと群れはバラバラになり、羊は死んでしまうのだ。羊飼いはたとえば教師であり、羊は生徒である。
権力は”生徒指導に熱心な優秀な先生”の姿をとって行使される。こっけいなことに、かつての残虐な君主は自分が権力者であることを自覚していたからそれをセーブすることもあったが、近代の権力者たちはその自覚がない。
「暴力の学校・倒錯の街」は、福岡の女子高で起きた教師による体罰死事件の迫真のルポルタージュである。わずか1年で刑務所を出所した犯人である元教師は、公判で自分のことを“熱心な教師”だと主張している。カッとなって殴るので生徒から嫌われているのさえ「10年後によかったと思ってもらえれば」と言うのだ。
ここでは1人の人間の俗っぽい支配欲や自己中心性が、“羊飼いの使命感”にすり変わっているように思える。学校以上に「牧人権力」が支配しているのが病院であり施設である。病院を辞めるに際して山崎医師が書いた論文にそれが如実に語られている。
精神科の患者への抑制(手足を縛ること)の廃止を提案する先生たちに、ある婦長がこう言う。「患者さんの安全と清潔のためには抑制は必要です」と。おお、すばらしい責任感ではないか。羊飼いの使命感はこうでなくてはならない。かくして患者は、骨折の危険もなく、尿や便で汚れて不潔になることもない、“安全と清潔”な身体で崩壊していくのだ。
「牧人権力」は、「健康管理」とか「清潔の保持」とか「保健指導」という姿で現れる。もちろん「専門性」「善意」「ヒューマニズム」そして「ケアプラン」としても。懇親会に同席していた老健スタッフがこう語ってくれた。
「タバコの好きな老人がいるんです。でも夕バコはナースステーションで管理されてて、欲しいと車イスでやってくるんです。2本の指を口に近づけて、タバコのサインをするんだけど、“ちゃんと口に出して言うまでタバコを渡さない”というのをケアプランで決めてて「“タバコをください”つて口で言ってごらん」なんて言って無理やり言わせてるんですよ。僕はそんなことしないですけどね」。
やれやれ。介護職まで権力者に仕立てるほど近代のシステムは巧妙なのである。介護職よ。自分を“羊飼い”にするな。つまり老人を“羊”と見なして教育的指導なんかするな。医師という大きな権威を持っている人たちはそれだけワナにはまる危険が大きい。
にもかかわらずそこから自由になる生き方をしようとしている人がいるのだ。看護婦や介護福祉士なんでミニ権威”にすぎない者が、そのワナにはまってどうする。山崎医師の「いずみの杜(もり)診療所・デイケア」は4月に仙台市泉区にオープンの予定。
 ※フーコーに関する引用は「フーコー・知と権力」桜井哲夫(講談社)による。
※フーコーに関する引用は「フーコー・知と権力」桜井哲夫(講談社)による。
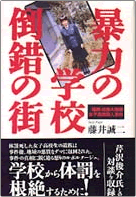 「暴力の学校倒錯の街」
「暴力の学校倒錯の街」
著者:藤井誠二
発行:雲母書房
判型:四六上製320頁
定価:2100円十税
- 1999.01月 地下水脈 意識の高みからではなく無意識の深みから
1998年は現場にとっては介護保険やケアマネジャーに振り回される異常な1年だったが、私にとっても4冊もの本を出すという異様な年であった。「身体障害学」と「介護技術学」は、講座でしゃべってきたことをまとめただけとはいえ、話しコトバを活字にすることや、特に「介護技術学」の実技を本で表現することには、いささかの労を要した。
「老人介護・問題発言」はこの「地下水脈」を中心にまとめたが、本誌読者にも改めて読んでほしいこともあって「民間デイの七不思議」と「民間デイのつくり方」を書き加えた。もう1冊の「じいさん、ばあさんの愛しかた」は全文初の書きおろしで、後半の書き直しも含め、ほぼ3か月間、手をとられることとなった。
そんなこともあってこの1年間、読書量は近年で最も少なかった。新しい読者との出会いが増える喜びがあるとはいえ、それでは埋めることのできない淋しさが残る年であった。吉本隆明の「アフリカ的段階について」(春秋社)は、いきなりヘーゲルのアフリカ観の批判から始まる。私はまだ、彼の「母型論」(学研)に圧倒されて十分読みこなしていないところへもう次のモチーフについての本が店頭に並んでいるのである。
「母型論」が個体としての人間の最も基本的な部分を考察することで、精神分裂病の原因をも探ろうとしているのに対し、「アフリカ的段階について」は、人類史の基本的部分の意味を見出すことで、現代という病理への処方を示そうとしているかに思える、そんな本である。
ヘーゲルはアフリカ的世界を、野蛮で未開な、残虐でヽ残酷な世界だとし、原住民には、豊かな感情も倫理もない、生命の重さや人間性を軽んじている世界だと見ていた。それに対して吉本は、アメリカインディアン、チェロキー族の作家、フォレスト・カーンの『リトル・トリー』や『ジェロニモ』、ナンシー・ウッドの『今日は死ぬのにもってこいの日』(いずれも「めるくまーる」より出版)さらに、アイヌについて記したイサベラ・バードの『日本奥地紀行』(東洋文庫)などを引用しつつ、野蛮や未開と呼ばれている世界の精神性の高さを示してみせるのである。
それは、西欧近代とは「異質の仕方で自然物や人間を滲みとおるように理解し、自然もまた言葉を発する生きいきした存在として扱っている豊かな世界」であり「独特な視点から万有を尊重している仕方」だというのである(第1章)。野蛮とは自然にまみれた非人間的世界ではなく「人類が無機的な自然や植物や生物や動物を内在的に了解している精神の段階」とも言っている(第Ⅱ章)。
西欧近代こそが最も人間的であり、アジアやアフリカが劣った非人間的なものであるというヘーゲルの自己中心的世界観は、決して過去のものではない。老人問題を語る文化人やジャーナリスト、文化人化した現場の人間からは、老人介護の世界は、「ヘーゲルの見たアフリカ」と同じように見えているようである。
そこではプライバシーも守られていないし、人権も大切にはされていない。入浴や排泄に異性介助が行われているし、介護職員は老人を「じいちゃん」とか「ばあちゃん」、ときには「クソババ」なんて呼んでいる、意識の遅れたひどい世界だというふうに。だから、彼らは私たちに「人権意識がない、もっと意識を高めろ」と説教してくださる。
もちろん、ウンコ、シッコに関わっている者こそ、人権を守っているのである。傷つけることもあるから守ることもできる。手を汚さぬところから説教される筋合いなどないよ、と私たちは言い続けてきた。“意識の高い”彼らが大切にしているのは、人権という理念でしかない。私たちは目の前のジジ・ババを大切にする方法を考えているのだ、と。
だが最も大切なことは、彼らが介護現場に創り出されている、吉本流に言えば“野蛮や未開の世界の精神性の高ざを全く理解しえないことにこそあるのではないか。いい介護現場では、どんな問題老人でも“滲みとおるように理解じ、コlヽバの通じない失語症者や呆け老人さえ”言葉を発する生きいきした存在として扱っている豊かな世界”が、そこには存在しているのである。
そこでは、老いも呆けも”内在的に了解”されているように感じられるのである。つまり、本を読んだり、理屈をとおしたりすることではなく、老いも呆けも自然の一部として扱っている世界なのだ。谷川俊太郎さんは、老人ケアには古代がある旨発言された(『老人介護・問題発言』所収)が、私はさらに、未開や原始、生きものどうしとしての無意識の世界での共感までが内包されているような気がしてならない。
今年読んだ数少ない本の、私のいささか我田引水的読みかたを紹介させてもらった。本、特に吉本隆明さんのような難しい本は、自分のそのときの問題意識に引き寄せてしか読めないから、と言い訳しておこう。来年は本をたくさん読みたいと思っている。- 1998.12月 地下水脈 介護保険を逆手にとる
介護保険の問題点については、誌上でも講演でも何回も指摘してきたが、ここでそれを整理してみたいと思う。まず1番目の問題は、ケアを知らないケアマネジャーが大量に発生することである。医師や理学療法士、看護婦といった職能集団が、ただ自分たちの権限が縮小することを恐れるという理由だけで組織的に受験するといった事態が起こっている。
彼らのような、排泄ケアも入浴ケアもしたことのない連中がケアマネジャーになるらしい。もちろん、実際にケアをやっているからといってケアマネジメントができるとは限らない。でも「ヘーえ、あんたたち、そんなに介護に興味があったの」と皮肉を言いたくなるくらいだ。
ケアに興味をもつどころか、「シロウトのやること」とバカにしてきた連中が、厚かましくも受験しているのである。こうした動きに対しては、再び「恥を知れ」と言っておこう。(『老人介護問題発言』雲母書房、第1章「恥を知れ」参照)
2番目の問題点は、介護というものを「支給限度額」という数字に還元してしまうという点である。一人ひとりの個性を数字で表せるはずがないように、老人の生活状況も必要なケアも数字になるものではない。個別の老人の個別の状況に対して、それぞれ個性をもった介護者の個別の関わりが必要とされているはずなのである。
これまで行われてきた「良いケア」と言われているものは、それらの個別性の見極めがちゃんとできていたからだと言ってもいい。しかし、ケアを知らないケアマネジャーによってつくられるケアプランなるものは、そうした個性や個別性を無視した、せいぜい「介護力」という抽象的なものとしか介護を位置づけようとしないだろう。
第3の問題点は、こうしたケアマネージャーによって行われる、要介護認定という名の状況とケアの数量化とケアプラン策定は、結局のところ、寝たきりと呆けの後始末にしかならないだろう、という点である。
私たちにとっては常識だが、寝たきりは身体障害が原因なのではない。寝たきりにならなければならないほど重度の身体障害の人は5%もいないはずである。さらに痴呆は脳細胞が萎縮する疾病が原因ではない。これまた痴呆のうちの5%もいないはずである。
寝たきりになるはずもない身体障害をきっかけにして老人が寝たきりへと至ってしまうのは「生活障害」と「関係障害」と私たちが名づけた状況による。そして、物忘れやおもらしという、生理的老化にすぎないものをきっかけにして老人が呆けへといたるのもまた「関係障害」と「生活障害」が原因なのである。
となると、たとえ寝たきりと呆けがなくて要介護度が「要支援」ですらなくとも、そこに生活障害と関係障害があれば、おそらくそのケースが呆けと寝たきりに至ることは容易に判断できるはずである。つまり要介護度は高いはずなのだ。
また、要介護度が4の「最重度」や5の「過酷」と認定された人でも、身体の障害に伴う手足のマヒや老化に伴う物忘れならともかく、生活と関係から生じた問題は治療可能なはずなのだ。もしケアマネジャーとケアワーカーがそうした視点をもっているならば。
しかし、その視点がないなら、これは膨大な“後始末”の巨大なシステムづくりとなるだろう。そのとき、介護はその意味を失い、誰にでもでき、誰がやっても同じ「労働力」になってしまうだろう。
もちろん私たちは、こうした介護保険の問題点を挙げつらうだけで終わるつもりはない。“老い”の問題点をプラスに転化してきたように、これらを逆手にとって現場に生かしていくだろう。
問題点の1つ目は、逆に言えば、医療職をはじめとするあらゆる職種が、介護に関わらねば生きられないと思いはじめたということでもある。これを機に、彼らを介護世界に引きずりこんで「関係論なき個体の論理」(『関係障害論』参照)を打ち破るチャンスにしていけばいいのである。
問題点の2つ目にしても、数量化という形で介護がやっと社会化されたとも言えるのである。客観的数字にするほかには、社会から膨大な金を引き出すことはできないからである。
そこで私たちは、要介護区分にこだわらず、生活と関係を評価する目で探り出した「二-ド」に基づいてまず必要なケアを、次に金額を、その次にその金額に見合う要介護度にランク、という逆の順番で仕事をするだろう。数字にさえすれば勝ち、なのである。
3番目の問題点は深刻である。介護保険という制度ができる前から、介護を後始末だと思い込んでいる人が大半だからである。特に安静看護を未だに信奉する看護職を中心に。しかし、だからこそ私たちが見張らなくてはいけないのだ。
「この本は安静看護技術に引導を渡すために書かれた」という前書きで始める『介護技術学』が飛ぶように売れていることも、現状に疑問を感じている人がいかに多いかを示していよう。
私? 私はケアマネジャーなんかにはなりませんよ。その代わり、「お前、それでもケアマネジャーか、ケアも知らないで」と言う立場でいます。受験しない人と落ちる人、私といっしょに文句を言い続けましょうよ。- 1998.11月 地下水脈 『歯は老化ではなくならない』
~ひと月遅れの「私の一冊~ 「じいさん、ばあさんの愛しかた」は、おかげさまで好評で、日本経済新聞に徳永進先生が書評を寄せてくださったこともあって、20日足らずで増刷になるなど売上も好調である。
この本の企画を、法研の編集者と共に私のところに持ち込んで来たのが、編集事務所を開いている秋元秀俊さんである。彼は歯科医療について何冊もの本を書いている医療ジャーナリストで、最近知り合った歯科医の先生や歯科衛生士さんたちに彼の名前を出せば、誰一人知らない人がないくらいの人である。
その秋元さんは、私の本を編集しながら同時に自分の本をも書いていたのだという。打ち上げの席でいただいたその本の題名は『良い歯医者と治療がわかる本』。私は歯や歯の治療でそれほど困ったこともないので、特に興味があったわけでもないのだが、ページを開くと、あっという間に半分ほど読み進んでしまった。
一般の人向きの本だから読みやすいというのもあるが、なにより内容が面白いのである。まず驚いたのは、大半の歯科医は、むし歯の治療をしていない、という著者の主張である。じゃあ、あの歯科医院で受けている“治療¨は何なのかというと、あの削って、埋めて、かぶせるのは、むし歯の“後始末”であって、決してむし歯の治療ではないのだという。
それは「たとえば、目がかすんで目医者に行く。糖尿病のために生じた網膜症だとわかったとする。…そこでこの目医者が、めがねをあつらえて『これで糖尿病の治療は終わりましたよ』といって」いるようなものだと著者は言うのだ。ちょうど、オムツ交換は決して排泄ケアではなく、排泄ケアの不在の後始末である、と私たちが主張しているように。
むし歯にはいろんな原因がある。むし歯になる原因を治すことをしないで、多くの歯科医は、むし歯の痕跡を簡単に削り簡単にかぶせてしまう。だからむし歯はますます進行する。すると今度は簡単に抜いてしまう。
従って著者に言わせると、歯科医師会と厚生省による「8020運動」(80歳で20本の自分の歯を残そう、というキャンペーン)も、歯科医たちが簡単に抜きすぎて、治療すべき歯がなくなることを恐れてのものだという。
もうひとつ教えられたことがある。それは、歯は老化によってはなくならないということである。総入れ歯の老人を多く見ている介護職の私たちは、齢をとれば歯が抜けてしまうのは仕方がないと思っているところがある。
ところが老人の歯がないのは、1つは歯科医がどんどん抜いてしまったせいであり、もう1つの原因は歯周病という病気のせいであって、決して老化が原因ではないというのだ。そしてその歯周病についても、治療が行われることは少なく、後始末に追われているのだという。
この本は歯科医療の現状に対して、根底的と言っていいくらい批判的である。多くの医療ジャーナリストが医者のタイコ持ちみたいな記事ばかり書いているなかでは異色といってもいい。だからといって医療への告発本のような批判ばかりではない。具体的提言もあるし、何人かの魅力ある歯科医が登場してくる。
その人たちは、ちょうど私たちが介護のおもしろさを、ブリコラージュという言葉で表現したように、他科の医療にはない、¨自分の手で治せる”ということにおもしろさと奥深さを感じているように見える。
著者は最後にこう書いている。昭和30年代から40年代に、先進国では「むし歯の洪水」といわれる現象が起こった。その時「この問題を解決するのに大きな分かれ道があった。病気をなくすのか、治療する人を増やすのかという選択である。欧米などでは病気をなくす方向を選んだ」。
ところが「この時期にわが国は、まったく違う選択をした。昭和40年ごろから歯学部、歯科大学を次々に新設し、保健政策よりも疾病保険の充実がすすめられた。病気を防ぎ、治すことは無視され、後始末の医療に全精力が注がれたのである]と。
おやおや、この国は、懲りることも反省することもなく、全く同じ間違いを再び拡大再生産するつもりのようだ。つまり「後始末の介護」のための介護保険制度とケアマネジャーの養成である。
 「良い歯医者と治療がわかる本」秋元秀俊著(法研)
「良い歯医者と治療がわかる本」秋元秀俊著(法研)
本体1,500円
- 1998.10月 地下水脈 『仁ちゃん』のタバコ
~『じいさん・ばあさんの愛しかた』より抜粋~ 【臭いのは3日で慣れる】
フリーになってからのことだが、北海道新聞で「老人介護Q&A」というコーナーを、週に1回、2年半、書かせてもらったことがある。介護者からの質問がくることはくるのだが、いずれも便箋に発病以来の経過や家族間の問題などが細々と書かれ、とても新聞で取り上げて一般的に語る内容ではないものばかりであった。
しかたなく、一人一人に手紙を書いたり、住所によっては知っている保健婦さんに訪問を頼んだり、というかたちで対応したものである。というわけで、Q&Aといっても、自分でQとAの両方を書く回のほうが多いという有様だったのだが、予想外にも若い人からの質問が多くきたことには、時代の変化を感じたものである。
老人介護の仕事をしたいのだがどんな勉強をすればよいのか、介護福祉士の資格はどうやれば取れるのか、といった質問が高校生を中心にいくつもくるのである。なかにはこんなのもあった。「お年寄りのお世話をする仕事をしたいと思っています。
でも家族や友達に話すと、「オムツ交換は臭くて大変な仕事だよ」といわれます。お年寄りとの話や、世話は好きですが、それだけでは勤まらないかと思います。オムツ交換って、ほんとうに大変ですか?」
私の答えはこうである。「臭いのは3日で慣れます」
もちろんそれだけでは紙面は埋まらないから、今では生理学を応用してオムツに排便させたりしない排泄ケアが始まってますよ、なんてことも書くのだが、こんな、「やらせ」を中心としたQ&Aでも、まとめてみるとそれなりに内容のあるもので「老人介護Q&A」と「ねたきりゼロQ&A」(雲母書房)という二2冊の本にまとめられているので興味ある人はどうぞ。
たしかに初めてオムツ交換を体験すると、昼食は口に入らないに違いない。しかし、人間というものの適応力はすばらしいもので、本当に3日目には、カレーライスを食べながら「○○さんの便、ちょうどこんなふうだったわよ」なんて言ってるのである。だから、いくら、臭くて汚い仕事はイヤだ、と思っている人でも、3日我慢すればあとは3年でも10年でも続けられる。
【インドに旅立った彼女の場合】
この仕事を続けられないのは別のタイプの人。「不幸な老人のために自分の人生を捧げたい」と思って老人介護の仕事につく人である。彼や彼女らは、老人の便が臭いとか汚いとか言って仕事を辞めたりはしない。それどころか、臭いなんて感じてはならないと思っているのである。
私は「生活リハビリ講座」というセミナーを開催して飯を食っているのだが、その講座に熱心に通っていた当時30代の女性、Aさんは、講座の終了した会場でももちろん、酒場でも熱心に老人介護の話を続ける人だった。
寝たきりやボケの人に自分がどう関わってどんな変化があったかを、何時間でも語るのだ。聞けば彼女は、休み時間でも老人のそばを離れず、休日までボランティアで出かけているのだという。そのときは、熱心な人だな、という印象であった。
だが、私の講座は当時毎月1回開催されていたので1ヵ月ごとに受講者とお会いし、何人かと一杯やるのだが、そのうち彼女の話にグチが入るようになった。自分がこんなに熱心にやっているのに相手が認めてくれない、というのだ。
老人の立場に立って仕事をしているのに、管理職や同僚が認めてくれない、というグチはたくさん聞かされてきた。だが、老人が認めてくれない、というグチは珍しい。私は思った。この人は、口では老人が好きだといっているけれど、ほんとうは、老人を介護している自分が好きなだけではないだろうか、と。
はたしてさらに1ヵ月後、彼女は「うちの施設の老人には感謝の心がありません」と言い始めた。私たちはシラけ、誰も彼女と話そうとはしなくなった。彼女がイメージしている施設の老人とは、不幸な弱者なのである。そんな人に対して自分は真心と熱意で休みの日まで使って尽くしている。そんな自分ってステキ!(若い人ならここにハートのマークでも入れるところだ)
そう思っていたのだが、現実の老人は「不幸」でも「弱者」でもない。そうだとしてもそれは一面でしかない。なにしろ、第一節に出てきた岡田マサさんみたいな人がどの施設にだっているのである。そんな老人たちに「感謝の心」を期待しているような人は、3日は続くが半年ももたない。
実際に彼女は4ヵ月めに施設を辞め、その後、私の講座にも出てこなくなった。風の便りによれば、マザーテレサの跡をつぐと言ってインドへ旅立ったとのことである。私には、彼女はもっと「不幸な」人を探しにいったのだろうと思えるのだ。岡田マサみたいに文句や注文をつけたりせず、ましてや、介護する側を憐れんだりしない、もっと不幸な人を。
そこでは、「介護するステキな自分」像は壊されることはないし、彼女の老人像、人間像は無事なままなのだから。もちろん人のことはいえない。私だって老人介護の現場にきたときには、彼女と同じような老人像を描いていたのである。
だが、現実の老人に出会ったとき、私は自分の老人像を守るためにインドに向かうのではなくて、自分の老人像、人間像のほうを解体したのである。それは心地良い解体だった。解体され再構築されるたびに人間像は多様になり広くなった。
【「やーい、どうせ歩けんだろう」】
森田仁之介は、いくつかの病院と施設で、いずれも「問題老人」として退院、退所を命じられた人である。福祉事務所の担当者が「そちらの施設なら、あれでも落ち着くかも……」といって入所にいたったという。まあ、確かにすごい人ではあった。脳卒中による片側マヒで10年以上も寝たきり。
当時は脳卒中で倒れたら、動かしてはいけない、といわれた時代だから、マヒした右手はギューツと固く縮まったまま、右足はふつうピーンと伸びた状態で固まるものだが、この人の場合には、立てたヒザをそのまま外に倒した形で固まっていた。おまけに背中は全く凹凸がなくなったカマボコ板状態である。
いくら問題老人だといっても寝たきりで歩けないのなら、さほど困りはしないじゃないか、と思っていたのが間違いであった。まず、コトバがすごい。入所してくるや否や、まわりの職員や同室者に脅しをかけるのである。ヤクザ映画でおなじみのあの広島弁を2、3倍汚くしたものだと思っていただければいいだろうか。
まずは、自分を甘く見るなよ、というあいさつ代わりなのだろう。気に入らないことがあると、使える左手でベッドサイドにあるものをつかむや、相手に向かって投げつける。こりゃかなわん、というので手の届く範囲からものを遠ざけるのだが、食事を持っていくと、はしやスプーン、茶わんを投げるのである。
投げるものがないと、近づく人をなぐる、ひっかく。私は入浴介助のため、「首に手を回してください」と言って頭を差し出したら、アッという間にメガネを取られ投げられてしまった。やむなく、左手を使えぬように手で抑えて介助しようとすると、こんどはツバをペッベッと吐きちらすのである。
「うちの施設の老人には感謝の心がありません」といってインドにいったAさんほどではないにせよ、どの施設にもAさん的な職員はいるもので、そういうタイプの人は、森田仁之介に対しても嫌な顔も見せないで献身的と言ってもいいほどのケアをするのだが、なぜか当の森田さんからはますます嫌われるのである。
というのも、ときどき「人間、感謝の心を少しは持たなきゃいけませんよ」なんて説教をしてしまうからである。仁之介はこれがよほど気に入らないと見えて、入浴中に怒って介助していた寮母に水をかけ始めたのはいいが、特殊浴槽という寝たままの姿勢で入る浴槽に沈み込んでしまい、助けられて目を白黒させながらも、まだその寮母の悪口を言い続けているのだった。
一方、彼と半年くらいかけて少しずつ気持ちが通じ合う職員も出てくるのだが、それは、“Aさん”とはかけ離れたタイプの人なのである。その1人が主任指導員だった。彼女は仁之介にコップを投げられ、「何をするんね」と恐い顔でにらみつけて近づいて行き、左手を振りあげる仁之介に、「叩くなら叩いてごらん、承知せんよ」とすごんだのである。
その迫力に圧倒されたのか、さすがの仁之介も左手をおろしたという。あとで私の耳に聞こえるように「女をなぐってもしようがないけえの」と、しきりに負け惜しみを言っているのが印象的だったが。
もう一人は看護婦のMさんである。この人はざっくばらんな人柄で、彼を“仁ちゃん”なんて呼んで怒らせているのだが、本人は怒りながらも喜んでいるふうでもあるのだ。「このクソジジイには困ったもんだ」なんて本人の前でも平気でいうのだが、¨仁ちゃん”も、ときどき面会にやってくる奥さんからも、一番人気の職員なのである。
しかしこのM看護婦、ときには“仁ちゃん”をわざと挑発したりもするのである。「やーい、どうせ歩けんだろ、くやしかったらここまで来てみろ」なんて具合である。“仁ちゃん”は顔を真っ赤にして怒っているが、悲しいかな、取って投げる物もまわりにはなく、ツバも届かないのだ。
だいたい、入所老人を“仁ちゃん”なんて呼ぶことはもちろん、こともあろうに老人の障害による歩行不能をひやかしてみたりすることが、福祉施設職員にふさわしいこととはとても思えないではないか。だが、ちゃんと研修で教えられたとおり「森田さん」と呼び、相手の障害のことは話題にもせず関わる職員にほど、彼は心を開こうとはせず、主任指導員やM看護婦と対してケンカをするたびに、人なつっこい笑顔が出てくるようになったである。
【老人の心を開かせるもの】
不思議なことに、心理的に落ちついて笑顔が出始めると、誰彼かまわず暴言と暴力をふるっていたときにはまったく出なかった精神症状が、出現してきたのである。ある朝、私たちが出勤すると、森田さんは電動ベッドのスイッチを自分で使って、ベッドを一番高い位置にしているではないか。
驚いたのは、その上、背中を起こす装置、これはキャッチと呼ばれているのだが、それもほぼ直角近くまで起こしているのである。なにしろ彼の背中はカマボコ板で腰が曲がらず、入所時にはとても普通の車イスには座れないため、リクライニング式の車イスに苦労して座ってもらい、少しでも起こすと「痛い!」と大騒ぎだったのである。
その腰の痛みを我慢して、ベッドの背中さえ起こして高い位置を確保しているのにはもちろんわけがあるのだ。
「洪水じゃ、水がここまで来とる。助けてくれ」 左手でおへその位置を示しつつ、恐怖のまなざしで訴えるのである。
彼は今までの人生で二度も洪水にあっているらしく、何か心理的に不安になったりしたときに、その体験がよみがえるらしいことがあとにわかるのだが、ちょうどそのころ、夏場で、施設の水をまかなっている自前の井戸が枯れ始め、私たちは連日「水が足りない」「水がない」と騒いでいたのだ。
すると彼が「水ならここにいっぱいあるじゃないか、これを使え」と叫ぶのである。そこへやってきたM看護婦が、こう一喝する。「あんたのチンチンがつかっとるような水は汚のうて使えんでしょうが!」すると彼は「それもそうじゃのう」と納得してしまうのだから、面白いというか不思議というか。
そんなエピソードを年に何回か提供しつつ、彼は「問題老人」ではなくなっていく。もちろん、ときどき暴言もツバも吐くが、強烈な個性を持った老人の一人、そしてそれゆえ、強い愛着を感じさせる一人になっていくのである。
私はこの過程を見ていて思った。まごころ、なんてものは通じない、と。いや、正確にはこういうべきかもしれない。ほんとうのまごころが相手に通じるということは、とてもきれいごとじゃないんだ、と。
自分の“まごころ”で相手を変えてやろうという、その“意図”そのものが、老人の反撥を呼ぶのである。そこには、今あるがままのあなたは、本来の人間の姿ではないから早く人間らしい人間になりなさいよ、という、自分の人間観、老人観へ相手を誘導し閉じこめようとする気持ちが無意識のうちにあり、それが老人の心を開かせないのだ。
一方、そんな意図は持たず、つまり、本来の人間の姿、なんて幻想なんか抱かないで、今あるがままのあなた、つまり、それは、暴言を吐き、物を投げつける森田仁之介をそのまま引き受けて、だからこそ半ば本気で怒ってケンカもし、ひやかし、挑発さえするという関わりかたが、相手との共感的世界を形づくっていくのである。
教科書に書いてあることや、研修会で人格者の説く倫理的お説教が通用しない世界が目の前にあった。だけれども、それは何とも自由で、自分自身も“本来あるべき存在”になるために無理しなければならない、という強迫観念からも解き放たれた晴ればれとした世界でもあった。
ある晴れた春の日に、ちょっと時間が自由になった。「森田さん」。私は若僧だから、とても「仁ちゃん」とは呼べないからちゃんと名字で呼ぶ。
「ストレッチャーで庭に出て、いっしょに夕バコ喫いませんか」
「おっ、ええの」
もうメガネを取られることもない。しかし、怖がりだから左手で私の首を痛いくらいしめつけながら、寝たままで移動できる車に乗る。
瀬戸内特有の春がすみがただよう極楽寺山の中腹で、いつもは「わかば」を喫っている彼が私の「セブンスター」を1本ねだって、親指と人差指で持って、うまそうに喫っている。この持ち方は、フィルターのないタバコをできるだけ先っぽまで喫うためのもので、老人にはポピュラーな方法である。なかには、つまようじで剌して喫う人までいる。
「外で喫うと、風があって早うなくなって損じゃのう」と、笑う森田仁之介は、「仁ちゃん」と呼ぶのが似合う、少年のような顔に見えた。- 1998.8-9月 老人につきあわされるケアを
「回想法についてどう思いますか」という質問を受けた。「三好さんが編集してるブリコラージュに書評が載ってたけど、まさか、三好さんが回想法を推薦してるとも思えないんだけど」と質問者。そのとおり。私はあの「回想法」なるもの、そうとう変だと思う。
まず、イギリスなんかに行って研究やら実践やらしてそれを日本に紹介しようなんて態度からして変である。日本のケアに関わりたいなら、どこでもいいから近くの特養ホームにでも1~2年入り込んだらいい。
そしたら、「さあ、今から回想法をしますから集まってください」なんてやり方が全く通用しないことくらいすぐに判るはずである。第一そんな時間とマンパワーがどこにあるというのか。もしあったとしても私はそれは食事や排泄、入浴介助にこそあてるべきだと思う。
老人が過去に帰るのは現在の老いた自分が自分だという気がしないからではないか、そこでかつての自分らしかった時代に戻ることで自己回復を計っているのではないか、というのが、拙著『老人の生活ケア』(医学書院刊)の「暗喩としての痴呆」以来の主張である。
ちょうど私たちが自分を失いかけたときに、旅に出て自己を回復するようなものだから、旅から帰るのを待ってあげよう、とも言ってきた。問題は現在の老いた自分と自分自身がつきあえないという関係障害にこそあるのだから、今、ここの生活をどうつくりあげるかが大切であることも声を大にして訴えてきた。問題は過去ではなくて現在にあるのだ、と。
だからといって、過去を回想しその世界に遊ぶことが無意味だなんてちっとも思わない。しかし、意味があるのは「回想」であって「回想法」ではないのである。「さあ皆さん集まって今から回想しましょう」なんてシラジラしいやり方に乗ってくるような老人なら大した問題はないはずである。
朝の自己紹介で戦争に行った経験を語りはじめるおじいさんがいる。敗戦後、ロシアに抑留されていた話が延々と続き、みんな困った表情である。何しろ週に1回の利用日の朝に毎回この“自己紹介¨を繰り返すのだ。
だが、話の内容が深刻なだけに、司会役のスタッフは途中で止める訳にもいかない。そこへ、1人のお婆さんが「本当にご苦労様でございました」と何とも気持ちのこもった一言。それで“自己紹介”は無事終了。こうした老人の側からの自発的な“回想”につきあってあげられるだけの時間と心の余裕があることこそが求められているのである。
思えば、老人たちはあらゆる場で“回想”をしているはずである。送迎のバスのなかで飛び出す昔話や歌。入浴場面での温泉に行った体験談、お菓子を食べながらのばあさんたちの露骨な下半身ネタまで含めて、自発的回想はいくらでも行われているのである。
運転しながら、入浴介助しながら、お茶を入れながら、それを楽しむだけの余裕が果して介護現場にあるかどうかが問われているのだ。ところが「回想法」の時間と人手を捻出するために入浴も送迎も時間に追われてしまうのでは本末転倒というものである。
風呂の中で1人のばあさんが歌い始めた「ローレライ」に他の人も加わり大合唱となる。「あんたも歌え」と言われた若い寮母がしかたなく老人に教わったばかりの「アリラン」を口ずさむと、これまた風呂中が大合唱。おかげで男性の入浴時間が15分も遅れてしまった。
入所予定のおばあさんは9年連れ添った猫と別れるくらいならこの家で死ぬ、と言い張るのでやむなく猫といっしょの入所になってしまった。猫嫌いの入所者もいるのでこれから飼い方をいっしよに考えていくことになった。
つまり、音楽療法より音楽、アニマルセラピーより猫を飼うこと、なのである。音楽療法をわざわざせねばならないほど、生活のなかに音楽がない、アニマルセラピーをしなければならないくらい生き物を飼う自由がないという生活こそが問題なのだ。
回想法をわざわざやらねばならぬほど、回想するゆとりのない生活のほうをどうにかしろ、と私は言いたい。なにしろ介護職が余裕を持てるようになる方法論はちゃんとあるのだから。私たちが提案している入浴方法もその1つである。
こちらが設定してやる「回想」や「音楽」や「アニマル」ではなくて、老人の回想や歌や猫に、こちらがやむなくつきあわされるようなケアこそめざすべきではないか。そのとき老人は、客体から主体になっているのだから。- 1998.8-9月 投稿と質問に答えて
前号の介護保険特集にいろんな反応を、いただきました。そのなかで「三好さんはケアマネジャーの試験を受けるんですか」というのがありましたのでお答えします。
私は、ケアを知ってる人こそケアマネジャーになろう、と書きました。なにしろ、入浴ケアも排泄ケアもしたことのないケアマネジャーが大量に出来上がるのですから。でも私は受験しません。私は今もっている資格と知識、技術ですらまだ老人のために使いこなしてないと思っています。
ですから新たな勉強や資格を、という発想にはならないんです。受験しないで「あんたはそれでもケアマネジャーか、ケアも知らないで!」と言う立場にいようと思います。もう今さら受験勉強なんて、と思ってる多くの皆さんもぜひごいっしよに「ケアを知らないケアマネージャー」を脅しましょう。
前号の沢田研さんの投稿だけでなく「告発者が好きじゃない訳」への反響を何人かからいただきました。特に大阪で行政と組合活動のなかで差別問題と取り組んでこられた2人の方から「意見交換をしたい」との申し入れがあり、話し合いの場をもちました。
2人が問題とされたのは、まず自らの論敵を「精神障害」になぞらえて批判することの危険性についてで、これは私も不適切、不穏当であることを認めました。少し大げさになるかもしれませんが、ナチスやスターリンが自らの政敵や少数者を葬ってきたやり方と通じると言われてもしかたないと思います。
ただ、私自身の真意については次のように説明しました。私は、論敵を精神障害になぞらえたのではなくて、精神障害という概念を日常的に広げることで精神障害への特別な違和感を、一般的な違和感に拡散したいと考えているということです。
つまり、「メガネをかけているのも背が低いのも身体障害ではないか」という言い方で、身体障害を特別なものではなく、個性のひとつだと考えていこうとする方法論があるように、精神障害もまた、個性のなかに含め共存していこうという考えがあって、ああいう表現を使ったというわけです。
しかし、私は文章のなかでそのことには触れていませんし、一般に精神障害者に対する差別意識が深く存在しているところへこうした表現をすることは誤りであったと思います。指摘に感謝し、関係者に謝罪します。
もう1点は、沢田研さんの意見と同じように、人権を訴え差別をなくす運動に対してどう考えているのか、という点でした。これについては私は次のように考えてきました。進歩主義者が社会の進歩をもたらした訳ではないという事実と同じように、こうした運動が人権を守ってきた訳ではないのではないか、という疑問を私はもっています。
たとえばジャーナリストや大学の教授なんて人は、介護職に対して「人権意識が低い、コトバ使いが悪い」とよくお説教をし、啓蒙しようとします。しかし、実際に老人の人権を守っているのは、毎日排泄ケアをし、お風呂に入れている人ではないでしょうか。
もちろん乱暴なケアをしたり、心ないコトバで老人を傷つけるといった現実もありますが、傷つける立場にいるからこそ人権も守れるのだと思うのです。ウンコ、シッコや風呂から離れだ外野¨から「もっと上品に」と言われることには私は一貫して反発してきました。
「じゃ、あんたやってみてくれ」と言いたくなるんです。もし、「介護の状況をどうにかしろ、人権を守れ」と言うのなら、それは具体的な方法の提案でなくてはなりません。もちろん私たちは、排泄ケアについても入浴ケアについても、できるだけ老人が主体になり、介護職の老人への無意識が体験を通して変化していくような方法を提起してきたつもりです。
そうした現実を変える具体的な方法を提起できない人ほど、意識やコトバの問題としてしかケアを語れないのではないかと思います。そうした、コトバとか人権といった理念の側からのアプローチは、結局、事なかれ主義をつくるだけではないのか、という私の苛立ちが、あの「かかし」を巡る文章でした。
その苛立ちが強すぎて、批判の調子が苛烈すぎたことも、2人を過剰に反応させてしまったことの一因だったようです。理念的なのは無効だ、という主張そのものが理念的でイデオロギッシュになっていることについては私の反省するところです。
人権を守る方法論として、意識を変えるというやり方と無意識を変えるというやり方のどちらが有効なのか、理念が先なのか現実が先なのかという問題は、単なる有効性ということを越えて、人間というものをどう捉えるかということも含まれており、今後も議論を続けるということで、話し合いは友好的に終わりました。
気がつくと、大阪の街の夜景が遠くまで続いていました。私を含め40代と50代の男が3人。こんな問題を熱心に話じ合っているということが、状況からは遊離しているような気がするのでした。3人ともかつて政治や社会運動に関わってきた者でした。果して、思想とは何だったんだろう、という思いを抱いたのは3人のなかで私だけだったでしょうか。- 1998.7月 介護保険・現場の見方、使い方
現場の基本的スタンス
これまで、「ブリコラージュ」でも介護保険について取り上げてほしい、という意見が寄せられていたのですが、私どもは意識的にそういう特集を組んでいません。それは、他の雑誌がやるだろうということもあるのですが、基本的なスタンスとしては、法律や制度がどうなろうと、現場のやることは同じなのだ、ということです。
いいケアさえちゃんとやっていれば、税金からであろうが、保険からであろうが、どこから金がこようがそれほど下っ端の人間には関係ないよと思っています。たとえば特養がつぶれようが、病院が赤字になってつぶれようが、我々は、また別に給料をもらうところを探せばいいだけの話です。むしろ、時代に応じきれないところがつぶれていくほうが、いい人材が流動化して新しいニーズに応えられるということにもなります。
いまのアメリカが好景気なのは、競争に破れた企業がどんどんつぶれていき、人材が流動化し、それがまた新しい産業をつくっていくという循環があるからです。日本で新しい産業が興っていかないのは、既存の企業がつぶれないということも一面にはあります。人材が流動化する、要するに、失業者が増えるということは、それほど悪いことではないと私は思います。
そういう意味では、この世界もその時期にきているのではないかと思っているのです。ですから私は、東京の特養が半分つぶれるという噂が出たときは内心喜んだんです(笑)。だって呆けや寝たきりは入れてくれない、終末は看てくれないなんて、特養にあるまじきところが、地方の2倍の職員数でやってるんですから。
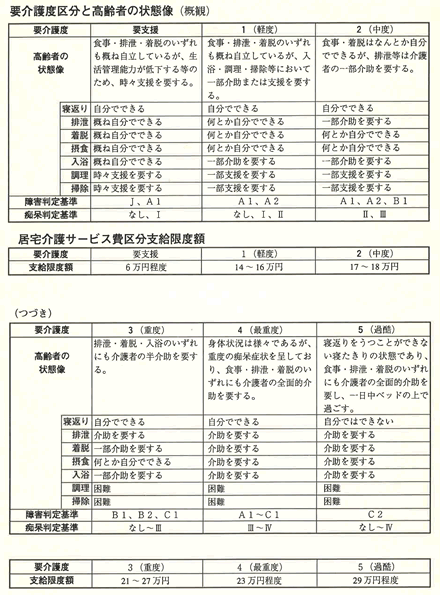
そのうえで、では現実にやってくる介護保険というものをどうとらえるのかということですが、私はひとつは、大変な危機だと思っています。ケアプランというかたちでのみケアが語られ、ケアマネジャーを養成することによって、介護という問題が量のみに還元されていく、という危機です。
介護がせいぜいADLと呆けのレベルで「要介護度」別に分けられ、「支給額」---金というきわめて典型的な数字に換算されていき、質の問題が問われないことになっていくおそれを、大変感じています。これまでも同じだったじゃないかと言われれば、それまでですが、しかし、それが制度化されてしまうという気がしています。
呆けと寝たきりを排除させないチャンス
もうひとつ、私はこれをチャンスだと考えています。つまり、老人ケアというものが国民的課題などといわれ、保険によって賄われるという意味では、老人ケアという分野そのものが社会化されることでもあり、いろいろな人が語りはじめています。たとえば舛添要一という国際政治学者が『母に襁褓(むつき)をあてる時』という本を書き、ベストセラーになっています。
この本はジジ・ババのウンコの話や、母親の介護をめぐって親戚じゅうが人間関係でもめる、というすごい話ですが、国際政治学者でさえも、そういう世界を無視できなくなっているというあたりが象徴的だという気がします。
余談ですが、数日前、岡山の民間デイサービス「ぶどうの家」から電話がありました。民間デイサービスの連絡会ができ、補助金が入るのだそうです。そこで、舛添要一を呼んで講演をやるから、私に対談しろというのです。私は、貧乏をウリモノにしているデイサービスが、高い講演料の人を呼ぶと反発をくうから、やめたほうがいいと言ったのですが (笑)。
まあ、ああいうタイプの人が老人介護の話をする時代になったというだけで、おもしろいかなという気がしないでもありません。先日、新潟県で新しく老健施設ができるので、職員の研修会をやってほしいという依頼がありました。
これまた予算がけっこうあったものですから、熊本の悠紀(ゆうき)会病院の松下明美さんと、福島の桃花林(とうかりん)という老健施設の婦長をやっている永田則子さんを呼んで、3人で3日間講習会を行いました。永田則子さんは老人病院の老人介護病棟にいて、そこから老健施設に移り、今度は50人定員の痴呆ばかりの老健をつくり、この4月1日にオープンしたばかりです。
50人を4つのグループに分け、畳に掘りごたつというやり方でやっていますが、まわりからは、「ボケばかり集めてどうするのか」と言われたそうです。それに対して彼女が、「なに言ってるんですか。介護保険になったら、ボケでないと金はとれないんですよ!」というと、すぐ納得したそうです(笑)。
これまでボケや寝たきりを排除してきたところが、金に誘導されてというのも情けない話ですが、やっと、いちばん困っている人のために乗り出さざるをえないという、介護保険というものはそういうことに使えるチャンスではあるなという気はしています。
制度は現場が使いこなすもの
どんな法律でも制度でも、完璧なものはありません。絶対に問題は出てきます。たとえば、私たちが関わっていて、ほんとうに大変なのに認定ではどこにも当てはまらないというようなケ-スが必ず出てくるでしょう。そのとき、現場の私たちが介護保険をどう使いこなすかということをやらなければいけないだろう、と思います。
これまででもそうですね。たとえば、寝たきり老人になるとそれなりに援助がありましたが、寝たきりにならないでがんばっている人には何の援助もないという状況がありました。そういうなかで「この人の危機はどう突破するのか」というとき、我々はちゃんと“寝たきり”にしました(笑)。「寝たきり」にはきちんとした定義がないわけですから、「寝たきりです」ということにすればいいだけの話です。
10年くらい前でしょうか。「寝たきり」とは「日中3分の2以上臥床している65歳以上の人」という定義でしたから、家でテレビを見ている人はみんな「寝たきり老人」とすれば、ちゃんと制度が使えました。また身障手帳なども、2級なら車イスが支給されたりして役に立ちますが、歩けるとなると3級に認定されてしまい、ほとんど役に立ちません。
ある脳卒中の人を訪問したとき、私か「歩けますか」と聞くと、その人は保健婦さんの顔をじっと見ているのです。保健婦さんは「あっ、今日の先生は歩いていいのよ」(笑)。「何ですか?」と尋ねると、「じつはこのあいだ身障判定に行ったんです」とのことです。歩くと2級と認定されないので、身障の判定のときには「今日は歩いてはだめよ」と言って2級をとってきた、という話でした(笑)。
つまり、法律の不備をいかに我々の知恵で埋めるかということですから、介護保険でも、こういう知恵を、現場のケアマネジャー、あるいはケアマネジャーをつっつくまわりの人たちがどれだけもっているかということが大事だと思います。みなさん方のような人は、どんどんケアマネジャーの資格を取って、そういうやり方をしてほしいと思います。
「ケアマネジャー何万人養成」と大騒ぎをしていますが、しかし、それは何かというと、結局は寝たきりとボケを結果としてとらえ、これを段階化してケアプランで数字化するというものです。「このケースは29万円か、16万円か」というふうに値踏みをするというやり方になるみたいです。内容としては、せいぜい、デイと訪問の組み合わせくらいしかないんです。
なぜ、いま、この人が寝たきりなのか、なぜ、こんなにボケ症状が出ているのかという原因を考察していくとか、あるいは、いまはたいしたことはないけれど、半年後にはこうなるだろうと予測していく、それがケアということであり、そこで質の問題-どういうケアをすればいいのかということが出てくるわけですが、たぶん、そこはほとんど語られないまま、ケアマネジャー養成が行われていくだろうと思います。
今こそ問われる介護とは何か
これに対して、ケアマネジメントを逆手にとってこの中身をなんとか……と考えておられるのは竹内孝仁先生くらいでしょうか。残念ながら、全体で何万人と誕生するケアマネジャーの大半は、入浴ケアなど一度も体験したことがないというような人たちで、そして、その人たちがケアプランを立てるということがどんどん出てくると思います。
つまりそれは、ボケの問題行動や寝たきりを結果としてだけとらえて、その後始末をどうするのかというとらえ方で、それはケアではないだろうと思います。もちろん、なかには、結果としてそれしかしようがなかったというケースはいくらでもありますが、しかし大半のケースは、実は生活に問題があり、どんな生活をしているのか、生活をどうっくり変えていくのか、あるいは、どういう人間関係のなかにいて、その人間関係をどうっくり変えていくのかということのなかで、たとえば痴呆で最重度といわれているケースが、あっという間に問題がなくなるというようなことは、私たちは、素人なりにいくらでも経験してきたわけです。
それをやらないで、「最重度23万円」とか、「苛酷、29万円」なんてやり方をするのはどんなものかという気がします。そういう意味では、いまこそ、介護とは何かということがいちばん問われている時代だろうと思っています。
何が必要か、から認定を決めろ
たとえば痴呆性老人の場合、在宅で看ていこうと思うと、まずデイサービスを毎日使うということは前提です。週1回、2回ではほとんど役に立ちません。そして土日は、ヘルパーさんが午前・午後に1回ずつ来て援助をする、というくらいのことをちゃんとやる。
私は必ずしも24時間介護が必要とは思っていません。夜ぐっすり眠るような関わり方を昼間しっかりやっておけば、わざわざ夜寝ているところにオムツ交換にやってきて不眠症にするなんてこともなくなるわけです。もちろんそこまでやらないといけないケースもありますが、しかし、今いわれているほどではないと思うのです。
デイサービスを毎日使おうと思うと、たとえば「介護保険制度の要点」(あけび書房)の費用を参考にしますと、約12万円くらい費用が必要になってきます。土日・祝日にヘルパーさんに午前・午後1回ずつ、各2時間来ていただくと、これまた12万円くらいかかる。
そうすると、1ヵ月24万円くらいあれば、この人の生活はなんとか支えられる。 24万円というと、要介護度判定でいえば 「3」です。「要介護度3」というと「排泄、着脱、入浴のいずれにも介護者の半介助を要する」ですから、食事は自立していてもいいけれども、排泄、着脱、入浴は半介助ということにしておこう、というふうにすればいいんです。そういうやり方がどうできるのかということが、この制度をいかに使いこなすかということだろうと思っています。
私は、わずかながら利用料をいただき、少人数・小規模でみていこうという自発的な、ボランタリーな民間デイをどんどんつくろうということをやってきました。民間デイの人たちが、いま厚生省と交渉したりして、「介護保険の指定施設に」ということをやっていますが、利用者はほとんどがボケの人で要介護度「4」にランクされるような人ばかりですから、もし彼らのところにこれだけのお金がおりてきたら大儲けという世界だろうと思います。
だいたい、公的デイの3倍の仕事をしていますから、おそらく笑いがとまらないという世界になるのではないかという気がします。その方法論を施設も病院も学べばいいんです。ボケを呆けのまま、寝たきりを寝たきりのままケアすれば大変ですが、ボケを落ち着かせ、寝たきりを少しでも自立させることさえすればいいんですから。そんな方法はちゃんと私たちはもっているんですから。
県や厚生省が監査に来ても、老人一人ひとりと書類とを照らし合わせたことなどありません。仮にそんなことがあったとしても。 「いや、今日は興奮して、ずいぶん調子がいいですね」と言っておけばいいだけです (笑)。ですから、いい仕事をしてたくさんお金をもらうための、現場の知恵として大いに使えばいいと思うのです。
その意味では、重度の人にどんどん入ってもらい、どんどんよくして、ボーナスをたくさん出せるようにする。そんなやり方ができるという意味では、私はこの介護保険導入というのはチャンスだと思っています。ただ、1割負担が減らないのでちょっと申し訳ないんだけれど。ですからこれからは、評判の悪い病院から、呆けさせられたり、寝かせきりになっている老人をどんどん引き受ければ経営は安定です。
ケアを知っている人こそケアマネージャーに
ぜひ、ケアを知っている人がどんどんケアマネジャーになってください。医師会は「ケアマネジャーの中心は医師がなるべき」といい、看護婦協会は「看護婦がやるべき」といっていますが、とんでもない話です。介護などというものに興味もなかった医師が中心になってやれば、恥をかくだけですし、安静看護は知っているけれど介護は知らないという看護婦がケアをすれば、老人は駄目になっていくばかりです。
「どの職種が」ということではないと思います。興味のあるお医者さん、いい看護婦さんはたくさんいます。素人を含めていろいろな職種で、ああでもない、こうでもないとやりながら、やっとケアらしきものが成立するというのが、いまの状況です。介護については、「医者だから」「介護福祉士だから」などといえる、それはどの経験をもっている職種はどこにもないだろうと思います。
経験はあるけれど素人だという人と、専門職だけど老人のことはよくわからないという人たちが集まって、ワイワイ、ガヤガヤやりながら、ケアをつくっていくというのがいまの状況かな、という気がしています。
それから、大きな施設からだんだん小さい施設へという話もありました。 100人の老健でくたびれ果てているという話もありましたが、ほんとうにくたびれ果てますよね。私は、50人でも一人ひとりのことを頭に入れてケアするというのは神技だと思っています。
たとえばお風呂に入れるときでも、この人は最近どういう状況なのか、家族と面会がなくて寂しがっているから冗談でも言って笑わせようとか、最近は体調が悪いから観察しようとか、一人ひとり個別に対応できるには50人で神技、100人となるととても無理で、完全に作業です。それで「個別にやれ」といっても無理な話です。
ですから、もっと小規模でやっていこうということは大いにけっこうなのですが、この間、仙台でグループホームの全国大会が開かれました。そこに参加した人から「ブリコラ-ジュ」に投稿があったのですが、参加してみてどうも違和感を感じたというのです。 (ブリコラージュ5月号参照)
小規模のグループホームをつくるにはどうすればいいか、みんなその運営の仕方を学んで帰っていく。そこには、なぜ小さいほうがいいのかという初心みたいなものがなくなっていて、経営の一環として「これからは小規模のほうがいいらしい」ということで参加している人がほとんどみたいだった。
そういう発想で小規模の施設をつくったら、結局、老人をもっと狭いところにとじ込めてしまって、人間関係はますます煮詰まるばかりではないか。だから、小さいことがいいのではなく、いいケアをするという過程のひとつに、規模の問題が出てきているというふうに考えなければいけないのではないか、という内容でした。
自発的な民間デイサービスみたいなもので、ボケや寝たきりの人たちを落ちつかせるという実践をしてきたところが、介護保険を使って「こんなに金をくれるのか」という時代がくるとしたら、我々の活動が時代を先取りしていたということになるのだろうという気がします。もちろん、その先どうなるのか、小さければいいというものではないということも含めて、次の課題がまた現れてきているのかという気もします。
(1998.4 とうきょう地域ケア研究会セミナーでの講演より)- 1998.6月 差別告発者が好きじゃない訳
「肩たたき体操をやってると『障害者差別の歌を使うなんて』と言われたんですけれど、三好さんはどう思います?」 こんな質問をいただいた。
肩たたき体操とは生活リハビリ体操のなかで、体幹のひねりと座位バランスを目的として行っているもので、「山田のかかし」の歌に合わせて身体を動かしているのだが、その歌が、「片足のない人に対する差別だ」と言うのだそうだ。
私の意見ははっきりしている。これは障害者差別の歌ではない。なぜならこの歌は、かかしの歌だからである。私にとってはそれ以上の説明はいらないと思うくらい単純で自明のことだ。これは、かかしに対する好意的ひやかしの歌であって、それ以外の歌だというのにはどう考えても無理がある。
ある私の尊敬する人格者が講演で「制度だけつくっても中身がないんじや片手落ちだ」と語ったところ、「片手落ちというのは片側上肢欠損者、切断者に対する差別だ」と言われたことがあるそうだ。やれやれ、と私は思う。
“手”にはいろんな意味がある。上手(かみて)、下手(しもて)というのは方向を指すし、名手と言えば技術や芸を意味する。手を加える、というときの手は世話のことだし、手を切る、とは交際を断つことである。両てんびんの左右の棹もまた、手と呼ばれる。
片方にのみ重いものが置かれていて片側の棒が垂れ下がった状態を、片手落ちという。つまり、バランスが崩れている状態のことを言うのだ。こうなると、差別の告発が自らの無知を告白しているに過ぎないと思うのだけれども。
無知だからといって批判しているのではない。私なんぞは、本を出すたびに無知を指摘する手紙をいただいている。つい先日も最新刊の『身体障害学』のあとがきのラテン語のスペルの間違いを遠藤尚志さんから手紙で教えていただいた。それにしてもラテン語にまで詳しい遠藤STとは何者なのか。ま、神学を専攻していたと聞いたこともあるから当然なのかもしれない。
問題は無知にあるのではない。私はこういうことを言う人は、実際には障害者とつきあってない人にちがいないと思っている。だって「山田のかかし」や「片手落ち」というコトバから彼らは身体障害者を想い起こしてしまうのだが、そのときの障害者とは、抽象的な障害者でしかないだろうと思うのだ。
たとえば、悪ガキ共が何人かで、片足切断者に対して「山田のかかし」を聞こえよがしに何回も歌ったりすればこれは問題であろう。なぜなら、その人は他にもいろんなその人らしさをもった存在なのに、ことさら身体の障害という差異の部分だけを意図的にとりあげてその人を限定しようとしているからである。
ところで、「山田のかかし」を差別だと言う人たちこそ、一人ひとりの身体障害者を、身体障害という差異の部分だけで意識している人たちなのである。だからそこに過剰に敏感になっているのである。それこそ、身体障害者を、身体障害という差異のみで限定してしまおうとする暴力であり差別ではないだろうか。
障害者とのつきあいが浅いとき、障害という部分ばかりに意識がいってしまうということはあろう。だが関係が深まれば、それはどんどん部分化し、あ、そういえばあの人片足が不自由だったよね、なんてときどき思い出すようになることこそ、差別を無化していくことではないのか。
多くの差別告発、それも当事者によるのではない差別代理告発者こそ、じつは、障害者を障害という部分でしか見ていない差別者ではないのか、というのが私の意見だが、もっと率直に言わせてもらうと、どうもこういうタイプは、一種の精神の病なのではないかと思われる人が少なくない。
「オイ、オイ、そこまで言うか」と言われるかもしれないが、この際、自分の出している雑誌でもあるから、言いたいことを言っておこう。こうした「正義」を振り回して他人を啓蒙したがる人は、何か生活に問題をもっているに違いないと私はにらんでいる。
だって、どう考えたって彼らの言うことは不自然で無理があるし、実際に会っても違和を感じるのである。精神病の最終的診断根拠とはこの違和感、そらぞらしさしかないと言われているのだが、だとしたら彼らこそ精神障害を有しているのではないか。
「そりゃ、違和感を感じているお前のほうが健全であるのが前提だけどもね」 ハイ。
- 1998.5月 怒れる老人が少なくなった訳 ~個人主義は排他主義~
「荒れる老人が最近少なくなったと思いません?」 介護の仕事を長くしてきた女性が私にこう話しかけてきた。「そう言えばそうですね。昔は怒りを周りの人みんなに向けていて暴言、暴力を振るう老人がどの施設にも病院にもいたもんですけどね」。「薬を盛られてるからおとなしくなってるのかしら」。
“薬を盛る"という言い方もすごいけれど、老人にとっての睡眠剤とか安定剤は“毒”であることが大半だから、私たちの間では自然にこういう表現になる。 「いや、昔だって薬を使うところは使っていたし…」 「介護の研修なんかも多くなって関わり方がうまくなったのかしら」 「いや、昔だってちゃんとやってたところはやってたし、今のほうがわけの分からない人がどんどん介護の世界に入ってますからねえ」 「なんで老人がおとなしくなったんでしょうねえ、時代と関係があるのかしら」
私は20年以上前の特養ホームの職員の時代を思い返していた。いくつかの病院と施設を前代未聞の“問題老人¨として追いだされたあげく、福祉事務所の担当が「おたくの施設ならひょとして落ち着くかも…」と言って紹介してきた森田仁之助(仮名)さんのことである。
脳卒中によるマヒで森田さんの右上肢はこれ以上は曲がらないというくらい拘縮していた。右下肢はふつうピーンと伸びて固まるのだが、彼の場合は膝が曲がり横に倒した“屈筋共同運動”のパターン(新刊「身体障害学」参照)で固まっていた。
マヒした手足は緊張したり興奮すると拘縮しやすいのだが、彼の拘縮がひどいのも、その興奮によるところが相当あるはずである。なにしろ、ストレッチャーで入所した途端、周りの全ての人に毒づき始め、ベッドに移ってもらうために介助しようと近づいた私のメガネを取るやホーンと投げつける。やむなく一人が手を握っているすきに介助すると、ペッペッと唾を吐きちらしたのである。
その森田さんのその後の話はまた別の稿に譲るとして、当時はとにかく怒りを周りに発散している老人がいた。もちろん介護は大変なのだが、そこには“怒る”という自己主張があり、“自己”があった。だから私たちも“自己”をぶつけて関わり、関わる喜びすらあったように思う。
最近の老人の荒れ方は少しちがう。同じ“問題老人”でも、外向的ではなく内向的なのである。自分の世界に入り込んでいる。その世界に私たちが介入しようとすると怒ることはあるのだが、怒るという形も含めた自己主張があまり感じられないのである。
同じ“問題老人”でも、森田仁之助さんには、怒るという形での自己肯定があったのに対し、最近の老人には、自閉という形での自己否定を感じるのだ。これは彼女が言うように、時代と関係があるのではないか、と私は思う。森田仁之助さんのような明治生まれの人が教え込まれたのは家族主義であった。
“身内”はその言葉どおり、身の内なのである。その身内と世間に(この“世間”という言葉も面白い。世の間、つまり実体的な社会ではなく、目に見えない人間関係を指している)のために人は生き、老いればその身内と世間が面倒をみてくれるはずであった。
少なくとも〈老い〉は大家族主義の中で尊敬を得られるものだと思われていた。ところが戦後、価値観は転換した。身内に扶養義務はなくなり、実際その力を失った。老いて障害をもって病院や施設に追いやられた森田仁之助さんたちにとっては、勝手に変わった社会の側こそが悪いのである。それに対して彼は暴言、暴力で対抗する。“自分はちっとも悪くないのになんでこんな目に合うんだ!”と。
いま老いを迎えているのは戦後の新しい価値観を受け入れることのできた世代である。彼らは家族主義にとって替わった個人主義を受け入れ、戦後の経済成長を担うべく、田舎の明治生まれの両親を置いて都会に出、核家族を形成してきた。その個人主義は資本主義の成長には都合が良かったが、〈老い〉とは相入れないものだった。親の老いからも逃げ続けたこの世代がいま、自分自身の老いに直面した。
個人主義とは排他主義の別の名であるという。その排他主義が、自分のなかの〈老い〉という他者性を迎えたとき、自分自身を排することになっているのではないか、なんて少々むずかしい仮説を本に書かせてもらった。岩波書店から出版された「現代日本文化論第5巻・ライフ・スタイル」(2,300円十税)に所収されている。シリーズ全体の編纂は河合隼雄氏、5巻は谷川俊太郎さんと河合隼雄さんの共同編集。谷川さんの紹介で私なんかに依頼が来たらしい。興味のある方はご注文を。
- 1998.4月 「人間」が具体性を取りもどす場
「病気を見ないで人間を見よ」とは、現在、医療者に対してよく言われるコトバである。ところが、医療の草創期には、今とは逆に、「人間を見ないで病気を見よ」と教えてきた。それが、よい医療者だと言われてきたのである。
この、医療を巡る言説の、正反対の違いをもたらしたものは、この問の「人間」というものについての見方の変化なのである。
◇
『解剖の時間』という本がある。養老孟司と布施英利の共著で、「瞬間と永遠の描画史」というサブタイトルがついている。(哲学書房、1987年、3,200円) その本のいちばん最初のページに、解剖図が登場する。 1685年に出版された、ビドローという人の「解剖学」の中の解剖図だという。不思議なことに、この解剖図の右下あたりにハエのとまっているのが、ていねいに書きこまれているのである。
当時は写真はまだなかったから、こうした解剖学的知識を広く知らせるには、ていねいなデッサンが用いられており、この図もずいぶんリアルなものだが、それにしてもなぜ八工なのだろうか。
◇
現在でも学生に解剖図をデッサンさせることは行われているが、もし学生の1人が、死体にとまっているハエを描いたとしたらどうだろう。教官はこう言って叱るだろう。「目の前のものをそのまま書けといってるんじゃない。人体の構造を覚えるためのデッサンなんだから余計なものは書かなくてよろしい」と。
もっとも現在では、死体が腐らぬよう、強い臭いの薬品に漬けられているから、寄ってくるハエはいないだろうが。 だが17世紀後半の学者の“目の前のものをそのまま”書くという姿勢は、ハエだけにとどまらない。この図をよく見ると、光の当たっている所は明るく、光の当たらない部分は暗く描かれているのである。
光は、上方やや左側から当たっていることが容易に判る。 現在の学生なら、少しくらい暗くて見えなくても、ちゃんと光が当たっているものとして描くだろう。当然ハエなんか、最初から描こうとも思うまい。 この17世紀後半の学者の「目」と、現在の私たちの「目」の差は、いったい何か。
◇
どうやら私たちの「目」は、目の前のものをあるがままには見なくなっているらしい。目の前の人体には光と影の部分かちゃんとあるのに、影にも光を当て、“本来の姿”を見ようとする。ハエがたかっているのを見ていてもそれはないことにして、人体の“一般的な姿”を見ようとする。
この目の前の現前性から、一般性、普遍性へと抽象化していくことが、人が知識を手に入れていくことだったのだろう。それは決して悪いことではないどころか、それが科学の進歩をつくりあげてきたのは言うまでもない。
医者が目の前の患者の一回性、個別性にのみ目をうばわれて、過去の経験から得た知識をあてはめて診断、治療することをしないでいたのではそもそも医療も学問も成りたたないからだ。 だが私たちは、より普遍的なもの、より科学的で学問的なものを追い求めるあまり、目の前のあるがままの姿を見られなくなったのではないだろうか。
見ないことこそが科学的で学問的なのだとさえ思っているのではないだろうか。だから、かつてこの欄で書いたような、目の前の老人の表情や家族の涙ながらの訴えは、見、聞こうとせず、セミナーでの権威者の最新理論ばかりを追いかけるなんてことが起こってしまう。(本誌1995年8月号地下水脈「『オムツ外し』なんてやめよう」、新刊の『老人介護問題発言』に「情報社会が老人をダメにする」と改題されて収録)
◇
かつて「人間」とは、特定の人種と民族、個別の職業と階層、個別の服装をした、目の前の具体的な人間のことであった。だから、そうした人種や貧富の差によって人間を区別せず、“病気”を見るべきだ、と教えられたのだ。
それに比べて私たちが使っている「人間」というコトバの抽象性はどうだろう。人間愛を唄うヒューマニズムは美しいが、そこにイメージされる「人間」とは、特定の人種でも民族でもなく、男でも女でもない、普遍化され一般化され平均化された抽象的理念でしかない。
ヒューマニストや、同じ抽象的人間観を基礎とする「人権」主義者たちのお説教が現場にさっぱり通用しないのも当然である。
◇
介護現場とは、抽象化された人間の具体性、関係性をもう一度取り戻していく場でなくてはならない。だって現場では、「人間」とは目の前の具体的なジイさんやバアさんのことなのだから。この人間観は強い。
その具体的人間に触れることなく「介護福祉士」だの「ケアマネージャー」なんて資格取得に走ってしまう人たちが“介護を知らない介護士‥ケアを知らないケアマネージャー”になってしまうのは当然である。まず現場の臭いを嗅ぎにいけ。
◇
ミッシェル・フーコーが人間主義を鋭く批判したのはその抽象性なのである。
- 1998.3月 暗順応していく目
1998年の初仕事は栃木県塩原町の特養ホーム「生きいきの里」の施設内研修であった。96年の3月末に、開設にあたってオープニングセミナーが開かれ、大勢の参加者があったから読者のなかにも、その後の成り行きに注目されている人も多いと思う。私もその1人である。
まずは園内を案内してもらう。ドーム状の高い屋根の多目的ホールを中心に、浴室と3つの居室棟が枝のように伸びている形で、それぞれの棟にキッチンと小さな居間のようなスペースが設けられているのだが、ほとんどの人はホールに集まっていて、居室棟はカランとした印象である。
やむなくホールに腰を落ち着けてみることにしたが、せわしなく園内を動き回る1人のお婆さんを除くと、残りの人は椅子やソファに、ただ座っているだけに見える。玄関脇のデイサービスは別だが、ここの職員は老人にあまり“仕掛ける”ことをしない。行事もほとんどないと言うし、グループ活動めいたものもやっている様子はない。
ときどき、職員の誘いに応じて席を離れるのは、トイレとお風呂らしいのだが、風呂の順番も特に決まっているふうでもない。やがて夕食の時間になる。ホールの一角に炊飯器と鍋が置かれ、ご飯、味噌汁、おかずが盛られた順にテーブルに配られる。
一人ひとりの名前のついた膳に、大盛りだの中盛りだの、キザミだのおかゆだのと細かく分別していく形ではないから仕事は早い。あまり飾りっ気のある食事とはいえないが、ご飯も汁も冷めたりはしていしていない。
◇
半日ホールにいると、少しずつ老人が見えてくる。そしてテーブルごとに自然に形成されたグループの性格のようなものが判ってくる。こちらは園内の知的会話のできる人たちのグループらしく、テレビのワイドショーを見つつ何やら解説し合っている。こちらは、常にかまって欲しくて大声を出し続ける婆さんに「うるさい」と言いながらも相手をしてくれている人たちのテーブル。
向こうは、放つておくとすぐ居眠りをはじめる人たちに、ときどき職員が刺激を与えにやってきているらしい。こっちは洗濯物をたたむために待っている人たち、という具合に。最初は、所在なげに座っているだけに見えた老人たちが、実は、その¨所在”そのものが意味を成しているらしいことが見えてくる。
ちょうど、映画館のような暗い場所に入ったとき、最初は何も見えない暗闇だが、うすぼんやりと回りが見えはじめ、そのうち遠近を伴って立体感が感じられていき、さらに、それまでの強い光に幻惑されていた目に、この薄明かりが心地よくなっていく、そんな感じである。
生理学で、「暗順応」と習ったなあ。老いという名の暗部に、私の目がようやく順応していったようなのだ。
◇
この施設を見学に来た人は戸惑うのではないだろうか。名の知れた施設でやっているグループ活動や、なんとか療法なんていう、“光”に慣れきってしまった目には、光の乏しい世界と映るのではないだろうか。ここではそうした、職員の側からの意図的なアプローチは、むしろ意識的に排除されているように思える。そして、そうした意図性のない世界こそが生活だろう、と主張しているかに見えるのだ。
ただ、ここでは、食事、排泄、入浴についてだけは、むしろ厳格に意図的になされている。食堂での職員と一緒の食事、トイレでの排泄、家庭用1人浴槽での入浴といった生活の基本をあたりまえに行うことは最初から行われていて、職員からは、「老人が嫌がっているのにトイレ誘導するのはどんなものか」という質問が出るくらいである。
当然ながらこうした新しい方法論は、従来の安静看護を基本としたケアが、老人の生活を不自然にしてしまったことからの反省からはじまっていて、放っておくと、“オムヅといった不自然に陥ってしまうのを避けるために、意図的に“自然”を取り戻すためのものである。
だが、意図的に何かを行うことはまた別の形の“不自然”になりやすいということは知っておくべきだろう。 ともあれ、ここには、そうした不自然さの恐れのある意図的ケアは、食事、排泄、入浴といった基本的ケア以外にはほとんど見られない。
テーブルの老人が、タバコを吸っている(喫煙率は高い!)その横で、職員もスパーッとやっているのが印象的である。何しろ職員には決まった休憩時間もないのである。田舎の老人たちの生活に定められた休憩時間がないように。気がつけば、ストレッチャーがホールを横切って浴室へ往復する光景も、オムツ交換車が部屋から部屋へ行き交う姿もない。見学者の何人がそのことに気づくだろうか。
◇
全てのベッドが、低床、幅広タイプというのが、「生きいきの里」の、“目に見える”特徴の1つであった。職員と一緒に何人かの老人のベッドの高さや向きの調節、移動用バーの取り付けを行ったが、幅広のベッドだからこそ起き上がりが自立している人が、少なくとも5人はいるはずである。
幅広ベッドによる自立度の向上と介護量の低減はめざましいものがある。これだけでも他の施設が見習ってくれれば、と思った。あの“自然さ”を見習うのはとてもむずかしいけれど。
- 1998.3月 徳永進◆三好春樹 対談
~ケアもコミュニケーションもブリコラージュ~ 徳永 私は医療部分とか、介護の部分には、意外と演技力、脚本力がいるなと思うんです。がんの末期、患者さんは死なれるわけでしょう。私は死ぬのだったら、ぱっとひと花咲かせて死んでいくんや!と思ったりするわけです。死を涙ばかりで受け取るのは本人もつらいし、家族だって、「ウウツ……」というのも、だんだん飽きてきますよね(笑)。
型にはまったなかで老いたり、死んだりすることに、みんな飽きてますよ。「この人にはどんなことが似合うだろうか」というふうに考える脚色力がもう少しいるなと思います。
三好 早川一光先生の講演を聞いていて、この人は死の演出家だなという気がしたことがあります。ことばは悪いのですが、一人ひとりの最後のドラマを本人と一緒になって、いかにでっち上げるか…。
徳永 いいですね。“でっち上げる”時期がいるんでしょうね。でっち上げて後悔して、少し違っ・たものになっていくのでしょうが、とりあえずはでっち上げる。そうすると、それのウソさに気がつく。
三好 自己満足だった、というようなこともある。
徳永 自己満足は多いですね。私たちは、おばあちゃんを海に連れていったことがあるのですが「死ぬ前に日本海が見たい」、「海がもう一度見たかった」というような本があったので、「よし、おばあちゃんは海が好きにちがいない」と思ったわけです。
「おばあちゃん、これ日本海だよ川と話しかけるのですが、「わかっとります」とノツてこんのです。最後にみんなでビールを飲むのがいいと書いてあったから、「さあ、ビールを飲もう!」と言うと、おばあちゃん「ああ、にが~」。看護婦さんだけ、グビグビ飲んでました(笑)。
部屋の人から「いいね、楽しかったでしょう」と言われて、「ええ、看護婦さんが楽しそうでした」(笑)。自己満足というのは、誰もがたどらんといかんところですかね。
三好 「自己満足もできないようじゃ……」というところもありますから、せめて自己満足でも、と。
徳永 そう。自分たちの自己満足で終わることもあるのだけれど、ディレクター性をもってやっていくというのはいいなと思っています。
【コミュニケ-ションを形つくるもの】
三好 痴呆の人のケアなどでとくにそうなのですが、その場でその人の顔、表情で自分がどうふるまうのかということが自然に出てくるときはケアがうまくいくんですね。あらかじめ「この人はこういう痴呆だから、こうすべき」というふうに考えて関わると、ちっともうまくいかない。それが何もなくて、その場でぱっとやっちゃうとうまくいくことがすごく多いんです。
徳永 医療の場もうまくいっているときは、思いがけない仕草のなかでお互いが動き出すような気がします。あれは何でしょうね。
三好 たぶん人間関係でいちばん大事なものは共感ということだとすると、共感というものはおそらく言葉ではないでしょうね。むしろ言葉が邪魔するような世界じゃないかな。
徳永 この間ホスピスの看護婦さんに会ったら、こんな話をしてくれました。理容院の人に洗髪をしてもらったら、耳の押さえ方や力の入れ方が違う。顔を拭くのもエステの人にやってもらうと、やはり上手だというふうに、町のプロに来てもらって、看護婦さんたちもいろいろ技術を身につけるのだそうです。
患者さんたちに喜ばれるのだけれど、「でも、私はやっぱり言葉だと思うんです」とその看護婦さんは言うのです。「どうぞ、ゆっくり食べてくださいね」と食事を出すとき、その気持ちを受けて「ありがとう」といわれる。言葉によってまず伝達されるから、ホスピスの武器のひとつは、言葉によるところが大きいということでした。たしかにそれはあるかもしれません。
でもそれは、言葉にのせられていった看護婦さんたちの気持ちが流れているものだから、言葉だけではない。いま言われると、そんな気がします。言葉も、心がこもっているものはグツときますね。
三好 すごくいい表情で何か言えば、相手にはちゃんと伝わるわけです。失語症の人にしろ、言語的コミュニケーションができない痴呆の老人にせよ、そういう意味でのコミュニケーションの豊かさはいくらでもできるのだけれど、どうもぼくらは言葉に頼ろうとするところがある。
しゃべらないコミュニケーションの仕方を学ばなければだめだという気が、すごくしているんですね。たとえば、特養ホームの食堂を見ていると、みんな言葉はちゃんとしゃべるんですよ。「○○さん、ゆっくり食べていいのよ」。次の職員がくると「ゆっくり食べていいのよ」、また次の職員がきて「ゆっくりでいいのよ、急がなくていいから」というのです。これは早く食べろと言われているようなものですよ(笑)。
おまえはゆっくりでみんな困っているのだけれど、一応、気にしていないよということを、みんなが言うんですね。ほんとうにいい介護は、何もいわないことだという気がするんです。どうも言葉に偏りすぎているという気がすごくします。
徳永 言葉でないものが入ってくるわけですね。目からもきます。「おはよう」といわなくても、目から、仕草から何かが流れますものね。
【老人ケアはブリコラージュ】
三好 老人介護の世界の特徴は、普遍化ができない、理論化ができないということです。効率的にやろうと思えば思うほど、うまくいかないのです。
世の中はどんどん進歩して合理化して、科学的になってきているのに、一人ひとり、ベッドの足の高さを決めたり、頭の向きを変えたり、ポータブルトイレの高さを調節したり、そういうことをやっているのは、時代に逆行している、遅れているという気持ちが老人介護の世界に入った当初のぼくにはありました。
徳永 いいね、それ。いまも遅れてる(笑)。
三好 レヴィ=ストロースという文化人類学者がいます。彼が『野性の思考』の中で、ヨーロッパ的な合理主義の立場から、未開や野蛮は遅れているというのは、ヨーロッパの一方的な見方にすぎないと言っています。それぞれに固有の文化があるのだと彼は言うのです。
レヴィ=ストロースは、近代的といわれる合理主義にのっとらず画一的にやるのではなく、目の前にある材料で頭のなかで組み立てて、その場でっくり上げてしまうことを指して「ブリコラージュ」とよびました。
この言葉を知ったとき私のやっている老人介護の仕事は、遅れているのではなく、じつは近代の問題を乗り越えていくような視点をもっているのだということに気がついて、火花が出たような感慨がありましたね。
徳永 身体あたりがいちばん“ブリコラージュ”ですね。食べてウンコが出て、シッコが出てということは、変えてみようと思っても変わりませんよね。目からごはんを入れてみようかと思ってもムリ。この身体の構造は、ほんとブリコラージュです。
やせ症の子がいるわけ。やせ症の子は、アイスクリームとか、そんなものばかり食べて、骨付きのものを噛むことを拒否しているのです。ウンコを否定するんですね。それで、治療のひとつとして、自分のウンコを見ることをするのです。ウンコをじっと見て、それから流す。なんなら新聞紙にとってよく見る(笑)。近代はこれをしなくなった文化ですよね。
 三好 カニでも肉でも、しゃぶって食べるものは何でもうまいですよね。しゃぶっているときは、いわば生き物として食べている実感がすごくあるでしょう。
三好 カニでも肉でも、しゃぶって食べるものは何でもうまいですよね。しゃぶっているときは、いわば生き物として食べている実感がすごくあるでしょう。
徳永 なるほど、カッコいいな(笑)。
三好 しゃぶるのをやめたということは、自分が自然であることを拒否していて、だからウンコだって拒否するわけですよね。
徳永 そうそう。そういう意味では、老人の場面では拒否がない。
三好 そういうのを拒否してきた人は長生きできませんからね。ボランティア刑というのがあります。刑務所に入る代わりにボランティアをする。そうすると「人から、ありがとうと言われたのは初めて」というような感じで、暴走族をやっていた人が感激して更生するというような話があるのですが、あれはおもしろいと思うんです。
老人がもっている治癒力というのがあって、老人というのは、自分が生きていることをずっと肯定してきた人だちなんですね。暴走族をやっていたのとか、オウムをやっていたとか、ああいう人をどんどん老人ホームに送り込めばいいと思う。
【関わり方ひとつで生きもすれば死にもする】
徳永 問題患者があって、カンファレンスを開いたりするわけです。その患者さんについて、けちょんけちょんに、これでもかというくらい言う。看護婦さんはこんなにボロくそに言うのかと思うくらい、言い出すととまらないですね(笑)。
みんなが爆弾を落としまくって、「ハーツ、すっとした」という感じのときに、ふと、中堅の看護婦が「でも、いちばんつらいのは、あの患者さんだでな」と言ったそうです。「だでな……」とみんなが言ったんだって。
三好 職業人なのだから、個人的感情を出してはいけないといわれるのだけれど、でも、いやなジイさんはいやなジイさんだし、クソババアはクソババアなんです(笑)。
介護場面で出してはいけないですよ。でも、ケース会議などではむしろ感情を出してしまうということを、意識的にでもやったほうがいいと思いますね。だいたい、それまではそのケースから逃げよう、逃げようとしているじゃないですか。
目をあわさないようにと、部屋に入っても違うほうを見たりとか。その人から呼ばれないように、呼ばれないようにしていたのが、ケース会議でボロくそにいって、言い過ぎたかなと思う。そうすると、部屋に入るときには、「今日はどうしているかな」と、ちょっと見るときの視線や姿勢が少し変わると思うのです。それが相手に伝わっているとしか思えないようなことが、すごくありますね。
徳永 なるほどね。おもしろいですね。
三好 ということは、逆にいえば、無意識のうちにどれだけ老人をだめにしているかということでもあるんですけれどね。意識的には何もしているわけじゃないけれど、廊下をすれちがいながら、部屋を出たり入ったりしながら、こちらが逃げようとしていたり、関心をもっていないということで、老人は傷ついたり、だめになったりということが、じつは気がつかないうちにあるんでしょう。
 徳永 進(とくながすすむ)
徳永 進(とくながすすむ)
夜中の東の星が好き。月はまぬけの18日の月が好き。茄子のみそ汁、筑前煮が好き。一汁一菜の粗食派。漬物はキュウリに蕪、梅酢の沢庵。出張先のエビ丼580、クルクル寿司の一皿130円も好き。霊安室の前のお見送りも好き。夜中の、早朝の、昼下がりのお見送り、どれも好き。内科医。
徳永 三好さんはお年寄り一人ひとりにエールをおくるでしょう。私は、「早く死んだほうがいいよな、もとをとっているんだから」と思うほうですが、あれはなぜ? あるいは老人介護をする人たちにエールをおくっていこうと思うのはなぜ?
三好 寝たきり老人の悲惨な状態を初めて見たのは、入院している人を訪ねていったときでした。その人は骨が見えるような床ずれがあり死んだような目でした。
あのとき、人間がこういうふうになっていいのかという気はしました。恐怖だったです。こんなになっていいはずがない。こうならないためにどうすればいいかという疑問や怒りをもって見るべきだと思ったのです。それがじつは、ごく素人である我々でも十分できるということがわかってきた、ということがあると思います。
特別な勉強をしなくても、制度政策がよくならなくても今日から素人でもできることがたくさんあるのです。ぼくは扇動しているといわれるのだけれど、それがわかったときに扇動でも何でもしようという気になったんですね。
徳永 人間の悲惨さを見た三好青年が、ヒューマニズムな心でこの世界に切り込んだ、という感じですね。すごいですね、一度そこを聞きたかったんですよ(笑)。
【会場とのやりとりから】
◆ 私は保健婦です。Mさんはアル中でした。食道静脈瘤もありました。本人は医者にかかるのを怖がっています。生活も悲惨で、奥さんは逃げてしまい、中学生の子どもと二人暮らしです。炭焼きをして生計を立てているのですが、いまの時代そんなに仕事があるわけでもなく、栄養状態もよくありません。
とにかく医療につなげるのが私たちの役目だと思い、なんとか医者に行ってほしいというのですが、行きません。電話はしょっちゅうありましが、結局は、食道静脈瘤破裂で亡くなられました。
「きっとそうなる」とわかっているのに、その人の恐いという気持ちに対して上手に説得できなかったということもあって、非常に悩みました。こういうケースを、先生方はどういうふうに考えられますか。
徳永「お見事! ごくろうさんでした」という感じです。「こうなる」と思っていたとおりになったわけで、それは阻止するのはむずかしいし、阻止して幸せかということはむずかしい。運命というのか、裁きのなかで一人ひとり生きているわけで、そういう意味では医療は微力なものですから、それでいいのだと思うのです。
◆ 私のなかでは、その人がほんとうにその人らしく死んだのだろうかという疑問が残ったのですが。
徳永 詳しくはわからないので、そういう部分はあるかもしれませんが、私は、距離があるので「いいじゃない、それ」という感じです。距離が違うと別のものが見えるんですね。こんな遠くにいる私などに意見を求める必要はまったくなくて、ただ、あなたの距離で思ったことは、思ったことなのでいまは自問自答だけですね。
三好 私もアル中の人にいっぱい関わってきましたが、アル中の人はマイナスのほうへ、マイナスのほうへと自分の人生を選んでいるような気がします。我々のような若造が関わって、方向転換させようとしてうまくいったことはないです。
それでは放っておいていいかというと、私たちの仕事としては、私はこういう表現になると思います。どこまでお節介をするのか。おそらく本人は、電話をかけてきたりするくらいですから、お節介をやかれることをそれほど嫌ってはいないという雰囲気はありましたね。
だけど、「この人を医療につなげよう」「この人の人生を変えよう」というようなスケベ心がこちらにあるうちは、だめですね。この人がこの人生を選んだのなら、最悪のことだけにはならないようにつきあおうと、全部あきらめて、むこうに委ねたとき、見えてくることがあるというのが、ぼくらの経験です。
そのとき、こちらを信用してくれて「医療を受けてみよう」と言ってくれるかもしれない。医療につなげようとするのではなく、こちらにスケべ心がなくなったとき、自分との関係ができたとき初めて、医療なら医療につなげていけるような気がします。ある意味ではこちらの意図性を捨てる、捨身の関わり方しかないという気がします。
徳永 ひとつの正しい道というものはないわけです。ぼくの好きな詩を紹介します。
道ができているところでは
私は 私の道を見失う
大空には 大海には
どんな道も通っていない
道は 小鳥の翼のなか 星のかがり火のなか
移りゆく季節の花のなかに隠されている
そこで 私は私のむねにたずねる
おまえの血は 見えざる道の知恵をもっているか
みなさんなどもまったくそのとおりで、そこから出発しているのだと思うのですが、「道ができているところでは 私は私の道を見失う」というのは、実はほんとうなんですね。この世界もきっとその世界なのです。ブリコラージュもそこを出発にしている。
そして、私たち一人ひとりの生き方も。それは、ほんとうのことがそこにあるから、どっちにしても、おもしろいのです。そこをどうやって工夫しながら生きていくのか。そういう意味では興味ある世界ですね。
三好 先生はたくさんの本を書かれています。これを機会にぜぴ徳永ワールド”を散策していただければと思います。
(1997年3月15日 北陸オムツ外し学会にて)
- 1998.2-1月 “入りたいホーム”という欺瞞
先月号から連載まで書いていただいている、徳永進先生と同席して、会場からの質問を受けていたときのことである。会場の1人の保健婦さんからケースの相談を受けた。
治療も介護も必要としている一人暮らしの老人が、いくら説得しても通院も往診も受けつけず、施設入所はもちろんヘルパー派遣もうまくいかず、結局、足の踏み場もない部屋で亡くなってから発見された、というのだ。
「私はどうすればよかったんでしょうか」と、いかにもきまじめな保健婦らしく、ケースの細かい紹介の後で、そう質問をしめくくった。それに対する徳永先生の答。
「なんと立派な死に方じゃありませんか!」
うーむ、なるほど。私たちはそんなケースの状況を、問題点だらけだと見る。いまのままじゃいけない、と思って、入院や入所によって問題を解決しようとあせる。
だが、徳永先生は、そうした老人の頑固な生き方を丸ごと肯定するのだ。その人の生き方を認めるのである。おそらく私がこの老人に関わっていたとしても、加療や入所をすすめただろうと思う。考えてみれば、いらぬおせっかいばかりしているのが私たちの仕事である。
大事なのはそのとき、同じようにおせっかいをするにしても老人のいまの状況、それは長年の彼の生き方の結果なのだが、それを、あってはならないと感じているか、丸ごと認めているかの違いなのではないだろうか。前者は老人の前であせり、説得せねばと強迫めいており、表情にゆとりはないだろう。
そうなると老人はますます私たちの提案を拒否するに違いない。徳永先生はまずその深刻さとゆとりのない語り口や表情をこそやめよ、と答えたかったのではないか。私にはそう思えた。老人の生き方=死に方を、問題点としてあげつらう権利は私たちにはないんだよ、とも。
◇
考えてみれば、私たちから見ればどんなに悲惨に見える老人の生活だろうと、その老人にとっては病院や施設よりはいいに違いない。何しろ病院や施設に入ることは、生活の個別性と自律性を手放すことに他ならないのだから。それでも私たちは、その悲惨さを見ていられなくて入所を勧めたりする。
それは「あんたらがそこまで言うなら行ってみようか」なんて形で入所することもアリだ、と思っているからである。つまり、生活の個別性と自律性の大半を手放すことを、そこに新しい関係性が生じることで代償できるかもしれないと思うからである。
◇
「住民がつくる老人ホーム」なんていうと必ず「入りたいと思うホーム」なんて言われる。その結果、大金を使って豪華な全館個室なんて老人ホームがつくられてしまう。現在の職員定数で全館個室にすれば、“全館独房”になるのは目に見えているというのに、人権を声高に訴える人はなぜ全館個室に反対しないのだろうか。不思議でならない。
たとえ将来、介護職員の数が2倍になったとしても、すべて個室なんてのが老人のニーズにかなっているとは私にはとても思えない。そもそも「入りたいと思うホーム」というのに無理がある。もっと言えば欺膨がある。老人ホームぱ入りたい”と思って入るところではない。しかたなく入るところなのだ。
それは、封建的意識がなくなろうが、民主的権利意識がいくら広がろうが変わらないだろうと私は思う。豪華なホテルのような施設であってもなにも変わりはしない。人は足の踏み場もないような狭くて汚い部屋であろうが、そこにある個別性と自律性を手放したいとは思わないだろう。
だから老人たちは、老人ホームには「死ぬ気で来た」と言う。死ぬよりはましだ、と思って入ってくる。そして「来てよかった」、つまり、生きていてよかった、と思ってくれる施設が確かにある。だがそんな施設ほど、豪華でもないし、全館個室でもない。
だってそんな状況の人間にとってのニーズは、もう一度この老いてマヒした身体で生きていこう、と感じられることである。病院でチューブを入れられ、手足を縛られていた身体をもう一度自分のものへと取りもどすことである。孤独と不安を取り除いて笑顔をつくりだすことである。
プライバシーなんていうニーズの順番はそのずっと先である。人権といえばプライバシーしか思い浮かばないような人は、特養に入所する老人たちの現実を知らないおしゃべり屋さんだ。そもそも、雑居部屋に対して、個室しか思い浮かばない発想の貧困さが問題である。
日本人は個室ではなくて、障子やふすまで区切られた空間で暮らしてきた。隣に誰かいることはわかるが、なにをしているかはわからない、といった関係のなかでこそ日本の老人は落ち着いてくれるではないか。痴呆が進めば大部屋のタタミでザコ寝がいいなんてこともよく知られている。
日本のケアをしようよ。老人を大事にするということは老人の生活習慣を大事にするということなんだから。日本人へのケアを。