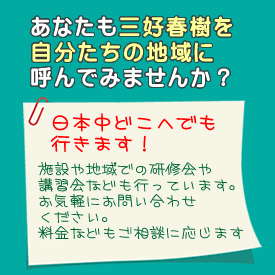●「投降のススメ」
経済優先、いじめ蔓延の日本社会よ / 君たちは包囲されている / 悪業非道を悔いて投降する者は /
経済よりいのち、弱者最優先の / 介護の現場に集合せよ
(三好春樹)
●「武漢日記」より
「一つの国が文明国家であるかどうかの基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である」
(方方)
● 介護夜汰話
追悼レヴィ=ストロース
介護夜汰話 高反発マットレス、その使用報告と考察
介護夜汰話 介護に覚醒剤はいらない
35年前のイメージ 酒井法子が介護職に
介護夜汰話 ひさしぶりに見た月 ~善了寺の庭にて~
介護夜汰話 固有名詞の介護 『夫・荘六の最期を支えて』
「地方分権」が聞いて呆れる
介護夜汰話 団塊オヤジはなぜ蕎麦を打つのか ~介護のホントの3K~
介護夜汰話 介護者の孤独とは何か
介護夜汰話 闘うべき3Kは4Kだった ~近代科学が野蛮と結びつく~
介護夜汰話 未来へのタイムマシーン ~インド・ヴァラナシへの旅~
介護ブームらしいぞ
介護夜汰話 介護現場のほんとの3K
「問題」をユーモアに変えるコトバの力、文化の力
介護夜汰話 マルクスの代わりに出産がきた ~『102歳の嫉妬』の書評に代えて~
インドレポート 阪井 由佳子
TV評 NHKスペシャル「闘うリハビリ」
介護夜汰話 私たちが医療に興味を示さない理わけ由 ~βアミロイドの沈着をめぐって・2~
麻生政権が生き延びる道
介護夜汰話 ~βアミロイドの沈着をめぐって
介護夜汰話 「プライバシーを守れ」という差別
介護夜汰話 「美しい」の謎が解けた
ミネルヴァの梟は日暮れて…
大学のセンセなんかに惑わされれるな!
介護夜汰話 介護職よ、給料分の仕事をしよう (その2)
介護夜汰話 介護職よ、給料分の仕事をしよう
介護夜汰話 存在論的武装解除 ~質問に答えて~
介護夜汰話 なぜインドか、なぜ「共同幻想論」か ~「特集・介護保険に頼らない」に寄せて~
介護夜汰話 病院OTへの手紙
介護夜汰話 看護師にも介護職にもおすすめの1冊 ~『ためらいの看護』の書評を書いた~
介護夜汰話 介護現場のギャグの意味
※ ただいま、「ALL LIST」「年度別記事」を作成中です。各記事の確認は、上記の「年度別」のボタンをクリックしてご確認ください。各リストは、年月日順になっています。

- 2009 ~ 2008
-
- 2009年12月 追悼レヴィ=ストロース
クロード・レヴィ=ストロースが亡くなった。100歳だった。Bricolage発行人の私としては、2008年12月『思想』(岩波書店)に依頼されて書いた小文を紹介することで追悼に代えたい。
私が発行責任者になっている介護の雑誌がある。その名前は『Bricolage(ブリコラージュ)』。34年前に偶然に就職した特別養護老人ホームでの宿直の夜に読んだレヴィ=ストロースの『野生の思考』の中でこのコトバに出会った。
いつか自分で雑誌を出す時にはこの名前にしようと決めていたが、その後フリーになって介護のセミナーを開き始め、受講者通信を出すことになってその思いが実現した。不定期刊から季刊、隔月刊を経て現在では月刊誌となり、刊行以来、直接購読のみ、広告なしで今年で20年目を迎える。
ただ、介護現場の人たちにはこの名前は覚えにくいらしく、「ブリッコなんとかという雑誌をとりたいんですが」とか「グリコーゲンの定期購読の件で」なんて電話がかかってくる。「構造主義はブルジョアジーの最後の砦である」などと言われていたのだが、読んでみると、そう言っていたサルトルこそ“マルクス主義の最後の砦”だったことを思い知ったのが『野生の思考』であった。
だがそれと同時に、自分が首までつかっている老人介護という仕事が、医療や看護、リハビリといった近代的で専門的な世界に対してコンプレクスを感じなくていいのだということを教えてくれたのが「ブリコラージュ」だったのだ。
「ブリコラージュは工業社会ではホビーの世界にしか残っていない」とレヴィ=ストロースは嘆いているが、「ブリコラージュは介護の世界に健在だ」と叫びたいような気持だった。なにしろ介護にはマニュアルは通用しない。介護が関わるのは医療のような「人体」ではなくて「人生」だから客観性がないのだ。
同じ方法でも誰がやるかによって結果が違ったりもする。再現性がないのだ。文字通りブリコラージュ=手づくりなのだ。だから専門性がないと言われてきた。しかし彼は言う。「ブリコラージュはサイエンスにはなりえない。しかしアートにはなりうる」と。このコトバにわれわれ介護現場の人間はどれだけ勇気づけられただろうか。
レヴィ=ストロースが介護にとってもつ意味はそれだけでない。彼は老人問題とは何かということをも教えてくれているのだ。「老人問題」とはその名のとおり、老人の問題だと考えられている。つまり老いた個体の問題だというのだ。
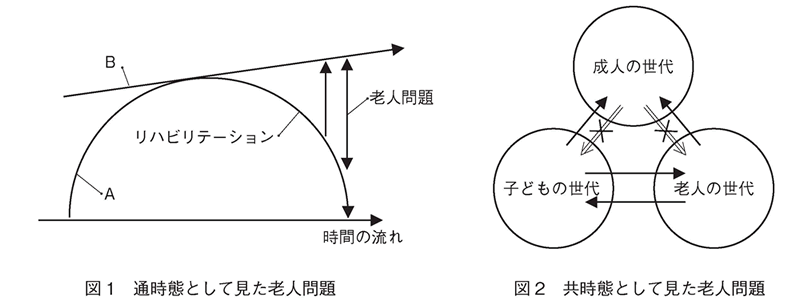
人生を経時的に観ていけば、図1のAのように、生まれて発達し、成人になり、そして老いていくものとしてとらえられる。一方で、社会は進歩発達していくものとしてとらえられている(B)から、ヒトが発達しているうちはこれに同調していられるが、停滞そして老化に転じると、AとBの間が問題となり、これを老人問題と呼ぶことになる。
あるべき時間の流れはBなのだから、個体は救済の対象とされる。かわいそうな人を助けてあげるという古いタイプの福祉がそれにあたる。しかし今やそれすら牧歌的だったと思える時代になった。最近では個体をBに一致させようとするのだ。
もっとリハビリテーションをと叫ばれ始めた。寝たきりにならないために「筋トレ」が、痴呆(認知症なんて妙な名前に言い替えられているが)にならないために「脳トレ」が強制されている。近代のどんづまりの日本社会はついに老いをあってはならぬものにしてしまった。
ところが、レヴィ=ストロースはこうした見方を「通時態」とし、それに対して「共時態」いう見方を提示してくれた。共時態で老人問題を捉えてみると図2のようになる。どの時代にも、子どもと成人と老人が並存していた。
老人問題とは、老人という世代に私たち成人の世代がどう関わっていいかわからなくなっているという世代間の関係の問題ではないか。
異文化を認めようとしない「自民族中心主義」になぞらえるなら、老人を救済や矯正の対象としか見ない「自世代中心主義」こそが老人問題の本質ではないか。その証左として付け加えるなら、私たちは老人への関わり方だけでなく、同時に子どもへの関わり方も失っているのではないか。- 2009年12月 介護夜汰話 高反発マットレス、その使用報告と考察
月刊Bricolageで初めてブレスエアーを使った高反発マットレスを紹介したのは、2007年11月号のことだ。「スロークロージング」と題した特集号だった。そこで私はこう書いた。
「じつは私もこの『そよかぜ』を使って寝ている。腰痛が出ない。もっともそれは偶然体調がいいからかもしれない。私ひとりの数か月のデータは科学的根拠にはならない」と。それから2年も経った。偶然ではなかったというのが結論だ。腰痛も肩こりも出ていない。
なにしろマッサージにほとんど行かなくなった。ひどい時には毎週のように通っていたから、月に2万円もかけていたことになる。マットの代金はとっくに回収したということだ。私は不思議で仕方がない。私の腰痛は、「中卒」や「高卒程度」という条件を見つけて入り込んだ工場での肉体労働のせいで、病歴は40年近くにもなる。
肩こりはいつごろからだろうか。ひどい時には酒も飲んでいないのに真夜中に嘔吐することがあって、それが肩こりのせいだったこともあったくらいだ。それがマットを変えるだけで出現しなくなるとは!?
腰痛と肩こりには本当に困らされた。同じような筋肉の痛みでも、手足の筋肉痛とはその様子がかなり違っているからだ。私はこう見えても山登りが趣味だ。といっても、軽い高所恐怖症だから登れる山は限られていて、今年の夏に登った、百名山のうちの2つの山、蓼科山と大雪山旭岳が限界だが。
登山の後、特に蓼科山の後は数日間、大腿が痛くて、和式トイレが使えない。横断歩道で信号が赤になっても走れない状態が続いた。でも、こうした筋肉痛は、時間がたてばそれに比例してどんどん治っていく。その時間が歳のせいで長くなってはいるが。
ところが、腰痛や肩こりはそうはいかない。痛みやこりに直接の原因がないことのほうが多いし、痛みも筋肉痛とは違っている。深くて鈍い痛みといったらいいだろうか。眠れなかったり、生活意欲すら低下してしまうような症状である。何もする気がしなくなるのだ。手足の筋肉痛ではこんなことがない。
そもそも腰痛と肩こりとは何だろう?いろんな本を読んでみた。理学療法士としての知見はあまり役に立たない。医学よりは、もう少しスケールの大きい生物学、系統発生についての考察がおもしろい。
私自身が納得できる仮説は、ヒトが二足歩行を始めたことが原因だというものである。この説は珍しいものではない。でも、なぜ二足歩行によって腰痛が出るかという理由は、その直立姿勢のせいで「腰に負担がかかる」というのみで詳しくは語られていないし、肩こりについてはふれられていない。
私は、二足歩行によって腰と肩の筋肉の働き方に変化が生じたからだと思う。動物にとっての基本的な動きである移動について考えてみよう。歩行する時の筋肉は、収縮と弛緩を繰り返す。筋肉の中には血管がたくさん走っていて、この収縮と弛緩によって血流が促進される。これは、「筋肉ポンプ」と呼ばれ、特に足の筋肉は「第2の心臓」と言われていて、血液の心臓への還流の役割を果たしているのだ。
動物のような四足歩行の時には、腰の筋肉も肩の筋肉も手足の中枢部として、同じように収縮と弛緩を繰り返している。しかし二足歩行では違ってくる。腰の筋肉は立位を保つために働かなければならない。そのためには、収縮と弛緩の繰り返しではなく、一定の緊張を保つという「等尺性収縮 ※」を強いられることになる。すると、筋肉はポンプ作用をもたず血流は悪くなる。
直立姿勢の目的は、視野を高くするためとも言われているが、上肢を使用するためとする説が強い。この上肢の使用、労働が、同じように肩の筋肉に姿勢保持を要求し、「等尺性収縮」を強いることになった。
二足歩行と上肢の使用による「等尺性収縮」、これが腰痛と肩こりの第一原因である。それに2つめの原因が追討ちをかける。それがヒト特有の背(仰)臥位での睡眠だ。動物は腹這位で眠る。背骨の構造が弓状になっていて背臥位では安定しないし、外敵がたくさんいるなかで弱い腹面をさらさないためだ。
ところが人間は二足歩行のせいで、長い歴史的時間を経て背骨が独特の湾曲をつくった。それは重い頭を支えるためのじつに見事なカーブになっている。そのせいで腹這位よりも背臥位のほうが楽になった。もちろん、外敵から身を守るための家や武器という安全を手に入れることで、弱い腹面を上にしてもよくなったのだ。
この背臥位での睡眠によって、肩と腰は夜の間、自分の身体を支えていなくてはならなくなった。ところが肩も腰も、もともと体重を支えるようにはできていない。褥瘡のケアでもよく言ってきたことだが、人間の身体には褥瘡に強い部分が3か所ある。手のひらと足のウラ、それにお尻の下である。
手のひらと足のウラは四足歩行で体重を支える部分、お尻の下は現在では座位の時にしか体重を支えないが、動物はここを床につけて寝ているのがわかるだろう。これらはいずれも圧迫に強い独特の構造になっている。しかし、腰と肩にはそんな構造はない。1日中「等尺性収縮」を強いられて疲れているというのに、さらに、寝ている間さえ血行が悪くなるのだ。
圧迫に弱い部分をゴムやビニールに圧着させていては、ますます血行は悪くなるばかりだ。エアマットが効かないのも当然ではないか。この圧迫に弱い肩と腰を空気の上に乗せようというのがブレスエアーである。これこそホントのエアマットだと思う。寝ている間の血行を阻害しないだけではなく、ゴソゴソ動きやすいから、無意識に筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、血行を促進するのだ。
私の仮説が正しければ、腰痛と肩こりの予防と治療には、ブレスエアーをマットとして使うことともう1つ、四つ這いをすればいいということになる。肩と腰の筋肉は本来の機能である収縮と弛緩を繰り返すから血行がよくなるだろう。
四つ這い移動を脳性マヒの治療に使うのは聞いたことがあるが、腰痛と肩こりの治療法にも試してみないか。誰かデータをとってみる気はないだろうか。
※-----------等とうしゃくせいしゅうしゅく尺性収縮
(isometric contraction)
関節の動きを伴わない筋肉の収縮のこと。姿勢の保持などの時の筋肉の働き。反対語は等張性収縮isotonic contractionといい、筋肉の収縮に伴って関節が動く動きのこと。
※------------------------------------------------------※
- 2009年11月 介護夜汰話 介護に覚醒剤はいらない
タレントが覚醒剤を使用していたとして逮捕された事件で、テレビも週刊紙も大騒ぎである。エコロジーだの温暖化防止のキャンペーンをやっている放送局が、釈放された容疑者をヘリコプターまで動員して追いかけまわすのはどうかと思うなあ。そもそも同じような番組しか流してないんだから、2、3局なくしたほうが温暖化防止に役立つと思う。
もっとどうかと思うのは、覚醒剤使用を個人のモラルだの所属事務所の管理の問題だとしてのみ取り上げる傾向である。だって世の中全体が「覚醒剤社会」になっているのだから。つまり、覚醒剤やそれに類似したものを必要とせざるを得ない世の中になっていると私には思えてならない。
「24時間戦えますか」というドリンク剤のコマーシャルがあった。ビジネスマンに、これを飲んでバリバリ働けというのだ。私が厚労省の大臣なら、メタボ検診なんかやらないで、こうしたコマーシャルをすぐに止めさせる。表現の自由だといって法的には止めさせられなくても圧力をかけてやる。だって肥満より、煙草より、働きすぎのほうがはるかに健康に悪いのだから。
だいたい24時間働いちゃいかん。労働基準法違反じゃないか。厚生、労働のどちらからも放っておくべきものじゃない。しかし、テレビコマーシャルに煽あおられるまでもなく、現代人は働き続けることを強いられている。効率主義だのグローバリズムだのといって、密度の濃い労働を求められる。
効率をよくすることで労働時間が短くなるかというとそうではない。逆にますます労働時間は増えていって労働基準法なんかとっくに有名無実である。これが脳血管障害や心臓病を大量に引き起こしている。これらは「生活習慣病」ではなくて「働かせすぎ病」である。影響は身体だけではない。日本での大量の自殺者と、国民病のようになっている、うつ病といったかたちで精神にまで悪影響を及ぼしている。
ある者は身体が悲鳴をあげ、ある者は精神が世界を拒否する。それに比べれば、覚醒剤まで飲んで世界に適応しようとする人たちは、健けなげ気だとさえ言えるのではないか。しかし、国は覚醒剤は認めない。国家が認めた“覚醒剤もどき“(店頭にズラリと並んだドリンク剤)なら許そうというのだ。
効率主義の世の中では時間は金に換算される。典型的なのはテレビだ。コマーシャルが騒々しく流れるだけではない。番組そのものも、かん高い声のレポーターが芝居がかった早口でしゃべり続ける。だって1秒1秒が金なのだ。黙っていることは許されないのだ。
かろうじてNHKはその超高速の時間の流れに巻き込まれていないように見える。強制的に取り立てる受信料と税金によって成立しているからだ。だからこその、“親方日の丸“的なところも権威主義なところもある。時の権力に弱くて、番組内容をかつての自民党幹事長の安倍某に検閲させたりすることもあった(なら受信料を取らずに安倍から金をもらえよ、私は思ったものだ)。でも時間の流れという点ではNHKは評価してよい。
介護が“措置”から“保険”という近代的契約になったのは、ちょうど、NHKから民放に変わったようなものだと言える。「税金の中からこれだけ渡すから適当にやってくれ」というのが措置制度だったと言えよう。“親方日の丸”も権威主義も権力への迎合もあったが、現場がやる気になればいいケアができた。ちょうどNHKが「NHKスペシャル」みたいな見事な番組をつくったように。
ところが介護保険でケアは商品になった。消費者(利用者家族)に迎合し、効率よく働いて利益を上げなくてはならない。“サービス業”であることがあたかも新しいもののように強調されたが、何のことはない、「サービス」という言葉の語源は奴隷ではないか。介護までもが効率主義に巻き込まれたこんな時代に、身体や精神を犠牲にせず、覚醒剤にも頼らずに、健全に、いやそれなりに生きていく方法はあるだろうか。
かつて私は介護現場に入る前に十数か所の民間の職場で仕事をしてきた。今ほど効率主義が叫ばれてはいなかったものの、仕事は生産量や売り上げでチェックされ、成績の悪い者はいとも簡単に解雇された。
そこでの私の生き抜き方は、「ゲリラ闘争」である。とても正面からは闘えない。だから、ゲリラ=非正規軍の闘いだ。まずサボる。そして休む。そのために仮病をよく使った。日頃から身体が弱いと思わせておくとうまくいく。
だが介護の仕事はそうはいかない。サボったり休んだりすると、仕事仲間や老人に迷惑がかかるからだ。私の今の仕事もそうはいかない。だから休みには山に登って都会の時間の流れから逃げる。年に1回はツアーを呼びかけてインドに行って近代の時間の流れから逃げる。
でも、じつは介護の世界にはこの時間の流れの中で健全に生きるための方法がある。それは老いとつきあうという仕事そのものである。私たちはそこで、近代的で都会の時間の流れから逃れて、老いというゆったりした時の流れに入り込む。昔話を聞き、昭和の歌謡曲をいっしょに歌う。
もちろんずっとそのなかにいるわけにはいかないから、老人の部屋を出るや、また速い時間の中に帰るのだけれど、でもそのおかげで私たちは疲れを忘れ、感動まで得られて、覚醒剤などなしでやっていけるのである。
デイサービス「玄玄」の代表、藤渕安生君の大阪と小山での報告で上映された映像の中に「Japanese Underground Care」というコトバが出てきた。そうか、介護という仕事そのものが地下活動=ゲリラのようなものなんだ。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【トークセッション】 降りてゆく―命の傾きを生きる
向谷地生良 × 三好春樹 × 辻 信一
§---------------------------------------------------------§
- 2009年11月 35年前のイメージ 酒井法子が介護職に
酒井法子が介護職になるなんて言ってるというので驚いている。
ちょうど Bricolage の11月号の「介護夜汰話」で「介護職に覚醒剤はいらない」という文章をのせたばかりだったからだ。
まるで予測していたみたいだが、それにしても今回の”介護”はまるで”尼寺”だもの。
35年前のイメージと変わってないではないか。- 2009年10月 介護夜汰話 ひさしぶりに見た月
~善了寺の庭にて~ 私は神奈川県の湯河原町に住んでいる。神奈川県の西の端の町で、すぐ隣は静岡県の熱海市である。その静岡県に静岡空港が開港した。福岡や熊本にも便がある。私の家からだと羽田へ行くのと距離は変わらないのでダイヤを調べてみたのだが、とても使えない。空港までのアクセスが不便なのだ。
もっと近い静岡市内に住んでいる人も使えないと言っている。静岡市の老健に単身赴任している高口光子さんは熊本に自宅があるので「里帰りに便利になったじゃないか」と言うと「羽田まで行ったほうがよほど便利」とのことだった。浜松の人は「中部空港まで行く」という。誰が使うんだろう?
お盆の後、九州からはじまって青森までの15泊16日の仕事の旅から帰ってくると、政権が変わることになっていた。でも私はとても民主党なんかに期待する気にはならない。なにしろこの静岡空港、県議会の民主党は建設に賛成なのである。
「無駄をなくす」と言っている党ではないのか。これが無駄でなくて何を無駄というのか。膨大な建設費だけでなく、膨大な維持費と赤字をほぼ永久に税金で穴埋めし続けるのだ。甘い汁を吸ったのは土建屋とその上前をはねた政治家だけではないか。
「地方分権」なんてのはもっと信用できない。そもそも「地方分権」とは、税金の甘い汁を東京のボスだけじゃなくて地方の俗物にも回せという主張をきれいごとに言い換えてるだけだが、マスコミがよく取り上げる宮崎や大阪の俗物知事の主張にそのことがよく表れている。
宮崎の知事は、あの宮崎にフル規格の高速道路をつくれというし、大阪の知事にいたっては、京滋バイパスがあるというのに第2名神をつくれと言い張っている。おそらく「地方分権」になれば、高速道路も空港もさらにつくられるだろう。埼玉空港、千葉空港、奈良空港、淡路島空港…etc。冗談とは思えないところが恐いではないか。日本中を税金を使って、緑の大地をコンクリートで固めるに違いない。
民主党は介護職に月4万円給料を増額し、子ども1人に2万6千円支給するという。財源は無駄を省くことで確保するというのなら、空港、高速道路、新幹線はつくらない、それどころか赤字の空港は廃港にしてその金を子どもと老人に回す、と言わないか。誰が見ても無駄な空港1つにも反対できないでは誰も信用しないだろう。
「選挙前で軽いコトバばかりが飛びかっているからこそ、今夜のトークショーの意味がある」という辻信一さん(明治学院大教授)のあいさつで始まったのが「降りていく…」と題されたイベントである。発言者は他に、会場である善了寺の住職成田智信さん、べてるの家のソーシャルワーカー向谷地生良さん、それに私である。
辻信一さんは『スロー・イズ・ビューティフル』(平凡社ライブラリー)という著書のある環境運動家。経済成長一本槍の世界とそれに振り回される私たちの人生に対して「疲れ、怠け、遊び、休むことの復権」を訴えている人だ。
その辻さんが共感したのが「べてるの家」という運動体だ。『べてるの家の「非」援助論』『べてるの家の「当事者研究」』(いずれも医学書院)などから介護の世界も大いに刺激を受け、学んでいる。精神障害者とはまさしく、上昇志向の世の中から疎外され、“降りていく”人たちである。「べてるの家」がその“降りる”という生き方を肯定しようという革命的な思想を生み出したと言っていい。
成田住職は、自分の寺でデイサービスを始め、私を築地の本願寺で講演させたり、辻さんと寺で“スローカフェ”を催したりしている人で、彼の強引な企画力でこの日のトークショーが実現したのだ。私は要介護老人たちは“降りてきた人たち”だと述べた。そして、降りたところにともに立ってみると、世の中のおかしさが丸見えだということも。
ついでに、私は“降りていく”ことを思想的に表現した浄土真宗の「還相(げんそう)」というコトバにふれ、キリスト教は、神の国に向かって突き進む往きっ放しの思想ではないか、と述べた。すると、クリスチャンである向谷地さんが、「キリストは神の国から地上、それも馬小屋に降りてきた人なんです」と言うのである。
そうか、私のキリスト教とは、歴史を神の国へと至る弁証法としてとらえるヘーゲルの思想にすぎなかったのか。キリスト教も還相から始まっているらしい。浄土真宗の寺の本堂で、住職とクリスチャンの向谷地さん、キリスト教の大学の教授と学生たち、それに無神論者の私という脈絡のない顔ぶれだったが、電気による照明を消し、ローソクの淡い光の中でのトークショーは、現代社会への違和という共通感覚が共鳴しているようだった。
外に出ると半月夜だった。横浜の戸塚駅から徒歩5分、建築中のコンクリートのマンションに囲まれた緑の丘にある善了寺そのものが、現代を生きのびるためのノアの方舟のように思えた。都会の照明の中の月は弱々しく目立たないが、善了寺の庭から見る月はなんとも印象的だった。
近代という光の眩しさに幻惑された私たちの目には、精神障害者や老人という近代の影の部分は“闇”だと感じられている。この目をちゃんと暗順応させていくこと、それが問われているのだ、とその月を見て思った。- 2009年9月 介護夜汰話 固有名詞の介護
~『夫・荘六の最期を支えて』~ 25年間にわたって、私は介護とは何かを書き、話してきた。教えてきた、と言うべきかも知れない。なにしろ介護職にとっては安いとはいえない受講料をいただいてセミナーに参加してもらっているのだから。
しかし私には、教えてきたというつもりはない。介護の現場に私のコトバが届くこと、介護している人と共感できること、それができればなんとか受講料分の仕事になるのではないか、と考えてやってきた。
だが今回、講談社から出版された『夫・荘六の最期を支えて』という本を読むと、私は何を語ってきたのかと自問せざるを得ない。介護とは何かを語るためには、介護する人とは何かが語られねばならない。

夫・荘六の最期を支えて
著者:杉原美津子
発行:講談社
体裁:四六判・並製・197頁
定価:1,400円+税
そして介護される人とは何か、さらに2人の人生とは何かが語られねばならないのだ。そこに初めて介護が立ち現れるのだ。そう、ここにあるのは「固有名詞の介護」だ。「杉原美津子による、夫である荘六への介護」なのである。
介助する人とは何か。かつて自分自身の生と死、さらに、自分に対する犯罪加害者の生と死にも真摯に向き合ってきた人である。そして介護される人とは、そして2人の人生とは……。
それは本書を読んでほしいが、それを知らないと、なぜ彼女がここまで自分の手による介護、それも、壮絶な介護を続けるのかはわからないだろう。
たとえば、私は施設に入所させることに後ろめたさなんか感じることはないと語り、書いてきた。介護によって人間関係が壊れてしまうくらいなら、入所という距離をおくことで、人間関係を取り戻すこともできるではないか、それこそが、老人施設が、「姥捨て山」ではなくて「介護施設」になることなのだ……etcと。
彼女はもちろん、そのことも考える。しかし、距離をおくことで回復する人間関係は、逃げることではないか、と考えて在宅ケアを続けるのだ。それは介護する人とされる人の人生がわからなければ理解は難しいだろう。「もっと手を抜いて」とか「施設入所は悪いことじゃないですよ」といった、一般的なアドバイスは通用しないのだ。
介護したいという彼女の願いに応えて、適切な助言をする医師が登場する。かつて彼女の生死に関わった医師である。彼は彼女の生き方も夫のことも知っている。だから専門外でもちゃんとしたことが言える。
「医者をあてにするな。医者なんて家族と比べたら何にもわかってない。患者本人の人生と関わってきたことがない人間に何もわかるはずがないさ」と。夜間のSOSの電話に駆けつけてきて、いやな顔ひとつしない看護師や介護職も登場する。私はそんなケアにホッとする。介護という世界も捨てたものじゃない、と思う。いや日本にもまだ救いがあるとさえ思う。
だが、彼女といっしょに怒りたくなる関係者も出てくる。怒るだけではなく、同業者として恥ずかしいと思う。おそらく、この本に書かれているのはほんの一部分で、しかも怒りを抑えて書かれていると思う。だって、私の知る限り、「ホッとする介護」はまだ点のようにしか存在せず、大半が「恥ずかしい介護」なのだから。
恥ずかしいといえば、本書には私の著書からの引用が少なからず出てくる。最後には実際の私に会ったことまで書いてある。私は恥じ入っている。なにしろ、私にとっては介護は仕事である。人生ではない。取り換えのきく人生の一部だ。
そして、相手は家族ではないから所詮は他ひとごと人事である。私のコトバは「固有名詞の介護」の深みには到底届かない。でも彼女の人生の深みからのコトバは私に確実に届いたし、多くの介護関係者に届いてほしいと思う。本書に引用されている何十年も前に好きだった長田弘の詩を私ももう一度読んでみよう、そう思っている。- 2009年8月 「地方分権」が聞いて呆れる
「地方分権」が叫ばれ、大阪や宮崎の知事が毎日のようにテレビに登場している。しかし分権された地方で彼らは何をしようとするのか。大阪の知事は第2名神を作れと国に陳情している。国の段階で京滋バイパスをこれにあてればいいとされたにも拘わらずだ。宮崎の知事はあの宮崎県に高速道路をもっと作れ、という。自動車専用道で十分じゃないかね。
つまり「地方分権」されれば、いままでよりもっと高速道路、空港、新幹線を作るということだ。税金で自然を破壊し、膨大な管理運営費をたれ流すのだ。 地方分権とは、税金の甘い汁を中央の大物だけじゃなくて地方のボスにも回せ、ということに他ならない。
中身はちっとも問われないどころかひどくなっているのである。個室やユニットケアに似てるなぁ。大部屋を個室、ユニットにすればケアが良くなるかのように主張されたけれど、肝心の中身は語られることもなく、より管理的で閉鎖的な介護空間を作り出しただけではない。
気がつけば金持ち以外は特養ホームにさえ入所できないというとんでもない時代になってしまった!「地方分権」も“土建国家”の延命を助けることにしかならないだろう。
ヤレヤレ…- 2009年7月 介護夜汰話 団塊オヤジはなぜ蕎麦を打つのか
~介護のホントの3K~ 介護という仕事は“3K”だと言われている。もともと「きつい、汚い(または臭い)、危険」の意味だが、介護職場は「危険」の代わりに給料の安い“3K”だというのだ。でも、私は本当に介護職場で問題とすべき3Kは、権威主義、管理主義、金儲け主義ではないか(3月号)さらに、科学主義を加えた4Kだ(5月号)と主張してきた。
でもそれでは介護現場は3Kどころか7Kの夢も希望もない職場だと思われるのは、もちろん私の本意ではない。“4K”から少しでも自由になった時、俗っぽい世の中を越えた新しい世界が開かれるはずだ、というのが私の訴えたいことである。そしてその新しい世界には、本当の“3K”があると思う。
本当の“3K”とは、まず「感動」だ。ハリウッド映画やテーマパーク、高級ホテルが商売道具として売り物にしているそれとは違う。なんといっても、もう生きていくのさえやめようとしていた老人が、もう一度この身体で生活していこうという気になるところに立ち会えるのだ。
ひょっとすると、自分たちがそのきっかけになっているかもしれない、そんな仕事が世の中にあるだろうか。PTやOTはマヒした手足を動かせるようにできるかもしれない。医者は命を救えるかもしれない。しかし、動くようになった手足を使って生きていこうという気持ちがなくなっていては何のための回復だろう。
生きていてよかったと思えないようでは何のための救命だろう。その医療の進歩によって生じた新しい課題にこそ、介護は関わっているのだ。まして世の中の仕事は「感動」どころではない。感動さえ売り物にして金を出させようとしているではないか。
人をだましたり、そこまでではなくても、虚栄心をくすぐって大金を使わせようとか、従業員を安月給で奴隷のようにこき使って金儲けしようとする仕事で溢れているではないか。それらに比べるとなんといい仕事だろう。
2つめのKは「健康」だ。世の中の人は運動不足だというので、高い入会金まで出してスポーツクラブに入り、レオタードを着て動かない自転車をこいでいる。あれももったいない話だ。発電でもしたら世の中の役に立ちそうではないか。
でも介護職は1日働けば運動量は十分だ。特に、施設職員は1日1万歩は歩く。それに、痴呆老人が出ていけば追いかけていかなければいけない。それで痩せられると思えばよい。腰痛は介護職の職業病だと言われていた時代があったが、今ではそれは間違いだ。
安静看護法を介護だと教えてきたから腰を痛めたのだ。それに代わって流行した「ボディメカニズム」や「古武道を使った介護」も介護とは言い難い。なぜなら、本人の意思の発動がないという点では安静看護と同じだからだ。
老人の意思の発動を前提として、動作の生理学に基づいた動きを誘導、介助することこそ介護法である。ようやく、NHKがそうしたまともな介護法を取りあげるようになった。25年遅れではあるけれど。
「ためしてガッテン」なんて人気番組に、青山幸広、福辺節子の2人が出演したのもご存知のとおりだ。教育テレビで24回放送される「ワンポイント介護」も私が出ている。介護というコトバから人々が「健康」をイメージするようになるのも遠くないかもしれない。
さて、最後のKは「工夫」である。創意工夫だともっといいけど、それでは「S」になってしまうので工夫だ。介護者は老人を目の前にしてまず感じる。老人の声を聴く。意味のないコトバでもその口調を感じ取る。表情を見る。においを嗅ぐ。声をかけて反応を見る。そして考える。何を訴えているのだろう、私がすべきこと、してはいけないことは何か、と。
そして自分で判断し、自分であるいは回りの人といっしょにやってみる。そしてその結論が妥当だったかどうかを、老人の反応で確認する。介護には当たり前のこうした仕事の仕方は、じつは世の中にはほとんど存在していないものだ。やるべきことは既に決められているのだ。
マニュアルどおりにやるのが「仕事」というものになっている。それは、自分で判断してはいけないということだ。考えるな、感じるな、ということである。介護は、やるべきことが最初からわかってはいない。やりながらわかってくるのだ。
だから、自分の五感だけでなく第六感まで含めて感じ取り、考えなければならない。ケアプランどおりにやるというのでは介護は介護ではなくなってしまう。ケアプランは仮説の一つだと思えばいい。
こうした、自分で判断するな、考えるな、感じるな、という人間的とは言い難いような仕事は、コンビニやファミレスのバイトだけではない。大きな会社でも同じだ。私の中学、高校の同級生たちはほぼ全員大学に入り、大きな会社に就職した者も少なくない。
でもやるべきことは「シンクタンク」なんてところが「マーケットリサーチ」して決めるのだ。その結果、降りてきた年間目標という数字を達成するために、彼らは部下をこき使い、自分をギリギリまで酷使するのだ。
彼らはそんな仕事に飽き飽きしている。もっと人間的な仕事を求めているのだ。だから団塊の世代の退職オヤジは蕎麦を打つのである。蕎麦もいいだろう。だけど、だったら介護の仕事をしてみろよ、と私は言いたい。- 2009年6月 介護夜汰話 介護者の孤独とは何か
テレビ業界を始め、世の中は介護がブームなんだそうだ。南田洋子の認知症を取り上げた番組が高視聴率をとり、ワイドショーは清水由貴子の自殺について特集を組む。私にも女性週刊誌から取材の電話がきた。
「要介護度5というのは大変なんですか?」「今の制度はどうなっているんですか?」なんてことを尋ねるので、「そんなことは樋口恵子さんに聞いたほうがいい」と言うのだが、ヒグチケイコという名前すら知らないようなのだ。
こんな時には私はいつも高口光子さんを紹介する。彼女なら適当にあしらいつつ、ユニークなコメントをしてくれるだろう。「NHKのクローズアップ現代に出た人です」と言うと、マスコミも安心して取材に行く。この時も取材を受けた高口さんは電話で散々しゃべり、「後日、原稿をまとめてチェックしてもらいます」と言われたそうだが、翌日「すみません。クサナギツヨシの事件でページがなくなりましたので」というオチがついた。
ワイドショーを見ていると、その樋口恵子さんがゲストでしゃべっている。老人介護は大変であること、だから制度を活用すること、そして介護者を孤立させないことが大事だ、と。どの番組も清水由貴子と介護家族への同情にあふれている。でも私には違和感がある。いたましい事件で同情に耐えない。ゲストの識者が言っていることももっともだ。でも私はスッキリしない。
……この世の中には2種しゅるい類の人間がいます。ぼけた年寄りといっしょに暮らしたことがある人と、暮らしたことがない人……
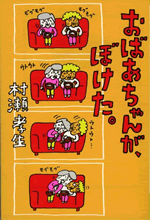 こんな大胆なことを書いているのは、詩人の谷川俊太郎さんだ。私が大絶賛している『おばあちゃんがぼけた』(村瀬孝生著・理論社)のあとがき「ぼけの驚異」の中の文章である。
こんな大胆なことを書いているのは、詩人の谷川俊太郎さんだ。私が大絶賛している『おばあちゃんがぼけた』(村瀬孝生著・理論社)のあとがき「ぼけの驚異」の中の文章である。
ちなみにこの本、子ども向けのシリーズなので小学校4年生以上で習う漢字にはふりがながふってある。ここでもそのまま引用した。
介護する人は身体的にも精神的にも大変であることは間違いない。まわりの人が誰も助けてくれないという孤立も少なからず感じるだろう。でも、最も大変なのは谷川さんが言っていることにあるのではなかろうか。つまり、自分がまわりとは種類の違う人間になってしまったという孤立感、疎外感である。
「大変ですねえ」とまわりの人は同情してくれる。しかし、介護は大変なだけではない。それと同じくらい楽しいことや喜びがある。それを“種類の違う”人たちはわかってくれない。なにしろ、その楽しいこととは、老人がしゃべったとか、笑ったとか、なんてことなのだ。
しかも、まわりから見れば意味のないコトバだったり、額にシワが寄っただけだったりなのだから。喜びとなると、もっと伝えることは困難だ。それまでの価値観とは別の世界が開かれるのだ。人間観、人生観が深いところで変わっていくのである。
金儲けや地位、名誉が人生の目的だと考えている世の中からは、認知症は嫌悪すべきものであり、その介護は最もやりたくないものである。「大変ですねえ…」という同情はその価値観を前提にしている。ところが、介護者は介護をとおして、そんな俗っぽい世の中をいつのまにか通り越してしまう。
そして、気がついたら種類の違う人=エイリアンになっているのだ。介護職はいい。同じ職場にエイリアンがいるから孤立はそれほどでもない。俗っぽい価値観のままの上司と闘ったり、皮肉を言ったりはしなければならないけれど。また、「安月給で大変な仕事をなぜやっているのか」と不思議がる家族とうまくいかないかもしれないけれど。
私がすごいと思うのは「認知症の人と家族の会」の人たちだ。彼女らが「介護に疲れた被害者」としてだけ登場するのなら、それは俗っぽい世の中の価値観そのままである。もちろん、それはそれで政治的主張をする資格は十分だと思うが、でもあの会の中心になっている人たちは、その価値観をやはり通り越す人がたくさんいるのだ。
ある人は、いやいや介護を押しつけられたというのに、親戚に要介護老人が出ると「私は経験者だから」と介護を買って出ている。また、ある人は親の介護が終わるや、自分で介護事業所を立ち上げたりしている。私には、彼らが“エイリアン”同士で自ら集まり、アナザーワールドをつくろうとしているように見える。
その家族会からいくつかの講演依頼が来ている。エイリアン同士の共感を得に行くつもりだと言うと迷惑がられるだろうか。Bricolageもまた、エイリアンによるアナザーワールド通信になりたいと思っている。谷川さんの文章(前掲書)を最後に引用したい。
……ぼけについて感じ、考えることには、人生そのものを問うことにつながる面白さがありますし、私わたしたちが今生きている時代の動きと切離すことの出来ない切迫感があります。ぼけの可笑しさ、不思議さ、怖さ、美しさを通して、私たちは人間といういのちの限りのない深みに触ふれるのです……
私は、清水由貴子さんが、その「エイリアンの孤独」で自殺したのだ、などと我田引水するつもりはない。ましてや、遺書で東京での葬儀を拒否したのも、俗っぽい価値観を拒否したいという気持ちの表われだ、などと勝手な解釈をしようとも思わない。
ただ、“介護地獄で自殺した”という通俗的な見方だけでは、老いやぼけ、介護への偏見を強めるだけだと思うのだ。もっと違う見方があってもいいのではないか。
ところで、件(くだん)の高口光子さんはどう思ったか。
「あれ? 更年期障害じゃないのぉ!? 更年期の女はひとりで介護しちゃいけないよ」
こんな俗っぽさはあってもいい。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【三好さん、ケアマネのおかれた状況をどう思いますか?】
インタビュアー:本間清文
§---------------------------------------------------------§
- 2009年5月 介護夜汰話 闘うべき3Kは4Kだった
~近代科学が野蛮と結びつく~ 前々号(2009年3月号)の「介護夜汰話」に「介護現場のほんとの3K」という文章を書いた。もともと「3K」とは、土木や建設現場の仕事が、「きつい、汚い、危険」の3Kだとされて人手不足になったのがきっかけ。
現在の介護現場ではそのうちの「危険」の代わりに「給料が安い」が加わって、3K現場だと言われている、というものだ。しかし、介護の現場にはもっと困った3Kがある、というのが私の主張である。それが「権威主義、管理主義、金儲け主義」の3つであり、これと闘うことなくしては介護現場はよくならない、と。
この3Kは本当に介護現場をダメにしている。でもよく考えると、現場をダメにしているもう一つのKがあるのだ。それは「科学主義」である。権威や管理、金儲けが悪いわけではない。でもそれに主義がついて自己目的化されると困ったことになる。
それと同じく、科学が悪いわけではない。それどころか、科学は私たちに大いに役立っている。なにより便利だ。でもそれに主義がついて「科学主義」となると困ったことになる。多くの老人が病院で、「ここまでしか治りませんでした」と言われて、特養ホームに入所してくる。
家族は「医者や看護婦といった専門家に見捨てられて、こんなところに親を入れなければならない」と強い罪悪感をもって、特養ホームにやってきた。私が特養ホームに就職した30年以上も前の話だが、今でも基本的には変わらないのではないか。
当時は、職員の中で資格をもっている者は2人しかいなかった。看護婦と栄養士で、あとはみんな“看護力士士”である。腰が丈夫という条件で採用されたのだ。ところが、そのシロウト集団が、目がトロンとした老人を元気にするのである。
声高に叫ばれていた「社会復帰」や「家庭復帰」はかなわなかったが、「人間復帰」や「生活復帰」は確実に実践されていたのだ。もちろん、「姥捨て山」がふさわしい特養ホームもたくさんあったのだが、私のいた施設や、周りのいくつかの施設では、そんな不思議なことが起きていたのだ。
だって不思議ではないか。専門家のそろった近代的な場でできなかったことを、シロウトばかりの施設がやっているのだから、世間の常識では考えられないことだ。いったい何が老人を生き還らせたのか?当時の私は考えた。それがわかれば学会で発表もできるし、本だって書けそうだ。
寮母たちに尋ねてみた。すると「いいじゃない、よくなったんだから理由なんかわからなくても……」と興味はなさそうだ。「でも問題老人のMさんがすっかり人気者になったけど、あれはどうして?」と聞くと、この時ばかりは「ああ、あれは理由がわかる、担当の寮母が好みだったのよ」なんて言う。たしかにそうだが、それでは学会で発表はできないではないか。
『介護職よ、給料分の仕事をしよう』(雲母書房)に私はこう書いた。
……それがそれ以来、何十冊もの本を書いてきた私の原動力になったと言っていい。それを解明することが私のライフワークになった。
でも、今になってそのことをたった一言で表すとするなら、私はこう言いたいと思う。「老人たちを元気にしたものは、老人が嫌がることをしなった」ということだと。
私たちに何か特別なことができたわけではない。特別なやさしさがあったとも思えない。やさしい人もいたが、そうでない人もいた。それは病院と同じだ。
でも抑制はしなかった。法的にもできないが、でも抑制している施設はいくらでもあった。だって抑制の方法を看護師が寮母に教えていたのだから。
医療や看護は“科学”をその根拠にしている。“客観的”な世界なのだ。だから医者の処方は客観的に正しくて、患者が嫌がったらどうするか、という場面設定がないのだ。……
そうだ、老人をダメにしてきたのは、まさに「近代科学」の客観的正しさなのだった。いや科学を擁護して言い換えるなら、人々の「科学」への前近代的な信仰心とでも言えばいいだろうか。あるいは、科学が及ぶ範囲を越えて適応しようとした誤りだと言ってもいいだろう。
それが「科学主義」と私が呼ぶものだ。その典型が、老い、特に認知症なんて名づけられている老人に科学を適応しようとしたことだろう。「認知症」の老人が医者の処方どおりにおとなしく点滴を3時間も受け続けるはずがない。ましてや鼻から入れられたチューブを抜かないはずがないではないか。
「本人が嫌がっています」と看護師が報告すると「それをどうにかするのが看護師の仕事だろう」と医者に言われ、ナースは嫌々ながら手や身体を抑制した。最初は嫌々だが、そのうち当たり前と思って縛るようになる。毎日のことだから感覚をマヒさせなければやっていけないからだ。近代的な科学は手を縛るという「野蛮」とたやすく結託する。
老人施設はそうはいかない。法的に抑制はできないのだ。やっていれば虐待で、虐待を知ったら通報する義務がある。くり返しになるが、ある施設では「私がやると朝まで抜けないわよ」と言って、介護技術の高さを誇る寮母がいたくらいである。牧歌的と見える世界も簡単に野蛮と結びつく。
しかし、私たちは、抑制なんていう発想すらしなかった。それをしたら、介護がもっている最大の武器、当時としてはほとんど唯一の武器を手放すことになるからだ。
さあ、それでも点滴が必要だということがあるだろう。その時、私たちは認知症の老人を「抑制」するという野蛮な方法以外にどんなやり方を工夫できるだろうか。現場で話し合ってみてほしい。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【特集 耳を澄ませて、こぼれた言葉をきく】
~臨床哲学からケアを語る~ 西川 勝
§---------------------------------------------------------§- 2009年4月 介護夜汰話 未来へのタイムマシーン
~インド・ヴァラナシへの旅~ 海外旅行はぜいたくだと感じる人も多いだろう。円高でちょっとした国内旅行より安いツアーはたくさんあるけれど、インドとなると、現地の通貨ルピーに対しては円高ではないし、インドの経済成長は著しいからデリーのホテルはそれなりの値段である。“きつい、汚い、給料安い”の3K職場の介護職にとっては簡単に行ける旅ではない。
それを承知のうえで、「介護職よ、北欧よりもインドへ行こう!」と私が呼びかけているのには理由がある。なにしろ、タイムマシーンに乗れるのだ。20万円足らずでタイムマシーンを体験できるのなら安いものではないか。
もっともこのタイムマシーン、過去への移動だけで未来へは行けない。日本で生活していたら、ロンドンやニューヨーク、どこに行ってももう未来を見ることはできないだろう。もっぱら過去を体験できるのが海外旅行、特にインドへの旅だ。
AI-307(エアインディア307便)と名づけられたこのタイムマシーン、調子がよくないらしく、いきなり出発が5時間以上も遅れる始末。午後6時にはデリーに着く予定が翌日にずれこんだ。それでもバスもガイドも待っていてくれるのだからインド人の「待つ力」はたいしたものである。
ホテルに入ってシャワーを浴びて、荷物を整理するともうモーニングコールだ。6時15分のニューデリー発の列車に乗らねばならないので、4時起床だったからだ。それでもツアーのみんなは元気。
「夜勤明けだと思えばいいんだから」
なるほど。
ニューデリーの駅前でバスを降りる。現地ガイドのアローラさんが「さあ、渡りましょう」と言うのだが、どう渡れというのか……。トラック、オートリキシャー、馬車で道はギッシリ埋めつくされているのだ。もちろん、信号もなければ横断歩道もない。でもそこで躊躇していると、一生渡れない。アローラさんを含めて総勢49人が一斉に車の間に入り込む。鳴り響くクラクション……!
やっと駅舎に入り込むと、毛布を敷いたり、かぶったりして人が寝ている。「列車を待ってるの?」と聞くと、アローラさんが答えた。「いいえ、住んでいるんです」。そうだった。インド3回目なのにそんな質問をしてしまった。日本ボケだ。年配の参加者が「終戦直後の日本みたい」と言う。そうか、AI-307便で六十数年前にやってきたのだ。
世界遺産のタージマハールやアグラ城を見学し、ヴァラナシへ向かうためツンドラという駅から寝台車に乗り込む。じつはこの寝台車がもっと過去へ向かうタイムマシーンなのだ。このタイムマシーンも性能はイマイチで、やはり4時間も遅れてヴァラナシの郊外に到着した。
ガンジス川の河岸に向けて狭い巡礼道を49人がほぼ一列になって歩く。下を見ていないと牛の糞を踏んでしまうが、下ばかり見ていると突然牛にぶつかったりするから大変だ。1000年前の日本の中世だと言えばいいだろうか。文明発祥の地インドだから、おそらく数千年も前から変わらぬ生活が繰り返されているのだろう。
列車が遅れたためわずか2時間半の街歩きだったが、昼食のために最新の近代的ホテルに入ると、その外と内との時代差に圧倒されてしまう。数千年を越えて現代に戻ったかのようだ。
もちろん、インドは急速に近代化されている。中産階級は新市街や都市郊外の防犯設備の整った塀の中に住み、子どもを私立の進学校に通わせている。ノイローゼやウツといった私たちと同じ近代人特有の病理をもつ人が増えているという。
でも少なくともヴァラナシの旧市街には、近代はほとんど影響も恩恵も与えていないように見える。それどころか、人々もそれを求めているように見えない。祖先が繰り返してきた生き方を連綿と引き継いで当然だと感じているようだ。

病気になっても近代医療は受けられない。老いや死にも近代は関与しないだろう。しかし、病気はともかく、生まれること、死ぬことに対して近代に何ができよう。死産を防ぎ、死を遅らせることはできたかもしれないが、陣痛促進剤の多用や点滴漬けでそれらを上回る問題をつくり出したのではないか。
老いやぼけ、死に対して医療をはじめとする近代的方法論は無力ではないか、と私たちは感じている。私たち自身の老い、ぼけ、死についても、近代は何も恩恵を与えてはくれないはずである。その時、では何に頼ればいいのか。私はヴァラナシの旧市街でそれを考えていた。
だって、彼らは近代に頼らずちゃんと生きている。近代的秩序はないがどうにかなる。少なくとも、金や薬や脳トレや筋トレに頼ろうとしている日本人よりもちゃんと生きているように思う。
最初に、海外旅行をタイムマシーンにたとえて、未来には行けないが過去には行けると述べた。だが、ここで私はインド、ヴァラナシの旧市街への旅は、自分自身の老いという未来へ向かう旅だったのだと気づくのだった。
近代的方法論が通用しない老いや、ぼけや、死は、あってはならないものだろうか。いや、近代的方法論が及ばないところこそが人生の基底なのではないか。
今回のインドの旅は個人的にも興味深いものだった。まず念願だった家族を同行してのインド行きが実現したこと。先入観があったことに加えて、ムンバイでのテロが起きた直後の旅行だったから抵抗が強く、半ば強制的に連れて行ったのだがよかったと思っている。
常識人の妻も興味を抱いたようだし、潔癖症の長男が「また行ってもいい」と言っている。また、子どもを連れていくことで、インド人の違う面が見えてきた。下の子といっしょに記念撮影してくれと何組もの家族が声をかけてきた。
街を歩いていると同世代の子が何人も声をかけてくる。物売りかと思ったが、そうではなくて話したがっているのだ。日本人の子どもが珍しいのだろう。
ガイドブックには「近寄ってくるのはすべて金目当て」などと書いてあったりするが、それはこちらが金持ちの日本人旅行客という立場だからなのだ。現地で盗難に遭って無一文になった時に、いかにインド人が親身になってくれたかというエピソードはよく聞くところだ。金をもたない子どもにもじつにフレンドリーに接してくる。
もうひとつ、個人的に興味深かったのは、2年前の初めてのインド旅行との因縁である。パスポートを紛失し、寝台車を10時間以上待ったあの旅行だ(「『生きたい』と『死にたくない』」本誌155号に掲載後、『介護職よ、給料分の仕事をしよう』(雲母書房刊)に収載)。
まず、ニューデリーで早朝に乗った列車が、2年前乗車直後にパスポート入りのショルダーバッグを紛失したのと同じ時刻の列車だった。当時のことを思い出し、どこかにバッグがスッポリ入ってしまうような隙間がないか、座席の下のほうを点検してみたが、もちろん、そんなスペースはなく、やはり盗まれたのだと改めて確信した。
さらに、因縁は続く。ヴァラナシへ向かう列車がなんとムガルサライ駅に到着したのだ。駅前で遅れた列車を10時間半待ったあのムガルサライ駅である。ムガルサライ駅はヴァラナシから車で1時間ほどの距離のところにある小さなまちで、曜日によってヴァラナシ駅に停まったり、このムガルサライ駅に停まったりするらしい。
駅に降りたった49人の中でもっとも興奮していたのは私だろう。駅前は2年前と同じく、オープンエアの立ち小便用トイレから臭いがたちのぼり、人やリキシャや、オートリキシャでごったがえしていた。いっしょに遊んだホームレス一家の姿は昼間のせいか見当たらなかったが。
私はこのムガルサライ駅に一生のうちにもう一度行ってみたいと思っていた。それが、わずか2年目にかなってしまった。私の一生は短いのかもしれないぞ。やりたいことをちゃんとやっておかねば、というわけで、来年もインドツアーを組んだ。いっしょにタイムマシーンに乗ろう!- 2009年4月 介護ブームらしいぞ
4月に入って、NHK教育テレビの「ワンポイント介護」が「三好流」と名付けて毎週放映し始めた。さらに2回にわたって総合テレビの人気番組「ためしてガッテン」が介護を特集した。
1回めには金田由美子さん、2回めには青山幸広さんに福辺節子さんと、私たちの仲間が出演したのは時代が変わったと感じさせた。
なにしろNHKは長い間、”安静強制看護法”を介護だとして教えてきた。その後こんどは”ボディメカニズム”とか”古武術”とかいった、エイヤッと起こしたりする”人を驚かせる方法”を紹介してきた。これらは新しく見えても、本人はじっとして受身になっているという点では安静法と同じである。
私たちの方法は、老人が自ら動く生理的動作を基本としている点では大きな変化だといえよう。私が新しい介護法を広め始めて25年目にしてやっと旧態依然としたNHKが変わったのだ。
だがやはり無理があるなあ、という印象は歪めない。どうしても、技術という結果だけを教えて、なぜそうなのかまでは伝わらない。なにより、バラエティ番組には介護という世界は向かないことがよく判った。
何でもテレビ界は介護をテーマにするのがブームだそうだ。視聴率がとれるらしい。でも私はせいぜい教育テレビまでにしておこう、と思った。ブームには乗らない。ブームは自分の作るものだ。- 2009年3月 介護夜汰話 介護現場のほんとの3K
介護現場にとって待ちに待った不況がやってきた。かつての不況時には介護の仕事に求職者が殺到したことがあるので、深刻な人手不足の解決になると期待されていたのだ。でも、派遣切りや正社員の解雇が続いているというのに介護現場の人手不足は解消されそうにない。それほど介護の仕事は大変だというイメージが一般化しているらしい。
3Kというコトバがある。かつての高度経済成長時代に、土木や建築現場の仕事が“3K”と言われて嫌われ、外国人労働者が導入されるに至った。3Kとは何だったか。①きつい、②汚い、くさい、③危険の3Kである。
介護現場も3Kだと言われる。たしかに、きつい、そして汚い、くさい。危険はどうだろう。介護職はそれほど危険とは思えない。危険なのは老人のほうだ。寝たまま入る特浴が楽でいいと思ったら大間違いだ。足は浮くし頭は沈む。リラックスするほど溺死しそうになる。
オムツ体験をしてみる介護職は多いが、特浴体験もぜひしてみるといい。私たちが特浴をできるだけやめて、安定・安心して入れる家庭用の浴槽を使おうと訴えている理由が身体でわかるだろう。
水着になって浴槽に入ってみる前に、互いにストレッチャー体験からやるといい。ストレッチャーに上を向いて寝て、施設の廊下を浴室まで“運搬”されるのだ。デリカシーのない職員に“効率よく”廊下の角なんか曲がられると恐怖である。実際に特浴での溺死事故、ストレッチャーからの転落事故が相次いでいる。
介護という仕事は、3Kのうちの「危険」はあてはまらないが、その代わりのKが「給料安い」である。しかし、この3Kは介護の仕事に本当にあてはまるだろうか。まず「きつい」。
私はかつて、看護や介護がきつい仕事だというのは、他の仕事をしたことがない人の言うことだと書いたことがある。残業はむちゃくちゃ、しかも成績が悪いと即クビ、労働基準法も何もあったもんじゃないという民間の仕事をいくつも経験してきた私にはそう感じられた。
ただ、時代は変わって介護労働はたしかにきつくなった。特に、小規模施設での「一人夜勤」は、日本社会からの介護職へのいじめであると言ってもいいくらいだ。大きな施設でも「ユニット」に分けて、1人で25人も30人もの老人を相手に夜勤させているところがある。「小規模のほうが個別ケアができる」などというデタラメをふりまいた罪は大きい。
2つめの「汚い」「くさい」はどうだろう。これは3日で慣れる。逆に介護現場を離れるとあの臭いがなつかしくさえなる。3つめの「給料安い」はたしかにそうだ。でも不況には強い。明日から来なくていいなんてことはない。
私の周りの介護職には仕事を辞める人が多い。経営者や上司とけんかして辞めるのだが、他の介護現場で介護を続けている。介護そのものに嫌気がさして他の分野に移る人もいるが、1年もするとまた介護の仕事に戻っている。「やっぱり介護以外の仕事はおもしろくない」というのだ。
こうした人たちは「3K」はあまり問題だとは思っていない。もちろん、きついのも、給料が安いのも何とかならないか、と日本の政治を呪ってはいる。でも、職場を変えたり、介護に嫌気がさしたりするのはこの「3K」のせいではない。別の「3K」だ。私が介護という仕事が抱えているホントの問題点であると思うのは「権威主義」「管理主義」「金もうけ主義」の3Kである。
権威はあってもいいが、権威のある人の言うことに従うべきという「権威主義」では介護職は元気にならない。そこでは医師を頂点とする専門家がハバをきかせて、老人の表情を見ている介護職の感じていること、思っていることは考慮されなくなる。
よく会議の最中に意見が違ってくると「私は看護師です!」と言う看護師がいる。知ってますよ。これは論争で旗色が悪くなると資格を持ち出すという典型的な権威主義だ。
管理はあって当然だが、「管理主義」は老人に合わない。従順に上を向いて寝ているという“患者”を老人に強制したことによって生じた無数の悲劇を思い出せばいい。いまだに手足を縛られて、あっという間に主体の死や認知症に追いやられる老人が続出している。認知症予防は脳トレではなくて、医療と看護が抑制をやめること、老いに適応していくことである。
金もうけは悪いことではない。しかし、それを目的とする「金もうけ主義」になると、介護も老人もその手段にされてしまう。「○○さんが初めて笑いました!」と報告しても「それがどうした。経営に何の関係がある?」なんて言われたのでは、そりゃ辞めたくなる。
介護現場をよくするために、人手不足や安い給料といった待遇の改善を求めることも、もちろん大切だ。でも介護の中身をよくするためには、そして待遇がよくなった時に、それをよい介護に結びつけるためにも「権威主義」「管理主義」「金もうけ主義」の3Kと闘い、克服することが必要とされていると私は思う。- 2009年3月 「問題」をユーモアに変えるコトバの力、文化の力
夕飯にビール飲もうと冷蔵庫 / ドアをあければ本が冷えおり
(山口県 大田孝子さん)
2月26日夜放映の「介護百人一首」で紹介された歌です。その本が私の「じいさん、ばあさんの愛しかた」(法研、現在は新潮文庫で「老人介護 じいさん、ばあさんの愛しかた」)だったそうで、司会の小谷あゆみさんも読んでいたので私の名前も出てきました。
ゲストの坂東英二さんも感心してたけど「問題」をユーモアに変えるコトバの力、文化の力を感じますね。こうした介護の現場で読まれていると思うと感無量です。- 2009年2月 介護夜汰話 マルクスの代わりに出産がきた
~『102歳の嫉妬』の書評に代えて~ この文章を書いているのは2008年の年末である。今年の講演の仕事をすべて終えた解放感のなかにいる。仕事が嫌なわけではない。むしろ好きなぐらいだが、それでもしばらく仕事がないとなるとうれしくなる。
2007年は働きすぎて、数えたら年間217回も講演をしていた。今年は少なくしようと決意していたのに、数えてみると209回だった。それに加えて、NHKやら、出版の仕事も加わったから、休みがうれしいのも当然だろう。
年内に残った仕事が一つ。それがこの「介護夜汰話」の2月号原稿だ。それを書くために家のコタツの上に2冊の本を並べている。1冊は『102歳の嫉妬』(大洋図書)である。本誌でも紹介したが(2007年12・1月号)、いつかちゃんと書かなければと思っていた。副題に「介護の日々を笑って暮らす8つのヒント」とある。
介護家族から始まって、介護に関わるさまざまな職業の人が登場する。私がいつかぜひちゃんと書かねば、と思ったのはそのなかに登場してくる阪井由佳子さんのことである。阪井さんは本誌の読者なら知らない人はあるまい。新しい読者のために簡単に紹介すると、彼女は富山市の「デイケアハウスにぎやか」の代表である。
老人保健施設のPTだったバツイチ・コブ付きの彼女が介護に入り込む過程と、その後の実践は『親子じゃないけど家族です』(阪井由佳子著・雲母書房)を読んでほしい。『102歳の嫉妬』にもインタビューが載っており、『親子じゃないけど家族です』とはまた違った臨場感があっておもしろい。しかし、この本での阪井さんの最大の魅力は「にぎやか」での初めてのターミナルケアの話である。
特養ホームの一部は、当たり前のようにターミナルを引き受けてきた。私も何十人ものお年寄りを施設で見送った。小規模施設でも、たとえば福岡の「宅老所よりあい」では、18年間で30人もの人を看取ってきたという。だから、生活の場の看取りは珍しいことではない。すごいのは、この体験を語る阪井さんのコトバである。「人が生まれる時と死ぬ時はすごく似とる」というのだ。
「最後の1回が止まった時に、一瞬みんな静かに……。時が止まったように、息がとまったん。で、その静寂のあと、みんなが泣き出す……。人が生まれる時と、人が死ぬ時って、すごく似とるとおもったわけ」
「つるんって、母親の身体から出てくる時に一瞬の静寂がある。そのあとに子どもが『うわ.ん』って泣くやん?」「あの瞬間って、また新しく時が始まるっていうか、生きる人たちの、新しい生がまた一歩始まる。トシちゃんの死のあとに、うちらがまた、1分1秒刻んでいく……」 (『102歳の嫉妬』212頁)
コタツの上のもう1冊の本は『経済学・哲学草稿』(岩波文庫)である。「昭和42年3月20日発行第6刷」とある。
阪井さんの発言を読んで、私がすぐに思い起こしたのが思想家カール・マルクスのこの本だった。当時17歳だった私には、容易には理解できない難解な文章だが、受験勉強を断念して読みふけった跡が膨大な傍線や書き込みとして残っている。そのなかで、私が最も傍線を引いている「第三草稿」の2「私有財産と共産主義」のなかにこんな文章がある。
死は〈特定の〉個人にたいする類の冷酷な勝利のように見え、そして両者の統一に矛盾するように見える。しかし、特定の個人は単に一つの特定の類的存在であるにすぎず、そのようなものとして死をまぬがれないものである。
私はかつて、この文章を要約して自分の本で引用したことがある。『なぜ、男は老いに弱いのか?』(講談社文庫)のなかでのことだ。私たちの求めているのは、どんな生き方をした人であれ、老いて死んでいくということを、丸ごと肯定できるような理念なのである。
個人が集まってつくったはずの社会や個人の集合体である人類、それに歴史のほうが、個人よりも価値があると思えてくるという倒錯から逃れるための論理は、実はマルクスが提出している。マルクスは、人間は類的存在であると規定し、個と類は統一されており矛盾しないのだと説いた後でこう書いている。
「個人の死は類の個に対する一方的勝利のように見える。しかし個人はある特定の類的存在であって死を免れないのだ」と。(『経済学・哲学草稿』)
これを私はさらに次のように読んだ。私がある特定の類的存在なら、私が属している類もある特定の類なのである。つまり私が死ねば、その特定の類も死ぬのである。もちろん、次の瞬間、私を含まない特定の類が誕生するのだけど。
つまり私は一人で死ぬのではなく、ある特定の類を道連れにして死ぬのだ。だとしたら、一人で死んでいくことにむなしさを感じる必要はないではないか。マルクスはこうした論理で個人を救済した。見事なものである。ただこの論理には大きな問題点がある。その論理の正しさに実感がついていかないことである。
何ということだ。阪井由佳子は大思想家マルクスの論理を実感で語っているのだ! 私は難解なマルクスを引用して、一人の老人の生と死を肯定しようとしてきた。彼女は、マルクスを読む代わりに出産をして、その体験を看取りと同じだ、と喝破して一人の老人の生と死、のみならず世界を丸ごと肯定したのだ。
それに関連して本を2冊、思い出した。1つは『詩と死をむすぶもの』(朝日新書)での谷川俊太郎さんと徳永進さんの対談のテーマになっている「もとのもとは1」だ。コトバができて世界を「善と悪」や「生と死」というふうに2分割する前には、ぜんぶ「1」だったという話。阪井さんは生と死を「1」にしちゃったのだ。
もう1冊はドストエフスキーの『罪と罰』の最後に出てくるコトバ。「弁証法の代わりに生活がきたのだ」そう、マルクスの代わりに出産がきたのだ。ラスコーリニコフ(『罪と罰』の主人公)が変わったように、私もより生活的な人たちにバトンタッチしていこうと思う。
§------------- 参考図書 --------------§
102歳の嫉妬
~介護の日々を笑って暮らす8つのヒント~
著者:鎌田孝志、他
発行:大洋図書
体裁:A5判・255頁
定価:1,600円+税
なぜ、男は老いに弱いのか?
著者:三好春樹
発行:講談社
体裁:文庫判・247頁
定価:552円+税
§---------------------------------------§- 2009年2月 インドレポート 阪井 由佳子

■1月7日(1日目)
~インドの飛行機、スチュワーデスにびっくり!~
12:00に出発する予定の飛行機が5時間以上遅れた。 でもインド人びっくりしない。文句言う人もいない。 日本人もすでにインドモードに切り替わっているためか、「さすがインド」と笑ってしまう。
待っている間、航空会社から大した説明も謝罪もない。スチュワーデスみたいな人たちに申し訳なさそうな態度もない。さすがだ。 出発からしばらくして、何の案内もなく機内食が配り始められた。
お盆をもったスチュワーデスらしき人が、顎でテーブルを出せと合図する。顎でだよ。顎を前に出して「ほら、ほら出せよ」みたいな。 でも食べたよ。まあおいしかった。 ビールも飲んだ。飲んでる最中、何度スチュワーデスらしき人にその缶を持ち上げられたことか…
片付けたいんだろうね。でも中身があるので置いていく。何も言わずに勝手に私のビールを持ち上げるんだよ。…日本じゃありえない。 でもこのとき、 昔山谷ばーちゃんが、食事介助のとき、いちいち聞かれるのが面倒臭い。って言ったのを思い出した。 「聞かんでいいから、あんたが食べるように食べさせてくたはれ」って。
介護職のマニュアルでは、食事介助の時、「何から食べますか?次は?」とか聞くことが人間の尊厳を守るみたいなことになるんだろうけど、そんなの毎日、毎食度にやられちゃかなわんよね。 それと、インドのスチュワーデスが重なった。 日本人スチュワーデスみたいに作り笑顔で親切すぎるのもうっとうしい。 おせっかい介護、やりたがり介護の人。インド人スチュワーデスに習えですわ。

■1月8日(2日目)
~私のおしっこがインドの地に吸い込まれていった~
早朝。ほとんど寝ていない。 でも気分はいい。1月のインドは寒い。 駅の構内にたくさんの人が道路に寝転んでいる。その人の多さに絶句。見たことのない光景。
新幹線のような電車にのって「タージマハール」に行くとの説明。 しかし乗った電車は新幹線とは程遠いものだった。 トイレのカギはかからない。紙もない。汚い。くさい。 そのトイレは前と後がわからない。とりあえず足を乗せる場所に足をのせてしゃがんだ。
穴からは線路がみえる。思いっきり穴からは電車の走る外の音が聞こえてくる。 そして、私のおしっこはその穴に見事命中し、インドの地に吸い込まれていった。 その時、私はなぜか、ひどく落ち込んだ。 しょせん、私も動物。野良犬と野良牛、そして車窓の外では並んでウンチしているインド人と一緒。
物乞い、物売りの子供たちにショック!! タージマハール(世界遺産)について大型バスが止まると、物売りの子供たちが殺到してくる。キーホルダーやTシャツを、「やすいよ」「にほんじんやさしいね」とか言いながら、ずっとついてくる 見たらかわいい子供だよ。

汚い服をきて、言葉巧みに物を売る。中には障害を持っている子供もいる。その姿は噂には聞いていたが見たくなかったぁ?。やっぱ切ないよ。直視できず、対応に迷う。同情で買ってあげればいいのか。でも同情なんて・・・その子供たちをどう解釈していいかわからない。自分の心のどこかに、この子供たちを可哀そうに思っていることに情けなくなる。「自分が何様なんよ!」
どこに行っても子供たちが集まってくる。戸惑いも大分慣れてきた。 そしたら、最初は不憫で可哀想に感じてたのが何だか不幸には見えなくなってきた。それどころか、子供でない大人の目をしている。 そして、この子供たちはこの物売り、物乞いのプロなんよ!!
この子供らはプすごいんだよ! この子供たちを直視できず完全に無視していたとき、私のまわりには全くまとわりつかなかった。買ってくれそうなやさしい人のところに集中して行く。その獲物は絶対に逃さないとばかりに。 ところが、ふと私の心に「ちょっと買ってもいいかな?」と思った瞬間、私に食らいついてきた。すごい。この子らは客の心を読んでいる。
人の心って読めるんだよ。 介護も人の心の読めない人、空気の読めない、状況判断ができない人は無理でしょ。やっぱプロなら心を読む力、センスを養わないといけないね。 それが分かった瞬間、私の中で可哀想な子供たちから、凄腕の仕事の達人という見方に変わった。
ちょっと気持ちが軽くなった。 そして、この夜寝台列車に乗り込み、昨夜寝ていないこともあり、汚いと思いつつ深い眠りに。
■1月9日(3日目)
~ガンジス川は汚かった。臭かった~
インド人はいっぱいいるから、命も軽い? ガンジス川の沐浴、火葬場を見るために移動~~~
途中でごめんなさい!
続きは「にぎやか」の広報誌『ブラボーにぎやか』でお読みください。
■連絡先
特定非営利法人 にぎやか 代表 阪井 由佳子
〒 930-0845
富山県富山市綾田町1-11-17
TEL 076-431-0466 FAX 076-431-0486
http://www.nigiyaka.jp/index.html- 2009年2月 TV評 NHKスペシャル「闘うリハビリ」
2月8日(日)夜のNHKスペシャル「闘うリハビリ」を見た。「闘うリハビリ」という題への違和感を持ちつつ見ていたが、やはり、身体が生活を一方的に規定するという古いリハビリの概念(IC-IDH)にもとずいた内容で、2週間の集中訓練で歩行機能を向上させたというケースも「家に帰ったら元に戻るんじゃないか」
「これから老化がやってくるのはどうするんだろう」
「障害のある人はこうして一生闘わなきゃいかんのか」という気分になった。
しかしさすがに大田仁史先生が番組の助言者になっているだけあって、最後に紹介された左片マヒの写真家の言葉には感動してしまった。
治るか治らないかはどうでもいい、自分のやりたいことができるかどうかだ、と言うのである。
主治医は長谷川乾先生。この先生には私は恩がある。”生意気なPT”として業界に出たときに誉めてくれたのだ。生意気とはいえ小心者の私には有難い励みになった。さすがである。リハビリとは闘うものではなくて、その人らしく生きることそのものだということを教えてもらった。- 2009年1月 介護夜汰話 私たちが医療に興味を示さない理わけ由
~βアミロイドの沈着をめぐって・2~ 認知症は脳の病気である、というキャンペーンが行われている。40代から起こるアルツハイマー病やピック病はたしかに脳の病気だろう。だが、高齢者の痴呆症状の原因を脳に求めるのは無理ではないか、というのが私たち介護職の実感である。
だが、NHKのテレビ番組をはじめとして、「脳の病気説」はますます勢いづいているし、介護職向けの研修でもまずは医者による脳の病変が講義される。特に、アルツハイマー型痴呆については、その病変が明らかになるにつれ、若年性のアルツハイマー病と同じであるとして、高齢者についても「.型」ではなくて、「アルツハイマー病」と呼ばれるようになった。
そのアルツハイマー病の病態解明を25年にわたって研究してきた学者の本を読んでみることにした。それによると、それまでは老人斑や神経原線維変化などがアルツハイマー病の病変とされてきたが、それらの原因や引き金でもある「βアミロイド」の沈着こそがアルツハイマー病の原因であるらしいこと、少なくとも因果関係があることが明らかになったと書かれている。
説得力のあるデータも載っている。βアミロイドの沈着と認知症の発症が見事に連動しているのだ。しかも若年認知症の脳にもβアミロイドの沈着が見られるとなると、認知症、少なくともアルツハイマー病とアルツハイマー型痴呆の原因と推察されるという論理にもうなづいてしまいそうだ。
しかし、図をよく見ると、私たちが関わっている80代の人では70%の人にβアミロイドが沈着しているのだ。90代では80%に及ぶ。となると、βアミロイドの沈着は病変というより、老化なのではないか。そうでないというのなら、老化が病気だと言い張るよりほかにないだろう。
βアミロイドは20年もかけてゆっくり沈着するらしい。それも老化と同じだ。βアミロイドと認知症は因果関係ではなくて、並存関係だろう。原因は両方とも老化ではないだろうか。若年認知症の場合は、何らかの原因で脳の早期老化が起こっていると考えれば納得がいく。
歳をとると、顔のシワが増える。一定の数以上シワがある人の割合と認知症の発生率は見事に連動するはずだが、顔のシワが認知症の原因ではない。さらに推察するなら、シワを美容整形術で伸ばしたとしても老化が進まないわけではない。それと同じようにβアミロイドの沈着を防止できたとしても老化は防げないので、認知症の予防にもならないだろうと、私は考えている。
学者たちの研究にもかかわらず、そうした試みは“錬金術”でしかないだろう。老化という自然への抵抗は無駄なことだ。もっとも科学の歴史の教えるところでは、錬金術は金はつくれなかったが、近代科学の発達には大きく貢献したわけだが。
私たち介護職がいくら官製の研修会で啓蒙されようとも「脳の病気説」に興味を示さないのは現場のリアルな体験のせいだ。76歳で特養ホームに入所して、98歳で大往生したOさんの22年間につき合ってみると、呆けが脳の病気というほど単純なものではないことが身にしみてわかる。呆けた結果だけを見ている医療者とは違うのだ。
私たちは、入院してわずか3日後には目がトロンとしていたSさんや、同じく入院して次の日には錯乱状態となり入院時に付き添った私さえもわからなくなったTさんを知っている。Sさんはトイレに行けないからとオムツをあてられ、Tさんはゴソゴソするからと手足を縛られた。わずか3日で、わずか1日で、βアミロイドが沈着する訳がないではないか。
こうしたケースに“病気説”は次のように反論する。「それまでβアミロイドが沈着していたから、オムツや抑制をきっかけにして認知症になったのだ」と。しかし、βアミロイドが沈着していても認知症にならないで一生を送る人もいるのだ。SさんもTさんもそうだったかもしれない。
そうであれば、原因はβアミロイドではなくて、「オムツ」と「抑制」と言うべきではないのか。認知症が治ったケースも私たちはたくさん経験している。それに対しても「認知症は治らないのだから、そのケースはそもそも認知症ではなかったのだ」とくる。これって、後出しジャンケンじゃないの?
私のこうした主張に対して、医学関係者のなかには「医学の全否定ではないか」と言う人がいる。また、「関係論の大切さはわかるが、関係論100%というのはまちがいだ」ともよく言われる。もちろん、私は医学をすべて否定してはいないし、関係論だけですべてが説明できるとは微塵も考えていない。
でも、医学関係者からはそう見えるらしい。なぜだろうか。たしかに私はβアミロイドには無知だが、そもそも興味がないのである。これもまた学者には腹立たしいことだろう。なにしろ、そのアルツハイマー病を25年にわたって研究してきた学者は医学だけでなく介護にもちゃんと言及しているのだ。
三好も少しは医学を認めたらどうだと思っているに違いない。なぜ、私や多くの介護職はβアミロイド説に興味がないのか。それを考えてみることにした。長くなるので、続きは次号で。- 2008年12月 麻生政権が生き延びる道
かつての総選挙のとき、評判の悪い安倍内閣に対して、こうすれば選挙に勝てるという提案をこのホームページでしたことがある。これを採用しなかったために、自民党は大敗し、その後安倍信三は辞任に至ることになったのだ(と私は思っている)。
さて、もっと評判の悪い麻生内閣に対しても選挙で勝てる策を提案したいと思う。もちろんこれは小沢民主党でも社民党でも公明党でもその将来を保証することになる政策である。金はない。それなのに介護・医療・年金は崩壊しそうである。景気は悪いから税収が増える訳もない。そこで消費税を、となるのだが、待ってほしい。いい方法があるのだ。
私の提案するのは以下のとおり。
1.もう高速道路は作らない。
宮崎や鳥取県知事は「高速を!」と訴えているが、自動車専用道で十分。それどころか、現在利用度の低い高速道路はコンクリートを解体して木を植える。それを「グリーンベルト」と呼ぶ。それを作れば自然を回復できるし温暖化防止にもなる。
2.もう空港は作らない。
それどころか赤字の空港はコンクリートを解体して木を植える。こちらは「グリーンスクエア」と名付ければいい。
3.もう新幹線は作らない。
山形や秋田のような在来線乗り入れで十分ではないか。
土建屋とそこから金を吸収している政治家は猛反対するだろうが、各選挙区に”刺客”を立てればいい。郵政で小泉がやった手だ。有権者は支持するはずである。土建屋さんや建設会社はコンクリートを解体して再利用する技術を開発すればいい。維持管理と耐震化の領域と合わせて生き延びていけ。
道路、空港、新幹線への予算及び、廃止した高速道、空港の赤字分で浮いた金を全て、介護と医療、年金に当てることにすればいい。もちろん以前に提案したように、介護職の給料は1.5倍にする。そうすれば、麻生大嫌いの私をはじめ、介護関係者と家族は投票するぞ!
それにしても麻生なんかを総理にしたら失言連発で自滅することくらい最初から判るじゃないか。自民党はそんなことも判らなくなってるのかねぇ。
- 2008年11月 介護夜汰話 β(ベータ)アミロイドの沈着をめぐって
なぜ、痴呆の老人に関わる私たち介護職が医療に興味を示さないのか、その理由を3点にまとめて考えてみたいと思う。
第1点。これまで医療のやってきたことに散々な目に遭わされたからである。出された薬の効き過ぎや副作用でどれだけの老人がダメにされただろうか。徘徊や奇声、不眠に対して処方された睡眠剤や精神安定剤のせいで目がトロンとなり、“問題行動すらできなくなった”老人は数知れない。
「『痴呆』に新薬」と新聞が報道するたびに、その製薬会社の株は上がり、老人病院などは大量に服用させたが、たとえば、かつての「ホパテ」なんて薬は副作用で多くの老人を死に至らせている。「昔の薬と違って、現在のものは効果がある」と言って処方しているが、それも怪しいものだ。医者がいないところで家族や介護者に「効果があると思うか?」と尋ねてみるといい。
「効果なし」ならまだいいほうで、かえって落ち着かなくなったというケースも多いはずだ。「問題行動があって困っている」と医者に相談すれば、医者はほかに手段をもっていないから薬を出す。それを知った私たちは、医者には言わないで、自分たちでいろいろ工夫してみるほうがはるかにマシだと思うに至ったのである。
第2点。「介護の方針を決めるのに医療の知識や情報は不可欠だし、役にたつはずだ」と意見する人もいる。三好のような“反医学”ではよい介護はできない、というのだ。たとえば、脳の画像診断という情報によって、いろんなことが予想できるという。脳の萎縮があれば、痴呆症状が出る可能性が高い、というふうに。
ところが、萎縮があっても症状のまったくない人がいることはよく知られているし、萎縮がなくても問題行動だらけという人もいる。脳のどの部分が萎縮していたら、どんな症状が出るかという予測もできるという。しかし、それも予測でしかない。当たるケースもあれば、そうでないケースもある。脳の画像診断とはそれくらいのものだ。
しかし、2日もいっしょに暮らせば、痴呆があるかどうかも、どんな問題行動があるかもわかるではないか。予想ではなくて、確定するのだ。しかも、どう関わればいいかということまでわかるのである。わざわざ画像診断をする必要があるだろうか。
第3点は、人間とは何か、人間と脳とはどんな関係にあるのかを問うことにつながっている。病気の原因を身体の特定の臓器の病変に求めるのを「個体還元論」という。中世では病気の原因は悪霊だなんて思われていたから、「個体還元論」の効果は抜群で、多くの病気が治癒できるようになった。
となると、精神の病気の原因は脳にあると考えればいいことになり、精神分裂病(現在の統合失調症)の原因を患者の脳細胞に探すという研究が始まることになる。ところが、ご存じのように、精神分裂病には脳の病変はどこにもない。これもご存じのように、現代の日本に大流行のうつ病にも何の病変も見つからない。精神分裂病もうつ病も、脳の病気ではなくて脳によってつくられる精神現象の問題である。脳は目に見える具体的な物質だが、精神現象は目には見えない。
医療関係者は、人間の意識、精神は脳がつくると考えている。確かに脳がなければ、意識も精神もないだろう。だが、意識の内容、精神の中身は脳が決めるのではない。頭がいいとか悪いとか、抽象的な思考をするタイプかどうかは脳が決めるのかもしれないが、何を考えているかとか、何を幸せと思うかまで決めるわけではない。
アインシュタインの意識は、彼の脳が生み出しているだろうが、脳を調べたからといって相対性理論が出てくるわけではない。ちなみに、私の『痴呆論』(雲母書房)を批判している学者さんは、テレビ局の依頼でアインシュタインの保存してあった脳の分析をしたそうだが、ちゃんと年相応の変化があったというからなおさらである。
ドストエフスキーの意識を彼の脳がつくったのは間違いないだろうが、彼の作品である『罪と罰』は彼の精神現象がつくり出したものであって、脳を調べても出てはこない。
精神の現象そのものによってつくられる世界を、たとえば、ヘーゲルは『精神現象学』という本で明らかにし、フロイドは意識に「無意識」を対峙させて、その世界を解明しようとした。吉本隆明は「精神」とも「意識」とも言わないで、「心的世界」と表現し、『心的現象論序説』(角川文庫)という本を書いた。
吉本は、生命体が自然から離れてしまったことによって生じたものを心的領域の始まりとし、それを「原生疎外」という独特の言葉で表現している。その疎外された心的世界は、心的世界そのものの働きによってその世界をつくっていく。これを吉本は「純粋疎外」と名づけている。
彼の表現に倣えば「原生疎外」は脳によってつくられているが、「純粋疎外」は疎外された世界そのものが自己展開していると言っていい。痴呆老人の意識、精神は彼らの脳がつくっている。しかし、その意識世界、精神の中身は脳には還元できない。心的世界そのものの内部がつくっている世界だからだ。
痴呆性老人の問題行動を引き起こす精神世界はこの内的世界で起こっていることだ。脳ではとても説明できない。したがって、どうケアすればいいのかは、脳ではなくて、老人の、吉本流に言うなら「心的現象」を解かなくてはならない。
見当識障害、つまり、ここがどこか、今がいつか、自分は何歳でなぜここにいるのかがわからなくなっていることを、医療では現実との差によって、+、++、+++というふうに数量化して見ようとする。
しかし、私たちはその見当識障害の中身を見る。いったい、いつの時代のどこに回帰しているのかと。すると、大半の老人は、大変だったけれど周りから頼りにされ、自分が自分だと感じられた時代に戻り、その頃いた場所に帰っていることがわかってくる。すると、これは現在誰にも頼りにされておらず、自分が自分だと感じられなくなった老人が、自己回復を図っているのではないかと考えることができる。
医療では、人物誤認もまた問題として、+、++、+++で、数量化する。でも私たちは、老人が周りの人を誰と思っているのかというその現象にこそ興味がある。すると、周りの老人や介護職は、かつて自分が最も自分らしかった時代に周りにいた人であることがわかってくる。すると、これは、過去の人間関係のなかで自己確認しようとしているとともに、過去の人間関係になぞらえて、新しい人間関係を受け入れようとしているのではないか、とさえ思えてくる。
なにしろ、デイセンターへの通所開始や施設入所というまったく新しい人間関係を、80歳や90歳になって受け入れなければならないのだ。人物誤認はもう認知症老人の智恵というべきではないか。
私たちが見当識障害に対して、リアルオリエンテーション、つまり、ここがどこか、今がいつかを教育しようとしないのも、相手の人物誤認をむしろ引き受けて、その役割を演じることがあるのもそうした心的現象から導き出したものだ。
それは老人を現実から遠ざけるものではないか、という批判は当たらない。なぜなら、私たちは一方で、過去の自分に回帰しなくても自己を自己として確認できるようになるアプローチもまた知っているからだ。それは『痴呆論』の「痴呆介護の7原則」の中で、たとえば「個性的空間づくり」「一人ひとりの役割づくり」、そして、「関係づくり」というかたちで提案してきたアプローチである。
見当識障害や人物誤認を受け入れたほうがよいということはよく知られるようになってきた。でも、「認知症の老人は脳の病気でどうせ言ったってわからないのだから、そのまま受け入れなさい」というふうに考えているのだとしたら、それはむしろ医療者や介護者の側こそ“認知症”なのである。脳だけ見て、宝の山である老人の現象を認知しようとしていないのだから。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【対談】 現場の閉塞感をうち破るもの
三好春樹×高口光子
§---------------------------------------------------------§
- 2008年10月 介護夜汰話 「プライバシーを守れ」という差別
介護現場にいる者は、哲学なんてものとは縁がないと考えているし、哲学者と会ったこともない。もし会ったとしても難しいことばかり話されて理解できないだろうと思っている。
しかし、看護助手として介護現場に入り、病院や施設で仕事をしてきた人が哲学の世界に入ったらどうだろう。それでも敬遠したくなる気持ちはよくわかる。だって現場からアカデミズムへ入る人は多いが、その人たちは、現場で感じていることややっていることとは別の世界としてアカデミズムに入り込んでしまうからだ。
でもこの人は違う。定例の読書会で読んでいる『ためらいの看護』の著者の西川勝さんである。ここでは看・介護現場の現実と哲学とがちゃんとつながっている。何とかつなげようとすることが彼の“臨床哲学”そのものだと言ってもよくて、この本のおもしろさはそこにこそある。
 ためらいの看護 ~臨床日誌から~
ためらいの看護 ~臨床日誌から~
著者:西川 勝
発行:岩波書店
体裁:四六判・上製・209頁
定価:2,300円+税
なかでも私が「オッ」と身を乗り出したのが、「隠すプライバシーで露わとなること」と題された第7章である。privacy というコトバの語源が明らかになっていく。現在では privacy は「私的な」と訳されるが、もともとは、ラテン語の privatus=奪われた、であるという。公務や公職に就けない、そうした権利を奪われた状態だというのだ。
「それは文字通り、なにものかを奪われている(deprived)状態を意味しており、ある場合には、人間の能力のうちでもっとも高く、最も人間的な能力さえ奪われている状態を意味した。私的生活だけを送る人間や、奴隷のように公的領域に入ることを許されていない人間、あるいは野蛮人のように公的領域を樹立しようとさえしない人間は完全な人間ではなかった(『人間の条件』ハンナ・アレント著、西川氏の引用による)。
そうか。プライベートとは、社会に名乗り出ることさえ許されていない、ということだったのか。私は長い間の疑問が解けたような気がした。その疑問とは「プライバシーを守れ」と声高にお説教する人への違和感である。まず専門家。ケース報告では「ケースA」「ケースB」、あるいはせいぜいT・Yなんていうイニシャルしか許されない。
次に、二言目には「人権」と言う人。発表スライドで写真をそのまま出したりすると烈火のごとく怒るのだ。でも「プライバシーを守れ」という彼らの言い分が、間違っているとは思わなかったから、“正義の私的所有者”として威張りたいんだろう、とか、「事なかれ主義」ではないのかと、心の中で批判してきたのだった。
その反対に、“プライベート”を気にしない現場の人には共感を覚えることが多かった。「Aさん」と言って始めたケース報告が、途中でいつの間にか「山下さん」という実名になってしまって「あっ、すいません。でももういいか……」なんて自分で言って実名を通したりするのも、よそ行きの顔が普段の顔に戻ったみたいでほっとしたものだ。
参加者の反応もほほえましさへの好意的な笑いであった。少なくとも私たちが主催する「オムツ外し学会」ではの話だが。地方でいい介護をしている老人施設に実践報告を頼むと、本人の顔が大きく映し出されるスライドと実名、さらには愛称が堂々と語られることが多い。「家族と本人の承諾は?」と尋ねると「喜んでOKしてくれました」なんて言う。おおらかというか、信頼があるというか。
そうか、「プライバシーを守れ」と言う人たちは、正義を武器に威張っているだけでもなければ、事なかれ主義であるだけでもない。彼らは施設や在宅の要介護老人を、公的なところで名乗る資格を奪われた存在だと考えている差別者だったのだ。納得である。
老化や障害によって要介護状態になったことや、施設で生活していることは、隠さねばならない恥ずかしいことだろうか。もちろんそう思っている本人や家族もいるだろう。でもそれは、老人ケアに関わるものにとっては、「そんなことありませんよ」と説得すべきことではないだろうか。だってそうした感じ方こそが老人や障害者を生きにくくさせているのだから。
さあ、要介護老人たちに名乗ってもらおう。もちろん私たちによる「ケース報告」としてではなく自らの自己表現として。私たちはその媒介になるべきなのだ。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【対談】 ブリコラージュ20周年記念
三好春樹ロングインタビュー
◎インタビューア/ 東田勉
§---------------------------------------------------------§
- 2008年9月 介護夜汰話 「美しい」の謎が解けた
今年の3月15日にNHK教育テレビで放映された「ETVスペシャル」を見た人も多いだろう。助言者として私のほかに、PTにして医者で『あんたは名医だ』(筒井書房)の著者である稲川利光さんにも参加してもらい、これまで「なるほど、なっとく介護」に出演していただいた要介護者と家族にも出演してもらって、なかなかいい番組になった。
私がうれしかったのは、真屋順子さんがゲスト出演を引き受けてくれたことだ。真屋さんはバラエティ番組にも出ていた女優さんだが、2000年に脳卒中左片マヒになって、現在は四本杖で室内歩行、外出は車いすである。
そんな彼女が、人前どころか全国版のテレビに出て、家のトイレを模したセットで排泄の動作までやって見せてくれたのだ。スタジオでもカメラが回っていないところで、最も重い片マヒ者を励ましたりしている。たいした人である。
だが、それ以上に私が感動したのは、真屋さんの介護者として参加していた夫の高津住男さんである。彼は真屋さんの動作をそばでじっと見守る。余計な手も口も出さない。介護職が一番苦手とすることだ。
「なんで見ていられるんですか?」と尋ねると「人は動くことで自分の世界を創っているんですから」との答え。さすが劇団主宰者だけあって、人の動きとは何かという問いの中からケアの真髄をも探り当てている。
そうか、手も口もつい出してしまう二流の介護者は、老人の世界の破壊者なのだ。ある日、高津さんは、家の廊下で真屋さんに出会う。真屋さんは洗濯物を干そうとして、よいほうの手は手すりを持たねばならないから、洗濯した衣類を自分の肩に何枚もかけて歩いていたのだという。
「それを見て感動しました」と高津さんは言う。俗っぽい世間の“主人”は「みっともないからやめろ」なんて言うのではないだろうか。自分だけの世界を創造しているというのに。
番組収録中に、トイレまで歩いて便座に座ったり立ったりすることはできても、着物を下ろすことが難しい、という話になった。立った状態でズボンと下着を下ろそうとすると、片手を手すりから離さなければならず、それでは立っていられないのだ。
そこで私は、手を離して立位がとれない人のズボンと下着の下ろし方をやってみせる。いずれも特養ホームや在宅の障害老人から習ったものだ。病院から特養ホームに入所してきたAさんが、何とかポータブルトイレにひとりで行けるように、と工夫した方法がある。
ベッドに寝ている時に、ズボンと下着をずらしてお尻を半分出しておくのだ。そして起き上がってベッドから足を降ろし、移動用バーを使って立ち上がると、ズボンと下着はストンと落ちる。これをAさんは「半自動式」と名づけていたが、パンツがうまく落ちてくれず、立って腰を振っているのがカーテン越しに見えたものだ(『介護技術学』の「起き上がり」の章に写真で紹介している女性である)。
Nさんの方法もおもしろい。やはり寝たままで着物をずらしておくのだが、起き上がってベッドに足を垂らして座り、身体を左右に振るのだ。右のお尻を挙げた時に右のズボンと下着をずらし、左のお尻を挙げて反対側をずらす。これを何回か繰り返す。おかげで彼女の座位バランスは抜群だった。
在宅のSさんはユニークだ。車いすから立ち上がって便器に座る前に、自分の額をトイレのコーナーに押しつける。それで倒れないようにして、よいほうの右手を使って着物を下ろすのだ。日本のトイレの狭さ、コーナーの安定性を生かした方法だ。
それを見ていた高津さんの感想に驚いた。「美しいと思いました」と言うのだ。「なるほど」とか「よく工夫されていますね」といった感想は聞いたことがあるが、「美しい」はもちろん初めてだ。なんで「美しい」という言葉がここで出てくるんだろう、彼の感じ方はどうなってるんだろう。
「アース」という映画を観た。地球温暖化に警鐘を鳴らすドキュメンタリー映画として話題になり、最近ビデオやDVDも発売された。それほど説教臭くないのは、やはり描かれている大自然のおおらかさによるのだろう。危機が叫ばれていても地球は本当に美しい。映画は北極の白熊から始まり、赤道を経て南極に至り、再び北極の白熊で終わる。
そのなかで私が最も美しいと感じたのは、肉食動物が草食動物を襲うシーンだった。追う側と逃げる側……、その動きがじつに感動的なのだ。スローモーションで映し出されたそのシーンは今でも鮮やかだ。どんな一流のデザイナーがつくった車でも、こんな美しい曲線はつくれない。ましてあんな動き方なんかできるはずがない。
私はなぜこのシーンを「美しい」と感じたのだろうか。ちょっと見方を変えると、残酷だと感じることだってできるはずではないか。追うほうも逃げるほうも必死なのだ。生きるために全力を尽くしているのだ。それが美しいのではなかろうか。
そうか。手足に障害をもった人が、生きるために必死で動いている。人によっては、“みっともない”と思うような動きを、だから高津さんは「美しい」と感じたのではないか。
もし彼がインドへ行ったなら、小便くさい乞食やつきまとう物売りや道に座りこんだ障害者を「美しい」と表現するかもしれない。だって彼らは、生きていくため、今日1回の食事にありつくために一生懸命なのだから。- 2008年9月 ミネルヴァの梟は日暮れて…
9月のNHKの番組で「オムツ外し」と出た! 出演者は東大医学部の泌尿器科の医者。第1回オムツ外し学会が1988年。20年遅れでやっとアカデミズムの頂点が動いた!
さらに「ためしてガッテン」で認知症予防法が取りあげられた。医学の進歩のあげくに「運動」と「会話」ではこれまた20年以上前の「寝たきりとボケの真の原因は”閉じこもり症候群”」という竹内孝仁先生の言っていることに追いついただけ。
まことに「ミネルヴァの梟は日暮れて飛び立つ」である。「NHKと」を付け加えるべきかも。意味のわからない人は辞書を引こう。
19世紀の哲学者ヘーゲルは『法の哲学』のなかで、「ミネルヴァの梟は夕暮れに飛び立つ」と述べています。 ミネルヴァ(アテナ)は女神の名前であり、梟は彼女が同伴している「知恵」の象徴です。 つまり、「知恵」は一日(時代)の終わりになってようやく翼をはためかせる=「形」を持つ、ということ。
- 2008年8月 大学のセンセなんかに惑わされれるな!
~「シルバー新報」連載記事の高口光子批判について~
「シルバー新報」という介護の業界紙に「だから職員が辞めていく」という連載がある。岡田耕一郎と岡田浩子の連名によるものだ。その7月18日付の連載の18回目に、「『○○のリーダー論』に惑わされるな」と題する高口光子氏への批判が載っている。
「リーダー論」の本といえば、上野文規さんと下山名月さんの編による「介護現場のリーダー論」(雲母書房)があるが、引用から推察するとここで批判の対象となっているのは高口光子さんの3冊のリーダー論(『リーダーのためのケア技術論』(関西看護出版)と医歯薬出版から出版されている2冊の本)を指しているものと思われる。
批判点は次のようなものだ。高口の著書の中の「どんなケアをしたいのかを自分に問う」という項目に「やりたいケアか、やりたくないケアか?この観点を大切にし、今までのケアを見直してみよう」とあるが、それではリーダーが変わるたびに猫の目のようにケアが変わってしまうというものだ。さらに、必要なのは「一定の質の介護を責任を持って組織として提供する」ことであり「趣味の介護を個人の立場で提供する」のではない、という批判である。
この連載を読んだ私の感想は次のようなものだ。肩書きを見ると、著者の一人の男性は某大学の経済学部教授である。
「大学のセンセじゃしょうがないか」。
私たちの発言や文章による発表は現実の場面で行なわれる。ところがこの著者は、書かれた文章だけを読んで批判しようとする。だから「やりたいケア」が、介護職個人による恣意(しい)的なもの、つまり個々人の勝手なものだと思ってしまうのだ。
介護現場の課題とは何か。急性期のみに通用する安静看護から脱却して、老人を主体にする介護への転換がずっと問われてきた。それは画一的な処遇から一人一人を主体として捉える介護への転換でもある。
高口さんの本を読み、「介護リーダー養成講座」に自分の休みに自費でやってくる人たちはそれをしたいと思ってやってきているのだ。そんな現場の介護職が切実に「やりたい」と思っているのは、恣意的でバラバラのものではなくて、大きな方向性を持っているのだ。それを前提にした上での文章を、文脈も背景も介護現場の現実も無視して文章だけを取り上げるというのは、文献引用を職業とする大学のセンセに相応しいだろう。
「一定の質の介護を責任を持って組織として提供する」ためにこそ、高口さんも我々もセミナーを開催してきたのだ。問題は大半の施設や介護現場で”一定の質”が保証されていないことだ。というより、伝統的な安静看護を基本にした管理的処遇が今だに続いているのである。これをどう変えるのかを提起できないなら「責任を持って組織として老人を寝たきりと呆けに追い込む」ことにしかならないのだ。
私も高口さんもその著書や発言によって、介護と呼ぶのに相応しい質の中身を食事、排泄、入浴について具体的に、しかも根拠を示して提起してきたつもりである。介護職が切実に「したいケア」を”趣味”としか捉えられないような人が「一定の質の介護を組織として提供する」というのは、結局旧態依然とした画一的ケアを守ることにしかならないのだ。だから「職員が辞めていく」のである。
シルバー新報よ、介護現場の外部の人を起用するのは悪くない、よい刺激になることも多い。しかし、介護現場の”今”を体感していない人が、一般的な経営組織論(世の中には通用してるかもしれない)を介護現場に説教するような内容では困る。老いや死を相手にする仕事は近代的方法論の枠には入り切らないのだから。
- 2008年8月 介護夜汰話 介護職よ、給料分の仕事をしよう (その2)
「介護職よ、給料分の仕事をしよう」と前号で書いた。それは老人をダメにしないことだ、と。本人が嫌がることをしないことだ、と。たとえ、医師の指示だろうが、ケアプランで決まっていようが、本人が嫌がっているようなら、躊躇し、ためらって、他の方法はないかとみんなで考え、本人に意見を聞いてみることだ。
もちろん、嫌だということを口に出さない人もいる。口に出せない人もいる。そんな場合には何を基準にすればいいだろうか。私たちは少なくとも2つの基準とすべきものをもっている。1つは、老人の声と表情だ。手足を縛られた老人は驚き、嘆き、怒り、そして絶望して、表情そのものを失っていく。あるいは自分の世界に閉じこもって独り言を言うようになる。ときどき笑ったりするが、その表情は虚ろである。
こうした老人の表情を見ても縛り続けられる人は、もう感じることをやめた人である。もう1つの基準は、自分が同じことをされたらどう感じるだろう、と考えることである。考えられないのなら自分でやってみればいい。オムツを着けてその中に排尿してみるという「オムツ体験」はやってみた人も多いだろう。
「抑制体験」をしてみるといい。ゴソゴソ動けないと、人は精神的に異常をきたすことがよくわかる。そりゃ、惚けなきゃやってられない。「特浴体験」もやってみよう。あの入浴方法を「寝たまま入れて楽でいいだろう」と思ったら大間違いだ。ひとは湯舟の中でリラックスすると筋肉が弛緩し、身体の比重が1.0より小さくなる。つまり身体は浮く。湯から出ている頭だけは重さがあるから、下半身が浮き、頭が下がって回転運動が生じて沈みそうになる。
もっと簡単なところで、ストレッチャーに寝て施設の廊下を移動させてもらうといい。これは恐怖だ。あれは、「移動介助」ではなくて“運搬”だ。カーブを曲がると身体が落ちそうで身がすくむだろう。
「チューブ体験」もやってみるといい。意識を失っているのならともかく、あんなものを鼻の穴から入れられて落ち着いていられるはずがない。私のように嘔吐反射が敏感な者は数十分で生きていく気がしなくなる。「自分がされたらどうだろう」と考えなくなった人は、想像力を失った人だ。
つまり、給料分の仕事、「老人が嫌がることをしない」というのは決して消極的なケアではない。それどころか、オムツを嫌がる人をなんとかトイレで排泄してもらうために工夫をする積極的なケアだ。特浴を嫌がる人を、それまでやってきたような生活的な風呂に安心して入ってもらう方法を学び身につけることだ。チューブを抜こうとする人に、なんとかして口から食べられないかと研究し試みてみる前向きのケアなのだ。
給料分の仕事、つまり「老人をダメにしない」というのは、それだけにとどまらない。それは一人ひとりの老人を誤解しないということでもある。病気や障害をもっている老人は、家族や介護者には理解できないような症状をもっていることが少なくない。いや、老人自身が気づいていない症状も多いのだ。
たとえば、脳卒中に伴う失語症という障害は誤解されていることが多いし、左マヒに伴う失行や失認については未だにその名前すら知られていないのが実情ではないか。介護する側の知識不足のために「問題行動」「問題老人」にされて、治療や矯正の対象にされるのでは老人はかなわない。誤解している人の手を借りなければ生きていけないというのは、地獄に等しいだろう。
パーキンソン病についてはもっと深刻だ。「やる気がない」とか「できるのに介助を要求する」などと誤解されている。これらは、「階段は昇れるが、寝返りはできない」というパーキンソン病の機能障害の特殊性によるものなのだが。
医療と看護の世界は、病気を治すための知識や技術を膨大につくり出した。治療のためにそれらを活用するためだ。ところが、その知識や技術が介護では役に立たない。むしろ、老人をダメにするために活用されてさえいる。なぜ医療や看護が介護に無力なのか。
それは、介護では治すためでなく、その人といっしょに生活していくための知識や技術を求めているからだ。そのために、知識と技術の再構成が必要なのである。医療・看護が、老人を治療対象とするために知識と技術を使うのに対して、介護は老人を主体にするために知識や技術を使うのだと言ってもいい。しかし、医療は介護に対して、そういうかたちで知識や技術を提供するという仕事はしてこなかった。
私は介護の教科書として『関係障害論』を皮切りに7冊の本(雲母書房・生活リハビリBOX)を書いてきた。特に老人をダメにしない介護法として『介護技術学』を、障害への誤解をなくすために『身体障害学』を書いてきた。
振り返ってみると、「給料分の仕事」というのは大変なことだということがわかる。たとえ、安月給とはいえ、世界の賃金レベルから言うと、それなりの金額なのだ。それくらいの知と技は手に入れたいと思う。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【初!対談】 あきらめる勇気
~老病死を地域、家庭でシェアする~
§---------------------------------------------------------§
- 2008年6月 介護夜汰話 介護職よ、給料分の仕事をしよう
私が特養ホームに就職したのは1974年である。当時は特養ホームの存在は一般の人にはほとんど知られていなかった。福祉関係者に次いで、病院の医療者に少しずつ知られ始めてはいたが、その認識は“どこにも行き場のない老人患者の行くところ”であった。一言で言えば“姥捨て山”である。
特養ホームに入所してくる老人は「医療と家族に見捨てられて、こんなところに連れてこられた……」と、ほとんど死んだ気でやってきたものだ。家族も「とうとう親をこんなところに入れなくてはならない……」と強い罪悪感を抱いてやってきた。
当時の特養ホームは、その大半が人里離れたところにあった。街なかに老人施設をつくろうという発想もなかったし、あったとしても住民の反対運動でつくれなかったに違いない。車で見知らぬ山奥に連れていかれる老人は不安で仕方なかったろう。
でも、家族も本人も建物の外観が見えると、少しだけ安心したかもしれない。当時、養護老人ホームは、戦前に建てられた古い建物か、建築資材のない戦後に建てられたものが多かったが、新しい制度下で建てられた特養ホームは例外なく、鉄筋の近代的建物だったからだ。
「これなら病院と変わらない」と家族はホッとしたかもしれない。建物も病院にならってつくられたが、介護(当時は“処遇”なんて言葉を使っていた)の中身もまた病院を見習って始められた。つまり、安静看護が指導され、シロウトの寮母たちに少しでも安静看護に近づくよう教育されていたのだ。
病院との最大の違いは、病院はよくなると出ていくところであるのに対して、特養ホームは一生いるところといったところだったろうか。
ところが、“死んだ気でやってきた”はずの老人たちが生き返ったようにイキイキするという“奇跡”が次々と起こったのだ。もちろん、看護師の指示に従って老人に安静を強制する介護をする、文字どおりの姥捨て山のような特養ホームはたくさんあった。でも、少なくとも私がいた施設では、そんな「奇跡」は珍しくないのだった。
う~ん。医者や看護師がたくさんいる病院から目がトロ~ンとしてやってきた人が、シロウトばかりの特養ホームでなんで元気になるんだろう、と私は考え込んだ。世間の常識ではありえないことが目の前で起こっているのだ。
医療や看護にはなくて、この介護現場にあるものとは何なのか。医者や看護師にはできなくて、介護力士士(『実用介護事典』P131参照)にできることは何なのか。老人たちを元気にしたものが何かがわかれば、介護とは何か、介護の専門性とは何かがわかるはずだ。
それがそれ以来、何十冊もの本を書いてきた私の原動力となったと言っていい。それを解明することが私のライフワークになった。でも、今になってそのことをたった一言で表すとするなら、私はこう言いたいと思う。老人たちを元気にしたものは、老人が嫌がることをしなかった、ということだ、と。
私たちに何か特別なことができたわけではない。特別なやさしさがあったとも思えない。やさしい人もいたが、そうでない人もいた。それは病院と同じだ。でも抑制はしなかった。法的にもできないが、でも抑制している施設はいくらでもあった。だって抑制の方法を看護師が寮母に教えていたのだから。
医療や看護は“科学”をその根拠にしている。“客観的”な世界なのだ。だから医者の処方は客観的にいつも正しくて、患者が嫌がったらどうするか、という場面設定がないのだ。「嫌がっても何とかするのが看護師の仕事だろう」なんて言われて、看護師たちは心ならずも手足を抑制したのである。そのうち、それが使命だと思いこんだりもした。だってそう思わなければやっていけないではないか。
老人は嫌がることさえしなければ、どんどん元気になった。足音が近づくと怯えた表情になって、顔を近づけると手で払うように拒否していた老人は、病院で抑制されていて、人間と世界が信じられなくなっていたのだった。「問題行動」とされたものの多くは、老人たちのルサンチマン(『実用介護事典』P681参照)だったのだ。
何かいいことをしてあげなくてもいい。ただ老人をダメにすることさえしなければ、老人は元気になっていくのだ。まず、怯えが消え、安心し、表情が出始める。ついでコトバが出て、笑顔を見せるという順番に。
介護職がなすべきことは今でもこのことではないか。まず、老人が嫌がることをしない。どうしたらいいかいっしょに考えることだ。それが給料分の仕事だ。だって安い給料ときつい仕事で、特別なことや、やさしい心を要求されたって無理ではないか。それは給料と職員の数が1.5倍になってからやればいい。まず給料分の仕事をしよう。それは老人をダメにしないということだ。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
ブリコラージュ☆インタビュー 医療と生活をしなやかにつなぐ
~生活を通したリハビリの実現を目指して~
稲川利光さん(NTT東日本関東病院リハビリテーション科部長・医師)
§---------------------------------------------------------§
- 2008年5月 介護夜汰話 存在論的武装解除 ~質問に答えて~
Q:::
『老人介護じいさん、ばあさんの愛し方』を読みました。あの三好さんが「認知症」という言葉に切り替えていたのに驚きました。新潮社から許されなかったのでしょうか。(愛知県・ゴンタ)
A:::
本誌4月号の「ブリコのおまけ」に載っていた読者からの質問です。私は「認知症」への言い換えを一貫して批判してきました。「呆け」や「痴呆」が差別用語であるという考え方にも、差別用語があるのではなく、差別的関係の中で差別用語になるのだと、主張してきました。
特に「認知症」という表現は、痴呆に必要な多様な見方とアプローチを、狭い医学的世界に閉じこめるものだと考えています。この点に関しては、私は原理主義者だといってもいいくらい頑固です。でも、私は原理主義者であるのと同じくらい合理主義者でもあります。
今回の文庫版での「痴呆」「呆け」の「認知症」への切り替えは、新潮社での意向ではなくて私の意志で決めました。というのも、「痴呆」という表現があるだけで、古い本だと思われるのです。内容も古くて現実の介護には役立たないと思われて、手にもとってもらえないということが起こってきました。
日本社会があっという間に“お上”の意向に従うという画一性のせいで、若い人には「痴呆」では通じなくなくなってさえいます。コンピュータで検索するせいで、「認知症ブックフェア」に『痴呆論』(雲母書房刊)が並ばないということもありました。
こうなると、原理主義を通していると、私が訴えたい原理を広く伝えるチャンスすらなくなってしまうことになります。そこで妥協することにしました。「間口は広く、奥行きは深く」と考えているのです。原理主義と合理主義のバランスが大切なのだと思っています。
Q:::
三好さんは有名人になったのだから、介護制度をよくしたり介護職の待遇を改善するために、もっとテレビで発言したりして、政治にはたらきかける活動をすべきではないでしょうか。(埼玉県・S)
A:::
これは、ある会場で受けた質問というか、苦言のようなものでした。でも結論的に言ってしまうと、そんなことをするくらいなら、テロを仕掛けるほうがまだマシだと私は思っています。
私は政治がよくなるなんて思っていません。政治を動かそうと思うと、そのためには多数派にならなくてはならないので、組織をつくり金を集めているうちに、その組織や金という手段が目的化していく、という堕落への道をいくらでも見てきました。
その点、テロはひとりでやれるからそんな堕落はしませんけど、ひどく非合理的です。「介護予算を増やせ!」と要求して厚労省を爆破しても、実際の効果はないどころか、世論の反発を招いて逆効果でしょうね。合理主義的な政治活動も、原理主義のテロも、どちらも通用するとは思えないのです。
じゃ、どうするんだ? と言われたら、前号の「なぜインドか、なぜ『共同幻想論』か」を読んでもらいたい。政治という共同幻想を変えるには、人々の感じ方そのものを変えていくのが、遠回りに見えてじつは一番確かな方法だと思っています。
「自己実現」とか、「自立」とか、「効果」とかいう言葉ばかりが介護の目的として語られているようでは、ろくな共同幻想は生まれません。介護とは、老いて呆けていくことに関わること、「自己崩壊」であり「依存」を支えるものなのですから。なんの「効果」もないのが介護なのですから。
そうした、本当のことをちゃんと語れるようにならなければ、政治なんか変わりようがないのです。たとえ、制度が変わったとしても実際には何も変わらないでしょう。かつて、老人の手足を抑制するのが当たり前だった頃、「看護婦の人手不足が原因だ」なんて能天気なことを言う“先生”がいっぱいいました。
それに対して私は「制度がよくなって看護婦の数が増えたら、余裕をもって手足を縛って歩くだけではないか」と皮肉ってきたのと同じように。
Q:::
三好さんの看護師や医者への批判はもっともだと思うのですが、介護現場では老人に関わる仲間なんですから、いっしょにやっていこうというもっと好意的呼びかけにならないものでしょうか。(東京都・ナース)
A:::
先日、介護に熱心な医師からも同じような指摘を受けました。以前にも本誌への投稿で看護職から同じような訴えが何度か載ったことがあります。前向きでもっともな意見のようですが、私にはどうしても違和感があるのです。
それは、介護職と医師、看護師が「仲間」になるためには条件があると思うからです。というのも、「同じチームのメンバー」とか「同じ人間」と言ってはみても、全然同じではないからです。まず、給料が違うでしょ。医師や看護師は世の中の評価だって介護職より高いし、自己評価も高いんです。つまり、一介の介護職からすると、医師はもちろん、看護師だって「権力」なんですよ。
同じ人間同士でも、片方は武器をいっぱい持っていて、片方は何の武器もなかったら「仲間」にはなれないでしょう。片方は言いたいことも言えないですよね、顔色うかがったりもするし。つまり、「仲間」になるためには「権力」をもっている側がそこから抜け出す努力が不可欠なのです。
具体的に言うと、会議の時に一介の介護職がしゃべりにくい雰囲気じゃダメなんです。「権力」の顔色をうかがったりしないで、自由に発言できなきゃチームワークなんか組めないですよ。「チームワーク」や「連携」という美名の下で「医療による介護の支配」になるだけなんです。
医師や看護師がしゃべると、介護職がシーンとなっているようじゃダメで、それなら何にもしゃべらないほうがいいんです。もちろん、「職種」を離れた領域で人間的につきあっているとか、冗談やバカなことを言い合えるようになっているともっといいんですけど。
こういう権力をもっている側に必要な努力を「存在論的武装解除」と名づけています。その人がいくらやさしかろうが、いばったりしない人だろうが、その存在そのものが相手を沈黙させてしまう、ということはあるのです。
たとえば、男であるというだけで女の人に脅威を与えたり、沈黙させたりということは歴史的な蓄積としてありますよね。ま、介護現場では資質でも人数でも女性が強いから、あまり心配はないけれど。
もちろん、私たち介護職も老人との関係では「権力」であることは言うまでもありません。医師や看護師に「存在論的武装解除」を要求する私たちも、老人の前で「武装解除」できなければ、とても「人間同士」なんていう聞こえのよいコトバを使う資格はないのです。
でも、そんな難しいことを考えなくても、無意識に「武装解除」できている人がいますよね。介護職はもちろん、看護師でも、ときには医師でも。そんな「教育」に汚されることのなかった人こそ、介護の資質のある人なんだろうと思います。
さて、ここからは私の独り言です。この世の中で生きていくには、「合理主義」に流されることが多くて困ったものです。だから、せめて仕事と関係のないところでは「原理主義」を貫きたいものです。
まず、私はプリンスホテルには泊まらないことにしました。ツアーでもプリンス系の宿泊があると参加しないつもりです。連合が呼びかけているのは効果があるでしょうが、私一人がやったって意味はないでしょう。
日本に徴兵制度ができても、私は「良心的兵役拒否」をします。もっともこの歳で兵役は来ないでしょうが。でも、裁判員制度は来るかもしれません。これも「良心的裁判員拒否」をするつもりです。だって、戦争と死刑という国家悪に手を貸さないというのが私の「原理主義」なのです。というより、自己満足かなあ。
- 2008年4月 介護夜汰話 なぜインドか、なぜ「共同幻想論」か
~「特集・介護保険に頼らない」に寄せて~ 昨年に続いて今年もインドを旅行してきた。今年は18人が2組に分かれての旅行だった。介護、リハビリ関係者でインドは初めてという人たちが中心の9人は、デリーからアグラ(タージマハール)、寝台車でヴァラナシ(ガンジス河岸の沐浴場)へ行って、飛行機でデリーに帰ってくる5日間コース。
昨年も行った私たちを中心にした9人は、ムンバイ(ボンベイ)から、石窟寺院で有名なアローラ、アジャンタ、男女交歓の彫刻で有名なカジュラホ、それにジャイプールを巡って最後にデリーで5日間コースのメンバーと合流する9日間の旅である。
今年は昨年のような事件は起こらなかった(本誌155号「インド・ムガルサライ駅前広場の夜」参照)。もちろん、記録的寒波のせいで、ヒーターもなく、すきま風の入るバスに早朝4時間、夜間5時間もふるえていたり、アンベール城へ登る象のタクシーで事故があり、乗っていた象がパニックになるなんて事件はあったが、それでも飛行機も寝台車も定刻(せいぜい2時間遅れ以内)に動いてくれた。
で、来年1月の正月明けに、今度は介護関係者に呼びかけてインド旅行をしようと思っている。題して『三好春樹と行くインド・生と死を考える旅』。介護関係者と行くといっても、施設見学なんかしないし、私の講演があるのでもない。ただ、名所を回ってカレーを食べ、寄ってくる物売りに物乞い、野良牛や野良犬にとまどう旅である。
日本の現実の中にいたのでは考えることのない「介護とは何か」とか、「人間とは何か」に思いをめぐらす旅だ。日本から離れて自分を自由にする旅といってもいいだろう。現実から離れるといえば、ブリコラージュでも案内している毎月の勉強会もそうした場である。
「えっ、介護職が介護の現場をよくするために集まって勉強しているんじゃないの!?」と思われるかもしれない。もちろんそうした側面もあるし、結果としてそうなっているかもしれない。でも少なくとも、私がこの場に妙に魅かれているのは、この読書会が日常から離れたところで、介護とは関係のないことを考える場になっているという点にある。
まず集まってくる人たちが、介護関係者以外の人も含めて、どこか現実に適応できないでいる人が多い。いつか、医師からPT、OT、看護師、介護福祉士、ケアマネまで、有資格者がそろっているので「このメンバーで施設をつくろうと思えばすぐできるね」という話になった。
でもすぐに、「協調性がない顔ぶればかりだからとても無理!」という結論になって、笑ったことがある。読んできた本も介護とは直接関係のない本ばかりだ。『野生の思考』(レヴィ・ストロース著)や、『愛と経済のロゴス』(中沢新一著)をなぜ読むのか、うまく説明はつかない。
おそらく、3月から読み始めた『ためらいの看護』(西川勝著)が唯一、例外的に介護に関わりのある本ではないか。もちろんこの本も、表層的な看護や介護からは深く離れたところから語られているから読むことになったのだけれど。
たとえば『共同幻想論』(吉本隆明著)をなぜ読んだのか。その説明は難しい。この本は、若き吉本が、国家、そして政治党派に振り回された経験から、規範、法、国家、宗教とは何かを論じたものだ。彼はそれを実体のない共同幻想、つまり、集団としての人間の観念がつくり出したものだとした。それは、人間にとって必然だったが、その中身は、幻想というだけあって自由、つまり恣意的であるとした。
人がどの国家やどんな宗教に属するかは、どこで生まれたかという偶然によるものだ。だから、国境や宗派が違うだけで、正しいこととまちがったことは反転してしまう。つまり、私が〈日本の常識〉を常識だと思っているのも何の根拠もなく、ただ偶然にすぎないのだ。
たとえば、あの石原東京都知事が排外主義者であることも、彼が日本に生まれたという偶然以外に根拠はない。もし、彼が韓国に生まれていれば竹島の日本侵略を批判し、中国に生まれていたら尖閣列島に上陸する反日運動家になっていただろうと思う。どこの国にでもいる、共同幻想と自分を同致させねばならない困ったタイプであるというだけのことなのだ。
『共同幻想論』を読むことで、私たちはこうした偏狭さ、迷妄さから少しは遠ざかることができる。国やマスコミが言う「正義」なんか幻想にすぎないぜ、と言える根拠が手に入る。「介護保険法」というのは、その国家というウルトラ共同幻想がつくり出した、これまた法という共同幻想である。
時代の要請で必然的につくられたと言えるが、その中身は恣意的である。だから、大学の権威あるセンセやマスコミが何か言うだけでコロコロ変わる。現場の切実な実感よりは、コトバ、スローガン、怪しい“科学的根拠”なんかで決まっていく。当然だ。共同幻想なのだから。
どれだけ現場のニーズに応えるかではなく、政策立案者や市民たちの幻想を満たすものでなくてはならないのだ。「尊厳を守るケア」「プライバシー」「筋トレ」「介護予防」……etc。それらは、結局「虚栄心と見栄を守るケア」「ぼけや寝たきりへの恐怖」を産み出しただけなのだが。
もちろん現場は、「制度ではなくてニーズに応える」のが介護であることを知っている。でも、なんでこんなに制度に振り回されるのかと頭にきた時には、人間の歴史的な偏狭さと迷妄さのせいだと知っておくといいと思う。
そうしたら、「行政批判」とか「政治批判」といった“ないものねだり”に向かうこともなくなるだろう。もちろん、批判したっていいんだけど、まず必要なのは私たちが日本の共同幻想のレベルから自由になることだと、私は思っている。
そう。インドには、老人や家族の虚栄心を満たすのがケアだと思っている連中を無化してしまう現実がある。介護保険がどうなろうと、私たちがやるべきことが見えてくる。だって、インドの現実は、虚栄や見栄ではなくて、ただ「生きたい」と言っているからだ。
生きられることが当たり前になったこの日本にも、こんな身体になってももう一度生きたい、と静かに叫んでいる人がいる。そこに関わることこそが介護なのだ。その時、私たちは、介護保険という制度に従うのではなく、利用するという立場を手に入れることができる。もちろん、利用しないという選択があることも。
- 2008年3月 介護夜汰話 病院OTへの手紙
昨年はNHK教育テレビで「なるほどなっとく介護」という番組を10本放映することができた。テレビ番組で「ゴソゴソすることこそ主体性」とか「立ち上がりの生理的曲線」、さらに「アヴェロンの野性児」まで訴えられるとは思ってもみなかったことだ。
ところでこの番組の3本目と4本目である「寝返り」と「起き上がり」の放映直後にNHK宛に手紙がきた。病院のOTからのもので「納得できるようなものではありません」という内容である。
具体的な指摘は次のようなものである。
①ベッドの柵を外すのは論外、危険である。
②床からの立ち上がりの最後の動きで、健側下肢を患側に引きつけているのは危険で、逆でなくてはならない。
③起き上がりの時、足をベッドから垂らさないで長座位にさせているのもまちがい、などである。
ちなみに、③については私の指導法は足を垂らすものだが、指摘を受けたのは自宅で夫が介助して起き上らせていた方法である。当事者がやっている方法を批判しても仕方がないと思うのだが、そうしたやり方を放映すること自体が認識が足りないということらしい。
同封されてきた冊子は「片麻痺の身体機能に合わせたADLレベル論」と題されたものである。手紙と冊子に眼を通したうえで、私は次のような手紙を書いた。
---------------------------------------------
拝啓 前略。
NHKへのお手紙拝読しております。
セラピストとして先輩にあたる方ですが、介護=生活の場に関わってきた者として遠慮なく感想を書かせていただきます。というのも介護のことはあまりご存じないようで、そのため、そのご著書で画一的方法を批判されていながら、生活場面に何通りかはありながらも身体機能だけを根拠にした方法を当てはめようとする画一的発想になっていると思います。
これではIC-IDH*の発想と同じではないでしょうか。DもHも(かつての古い表現ですが)Iから影響は受けても独自の領域であるというのが新しい障害観のはずです。まず、ベッドの柵が必要との主張は、狭くて高いベッドを前提とした病院的発想です。介護界では20年以上も前から、いいケアのメッカのようにみんなが見学に行く北海道の「湧愛園」は、サクはありません。
「落ちませんか?」と尋ねる見学者に「落ちます、ときどき」と言っています。ベッドが低いので、お尻から降りて廊下に這って出て、ベンチにお尻を挙げてタバコを吸っています。栃木県の「生きいきの里」も広めで低いベッドで柵はありません。だいたい私たちが使っている家のベッドにサクはないでしょう。介護とは当たり前の生活をつくることです。サクが必要なのは特別なケースだけです。
床からの立ち上がりのフィニッシュに健側を引き寄せることも批判されていますが、その方法を使う人はいっぱいいます。私もあなたの言うとおり指導していましたが、言うことを聞いてくれません。患側のコントロールが難しくてバランスを崩すため、患側を伸展して支持し、健側をすり足にして、つまり支持性と動作性の両方を兼ね備えた方法で動かすのです。
起き上がりの際、先に足をベッドから降ろさない人もいっぱいいます。左マヒで失行や失認のある人、その傾向のある人は特に足が宙に浮くのを怖がって、まずベッド上で起き上がってから足を降ろす傾向にあります。
先生がこうしたケースを見たことがないとしたら、それは、「指示どおり動いてくれる患者」としてしか老人を見ておられないからでしょう。サクの問題も含め「ホスピタリズム」だと言わざるをえないと思います。
老人の生活行為は身体機能だけでは決まりません。意識的につくられたPTやOTの専門の枠を越えて、人間の無意識があらわれてくる世界のようです。私は病院でのリハビリに口を出す気はありません。ほとんど体験していないからです。もし先生が生活の場の介護に助言いただけるのなら、1年でいいですから特養ホームで体験されてからしていただければと思います。もっとも、「先生」と呼ばれる立場でないかたちですが。
失礼を承知で一筆のみ。
敬具
生活の場のPT、OTを代弁して
三好春樹
------------------------------------------------------
じつは、私が書いたこの「手紙」は、NHKのスタッフとも協議して、結局、出されることはなかったものである。ただ、指摘のあった②の床からの立ち上がりについては、1月に放映された最終回のQ&Aで取り上げ、ケースによってどちらかを選んでほしいと話しているので参考にしてほしい。
一方で、視聴者や番組のモニターからの反応は好評であった。「食事ケアの番組を待ち切れなくて本屋で『新しい介護』を買って読み、病院に働きかけてチューブを外して口から食べられるようになりました」といった手紙が2通もきた。それだけでも、慣れない仕事をがんばった(そのストレスのせいか、この1年ですっかり頭髪が少なくなってしまった!)甲斐があったというものだ。
3月15日には90分スペシャル版が放映されるほか、新年度からは認知症ケアを中心とした10本の制作が予定されている。ああ、また髪が薄くなる!
*IC-IDH:障害を、機能障害(Inpairment)能力障害(Disabilty)社会的不利(Handicap)の3つの位相でとらえようという考え方。ところが、I→D→Hという一方的に規定されるとされたため、個体に対する医療やリハビリにアプローチが限定されることとなり批判が強くなった。現在では、DisabilityとHandicapというコトバが差別的であることも考慮され、Inpairment(機能障害)Activity(活動)Participation(参加)の3つの相が相互的に影響しう合うものとしてとらえるようになった。詳しくは拙著『ブリコラージュとしての介護』の中の「障害の定義をもっと変えるべきだ」を読んでほしい。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【特集】対談●三好春樹×佐藤義夫
~いい介護職場とは何か~
§---------------------------------------------------------§
- 2008年2月 介護夜汰話 看護師にも介護職にもおすすめの1冊
~『ためらいの看護』の書評を書いた~ 共同通信社から書評の依頼が来た。『ためらいの看護.臨床日誌から.』(西川勝著・岩波書店)である。著者の西川勝さんは、残念なことに、それまで知らなかった名前である。でもこの本を読んでもう忘れることはないと思う。書評は全国の地方紙の多くに掲載されたが、目にふれることのなかった読者のために全文を紹介したいと思う。
私の介護ぱためらい”から始まった。暴れる老人を抑制する(手や体を縛る)のはもちろんのこど、問題行動をできなくしてしまう投薬にすらも、自己嫌悪を感じざるをえなかった。だから、ベッドから転落する人には床に布団を敷いて寝てもらった。オムツの中の便に手を突っこむ人には、朝食後にトイレに座ってもらい。不快感の原因自体をなくそうとした。
三十年以上前の当時、介護に教科書はなかった。だから目の前の老人からまなぶよりなかった。固有名詞を持つ老人が教科書だったのだ。一方、看護には教科書も、体系化された教育もある。科学をよりどころにする看護には、常に「正解」があり、ためらってはならないものどされてきた。
「ためらいの看護」という魅力的な題の本書の著者は、見習い看護助手として精神科に勤務したのを皮切りに、老人介護施設などで二十数年、看護師どして働いてきた。そしてそこで出会った患者と、患者に振り回されているかのような自分を、まるで目の前に見えるように表現している。
著者のつづるエピソードは、症例報告のような味気ないものではない。臨床現場の迷いと小さな希望を率直に書いた文は、「正解」の実践にとらわれるあまリ硬直化した看護に、生気に満ちた息を吹きかけようとしているかのように思える。固有名詞の力を使って。
もちろん本書に患者の固有名詞は出てこない。でも一人一人の顔が浮かんでくる。著者が患者を分かったっもりにならず、ためらいつつ寄り添い、小さな声や身ぶりを感じどっているからだろう。目の前の困った人を放っておけない、どいう姿勢こそ、介護ど看護の出発点だったことを思い起こさせてくれる。
介護に携わる看護師の多くは今、悩んでいる。学校で教えられた正解と、現場で求められていることが矛盾しているからだ。介護の世界もまた「客観的データ」や「エビデンス(科学的根拠)」といった言葉か現場を脅かしつつある。ケアに大切なことは何か。「プライバシー」の語源をめぐる刺激的論考も含め、多くを学べる本だ。
文章がいつになく簡略で的確なのは共同通信社の担当者の手が入ったからである。以来、この本をいろいろな人に勧めている。
「いい題ですねえ」と言う人が多い。そして、決まってこう続ける。「看護師さんにはもっとためらってもらわなきゃねえ」と。
「どうしてあんなに、ためらいがないんでしょうかねえ」
「医者に対抗しているうちにそうなったんじゃないの」
そうか。見栄っ張り男と意地っ張り女の抗争のおかけで、老人ぱためらい”なく手や足を縛られるようになったのか。近代医療は科学に根拠をおいている。客観性に裏打ちされているのだから、ためらいはない。その医療に歯止めをかけるはずの看護も、また科学を自分たちの根拠にしようとした。このことが歯止めどころか、ためらいを失ってしまうことにより拍車をかけてしまったのではないか。
 ためらいの看護 ~臨床日誌から~
ためらいの看護 ~臨床日誌から~
著者:西川 勝
発行:岩波書店
体裁:四六判・上製・209頁
定価:2,300円+税
経験と歴史があり、体系化されて教科書があるのが看護の強みである。だが、それは看護にとっては不幸でもある。経験も歴史もなく、いまだに教科書も完成していないのは介護の弱みである。だが、それは介護にとって幸せでもある。
特に、元気と病気という二元論が崩れて、老化や障害、慢性疾患をもった人への関わりが求められるようになった時、従来の方法論で関わろうとした看護は通用しなかったのだ。シロウトの介護職は教科書がないからどうしていいかわからない。看護師に聞いてやってみるのだが、どうも老人がイキイキしない。それどころか、老人がダメになっていくような気がする。そりゃそうだ、障害や老化をもっていかに生きていくかを求めている人に安静看護の発想で、上を向いて寝ていることを強制していたのだから。
私たちは介護を教科書から習ったことはない。その代わり、一人ひとりの老人、その固有名詞から私たちは学んだ。これが介護の強みである。著者の西川さんは、幸福にもシロウトとして看護現場に入った。そして、看護師になり大学の准教授になった今でも現場で出会った患者の固有名詞を語ろうとするのだ。ちょうど私たちが介護を手づくりしてきたように。
章の間に入っている「病棟から」と題された短い文章がその典型である。精神科病棟での深夜勤。看護学生だった西川さんが詰め所で夜食のインスタントラーメンをつくっていると「30過ぎの彼」がじっと見ている。2人でラーメンを食べていると……。患者と看護者という立場を突然超えていった夜の出来事を描いた「夜空のラーメン」。
老人保健施設の詰め所に「杖を持ったOさん」がやってくる。咳が止まらず、最悪の体調の西川さんにOさんは「私、うちに帰れるんですか」としつこく訴え、そのうち嗚咽さえ始まる。西川さんが説得をあきらめて「風邪がひどいんだ……、絶対アウト」と言うと、泣いていたOさんが……。これまた入所者とスタッフという関係が崩れた途端に立ち現れる不思議な世界を描いた「咳」。
介護と看護に求められているのはこうした表現ではないだろうか。ケース報告なんていう固有名詞の消えた味気ないものでもなく、エピソードというほど軽くもない、現場に登場する世界を表現することなのだ。
この本を読んで気がついたことがある。前号で拙著『老人介護じいさん、ばあさんの愛し方』(新潮文庫)の解説を鷲田清一さんに書いてもらったことを紹介した。その文章の中にこういう部分がある。
それにしても、三好さんがずいぶんむかしの「現場」の声を細部までよく憶えているのにはおどろかされる。(中略)わたしには看護師として介護施設で働く友人がいるが、彼もまた。施設で暮らすお年寄りの言葉を、びっくりするほど丹念に、正確に憶えている。
そう、その「介護施設で働く友人」というのがこの西川さんのことなのである。なんという偶然だろう。鷲田さんの文章が活字になって初めて私に届いた翌日に書評依頼があったのだ。今年もうれしい偶然がたくさんあることを願っている。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
【特集】老いを支える おばちゃんパワー
~世界も介護もおばちゃんのものだ~
§---------------------------------------------------------§
- 2008年1月~2007.12月 介護夜汰話 介護現場のギャグの意味
拙著『じいさんばあさんの愛し方』は1998年に法研という出版社から発行されて版を重ねてきた本である。編集者のすすめで、私が初めて書いた一般の人向きの書き下ろしだ。でも現場の介護職の間で「おもしろい」と口コミで広がって売れ続けている。
その本が文庫になった。題は少し長くなって『老人介護じいさんばあさんの愛し方』となった。同じ新潮文庫から出版された『老人介護常識の誤り』に合わせたのだ。文庫本には解説文がつけられる。「誰がいいですか?」と聞かれた私は迷わず「鷲田清一さんにお願いしたい」と答えた。鷲田さんは哲学者で、最近大阪大学の学長になった人だ。
介護はアカデミズムとは無縁の世界だ。私なんかからは敵(かたき)だと思ってきた。そのアカデミズムの頂点に立っている鷲田さんだが、その著書も、発言も、そして容貌も、共感と親しさを感じさせるものだった。特に最近は介護に関する著作や発言が多く、私たちの間でも注目の人である。
鷲田さんはその依頼を受け入れ、超多忙なスケジュールの中で、私の『痴呆論』など他の本にまで目を通してくれて解説文を寄せてくださった。単行本を持っている人もこの解説を読むためだけにでも文庫版を買ってほしいくらいである。その一部を引用したい。
それにしても、三好さんがずいぶんむかしの「現場」の声を細部までよく憶えているのにはおどろかされる。「あなた、まだ若いのに。こんなところでこんな仕事をして。もっとちゃんとした仕事があるでしょうに」と言われたこと。「風呂なんか入らんでも死にゃあせん」というおじいさんの確固とした言葉。
「やーい、どうせ歩けんだろ、くやしかったらここまできてみろ」という、荒っぽいけれどじいさん・ばあさんからいちばん信頼されている看護師の言葉……。 わたしには看護師として介護施設で働く友人がいるが、彼もまた、施設で暮らすお年寄りの言葉を、びっくりするほど丹念に、正確に憶えている。
彼も。そして三好さんもそうなのだが、「科学」の言葉をよくよく知っているのに、それに当たり散らすのではなくそれを封印して、じいさん・ばあさんのつぶやきにばかリ耳をかたむける。
なにしろ、私たちの時代は介護の教科書もなかった。一人ひとりの老人から介護を学んだのだ。だからその介護は、言葉だけでなく五感をとおして身体に染み込んでいる。現在では介護の学校も教科書も増えた。でもニセモノが多い。それはすぐにわかる。あ、この人は現場を知らないなというのが身体でわかるからだ。
この本に三好さんの他の書き物と少しばかりちがうところがあるとすれば、それは、こんどはいい意味でだが、すきまがいろいろあることだ。ギャグひとつで、固まりかけていた想念か思わぬところへと風船のように漂い、飛ばされてゆく。「逸(そ)らせる」ということ、おそらくは老人介護のなかで憶えたわざが、読み手を相手にしてもついほとばしりでる。「そりゃ、老人には『しあわせの里』でも、家族には『シワ寄せの里』じゃないですか」といった駄洒落が、そこかしこから伝わってくる。するとふっと気がほどける。そういえば、わたしが知っているだけでも、介護現場にはギャグを言う人が多い。
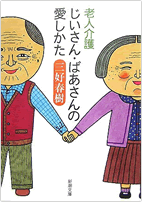 老人介護
老人介護
じいさんばあさんの愛し方
著者:三好春樹
発行:新潮社
定価:438円+税
体裁:文庫本・262頁
ISBN : 978-4-10-128652-5 C-CODE : 0177
そういえば、私にはこんな経験がある。役場の保健婦さん、社協のスタッフとケース検討会をしていた。精神発達遅滞で生活保護の夫婦のうち、妻が脳卒中発作を起こした。娘がいるのだが、発作の1か月前に母親と髪をひっぱりあう大げんかをして家出したまま連絡がつかない。救急車で運ばれた病院でも問題を起こしてすぐに追い出され、妻は治療さえ受けられないでいる。
考えられる最善策は夢のようなもので、やむなく次善策、次々善策となって、最後には最悪の事態が起きたらどうするかという話になっていく。みんな暗い気持ちになる。冷たい社会への怒りを感じたりもする。
そんな時、ひとりがこう言ったのだ。「でも、あの2人はちゃんと生きているんだから…」。
みんなが笑った。そう言えばそうだ。件の夫婦は医療を受けられないだけでなく、日常生活もひどいものだった。食生活なんてむちゃくちゃである。でも夫婦は生きてきたのだ。
今思うと、あの一言は鷲田さんが言われる「逸(そ)らせる」ということだったのだと思う。この発言は、真面目な人が聞くと、夫婦に失礼なコトバだと思うかもしれない。でも、真面目で深刻になっていくのは、どこか管理的で権力的になっていく傾向がある。
あまりに問題だらけのケースだと、「2人とも施設に収容してしまおう」という発想になるのと紙一重のところまでいってしまう。「でも生きているんだから」という言葉は、私たちを管理的で権力的な方向から逸らしてくれた。
そういえば、『実用介護事典』に「牧人権力」という項目を入れている。ぜひ読んでみてほしい。権力的にならない方法とは、これまた真面目で深刻なものではなくて、ギャグにこそあるのだ。鷲田さんの解説文の題は「ギャグの向こうに」という。