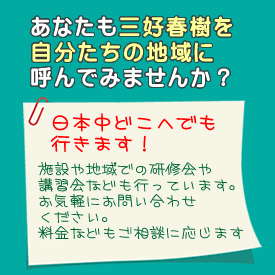●「投降のススメ」
経済優先、いじめ蔓延の日本社会よ / 君たちは包囲されている / 悪業非道を悔いて投降する者は /
経済よりいのち、弱者最優先の / 介護の現場に集合せよ
(三好春樹)
●「武漢日記」より
「一つの国が文明国家であるかどうかの基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である」
(方方)
● 介護夜汰話
介護夜汰話 介護現場のギャグの意味
介護夜汰話 新しい寝具で新しい介護を ~これからは高反発マットだ~
介護夜汰話 現実は厳しいからこそ本を読もう
介護夜汰話 人の動きの生理学が根拠 ~意志の発動のないものは介助ではない~
介護夜汰話 「ケア」を乱用するな ~美瑛で考えたこと~
安倍政権が生き延びるための秘策教えます
介護夜汰話 「脳トレ」やるほど惚ける、その根拠
介護夜汰話 現場が生んだ介護の本の最高傑作 ~村瀬孝生著「おばあちゃんが、ぼけた」~
介護夜汰話 「感情失禁」論
吉本隆明さんから叱られています…
介護夜汰話スペシャル 「生きたい」と「死にたくない」~インド・ムガルサライ駅前広場の夜~
老人ケアで起業するとはどういうことなんだろうか
三好春樹から皆さんへのメッセージ
介護夜汰話 「認知症は病気」、よく言うよ。
インタビュー『SIGHT vol.25 AUTUMN 2005』より一部抜粋
介護夜汰話 転職をすすめる根拠
介護夜汰話 近代的因果論への静かな異議 『ぼけてもいいよ』~こんな本を書きたかった
介護夜汰話 痴呆につきあえる人とは ~「心の闇をめぐって」~
『ユニット・個室』誤りの理由 ~ロシアで考えたこと~
介護夜汰話 なんて単純なんだろう
介護夜汰話 現場から届いたコトバ
介護夜汰話 ぬる問題
介護夜汰話 マイナスをゼロに ~ 幻想はもう捨てよう ~
介護夜汰話 異文化としての老い ~モロッコで考えたこと~
介護夜汰話 宅老所「よりあい」が元気だ
介護夜汰話 「事典」をコミュニケーション・ツールに
- 2007 ~ 2006
-
- 2007.12月 介護夜汰話 介護現場のギャグの意味
- 2007.11月 介護夜汰話 新しい寝具で新しい介護を
~これからは高反発マットだ~ 床ずれ治療の本がたくさん出版されている。製薬会社の主催・後援するセミナーには医師や看護師がつめかけている。この世界にも流行があって、患部を開いて乾燥させろと言っていたかと思うと、ラップで塞いで湿潤な状態に保てと言い始める。いずれにしてもどれも決め手になっていないからこそ、本も売れるしセミナーも盛況であることにまちがいない。床ずれ予防の介護用品も売れ続けている。
介護をしているお嫁さんに「亡くなった時に床ずれがあると親戚から何言われるかわかりませんよ」と言うと、一番高いものから飛ぶように売れたという。医師や看護師ですらつくってしまい、しかも治せないものをシロウトの介護者にちゃんとやれ、と要求するのは無茶な話だが、「床ずれのないのがいい介護だ」という通念が介護者を脅迫していたのだ。
それにしても、本でもセミナーでも、さらには床ずれの学会でも、どうして最も肝心なことが語られないのかと私は疑問を持ち続けていた。それは、床ずれをつくらない、そして治療のために最も基本的なことは、
①ベッド上でゴソゴソする自由を与えることと、
②昼間できるだけ座って生活することだ、
ということである。
もちろん、彼らは言うだろう。自発的に動けないし、座っていられないような重度な人を前提にしているのだと。つまり、寝たままの状態がやむをえない人だから、
①体位交換、
②エアマット、
③局所治療、
という方法で治そうとしているのだと。それならそれでいい。しかし、入院、入所して床ずれができたケースの大半は、どう考えてもゴソゴソすることはできたし、介助すれば座って食事も排泄もできた人だったのだ。
そんな人が、エアマットを敷いたためにゴソゴソできなくなり、座った生活づくりをしなかったために、かえって床ずれをつくっているのが実態なのではないか。さらに、ゴソゴソする体力や気力、座っていられる耐久力がない人でも、その状態は一時的なもので、すぐにそれが回復する人は多いはずだ。だが、その時にエアマットが敷かれていたのではゴソゴソすることが不可能になってしまうではないか。
エアマットは体重の圧力が1か所にかからないようにという目的でつくられた。無圧マットと呼ばれているものも同様だ。最近では、低反発マットが高級マットとしてホテルなどで使われるようになった。床ずれ防止だけでなく、安眠を保証するマットとして一般にも使われ始めている。
だが、これらのマットには重大な欠陥がある。圧力が1点にかからないエアマット、無圧マット、低反発マットには人間の自発的な動きを保証する床反力がないのだ。床ずれ防止と治療の第一条件である“ゴソゴソ”は、無意識に筋肉を動かし、床反力を利用して身体の位置や姿勢を微妙に変化させる。これが圧力の1か所集中を防ぐだけでなく、筋肉の収縮が血行をよくする。だから床ずれの予防と治療に有効なのだ。
ところが、これらのマットは反発がないから力を入れてもそれが吸収されてしまい、動きにならない。マットによっては身体が沈み込んでしまって動くことさえ難しいものまである。実際に、睡眠時の無意識な姿勢の変動が少なくなるから安眠できるのだと宣伝しているものもあるから、これでは逆に床ずれをつくるようなものではないか。
というのも、こうしたマットの欠陥は床反力がないことだけではない。通気性がないため、湿気が溜まってしまうのだ。さらに汚れても洗いにくいので不潔になりやすい。これまた床ずれをつくる条件になっている。
清潔で、通気性があって、ゴソゴソできない時には圧力が分散でき、ゴソゴソできるようになれば床反力があるなんていうマットがあれば、重度の人でも自発的動きのある人にも使えるし、重度を重度のままにしておくということもなくなるのだが。
そんな都合のいいマットがあるわけはない、と思っていたところに登場したのが、今号で本誌が勧める「ハッピーそよかぜ」である。このマットのすごさは、その材料にある。かつて身体を洗うのに使った乾燥させたヘチマをイメージしてもらえばいい。
つくり方によって固さ、反発の度合いを変えることができるので、重度でも自発的動きのある人にも適応できるものになっている。体重をかけるだけならそれを分散させ、力を入れると反発してゴソゴソできるのだ。さらに、画期的なのは通気性が保たれていること。そして、丸洗いができてすぐに乾くので清潔を保持できることだ。軽いのも助かる。
この「そよかぜ」、床ずれの予防と治療に効果があることは多くの学術的データによって明らかにされている。だが、私たち介護現場にとっては、もっと活用価値のあるものなのだ。それはこのマットが「オムツ外しのためのマット」だということである。
オムツを外したい。しかし、漏らして衣服やシーツ、マットを汚したら大変だ。衣服やシーツは替えればいい。しかし、マットは替えられないし、洗うのは大変だ。だから、マットの下半身部分には尿を通さないようにビニールやラバーのシーツが敷かれてしまう。当然、通気性は悪くなり、床ずれを誘発することになる。
しかし、このマットなら濡れてもすぐに洗ってすぐ乾く。安心してオムツ外しを試してみることができる。もちろん、濡らしたって叱ったりしない介護職であることが前提だ。「そよかぜ」は新しく開発されたブレスエアーという素材を使った常識を変えるマットである。医療現場も介護現場も保守的だ。それは命や生活がかかっているから慎重にならざるをえないのだ。
でも、上を向いて寝かせておくのが介護だと考えられていた時代があったではないか。今では座って食事をするのは当たり前、寝たまま入る特浴も不要になる施設が続出している。従来のマットでオムツ交換と床ずれの処置に追われる後始末ケアを続けるより、多少の失敗を笑い飛ばしてトイレに行ってもらい、床ずれ処置の時間で老人と冗談を言って笑っているケアをすべきではないか。
じつは私もこの「そよかぜ」を使って寝ている。腰痛が出ない。もっともそれは偶然体調がいいからかもしれない。私1人の数か月のデータは科学的根拠にはならない。しかし、深夜の通販番組で宣伝している高価な低反発マットを注文する気だけはなくなった。これからは介護でも私生活でも高反発マットが主流になるだろう。- 2007.10月 介護夜汰話 現実は厳しいからこそ本を読もう
最新の発言集である『介護の専門性とは何か』(雲母書房刊2005年)の「あとがき」にこんな文章を書かせてもらった。
「人生にはつらいことや悲しいことがある。生きていても仕方がない、と思えることだってある。そんな時に、それでも何とか生きていけるには<深み>が必要ではないかと思う。
<深み>とは、たとえば文学や思想のようなものである。映画や漫画だっていい。現実から一歩退却して、自分の内的世界があることが、現実に耐えられる最大の武器ではないか」
そこで、秋の夜長になぜか目がさえて寝つけないという時に読むといい本を紹介することにしたい。
大田仁史先生が「終末期リハビリテーション」を提唱されていることはもうご存知だろう。このコトバ自体が、回復期にしか興味をもたないリハビリの“いいとこ取り”への皮肉でもあるが、先生は理論と実技の2冊の本(『終末期リハビリテーション』『実技・終末期リハビリテーション』(荘道社刊))でそれを具体的に提起されている。
生活期はもちろん、終末期にこそリハビリの知識や技術を生かすべきだと訴えているのだ。
その大田先生にふさわしい本が出版された。なにしろ題が『お棺は意外に狭かった』(講談社)。亡くなった時、腕が固まっていると指が組めない。足が曲がっていると棺おけのふたが閉まらないことがある。すると、葬儀会社のスタッフが無理やり伸ばして、骨を折ってまで棺に入れることさえある。
こんなご遺体は、ここに至るまでの医療、看護、介護がすべきことをしなかったか、してはならないことをしたからだと先生は告発する。どれくらい足が曲がると棺に入らないかを調べるために棺おけの内径を調べて模型をつくり、実際にその中に入ってみたという。「三好くん、あれは狭いぞ。寝返りもできない」。ま、寝返りをする人はいないだろうけど。
人生の到達点である「死」の側から医療や介護を照らそうとする本だが、暗さや深刻さはない。父の死、母の長い介護、そして自分自身の病気が語られながらも、ユーモアにあふれ安心を得られる本だ。重い障害も深い痴呆も最後まで見てきた者が得られる楽天主義とでも言えばいいだろうか。
「介護よければ終わりよし。終わりよければすべてよし」。この本は介護する者の誇りを守ってくれる本でもある。
矢嶋嶺先生の本も出た。同じく講談社からだ。この本の題もすごい。『医者が介護の邪魔をする!』。3月に東京でのブリコラージュセミナーで先生に講演をしていただいた。「先生、あんなに言いたいことを言っていいんですか?」と講演のあとで質問したら「オレはもう後期高齢者に近いのだから何を言ったっていいんだ」という答えだった。
矢嶋先生は1933年生まれ。病院長を辞めて、小さな村の診療所で地域医療を始めて30年近くになる。ヘルパーといっしょに家庭用の浴槽を持ち込んで入浴ケアまでやっていた話は有名だ。先生が入院すると、「追っかけ患者」が隣室に入院してきたという。そんな老いた人と家族のニーズを身体で知っているからこそ、厚労省の政策やマスコミを含めた強迫的な健康ブームは徹底的に批判する。
「……骨粗鬆症健診が大流行になってきた。これは骨屋(骨やカルシウムが専門の医者・健康食品業界)の策略のようだ。病気を見つけて儲けようとしていると言われても仕方がない。老化とともに人間の骨ももろくなる。顔にシワがよるのと同じだ。顔の老化を『顔面皺増加症』とは言わない」(第1章・老人を苦しめる現代医療)。
そうだ、老人の骨折の原因は、骨粗鬆症ではなくて「長生き」だ。痴呆の原因も、脳萎縮ではなくて「長寿」だろう。それが問題になるのは、長寿にどう適応したらいいのか、その知恵と技を私たちが手に入れてないせいなのだ。この本もまた、介護する私たちへの数少ない本物の応援団である。
ちなみに、私はこの本を最後まで読んで驚いた。あとがきに「この書を書くにあたり、三好春樹さんの考え方に影響を受けた」とあるのだ。17も歳下の若造の名前をこんなふうに出してくれるところが、矢嶋先生のただものではないところである。
お盆休み、信州へ旅に出る時に私は1冊の本を持っていくことにした。20代の頃に夢中になって読んだ古井由吉の本だ。最新刊かと思って買ってきた本は『聖耳』(講談社)と題された本で2000年の発行だった。もう長い間、好きな作家の本も読んでないということになる。
かつての彼の作品は、山へ登る若者を主人公にした長編の連作だったが、こちらは作者も歳をとってきて、目の手術で入退院をくりかえす主人公の短編の連作であった。かつてスッと入っていけた独特の表現の世界に、なかなかなじめないまま最後の章を読み終えた。
自分の“現実から一歩退却した内的世界”が少し老化しているらしい。ま、当然だろう。こちらも歳をとっている。
今年の1月、インドを旅行してきた。その時の話は「ムガルサライ駅前広場の夜」と題してこの欄の3月号に書いたが、その文章が高口光子さんとの対談本『リハビリテーションという幻想』(雲母書房)にそのまま収録されている。そういえば、この本も秋の夜長におすすめだ。私も高口さんも、いつも飲んでしゃべってることを活字にしただけじゃないかと、どこかで思っていたのだが、思わぬ好調な売れ行きと反響に驚いている。
そのインドへ再び行くことになった。2008年1月末の出発だ。どうやら私の“現実から一歩退却した世界”は、内的世界から外国といった外的世界になりつつあるらしい。インドまで行かなくてもいい。本を持って行った先の八ヶ岳の山小屋で何十年ぶりかに天の川を見た。
その体験も現実に耐えられる立派な武器だ。文学世界から非日常の旅へと移行しつつある私は想像力を失っているのだろうか。それとも身体性を取り戻しているのだろうか。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
介護という新しい分野に
ふさわしい仕事の仕方が始まっている
~三好春樹~
§---------------------------------------------------------§- 2007.9月 介護夜汰話 人の動きの生理学が根拠
~意志の発動のないものは介助ではない~ ご存じのようにNHK教育テレビが私の番組を10本つくってくれることになって、5月と7月にそれぞれ2本ずつ放映された。内容は、かつての「生活リハビリ講座プログラムB.介護技術法」である。
もっとも講座で2日間かけてやっている内容を、30分番組4本にまとめるのには抵抗があった。介助法そのものを教えるのではなく、なぜこの介助法なのかという根拠を伝えたいと考えてきたからだ。
なぜなら、一人ひとりの老化も障害も体格も違うし、それを介助する側の体格も体力も違っっている。だからマニュアルなんかなくて、一人ひとりのやり方をつくっていく応用力が必要なのだが、そのためには人の動きの生理学とでもいうべき基本がちゃんと伝わらなければならない。果たして30分番組でそれが可能だろうか。
なにしろ、それまでのNHKの介護技術の番組は短い5分間くらいのもので、なぜという根拠は教えないで、楽な技術だけを示すというものだ。かつては看護師が安静看護技術を堂々と教えていた。
寝返りの指導では、マヒした手をよいほうの手で持って、頭の上まで挙げろと言うのだが、老人はマヒがなくてもそこまで挙がらない。肩関節の可動域180°というのは若い人が標準なのだ。この元師長さんは老人を相手にケアしたことはないらしい。
でも、足は少し違った。足首を重ねる古いやり方ではなくて膝を立てたのだ。「オッ、少しは変わったかな…」と思って私は見ていた。ところが、膝を引くと当然ながらモデル役の老人の身体は寝返りし始めた。すると、その元師長さんは「あ、まだですよ」とその身体を押しとどめたのだ。
やれやれ、身体の一部がひねられると身体全体がその動きについていくという反射的な動きすら認めようとしないのだった。ここでは、老人は完全な安静看護の受身的対象であり、自分の身体の主人公ではないのだ。
時代が変わると、新しい考え方の看護職による方法も登場した。安静看護法とは明らかに違うやり方だった。「ボディメカニズム」という言い方で、反動など物理学を駆使して楽な介護ができるというものだ。しかし、人の身体はメカ=機械じゃない。物理学で動いているのではなくて、生理学で動いているのだ。物理と生理は大きな違いだ。かたやモノだし、かたや生きものなのだから。
「ボディメカニズム」もまた、安静看護と同じく、老人を動作の主体と見なしていない。だから、老人が自立的に行う動きとはかけ離れたパターンで介助が行われる。たとえば、起き上がりは腹筋を使って直線的に起きてくるパターンだったりする。
これは若い人にしかできない方法だ。いくら楽にできたとしても、それでは老人を自立的方法から遠ざけていることになる。介護福祉士会の一部が研修にこうした方法を取り入れているのは情けない話だ。看護の世界には目新しい方法かもしれないが、介護にとってはとっくに古くなった、しかも老人を主体としてとらえる介護の本質に合わない方法なのだから。
最近の番組では古武道を取り入れた介護術が紹介されている。古武道ブームのきっかけとなった甲野善紀さんの身体観は興味深く、私たちが人の動きについて思いこんでいることを覆してくれる刺激的なものだ。
しかし、これを介護法だというのは無理があるだろうと私は思う。「ボディメカニズム」の方法と同じく、介助のパターンは老人の自立的な、つまり生理的動きに沿っていない。また、老人は自ら動く主体というよりは“見事な技を受ける対象”でしかない。
力を抜いてじっとしていることを求められているようだ。老人の意志の発動があって、それを助けるのが介助なのだが、これもまた、やればやるほど老人を自立から、主体から遠ざけてしまう。腕に力を入れないよう、指を立てて介助してみせるのもデモンストレーションとしてはよくできている。でも実際の介助には使えない。老人が倒れそうになったりという、いざという時にベルトを握れないし、老人が倒れるとつき指になる。
同じように武術を使うといっても、RX組の青山幸広さんのやり方は大きく違う。彼も全介助法を教えるが、その前に自立の方法を教え、ベッドの幅などの条件についても詳しく教える。だから全介助が必要な人は少人数だということも知っている。だからスタッフみんながその方法をマスターすることはない。職場の若い男性の何人かに「オレならあの人を風呂に入れられる」という人がいればいいのだ。
NHKの番組づくりのモットーは「中学生にもわかるように」だそうだ。かつて講談社が「一般の人にもわかるように介護法を図や表にしたい」と言ってきて、私が半信半疑のままでき上がったのが『完全図解・新しい介護』である。
NHKも講談社と同じように見事な手腕だと思う。専門用語をまじえたほうが立派で、ありがたく思われるのではないかなどと思っているようでは、多くの人に伝わることはないのだ。それは村瀬孝生さんの著書『おばあちゃんがぼけた』でも教えてもらった。一番大切なことは、子どもにもわかるやさしい表現で伝わるのだ。
「NHKが取り上げるとブームは終わり」というコトバがある。「NHKと朝日新聞」だったかもしれない。でもNHKが、私の介護を取り上げるまでにフリーになって23年かかっている。ここまでブームが続けば十分だろう。それに、NHKが私に痴呆ケアについて語らせるのにはしばらくかかるだろう。まだブームは続くぞ。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
めざせ!きれいなご遺体
~大田仁史~
介護職よ! 職場は辞めても仕事は辞めるな
三好春樹 × 大田仁史対談
§---------------------------------------------------------§- 2007.7~8月 介護夜汰話 「ケア」を乱用するな
~美瑛で考えたこと~ 6月2日と3日、東京発着の「北海道美瑛施設見学ツアー」が行われた。6月初旬にしては記録的な暑さ、とは言っても“内地”から来た者にとっては吹く風がさわやかな日で、道内からの参加者も含め30人近い一行に、北海道でセミナー開催中の私も加わらせてもらった。
私が住んでいるまちのホームヘルパーさんが2人参加しているのに驚いたが、ほかにもデイサービスなど、地域で老いを支える人の参加が多かったのはうれしいことであった。というのも、私は施設はもちろんだが、在宅の老人に関わっている人もまた、美瑛町の特養ホーム「美瑛慈光園」、老人保健施設「ほの香」から学ぶべきだと考えているからだ。
「地域ケア」とか「在宅ケア」というコトバがあって、そのコトバにはある種のイメージが付着している。それは、「施設ケア」に比べてよいものである、さらには理想的なものであるかのようなイメージだ。
これが、在宅や地域で老人に関わる介護関係者を堕落させたと私は思っている。ま、堕落とまでいかなくても、意識的によいケアをつくりだしていく努力を削いでいるように思う。当然ながら、長い経験と努力を積み重ねてきた老人施設にケアを学ぼうと思っている地域、在宅ケアの関係者は少ない。慈光園のような施設が存在してきたにもかかわらず。
そもそも「地域ケア」「在宅ケア」というコトバは存在しないはずだと思う。私に言わせれば「ケア」とは介護の中身を指すコトバであり、「食事ケア」「排泄ケア」「入浴ケア」という使われ方は適当だが、それ以外にはそぐわないものだ。
「ケアプラン」なんてのが、そのそぐわないものの典型で、ケアマネジャーがやっているのは「金の配分とスケジュールづくり」にすぎない。「ケア」の中身はまったく語られないのだ。週に何回訪問するかはケアではない。ケアの時間と場所を限定するだけだ。そこでどう関わればAさんがもう一度生きていこうと思うのかを施行錯誤するのがケアプランだ。
週に何回デイサービスに行くかというのも介護の時間と場所を決めただけだ。そこでどう関わればBさんに笑顔が出るかを工夫するのがケアプランではないか。言うとしたら「地域でのケア」「在宅でのケア」と言うべきではないか。地域とか在宅と言っただけで、ケアの中身が保証されると思っては困るのだ。そこでどんな食事ケアをし、排泄ケアをし、入浴ケアをするのかが問われているのだから。
美瑛の2つの施設に行ってみるがいい。「施設ケアは画一的だ」なんて言う人は、よほどお粗末な施設しか経験していない人にちがいない。一人ひとりの希望と介護スタッフの判断で、入りたい時間帯、浴槽、介助法が細かに話し合われている。もちろん、連れてくる人、脱がせる人、洗う人といった分業ではなくて、マンツーマンの介助だ。機械浴はほとんどない。
在宅で、当然ながら家に風呂があるというのに、寝たままの機械浴での入浴サービスに委ねているのとはえらい違いではないか。食べにくい人への工夫も細かいものだ。たとえば、ここで「キザミ」と呼ばれているのは、刻んだためにかえって嚥下しにくい「キザミ」ではなくて、細かく切ったものを魚なら魚の形にトロミで固めて飲み込みやすくしたものを指す。
こうした一人ひとりへの気配りを、ここが「地域」「在宅」とちがうところだが、24時間責任をもって支えているのだ。もちろん、その人の生涯にわたって。「出前をとりたい」と言っても、訪問看護師が「栄養が偏るからダメ」と言うような「在宅」。どちらがケアを行っているかは明白だ。
「ユニットケア」というコトバもそぐわない。「ユニット」でケアの質が保証されるわけでも何でもない。大規模には大規模の問題点とよい点があり、ユニットやグループホームのような小規模には小規模の問題点とよい点があるだけだ。むしろ、自ら抱えている問題点への自覚がないだけ小規模のほうが問題は深刻である。
少なくとも特養ホームは、50人、100人という大集団の中でいかにその問題点を克服するかを試行錯誤してきた。だから、オムツを外す方法も、普通の風呂に入る方法も特養ホームから生まれてきたのだ。おそらく、本当の個別ケアはこうした施設にあるのだろう。
「ユニットケア」は「ユニットでのケア」と言い換えるべきだ。そして「ユニット」ではなくて「ユニットでの食事、排泄、入浴ケア」を語るべきなのである。
- 2007.6月 介護夜汰話 「脳トレ」やるほど惚ける、その根拠
老人問題とは、老いていく個体の問題であると考えられている。だから、老いたりしないよう“筋トレ=(筋肉トレーニング)”に熱中し、“脳トレ”が大流行する。
読売新聞で2年めに入った「介護のこころ」という連載で「“脳トレ”をやるとかえって惚ける」と書いたら、抗議のメールや手紙がきた。「偉い先生が効くといっているのだから間違いはない」なんて書いてある。“偉い先生”の言うことだから正しいというのがすでに思考停止状態ではないか、と笑ってしまった。
ゲームや計算をやれば認知症にならないというのはあくまで仮説である。反射神経がよくなったり計算能力が上がったりはするだろう。だが、認知症にならないとは言えない。私には、人が惚けるということがそんなに単純なことだとはとても思えない。
計算問題を解くと脳の血管の血流量が増えるから認知症予防に効くなんてことが、最新の医療機器によって示されたりしている。でも、脳血管の血液量が増えることと、惚ける、惚けないこととに因果関係があるだろうか。かつても、脳血液量を増加させる薬を投与されて、脳出血を引き起こしたことがあったではないか。
計算を始めて落ち着いてきた老人がテレビの番組で紹介されたりもしている。人は生きる気持ちを失っている時、興味のあるものを見つけることで生き返ることがある。その人の場合、それが計算を解くことだったのだとしたら、落ち着くことはありうるだろう。
同じように、遊びリテーションで自分を取り戻した人も、墓参りでイキイキしてきた人も私たちはたくさん知っている。強制された“脳トレ”から解放されて表情が戻った人だっている。もっと多いのは、オムツから解放され、トイレに行くようになって「人間に戻りました」(家族のコトバ)なんていう人だ。
テレビ番組も“脳トレ”を取りあげるなら、オムツ外しや、機械浴をやめて生き返った無数のケースを取りあげるべきだろう。仮説は実証され、反証にも耐えて初めて科学的だとして認められる。もし、“脳トレ”が認知症予防に効果があると言えるとしたら、週何回か以上脳トレをやる人を大勢、追跡調査して、まったくやらない人と比べてみなければならないだろう。
10年後にどちらが認知症の発症率が高いか調べて、それが統計学的有意差があるかどうか検証して初めて証明されるのだ。私は統計学には弱いから有意差が出るには、果たして何人くらいの人で調査せねばならぬのか、よくはわからないが、何千人という数になるだろう。
しかも公正な立場の人によって調査されねばならない。タミフルを売っている製薬会社から金をもらっている人がその副作用の調査をしていても誰も信用しないように、ゲーム会社から資金が出ているところが担当したのではダメだろう。
ついでに言うと、タミフルをすぐに許可し、大量に備蓄するだけでなく使わせていることそのものが、アメリカ政府に追従する日本政府の“非科学的”決定だという話は説得力をもっている。タミフル製造で儲かるのはアメリカと製造会社の大株主であるラムズフェルドだからだ。
さてそうやって、公正な機関が何千人もの集団を10年かけて追跡したとしよう。脳トレをやってきた人の認知症発生率が有意に低い、なんて結果が出てくるとはとても思えない。それどころか、じつはこの調査そのものが成立しないはずなのだ。なぜなら、10年間、脳トレを続ける人はまずいないだろうから。いたとしたら、その人はちょっと変な人だ。執着気質というか、偏執狂というか。
10年後まで待つ必要はない。私たち介護職は、10年後をたくさん先取りしているからだ。高齢になってもその人らしく生き続けている人が周りにいるだろう。そうした人に、その秘訣を聞いてみればいいのだ。
20年前に保健婦さんと訪問したトキノ婆さんは当時88歳。足が不自由で歩行はできないが、農家の自宅の庭にゴザを敷いて草とりをしている。長生きの理由を聞いたらこう答えた。「食べるために一生懸命働いていたら、この歳になっとった」。
つい先日、車いすで海外旅行をしている老婦人に出会った。娘さんと2人で介助してくれる人を1人雇って8回目の海外だという。この人は「人生を楽しんでいるうちにこんな歳になったけど、今が一番楽しい」と言った。
その人らしくイキイキ生きている高齢者は「寝たきりにならないために」なにかをしなければ、とか「呆けないために」これをしよう、なんてことはしていないのだ。ほぼ全員、その時、その時の“今”を一生懸命生きてきた人ばかりである。「明日」のために“筋トレ”や“脳トレ”のようなことをやっていたという人にはお目にかかったことがない。
これが、“脳トレ”をやるとかえって惚ける、という私の仮説の根拠である。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
高口光子さんに聞く-施設のつくり方・育て方
よい施設の見分け方-何をどう見ればいいのか
三好春樹
§---------------------------------------------------------§- 2007年8月 安倍政権が生き延びるための秘策教えます
かって70%もあった安倍政権の支持率がいまや30%を切るほどに低下した。日本人はブームに動かされているだけで確固とした信念なんかなさそうだ。私なんか最初から支持なんかしない。断固とした信念を持っている。
なにしろ安倍と金正日は同じである。他国の国家犯罪には厳しいが自国のそれには甘い。片や日本の植民地支配を追及するが拉致は「部下がやったこと」ですましたいる。片や拉致は追及するが慰安婦問題は「民間がやったこと」ですましている。片や史上まれな独裁政権の、片や史上最悪の開戦という政策決定による必然的帰結ではないか。だから私は金政権を倒すべきだという同じ理由で安倍政権を倒したいと考えている。
しかしそんな私でさえ最近の安倍政権の不人気は同情したくなってしまう。そこで安倍政権が参院選で勝てる秘策を教えたいと思う。かっては新自由クラブだったのに今や安倍国家主義の旗振りをしている中川よ、よく読んでおけ。安倍首相が次の政策を発表すればいい。
「介護職の給料を1.5倍にする法律をつくる」と。 総理が指示すれば2日で法案はできるらしいし、財源は実力者揃いの自民党の税調の年寄りたちが考えればいい。
そうすれば介護職はもちろん、その家族、要介護老人にその家族もみんな自民党に投票するだろう。私だって入れていい。 2倍にしろと言えないところが介護職の謙虚なところである。
いい介護をしたい、と考えてる人が介護の仕事を続けられないという貧しい現実を変えられないようでは「美しい国」は皮肉としか使えない。老いを支えられない民族は滅びる。出生率の低下はその滅びの前兆だろう。まぁ安倍とともに滅んでもらおう。未来は他国の老人さえケアしようとするフィリピンの若い人たちにこそある。- 2007.5月 介護夜汰話 現場が生んだ介護の本の最高傑作 ~村瀬孝生著「おばあちゃんが、ぼけた」~
2006年11月号の本誌のこの連載で私は村瀬孝生さんの『ぼけてもいいよ』(西日本新聞社刊)を紹介して「こんな本が書きたかった」と書いた。いま彼の新刊『おばあちゃんが、ぼけた』(理論社刊)を読んで、そう書いたのは取り消さなければならない、と感じている。これはとても私には書けない文章だということがわかってきたからだ。
この本は「よりみちパン!セ」というシリーズの1冊として刊行された。本誌2006年7・8月号で徳永進先生の『死ぬのは、こわい?』を紹介しているが、それもこのシリーズの1冊で、他にも興味深い著者と題名が並んでいる。
「中学生以上のすべての人の」というキャッチフレーズがあるように、小学校4年生以上の漢字にはふりがながふってあるという本だ。しかし、宮沢賢治の作品が「童話」と呼ばれてはいても大人こそ読むべきものであるのと同じように、このシリーズも大人が読む本である。最近の大人は漢字が読めないから、ちょうどいいし。
私は数えてみると三十数冊の本を書いていて一般の人向きの本もあるけれど、中学2年と小学校4年の2人の子どもに自分の本を読ませようと思ったことはない。でもこの本は「ぜひ読んでみて」と勧めたくなる本で、いま下の子が読んでいるところだ。
自分の本と村瀬さんの本はどこが違うか。私の文は小学生や中学生に届くという気がしないが、村瀬さんの文はちゃんと届いているように思う。それは中学生向きに書かれた本だからというのではない。私が中学生向きに書いてもこうはいかない。
村瀬さんの“やさしさ”のせいだろうという言い方もできる。確かにどの本にも彼のやさしさはあふれている。それに比べると私の文章には皮肉が多くてひねた性格が露呈している。しかし“やさしさ”なんてのは陳腐だ。だって、やさしい人はいくらもいて、そんな人の書く文章というと、自分のやさしさに酔ったような自慢話みたいなものが多いもの。そこでは老人は自分のやさしさを確認するための、あわれで弱い存在として描かれることが多いし。
この本のよさをどうもうまく説明がつかないので、本の文章を引用することにしよう。
「食べる」「出す(排泄)」「眠る」。「おぎゃ.」と生まれて死ぬまでに毎日繰り返す行為。その毎日をどう繰り返すかが大切なんだ。無意識に行っていることほど、生きることに直結している。意識しないとできないことは実はどうでもいいことなのさ、そうたかをくくってみるのも悪くない。
ここで私は吉本隆明の「大衆の原像」というコトバを思い出した。もちろん、筋トレや脳トレといった意識的に行われる何やら専門的なことにばかり興味を示している介護の状況への批判も。
居眠りをして手に持ったお茶をこぼしそうになって湯飲みを取られようとしたトメさんが激しく怒るというエピソードが紹介されている。
まだお茶をこぼしていないのに湯飲みを取り上げられようとした。自分は結果を出していない。なのに他人から結果を予測され先手を打たれた。トメさんに限らず、「ぼけ」を抱えたお年寄りたちはそのことに抗っているように思えてならない。また、人の予測に導かれて生きていくことは、自分の存在意義すら見失わせる。
ここで私は日本の教育体制の中にいる子どもたちと重ねざるをえない。
最終章は「ふつうに生まれて、ふつうに死ぬこと」と題されている。読み始めて私は、あれ、これはあとがきかな、と思った。というのも、最後に谷川俊太郎さんの文が載っていることを知っていたからだ。それくらいこの章の村瀬さんは、詩人のような文章を書いている。生まれる、働く、老いる/ぼける、死ぬ、当たり前を生きる、という小見出しに沿って。
ぼけることが素晴らしいなんて思わない。素晴らしいと思えることは、人はたとえ「ぼけ」ても一生懸命に生きるということ。そのことを認めない社会をぼくたちは望まない。
最後のあとがきに代えて谷川さんは「ぼけの驚異」という文を寄せている。母の「ぼけ」と宅老所とのつきあいからこう思うようになった、というのだ。「これまで教わってきたこと、学んできたこと、正しいと考えてきたことを、もう一度解きほぐしてみる必要があるし、自分の感性をぼけに添ってゆるめていく必要もあるようです」と。
おお、“認知症”への専門家による教育の内容こそ解きほぐさねばならないものではないか。
私が厚生労働大臣なら全介護関係者(もちろん医者も看護師も)にこの本を読ませるだろう。もっとも“上”が読めというから読むような奴はダメだからそんなやり方に意味はない。だって必要なのは「固まりすぎた秩序をもう一度混沌に戻すこと」(谷川)なのだから。
現場が生んだ介護の本の最高傑作。大切なことは、難しいコトバよりも、小学生にも伝わるような文章で伝わるんだということを教えてもらった1冊でもある。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§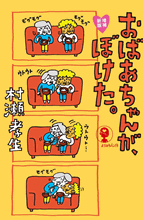 おばあちゃんが、ぼけた
おばあちゃんが、ぼけた
著者:村瀬孝生
発行:理論社
定価:1,200円+税
体裁:四六判/並製/173頁
URL : https://www.shin-yo-sha.co.jp/book/b455428.html
§---------------------------------------------------------§- 2007年4月 吉本隆明さんから叱られています…
吉本隆明氏の新刊「生涯現役」(洋泉社新書)の中で、私の実名が何度か出てきてお叱りをうけています。
 あわててインタビューの載った「SIGHTvol.25 AUTUMN 2005」(新書では「ROCKING ON」となっていますが、編集者が同じ渋谷陽一さんで別の雑誌です。しかし洋泉社の編集者もいい加減だなぁ。吉本さんから名指しで批判されるなんてのは個人としては大変なことなんだから、批判対象となった本くらい確認してほしいよね。読者が事実を確認することもできないじゃないか)を自分自身で読み返してみました。
あわててインタビューの載った「SIGHTvol.25 AUTUMN 2005」(新書では「ROCKING ON」となっていますが、編集者が同じ渋谷陽一さんで別の雑誌です。しかし洋泉社の編集者もいい加減だなぁ。吉本さんから名指しで批判されるなんてのは個人としては大変なことなんだから、批判対象となった本くらい確認してほしいよね。読者が事実を確認することもできないじゃないか)を自分自身で読み返してみました。
この話は、24歳で特養ホームに就職したときに、私がそれまでの老人観をいかに打ち破られたかという例の1つとして取りあげています。
従って、それに対して私や女性の生活指導員がそれをどう受けとめ、どう対応したかについて述べている訳ではないのですが、吉本さんは、推測で「笑い話」にした、とされています。
事実は違っていて、彼女は「三好君、いいもの見せてあげよう」といって、机の中にしまっている「ラブレター」を嬉しそうに私にだけ(?)見せたのを覚えています。
それで、「どう返事したの?」と聞くと、「ありがとうね、私ラブレターもらったの初めてだわ。」と言ったそうです。その上で「彼氏がいるから」と断ったそうですが、すると彼は「そうか」とだけ言って、そのうち若い実習生に手紙を出したり、手を握ったりしていました。彼女は多少面白くないようでした。
おそらく、吉本さんが本書で「こうすべきだ」と言われていることとそんなに外れているとは思えません。
問題はその事実よりも、このインタビューでの私の発言の中に、吉本さんが感じられたような「笑い話」にだけしてちゃんとした対応をしていないと思われるようなニュアンスがあるのかもしれません。たしかに発言の後で(笑い)とはありますが、全体を読んでいただけばそうした理解が生じるとは思えないのですが。
他の人がどう感じるか、読者に委ねたいと思って、洋泉社の本の一部と「SIGHT」の文章の全部をホームページに掲載したいと思います。さらに、老人と性の問題について、私たちの態度を知って頂くために、拙著『寝たきりゼロQ&A』の一部を掲載します。これも、吉本さんの言われていることと大きく外れているとは思っていません。
皆さんのご判断を。
●参考資料
「生涯現役」
「SIGHTvol.25 AUTUMN 2005」
「寝たきりゼロQ&A」
【追記】
洋泉社の新刊では、芹沢俊介さんと米沢慧さんへの批判も書かれています。それと私へのお叱りとにどこかつながりがあるとも感じていますが、それについてはまた後日、何らかの形で述べてみたいと思います。
●小堀先生のお手紙
信州・伊那の小堀求先生からお手紙を頂きました。うれしく、助けられる内容でした。掲載させていただきます。
拝啓
「生活とリハビリ研究所」のホームページで吉本隆明さんとの一件拝見しました。若干の感想を抱きましたのであまり参考にはならないかと思いますがお送りします。
論理的ならびに実践的には、三好さんと吉本さんのおっしゃっていることは、三好さんの御見解どおり違いはないと思います。
「……って書いてあるんです(笑)」の「笑」を吉本さんはたぶん実際以上に重くとられたのでしょうね。「笑」がなければ良かった。そんなせいもあって、三好さんの「達筆で」を「達者な」と誤読された。そんなところだと思います。
ただ、その元に、吉本さんの老いの実感からくる暗さ(『生涯現役』では余り表に出ないようにまとめてありますが)が三好さんのインタビューで感じられる(たぶん実際以上の)明るさに過敏に反応されたというところがあるのではないかと私には思われます。
インタビューというのも難しいものですね。
老人の暗さに介護側(医療の側でもいっしょでしょうが)が暗さで対応していれば悪循環、共倒れになってしまうでしょうから、こちら側としては「さりげなさ」で対応するしかないような気がしています。
ざっとこんなところです。乱筆乱文失礼いたします。
三好さんのますますのご活躍を期待しています。
敬具
三好春樹様
p.s. 最近、親鸞の「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」がひどく身に沁みます。そうでなければ、悪人はどこまでいっても救われませんものね。- 2007.4月 介護夜汰話 「感情失禁」論
特別養護老人ホームに就職して3日めか4日めのことだったろうか。まだ“見習い”のような時期で、午前の離床介助、午後の特浴介助という決まった仕事以外にやらなければならないこともなく、休憩時間といっても女性ばかりの寮母室に入り込むのも場ちがいな気がして、私は居室棟の廊下を何をするでもなく、うろついていた。
ベッド上の寝たきりのおばあさんと目が合ったので、私はその居室に入っていって声をかけた。何と言ったのかは覚えていないが、まだそんなに親しくなっている時期ではないから、何かあたりさわりのないことを言ったのだと思う。
すると、そのおばあさんの顔が見る見るシワだらけになり、声がつまり、泣きながら何か訴えだしたのである。「訴える」と言っても、私に向かって言っているというより、独り言に近い感じである。
私はなんとか聞き取ろうとしたが、どうしてもよくわからない。でも本人はこちらがわかっていようがいまいが、おかまいなく、声をつまらせて何ごとかしきりにしゃべっている。私はとりかえしのつかないことをしたのではないかと思った。なにしろ、ひとりの入所者を泣かせてしまったのである。頃合いを見計らって部屋を出た私は相談室に向かい、上司にあたる主任生活指導員の女性におそるおそる報告した。
「ああ、あれはね」
指導員の反応は意外にも平然としたものだった。「感情失禁といって、ちょっとしたことですぐ泣くのよ。いつものこと。心配しなくていいのよ」
少々乱暴な言い方だったのは、寝たきりのおばあさんのことを軽んじているからではなくて、私に対して気にすることはない、と伝えるためだったのだろう。
この時、「感情失禁」というコトバを初めて聞いた。ずいぶんひどいコトバだなと思った。尿や便を人前で排出するのは禁忌だから、それをコントロールできないことを失禁というのは不思議ではない。しかし、感情にまで失禁というコトバを使うなら、感情は人前で出してはいけないものだということではないか。
「老化や脳の病変などが原因で理性による感情の抑制ができず、些細なことで泣いたりする病的状態」
これが医学による定義である。むやみに泣いたり笑ったりするのは子どもで、一人前になれば、特に男は人前で泣いたりするものではない、と言われて大きくなった。実際に社会的地位や名誉のある人は泣くのはもちろん、笑うこともめったにない。
つくった笑顔は別だけれど。この世界では自分の感情を素直に表現するのは禁忌なのだ。そんな世界から見ると、たしかに泣いたり笑ったりするのはタブーであり、“失禁”なのであろう。
歳をとるにつれ、涙もろくなることはとっくに体験してきている。40代くらいから、映画を観て涙が止まらなかったり、介護実践の報告を聞いて涙ぐみそうになることがよくあるのだ。私の場合は早熟だったから老化も早いのだろう。
今回のインド旅行でもそんな体験があった。1年前のモロッコ旅行でも似たようなことがあった。無意識が撹拌されているらしく、昔のことを夢に見て涙ぐんで目が覚めたりした。モロッコではカルチャーショックを受けた。でも、それは文化の相対的差異へのショックだ。
今度は違う。絶対的ショックと言っていいだろう。夢も見たが、何より目覚めていても涙もろくなっているのだ。ツアー参加者の言動を見ていても、寝台車のインド人家族や窓の外の景色を見ていても涙が出そうなのだ。
3月号で書いたように、パスポートを紛失するなどという前代未聞の事態に動転していたからだとも言えるだろう。しかし、そんな時ほど、理性はなんとか感情を抑制しようとするのではないだろうか。
私は9時間半遅れのインドの寝台車の中で考えた。高齢者が声をかけられて泣いてしまうのは、些細なことで泣いているのだろうか。私が涙ぐみそうなのは、些細なことに対してだろうか。
高齢者は長い人生経験、それもつらい経験を経て、何が本当に感動すべきことなのか、わかってきたのではないか。特別なことではなくて、日常のさりげないこと、たとえば声をかけられるとか、ちょっとボディタッチされるとか、それこそが泣くに値することだ、と。
私が見たことも“些細なこと”ではないのだ。知人、友人と旅行に来ていることも、インド人家族がここにいることも、車窓からの景色も、みんな奇跡みたいなことではないのか。そうだ。あの時のおばあさんは、やさしい美青年(24歳の私のこと)から声をかけられて本当に感動したんだ。
3年前に大田仁史先生と共に監修した『実用介護事典』を引いてみた。一般的な説明の後ろに、私の文章が付け加わっている。
長期間、非人間的な扱いを受けていた人がやさしく声をかけられただけでワッと泣き出すことがある。これも感情失禁とよばれるが、脳の病変によるものではなく、感情が喪失した状態から回復するきっかけであることが多い。
おお、3年前の私もがんばっているではないか。そう思ったら涙が……なんていうのはナルシストのサインでしかない。「感情が喪失した状態から回復するきっかけ」であるなら、果たして、私はどう回復していくのだろう。- 2007年3月 介護夜汰話スペシャル
「生きたい」と「死にたくない」
~インド・ムガルサライ駅前広場の夜~  インドを旅行してきた。雲母書房の社長の茂木敏博さんがきっかけだ。なにしろ、彼は今回で6回目のインドだという。かつてインドへ行って、人間観、世界観が変わったという話をよく聞かされてきた私は、何が彼をこんなに惹きつけるのか、自分も体験したいと思ったのだ。
インドを旅行してきた。雲母書房の社長の茂木敏博さんがきっかけだ。なにしろ、彼は今回で6回目のインドだという。かつてインドへ行って、人間観、世界観が変わったという話をよく聞かされてきた私は、何が彼をこんなに惹きつけるのか、自分も体験したいと思ったのだ。
毎月やっている読書会のメンバー7人を中心に、仙台、松山からも参加者があった、因みにその2人は、雲母書房から出版されている本の著者である、といえば想像のつく人もいよう。
医療・介護関係者11 人に、昨年のモロッコ旅行で知り合った女性3人の総勢14 人。飛行機と列車、ホテル、それに駅や空港とホテル間の送迎だけはセットだが、それ以外はすべてフリータイムで現地ガイドもいないという旅行だ。
半分手づくりということで「ブリコラージュ旅団」と名乗っての旅である。
 なんとも不思議な旅だった。問題が起こり、疑問が生じては、それが何かによって意図されていたかのように解決し、答が見つかっていくというくりかえしなのだ。まず、私は多くのインド初心者と同じく、ショックに襲われた。路上生活者、物乞いをする身体障害者、アカと小便の臭いのする子ども……。
なんとも不思議な旅だった。問題が起こり、疑問が生じては、それが何かによって意図されていたかのように解決し、答が見つかっていくというくりかえしなのだ。まず、私は多くのインド初心者と同じく、ショックに襲われた。路上生活者、物乞いをする身体障害者、アカと小便の臭いのする子ども……。
私が物心ついた頃には戦後日本の絶対的窮乏はすでになくなっていたから、生まれて初めての経験でどうしていいかわからない。列車の床のゴミを這いながら片づけて物乞いする子どももいた。私の下の子と同じくらいの年齢だろうか。厳しいカースト制度のせいか、私たちには顔も見せない。仕事柄「人間的」とか「人間らしく」なんてコトバが飛びかっている。でも、私はもう使えないなと感じた。これも人間だぞ、あれでも人間だぞと言われているような気がしたのだ。人間なんて動物とどこに違いがあるんだ、と。
 ヒンズー教徒が聖なる川、ガンガー(ガンジス)の沐浴場に集まり、死体の焼却場(それもオープンの)があることでも知られているのがベナレスという町だ。朝日と共に沐浴する様子を見ようと、早朝の薄明かりの中、河岸を目指したが、私は足がすくんだ。何千という掘立小屋の店と人。その異様さに、ひさしぶりに恐いという経験をした。迷子になってはもっと恐いから、やむなく狭い路地を前の人について歩いたが、1人ならホテルに逃げ帰ったかもしれない。
ヒンズー教徒が聖なる川、ガンガー(ガンジス)の沐浴場に集まり、死体の焼却場(それもオープンの)があることでも知られているのがベナレスという町だ。朝日と共に沐浴する様子を見ようと、早朝の薄明かりの中、河岸を目指したが、私は足がすくんだ。何千という掘立小屋の店と人。その異様さに、ひさしぶりに恐いという経験をした。迷子になってはもっと恐いから、やむなく狭い路地を前の人について歩いたが、1人ならホテルに逃げ帰ったかもしれない。
椎名誠はこう書いている。「ガンガーに近づくにつれて、人人人人犬犬犬犬牛牛牛牛ホコリホコリホコリホコリ騒音絶叫警笛怒号………」(『インドでわしも考えた』集英社文庫)日本の終戦直後はこんな世界だったらしい。いや、中世へタイムスリップしたと言ったほうが正解かもしれない。死もあからさまだが、生もあからさまだ。
日本での「人間らしく」なんて考え方からは、こんなことはあってはならないことだ。「もっと福祉を充実させて、人間的生活を保障すべきだ」となるだろう。だが、私はそう思う一方でこれはあってもいい、と感じていた。これはどういうことだ。
 ベナレスからコルカタ(カルカッタ)へは寝台車での移動だ。乗車時間は午後5時。乗車駅のムガルサライ駅には1時間前に到着した。すると「2時間遅れ」との表示が出ている。ここからムガルサライ駅前広場の長い夜が始まった。なにしろ「2時間遅れ」は、3時間になり4時間になり、最終的には9時間半の遅れだ。午前2時半にようやく列車がやってきた。
ベナレスからコルカタ(カルカッタ)へは寝台車での移動だ。乗車時間は午後5時。乗車駅のムガルサライ駅には1時間前に到着した。すると「2時間遅れ」との表示が出ている。ここからムガルサライ駅前広場の長い夜が始まった。なにしろ「2時間遅れ」は、3時間になり4時間になり、最終的には9時間半の遅れだ。午前2時半にようやく列車がやってきた。
ムガルサライの駅前広場は、白黒の記録映画や映画のセットで見ることのある日本の終戦直後の駅前風景だと思えばよい。小屋のような店が並び、リキシャと呼ばれる人力車、オートリキシャと呼ばれるオート三輪車がズラリと客待ちしている。駅舎には列車待ちの人が毛布を敷いてズラリと寝ている。なにしろ、すべての列車が遅れているのだ。
 広場に住みついている家族とその子どもが「ハロー」をくりかえして、物乞いにやってくる。私はやはりどうしていいのかわからない。ところが参加者の女性たちがその子どもたちと遊び始めた。男性も紙ヒコーキをつくって飛ばし、子どもたちがキャーキャー走り回る。駅前学童保育である。
広場に住みついている家族とその子どもが「ハロー」をくりかえして、物乞いにやってくる。私はやはりどうしていいのかわからない。ところが参加者の女性たちがその子どもたちと遊び始めた。男性も紙ヒコーキをつくって飛ばし、子どもたちがキャーキャー走り回る。駅前学童保育である。
物乞いをする子どもたちを監督するように眺めていた母親が、うれしそうな表情で遊びに参加してくる。こんな表情を見たのは初めてだ。それを見ていたインド人のバスの運転手が「あなたたちはいい人だ」と言って、女性たちにチャイ(お茶)をおごってくれた。
 いくら待っても列車は来ない。私たちはバスの中で一人ひとり、旅の感想を語ることにした。起きた葛藤をボソボソしゃべる人、世界経済の動向からインドの未来を述べる人、ちょっとした講演会だ。
いくら待っても列車は来ない。私たちはバスの中で一人ひとり、旅の感想を語ることにした。起きた葛藤をボソボソしゃべる人、世界経済の動向からインドの未来を述べる人、ちょっとした講演会だ。
そこで、さっきまで運転手からリキシャを借りて乗り回して遊んでいたインド6回目の茂木さんはこんな話をした。「初めて来た時、乞食の子どもから手を出されて戸惑った。しかしその子といっしょに遊ぶことができた。その時に、われわれは金を乞う者と乞われる者という関係から解放されることができた」と。
そうか、さっきここで起きたことはそういうことか。どうしていいかわからないという状態への答のひとつは見つかった。バスの運転手まで含めた“講演会”が終わっても列車は来ない。
 そこで身体を動かそうということになって、広場でラジオ体操が始まる。それが終わると遊びリテーションだ。インド人が周りで不思議そうに、そのうち笑いながら見ている。これはデイサービス、いやミッドナイトサービスである。いつもは外国人ツーリストによって大型バスの窓から眺められている現地の人たちが、逆にわれわれを眺めているのだ。ここでは関係の逆転が起こっている。
そこで身体を動かそうということになって、広場でラジオ体操が始まる。それが終わると遊びリテーションだ。インド人が周りで不思議そうに、そのうち笑いながら見ている。これはデイサービス、いやミッドナイトサービスである。いつもは外国人ツーリストによって大型バスの窓から眺められている現地の人たちが、逆にわれわれを眺めているのだ。ここでは関係の逆転が起こっている。
私はこのツアーの参加者に感心してしまった。10 時間半もの待ち時間というマイナスの状況をプラスに変えてしまう力をもっている。しかも私の疑問に答まで見つけてくれるのだ。とはいえ、深夜に乗り込んだ満員の列車にさらに14 時間乗っていなくてはならない。
 ところが、そんな心配も無用だった。目覚めた彼ら、特に女性たちはすぐに周りのインド人乗客たちと親しくなり、食べものの交換どころか、路上生活者の性生活まで聞き出す始末なのだ。ここでも、マイナスを国際交流というプラスに転化するのだ。
ところが、そんな心配も無用だった。目覚めた彼ら、特に女性たちはすぐに周りのインド人乗客たちと親しくなり、食べものの交換どころか、路上生活者の性生活まで聞き出す始末なのだ。ここでも、マイナスを国際交流というプラスに転化するのだ。
私なんかこんな時せいぜい、「本でも読むか」ぐらいにしかならない。まあ今さら彼女らのようにもなれないし、これも私の個性なんだからしかたあるまい。ところが読んでいたその本にまた答が用意されているのだ。
寝台車で読んだのは『社会学入門』(見田宗介著・岩波新書)である。インド関連本として読書会のメンバーの1人が持ってきた4冊の本のうちの1冊である。著者が学生を連れてインドに来た時の話が出てくる。
デリーから有名なタージマハールのあるアグラへ列車で行くことになった。朝早くから待っているのに1時間遅れとアナウンスがあり、それが2時間になる。みんなウンザリしているが現地の人は平気だ。そのうち、今日の運行は中止になったと知らされる。どうしていいかわからずにいるうちに、周りの人たちはとっくにいなくなってしまって、自分たちだけがプラットホームに残されたという話である。
スケールはちがうが、似た体験ではないか。著者の見田は、時間を予定どおりに過ごしてきた者はその予定が狂うとどうしていいかわからなくなる、私たちは時間を「使う」ものだと思っている、だから遅れるとそれを無駄な時間だと感じてしまう、でも、時間は「使う」ものではなくて、「生きる」ものだと言う。
おそらく見田の経歴からすると、連れて行った学生は、最も時間を上手に「使う」ことをやってきた者しか入れない大学の学生だったろう。たとえ待たされた時間は短くても、その茫然感は私たちの比ではなかったにちがいない。
 時間は「使う」ものではない。つまり、消費するものではないのだ。自ら主体的に生きるものなのだ。だから無駄な時間なんかない。ツアー参加者はあの時間を生きていたのだ。日本人は、日本の子どもたちは、時間の上手な「消費」をしているだけではないか。インド人の豊かさが見えてくる気がした。茂木社長がなぜよく時間に遅れるのかというナゾも解けてきた。
時間は「使う」ものではない。つまり、消費するものではないのだ。自ら主体的に生きるものなのだ。だから無駄な時間なんかない。ツアー参加者はあの時間を生きていたのだ。日本人は、日本の子どもたちは、時間の上手な「消費」をしているだけではないか。インド人の豊かさが見えてくる気がした。茂木社長がなぜよく時間に遅れるのかというナゾも解けてきた。
私の最初の疑問、こんな現実があっていいはずがないと思いつつ、一方で、これでいいのだと感じているのは一体なぜか、に答えてくれたのも旅行中に読んだ本だった。『インドで考えたこと』(堀田善衛著・岩波新書)という有名な本である。
なにしろ、私が高校生の時、現代国語の教科書にその一節が載っていたくらいだ。アジア作家会議でインドに招かれ、事務局としてしばらくインドに滞在していた時の見聞と考察が書かれている。東西冷戦時代に書かれたものだから、現在の感覚で読むと古い枠組みの中の話だという感は否めない。社会主義への幻想は生きていたし、特に革命中国への期待が文中にあふれている。大躍進の破綻や文化大革命の悲惨さ、ソ連邦の崩壊なんか予測もできなかった時代なのだ。
それでも私は途中でやめないで最後まで読み通した。他にすることもないのだ。すると、最終章の結語にすばらしいコトバがあった。『アジアは生きたい、生きたいと言っている。ヨーロッパは死にたくない、死にたくないと言っている』見事なものだ。私は自分の疑問、矛盾、葛藤がスーッと消えて、なぜこのインドの状態をよしとすべきだと感じているのか、わかったような気がした。
今や、日本はかつてのヨーロッパと同じように「死にたくない」側になった。つまり、生きていられるのが当たり前になったのだ。だから「死にたくない」ために、老人がバンダナを巻いてエアロビクスに励み、みのもんたの番組を見ては食品の買い占めに走る。これは不健康ではないか。
たとえ、どんなに貧しくても「死にたくない」よりは「生きたい」ほうが健康だ。生きるのに必死な人はエアロビクスも納豆の買い占めもしないだろう。インドの人々の「生きる」ことそのものを目的としていることの強烈さ。「生きる」ことが保障された途端、人は生きる目的を失ってしまうのだろうか。少子化もそのあらわれかもしれない。因みに、インドでは人口は爆発的に増えている。
私たちは「生きる」をケアしたい。「死にたくない」をケアするのは嫌だ。介護予防、筋トレ、脳トレ……、みんな「死にたくない」に迎合したものではないか。生きていてもしかたがない、と感じていた人が、もう一度この身体で生きていこう、と思うようなケアがしたいのだ。
問題や疑問が生じては、それが解決し、答が見つかるという不思議な旅だった、と、最初に書いた。介護の仕事は好き。だけど職員間がうまくいかず精神的にやられてしまう子。『資格』が邪魔になってしまうこと。いろんな情報を聞き、中間管理職としてどう対応したらいいのか…。
 私自身、人とのコミュニケーションは苦手だから悩んでる。世間のじつはその典型ともいえることが私の身に起こった。インドに到着して3日目の早朝、ニューデリー駅からアグラへと向かう列車に乗り込んだ時に、パスポートと帰りの航空券、それに相当額の日本円の入ったショルダーバックが忽然と消えたのである。
私自身、人とのコミュニケーションは苦手だから悩んでる。世間のじつはその典型ともいえることが私の身に起こった。インドに到着して3日目の早朝、ニューデリー駅からアグラへと向かう列車に乗り込んだ時に、パスポートと帰りの航空券、それに相当額の日本円の入ったショルダーバックが忽然と消えたのである。
ホテルやバスの中に忘れたのではないかと考えたが、数分前に駅のプラットホームで撮ったデジタルカメラの映像にはちゃんとバックが写っている。シートにバックを置き、リュックを棚に乗せている間に盗難にあったと考えるよりほかなかった。
アグラの警察に届けを出し、証明書をもらう。これがパスポートを持たない非国民が再び日本に帰れるための唯一の証明書だという。私一人がデリーに戻って大使館に行けば、パスポートの再発行が間に合ってコルカタから戻ってくる13 人と合流して予定通りの便で日本に帰れるかもしれないのだが、それではベナレスもコルカタも見ないまま帰ることになる。それになにより、こうなると1人になるのが不安でしょうがない。
そこで、帰国が何日か遅れることは覚悟で、みんなと行動を共にすることにした。最終日、コルカタからデリーへの飛行機は3時間遅れた。でも誰も「遅れた」とは思わない。ムガルサライ駅の10 時間に比べれば定刻だと言っていい。しかし、これでその日のうちに日本大使館とインドの出入国管理局を回って、予定されていた便でみんなといっしょに帰るというのは絶望的になった。
帰りの飛行機のチケットは一番安いのが12万円。日航系のホテルだと1泊4万円もかかるという。やれやれ……日本大使館の窓口は2時半にならないと開かない。名前を告げると、やや反応があって日本人が出てきた。なんと、バックが出てきたというのだ。
 その日の午前中、ある婦人から大使館に電話があって、パスポートの入ったバックを預かっているという。さっそくガイドが連絡をすると、「本人でなければ渡さない」とのこと。しっかりした人だ。門番も使用人もいる立派なアパートで、栄養豊かな女性と15 歳のやはり丸々とした息子が迎えてくれた。
その日の午前中、ある婦人から大使館に電話があって、パスポートの入ったバックを預かっているという。さっそくガイドが連絡をすると、「本人でなければ渡さない」とのこと。しっかりした人だ。門番も使用人もいる立派なアパートで、栄養豊かな女性と15 歳のやはり丸々とした息子が迎えてくれた。
バックは、2日前電車のシート下で見つけたという。警察に届けようかと思ったが、現金があったので思いとどまったという。こちらでは現金は警察がボーナスとして抜いてしまうらしい。それで、直接日本大使館に連絡をしてくれたというのだ。
みんなが「奇跡だ!」と口々に言う。インドでは落とし物が出てくることはめったにないそうだ。ましてや盗まれたものが出てくる可能性はゼロに近い。それにしてもどうやって彼女が発見するに至ったのか、何か“ウラ”がある話なのか、いまだに諸説が入り乱れている。最後にインドの神秘が残った。
 パスポート紛失という大事件が起きながらも、結局は行程どおりのツアーで、予定の便で日本に帰ることができた。しかも帰国するその日に消えたパスポートが出てくるというタイミングのよさ。ドラマならご都合主義のストーリーと言われるところだろう。
パスポート紛失という大事件が起きながらも、結局は行程どおりのツアーで、予定の便で日本に帰ることができた。しかも帰国するその日に消えたパスポートが出てくるというタイミングのよさ。ドラマならご都合主義のストーリーと言われるところだろう。
茂木さんの説はこうだ。「神様が三好春樹にインドの現実とパスポート紛失というショックを与えてどう変わるかを試したのではないか…」オイオイ、神様に会ったら私なんかほっといてくれと言わなくては。
インド写真集みたい人は…- 2007年3月 老人ケアで起業するとはどういうことなんだろうか
介護保険制度が始まって、この不況のなかでも老人介護業界は注目されているんだと思う。どうやったら開業できるかとそのハウツーを求める声は巷に多くあります。
一方、「起業」というよりも私の目の前にいるこの人をなんとかしたい!という想いだけで動き始めた人たちがいます。この本はそんな無鉄砲で力強い実践者たちの話です。
内容としては、ブリコラージュでの2回の特集「一人から始める老人ケア」(2001年2月号・2002年2月号)、ブリコラージュインタビュー、連載から14人に登場していただきました。
編集していたときにも感じていたことですが、単行本にするために読み返していると、改めて彼らのパワーと一途さに圧倒されます。それぞれに困難さがあるのですが、どの実践にも悲壮感がありません。きっと「したかったことをしている」からなんでしょう。 「したいことをする」…究極の開業ハウツーです。
軽やかに時代を切り開いていく姿に心からエールを送りたいと思います。 さあ、次はあなたが自分の思い描く老人ケアをかたちにする番です。その気になったら、ぜひ編集部までご連絡を!- 2007年3月 三好春樹から皆さんへのメッセージ
~ 完全図解 『新しい介護』~
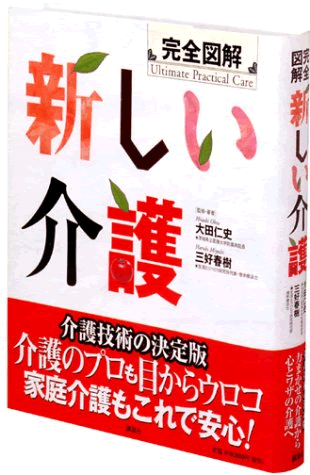 私が介護の世界に入ったのは1974 年、24 歳のときでした。 縁があって特別養護老人ホームの職員になったのです。就職したその日の午後に「特浴介助」をしました。裸のおばあさんたちを抱えてストレッチャーに乗せ、「特浴」と呼ばれる機械浴で寝かせたまま入浴させるのです。
私が介護の世界に入ったのは1974 年、24 歳のときでした。 縁があって特別養護老人ホームの職員になったのです。就職したその日の午後に「特浴介助」をしました。裸のおばあさんたちを抱えてストレッチャーに乗せ、「特浴」と呼ばれる機械浴で寝かせたまま入浴させるのです。
研修は何もありませんでした。なにしろ、介護の本が一冊も なかったのです。2 年くらい経った頃でしょうか、老人ホーム職員向けの「ガイドブック」ができあがり、全職員が購入させられたのですが、著者に大学の先生の名前がズラリと並んだぶ厚い本が、現場ではちっとも役に立たなかったのを今でもよく覚えています。
当時、介護職は私を含めて全員シロウトでした。教科書がないのも当たり前。全く新しい領域ですから、これまでの経験が役に立たないのです。医師や看護婦は急性期の安静を必要としている患者さんたちへのアプローチは教えてくれました。でも介護に求められているのは、むしろ安静にしないためのアプ ローチでした。
PT やOT は、マヒした手足の治し方、固まった関節を伸ばす方法は教えてくれました。しかし、私たちに必要なのは、マヒし、固まっている関節でどう生活していくのかという方法でし た。
やむなく私たち介護職は、既成の専門家に頼るのではなく、 介護職ならではの自前の方法論を創りあげていくことにしまし た。偉い先生の本よりは、目の前の老人の表情を見ることにしました。どんな関わり方をしたときに老人の顔が輝いてくるか、逆にどんなことをすると表情がなくなるのか、を判断基準にして、介護を手づくりしていくのです。
そうしてみると、介護現場は「宝の山」でした。そこでは新 しいコトバが生まれていました。「患者」という受身的な治療対象に代わって「生活の主体」という新しい人間像も立ちあがってくる場でした。
そうした現場で手づくりした介護の方法論を自発的に持ち寄って発表しあおう、と始まったのが1988年の「オムツ外し学会」でした。正式名称は「生活リハビリ実践報告会」でしたが、通称のほうが知れ渡り、現在まで続けられています。
当時、病院から特養ホームに入所してきた障害老人や痴呆性老人は、当たり前のようにオムツを着けられて寝たきりになっていました。それを、特養ホームのシロウト介護職が次々とオムツを外し、寝たきりから脱出させていたのです。いわば「オムツ外し」は、安静を強制する介護に代わる新しい介護の象徴 だったのです。
時代は変わり、介護保険制度ができ、介護は国民的課題といわれるまでになりました。しかし、マスコミや文化人が取り上 げるのは、制度や政策ばかりで、その制度、政策でどんなケアをするのか、という肝心の中身が語られることはありません。 さらに、その中身は、現場の介護職の奮闘にもかかわらず、未だに急性期にしか通用しない安静介護法や、患者という受身的人間観に基づいたアプローチが主流になっているのです。
本書はそうした状況に対し、ほんとうの意味での介護の発想と方法論を提出するために刊行されました。従来の専門性の枠の中に収まらない創造的な仕事をされている先生方のご協力と、 私自身の28年間の経験を、決して内容には妥協せず、しかし 表現はできるだけやさしく、その目的を果たせたと考えています。特に痴呆性老人のケアについては、脳細胞に原因を求める“個体還元論”を越える新しい人間観と方法論を提出しえたと自負しています。
上の文章は『完全図解・新しい介護』に「監修のことば」として寄せたものです。床ずれの予防でエアマットに×印をつけるなど、安静看護ではない介護を体系化したのはこの本がはじめてでしょう。特に痴呆のケアでは、“医療と闘う介護”を提出したつもりです。ブリコラージュの読者にこそ一番に目をとおしていただいて、介護を変えるための武器としてほしいと思います。- 2007.2月 介護夜汰話 「認知症は病気」、よく言うよ。
高口光子さんがテレビに出た。それもNHK総合テレビの夜の7時半、『クローズアップ現代』という花形番組である。聞けば、この番組は生番組だそうで、あのタカグチをよく生に出演させたものだと、NHKの勇気に驚いた。
もっと驚いたのは、NHKが放送した内容で、施設のユニット化が密室性を高め、介護職を追い詰めて虐待を招いているという報告だったことだ。『ユニットケアという幻想』(高口光子著・雲母書房刊)を読んで、ぜひにと声がかかったらしい。
この本には、石川県のグループホーム虐待致死事件を予測していたのではないか、と言われている私との対談も収録されている。番組の中で、千葉県の老人施設が紹介されていた。スタッフの1人が利用者に手を上げてしまい、辞めていったという話だ。よく取材をさせたものだと、その施設が開かれていることに感心した。
ただ、私にはひっかかることがあった。辞めていったスタッフがみんなに残したコトバである。「裏切ってゴメン」なのだ。私はちょっと痛ましい気がした。かつて属していた政治党派にいた頃の気持ちを思い出したのである。このコトバは、つまり、そうした使命感のようなものをもって働いていたということではないか。
「この仕事は自分には向かないので辞めます」と言って辞められないのだろうか。介護が、使命感で自分を支えねば続けられないのだとしたら、そのことこそが暴力行為の原因であろう。仙台の清山会福祉グループが自分たちのモットーを「介護道楽・ケア三昧」としている(同名の本も大好評!)理由がわかった気がした。
12月には「NHKスペシャル」が2夜にわたって「認知症」の特集をやって、こちらにも高口さんは出ていたが、長い番組の中のほんの少しの出番で、彼女をあんな使い方をするなよ、と思わず言いたくなった。
しかもその内容たるやひどいものだった。まず、認知症に効く薬が開発されている、と近代医療への幻想をあおるというジャーナリズムの毎度のやり方である。
…… 「呆けに新薬」というと新聞の経済面の記事になり、開発した会社の株が上がるが、その後その新薬はどうなっているのであろうか。そろそろ痴呆老人の数が減っても不思議はないはずだが…。 ……
私がこう書いたのは1989年のことだ。『老いの見方、感じ方』(筒井書房刊、1990年)に載っている。効果がないどころか、ホパテなんて薬は副作用でいっぱい老人を殺している。映像に出てくる実例も、薬を服用しているから呆けが進行していない、なんて説明しているが、じゃ飲まなきゃもっとよくなったんじゃないかと言いたくなる。
そもそも新薬が出ると、その効果を確認したがるものだから周りの人たちがよく観察し関わり始めるため、それでよくなるなんてことはよくある話だ。つまり、薬がなくても“関係障害”が治癒すれば、進行しないどころかよくなる人がいくらでもいるのだ。
認知症の「新常識」とか言って最初に強調されたのが、「認知症は病気である」だ。よく言うよ。病院でいっぱい認知症をつくってるじゃないか。検査入院しただけで、オムツを強制されて一晩で惚けの世界へ入った人、点滴のために手足を抑制されてやはり一晩で「人間じゃなくなった」(家族)人はいくらでもいる。
痴呆をつくり出している現実に目を向けたくないために「病気論」をふりまいているとしか思えない。たしかに、40代や50代で起こる「若年認知症」は原因不明の病気だろう。しかし、老人性の痴呆は違う。まず生活の中で強いストレスがあって、それから逃げるために怒ったり、過去へ回帰したり、現実から逃避したりする。
生きいきした現実世界との相互性を失った脳は再生が困難になり、萎縮や変性に至る。だからこそ、老人のいやがることを止めただけで呆けが「治る」ことがあるのだ。それにしてもこの「病気論」に介護関係者も文句を言わないところを見ると、自分たちもまた乏しい介護で呆けをつくり出している後ろめたさがあるのだろう。
そして、「病気」なら医療にまかせてしまえばいい、と最も困っている人のケアから逃げ出す口実だとでも思っているのだろう。
『自閉症..これまでの見解に異議あり!』という本が出た(ちくま新書609)。村瀬学さんの本だ。治そう、という目ではなく、ともに生きていこう、という目で見た自閉症児の世界は、問題行動だらけではなくて、私たちの存在の不安と共通した人間の基底部のあらわれであることが明らかにされている。
私に力量があれば、『認知症..これまでの見解に異議あり!』という本を書きたいところだ。誰か書いてくれないか。介護界に村瀬学さんが必要だ。
 自閉症 ~これまでの見解に異議あり!
自閉症 ~これまでの見解に異議あり!
著者:村瀬 学
発行:ちくま新書
定価:720円+税
体裁:新書判・233頁- 2007年1月 インタビュー『SIGHT vol.25 AUTUMN 2005』より一部抜粋
~倒錯した人間観を超えて 日本の「介護」と向き合う~
 SIGHT医療連載策9回目となる今回は、日本の「老人介護」に焦点をあてる。「2025年には65歳以上の高齢者比率が全人口の30%に」「劇的に減少する労働力人口」「若年層の年金負担が大幅増加」-もはや聞き飽きるほどあらゆるメディアで連呼されている、来たる「超高齢杜会」への警告であるが、この問題ほど当事者と非当事者で関心の度合いに大きな差があるトピックもないだろう。
SIGHT医療連載策9回目となる今回は、日本の「老人介護」に焦点をあてる。「2025年には65歳以上の高齢者比率が全人口の30%に」「劇的に減少する労働力人口」「若年層の年金負担が大幅増加」-もはや聞き飽きるほどあらゆるメディアで連呼されている、来たる「超高齢杜会」への警告であるが、この問題ほど当事者と非当事者で関心の度合いに大きな差があるトピックもないだろう。
つまり、当事者は「いま目の前の高齢者の現実」をシリアスに見つめ、ときに苦悩する。逆に身内に老人がいない非当事者は、たとえば「特別養護老人ホーム」ではどういったケアが行われ、「在宅介護サービス」とは具体的に何をするのかということにあまり関心がない。要するに、圧倒的な「二極化」が進んでいるのである。ただ、加速度的に進行が進んでいるのである。
ただ、加速度的に進行する「超高齢社会」への移行を目の前に、高齢者を取り巻く現実、とりわけ「介護」の現状を無視することは決して出来ない。また、「老い」が、すべての人間が必ず向き合わなければならない現実である以上、「介護」とはあらゆる人たちにとって切実なテーマなのである。
今回インタヴユーをさせていただいた三好春樹先生は、この「介護」という分野の第一線で活躍する日本有数のエキスパートである。また現在は、特別養護老人ホームでの豊富な現場経験をもとに全国各地で老人介護の講座を受け持つかたわら、その著作やご自身が編集する雑誌『ブリコラージュ』において、誤った介護観を徹底的に批判している。
そして、先生があらゆる老人介護の基本に据えている項目、それが「排泄ケア」である。いわゆる「下の世語」を重視するという考え方は、介護政策を打ち出す行政や病院などでは、これまでまったく無視されてきた。
ただし、このテキストを読めば、先生のこの思想が日本の介護の現状に対する根本的な間題提起であるということがよくわかる。その思想の根幹となる先生の人間観から、日本の介護の未来まで、丁寧にそして率直に語っていただいた。
■「癒し」としての介護
一番重要なコミュニケーションとは、自分の体の中の自然に耳を傾けること。つまり、尿意、便意ですよ
----- そもそも三好さんが、この介護という分野に入られた動機とは、ほとんど偶然に近いものだったんですよね。たとえば、「寝たきり老人を僕の力で助けるんだ」っていう、高い志があってというものではまったくなく(笑)。
「はははは」
----- そこが僕は非常に、ユニークであるし、ある意昧先生の原点でもあるのかなという気がしているんですが。
「そうですね、私、核家族のひとりっ子なんですよ。だからね、人とくっつくとか、距離が近いっていうのがダメで(笑)。どちらかと言えば観念的な人間で、文学だとか思想だとか、そういうことにずっと興昧があったんですよ。
ところが60年代の終わりに、学園紛争絡みで高校を無期停学処分になって。それに従わなくて、校長室占拠したりなんかしたものですから、結局退学になってしまいましてね。その後は、景気のいい時代だったから高校中退でも、職安に行けばいくらでも仕事はあったんですけど、自分となかなか合う仕事がなくて、職を転々としてました。
そんな時に、当時偶然一緒に読書会をやっていた牧師さんがいましてね。その人が、『特別養護老人ホーム』というのがあるんだけど、人手が足りなくて困っている、誰かいないかという話をしてて。
全然興味がない世界だったし、特別養護老人ホームって名前も、その時生まれて初めて聞いたぐらいでしたね。ただ、どうせならちょっとわけのわかんない世界に行ってみようかということで、この道を選んだんです」
----- そうやって、お若い頃に介護の現場に飛び込んだ経験は三好さんにどのような教育的効果をもたらしたのですか?
「要するにこれまでの僕は社会に対して、反体制という態度できたわけです。そんな中で老人というのは、社会の体制側でもないし、反体制側でもないんですよ。両方含めた、社会から疎外されている存在なんですよね。だから、老人と向き合ってみて、体制/反体制、あるいは権力/反権力っていう構図が『あ、そんなもんじゃ全然ないぜ』ってパッと明らかになったんですね。
どうしたらいいかわけわかんないっていう時代を、老人介護ということで、救われた感じがしましたね。今だと『癒し』って言うんでしょうけど(笑)。
それと、やっぱり人間はだんだん年を取ると、人格ができていくものだって思い込んでたわけですよ。いい大学出て、いい会社へ就職して、結婚して子供つくって、それなりの地位、名誉を得てね。それで定年迎えて孫ができて、心安らかに老後を過ごすっていう。そういう人生のレールがあるって、無意識に思ってたんですね。
ところが、老人を見てると、『あ、レールなんかないぜ』って思う。みんなばらばらですよね。特に特養の老人ていうのは、地位も名誉も全部剥がされて、丸裸になっている人間そのものなんですよね。そうするとそれが、個性の塊なんですよ。
初めは可哀想な老人をケアしてあげる、ぐらいのつもりで入ったんですけど、もうとんでもない!可哀想などころか向こうのほうがはるかにやり手なんですよ。だって80,90まで生きてるんだから」
----- (笑)なるほど。
「私の上司で、主任生活指導員の女性がいたんですが、その女性にじいさんがラブレターを書くんですよね。開いてみると見事な達筆で、『小生とキャバレエに行きませんか』って書いてあるんです(笑)。
それとか片方の手足麻庫して寝たきりで涎垂らしてるじいさんが、一日中ベッドの上で『赤旗』をずっと見てるんですよ。この人は共産党の闘士だった人ですけどね。その行動パターンから離れないんですよ。
もう濃厚な人間の縮図があるっていうか(笑)。地位とか名誉がある時は、威嚇もできるし、自分の本質を隠すこともできるんだけど、あそこにいる人たちはもう、それを剥がされて、要介護老人というふうになってるわけです。
そうすると個性が煮詰まるんですよね。これがおもしろいんです。私はそれまですごい人間嫌いでね。昔は『大人は嫌だ!』みたいなのがあったんですけど、『ああ、老人、嫌いじゃないなあ』と思って。で、この仕事は続くなあと思ったんですね」
■ "排泄ケア"に立ち返れ
----- 一方で現在の介護を取り巻く現状を見るとたとえば現場では、ユニットケアや家庭的ケアといった老人に対する倫理的・人権的配慮を背景にした制度やオペレーションが、急速に発達してます。ただ、三好さんはそういった傾向に対して、非常に距離を置いた立場をとっていますよね。これは、どうしてなのでしょうか?
「日本で一番有名な特別養護老人ホームというのが千葉県にありましてね。非常に進歩主義的な人たちがやっている施設で、どちらかというと良心的な施設だと思います。そこが全室を個室にすることを始めたんですね。グルーブホームのように家庭的な雰囲気を大事にしようと。
ただ、その施設が書いた本があるんですが、これはひでえなあっていう表現があって。つまり、介護職のスタッフが排泄ケアに一日中振り回されるのは可哀想だから、値段は高いけれども吸収性のいいオムツにしようと。
それで、オムツ交換の回数を1日4回にして、『残った時間でコミュニケーションを大事にします』という。おまけに、『オムツ交換というのは老人にとって大変屈辱的なことだ。だから回数を少なくしたほうがいいんだ』って言うんですね。
でも『ちょっと待てよ!老人は、オムツ交換が屈辱なんじゃなくて、オムツが屈辱なんだよ』って僕は思うわけです。要するに、トイレに行って排泄するっていう70年80年続けてきた、当たり前の生活を今日から断念しなさいっていうのがオムツだから。
僕は、最後の最後、赤ちゃんみたいになった時に使うのは一向に構わないけれども、プライドや自意識をちゃんと持ってる人には、できるだけオムツをしないっていうのが介護だと思うんですよね。
人間の尊厳を大事にするなんて大袈裟なこと言うけど、僕は最後までオムツをさせないっていうのが、一番尊厳を大事にすることだと思うんです。さらに問題なのは、排泄よりコミュニケーションのほうが価値があるんだっていう考え方ですよ」
----- それは具体的にどこが問題なのでしょうか?
「これは私に言わせると市民的価値観なんですね。市民の持っている、非常に表面だけの人間観だと思います。『さあ、時間が余ったからコュニケーションしましよう』っていうコミュニケーションがどこにあるんだよと。
じゃあ、一番大事なコミュニケーションとは何か?自分の体の中の自然に耳を傾けることなんです。つまりは尿意、便意ですよ。尿意、便意に耳を傾けて、トイレに行く。行けないんだったらそこで介助してあげるというのが、コミュニケーションを大事にしていることでしょうと。
それを抜きにして、オムツをさせて、時間あるからじゃあコミュニケーションしましようっていうのは、倒錯した人間観だと思いますね」
----- 最終的に介護というものは、排泄ケアに立ち返るんだっていうことですね。三好さんの言葉を借りると、「ウンコ・シッコに帰る」っていう。
「そうです。たとえば僕は痴呆性老人に対してどうするかっていう研修会をたくさんやっているんです。よく痴呆のケアっていうのは、何か特別、対人閑係をうまくして、ヒューマニズムを持って、とか言うけど、そんなことより、排泄ケアなんですよ。
というのは、痴呆の老人が夜落ち着かないで寝ないとか、大声上げるとか、徘徊するという原因の大体6割近くは、実は便秘なんですよね。便が出てないっていうことが間題行動の引き金になってるわけ。僕らなら便秘だってわかるけど、老人はそれがわかんなくて違和感だけがあるから、そのことを間題行動っていう形で、僕らに教えてくれてるだけなんです。
だから朝ごはんのあと、ちゃんとトイレに座って排泄するっていうことが、心身共に落ち着いた生活づくりの基本なんですよね。みんな排泄ってのは生活の後始末だと思ってるわけですよ。おむつ交換が排泄ケアだと思ってる。そういう人間の一番基本的なところを、大事にしないで、カウンセリングやコミュニケーションを重視するとかね」
■ 医療が人体を相手にする仕事なら、介護は人生を相手にする仕事なんです
----- また三好さんは著書の中で、そういった倒錯した介護観の背景には「二元論的人間観」が存在すると説明されていますよね。これはどういったことなんでしょう。
「たとえば医療の専門職と看護の専門職、これはもう介護に比べてものすごく専門性が高い領域なわけですよ。医者は特にね。ただ、それが老人に無力なんですよね。
じゃあ一体何で病院でダメな人が特養で元気になるんだと。要するに、病院は元気か病気かっていう二元論でしか見てない。病気を治せば元気に戻るって言うんですね。ところが、老化という元気でもない、病気でもない中間の領域というのが出てきた。病院はこれにどう対応していいのかわかんないんですよ。
そこで注目を浴びたのが、リハビリテーションなんです。これで、中間を全部元気に出来ると思ったんです。だからすごく期待されたんですけど、そんなこと出来やしないんです(笑)。かえって多様性が増えたんですよね。
つまり、これまでの発想を根本から変えなきゃいけないんですよ。『よくなったら生活に戻れるからそれまで我慢しましょう』っていうような医療のあり方ではなく。介護っていうのは逆なんですね。今日が一番いい。明日、あさっては老化するから、ますます条件悪くなるから、今ここから始められることからやろうよっていう。これが介護なんです」
----- では、医療とは根本的に違った考え方から生まれてくる介護において、具体的に必要とされる現場のオペレーションとはどのようなものなのでしょうか?
「私が生活リハビリ講座という講座を始めて22年になるんですが、そこでずーっと喋ってる最初のスローガンが、『リハビリより何より、まずベッドの脚を切れ』なんです。
ベッドが高すぎるから、足が下ろせなくて寝たきりになってる。脚を切って自由に下ろせるようにすれば、訓練なんかしなくても立てる人がいっぱいいるんですよ。今ベッドの高さは、電動で調節出来るようになったけど、じゃあ老人が一番立ち上がりやすい高さに設定されてるかっていうとそうじゃないんですよね。ベッドの高さを老人ひとりひとりの体格に合わせればいいんですよ。
実はこれね、150年前にナイチンゲールが『患者のベッドは高すぎてはいけない』って言ってることなんですけどね。病院のベッドは上向いて寝てるっていうのが前提になっているから高すぎるんですね。これはつまり、二元論の人間観しかないからなんですよ」
■ サイエンスとしての医療 アートとしての介護
----- なるほど。ところで、今お話にあったような現場レベルでの間題がある一方で、たとえば厚生労働省をその頂点とした、行政による介護へのアプローチにも問題は存在してますよね。この点についてどのようにお考えですか?
「結局、現場の自由裁量に任せるという度量がないんですよね。たとえば現場から見れば、個室がいい人もいれば、大部屋がいい人もいると。だから僕は個室に全面的に反対なわけじゃないんです。半分ぐらいはあっていいと思うんです。だけど厚生省は全室個室じゃなきゃ認めないっていう。
現場が考えて、『あ、これが二ーズに合ってるな』と思ったら、いろいろやればいいんですよ。最終的には消費者の側が、つまりは老人とその家族が、ちゃんと選択してけばいいわけで。それがいわば資本主義の原則ですよ。そうやって二ーズに応えたところが生き残っていくっていう。現場の二ーズを一番知ってる人たちがどういうやり方をするのか決めていくっていうやり方を、やらないね。
だから、厚生省っていうのは杜会主義的方法論から完全に抜けていないんだと思うんですよ。国家が上からやるべきだっていう。だけど、現場の二ーズは上から来ないですよね。
ひとりひとりの老人の二ーズを知って、どうやれば笑顔が出るのかを知ってる現場に、『あんたたち、好きなようにやってこらん。ダメならまたやり直せばいいから』っていうふうにやらないと」
----- また老人介護には、医者や看護婦など医学的な知識を持った専門家も必然的に関わってくることになりますよね。こうした現状において、介護そのものはどのように位置づけられるのでしょうか?
「医療の専門家、あるいは医療に関わる看護婦さん、彼らはサイエンスでいいんですよ、科学で。なぜなら人体を相手にする仕事だから。人体っていうのは、男女差とか個体差があるけど、基本的に構造はみんな一緒でしょ。ところが介護っていうのは違うんですよね。
介護は人体ではなく人生を相手にするんです。これはサイエンスが通用しないんです。じゃあサイエンスじゃないとしたら何だっていうと、私はアートだっていう言い方をするんですけどね。個性が出るわけですよ、それぞれ。ひとりひとり全部違うっていうのがアートですから。
でもまあ、さすがにアートだけとは言わないから。サイエンスとアートがくっついたもんが介護だろうと思います」
----- では、将来的に医療と介護の関係とはどのようにあるべきだとお考えですか?
「たぶん医療っていうのはほっといてもサイエンスとしてどんどん発展するんですよ。要するに人間を対象として見る。サイエンスっていうのは主観と客観をちゃんと分けて、対象を客観的に、操作対象にするというので発達してきたわけですよ。それはもう、どんどん進むでしょうね。臓器移植だとか、どんどんすごいところへ行くでしょう。
で、それが行けば行くほど、逆に介護っていう世界が必要になってくるっていう、そういう構図だと思いますよね。だから介護は医療の下位にあるものを補うっていうんではなく、最終的にはケアというもの、介護というものの中に医療が包摂される。
包摂されない部分ももちろんあるんですけど、そういうイメージですね。ただ、介護も医療にくっついていこうとして、同じように管理的になりたいって考えてる人も多いからね」
----- 介護というものの本質を考えるとその傾向は非常に怖いですね。
「ただそれが主流派なんですよ。でも、おもしろい看護婦や介護職は、医者と同じ土俵に乗らないんです。これは知り合いの医者から聞いた語ですけど、看護婦から『先生の処方は間違ってます!』って一言われても、医者はいくらでも反論出来るわけですよ。頭いいし勉強してるから。
でも、たとえば『この患者、点滴するから抑制しなさい』って言った時に、介護職はそうはいかないんだって。『可哀想でしょ』って泣かれるって言うんですよ。これが医者には一番こたえる。要するに『おまえの土俵は間違ってないか?』って言われてるわけですから。
で、介護ってのはそれだと思うんですよ。医療と同じ土俵に乗って、同じような専門家になろうとすると、絶対ダメになっちゃうから。『可哀想でしょ』って、一番最後に泣くのがいい(笑)。それを戦略としてやれれば大したもんだなあと思うんですけどね。そういう介護をやりたいな、と思ってるわけですよ。
戦略的に泣いちゃうっていうね(笑)」
----- インタヴユー=洪弘基- 2007.1月~2006.12月 介護夜汰話 転職をすすめる根拠
~『介護道楽・ケア三昧』の書評 その2~ 中学生が、いじめが原因だという遺書を残して自殺する事件が起きた。そのいじめに、担任の教師まで加わっていたというので非難が起こっている。「いじめをなくすよう教育しろ」とか「教師の適性検査をしろ」なんて主張が飛びかっている。
しかし、私がこの事件で感じたことは少し違う。一番感じたのは「学校は命をかけてまで行く場所ではない」ということだ。もし、私の子どもと同じ中学生たちに呼びかけることがあるなら、言いたいのもそのことだ。命を落としてまで学校に行き続けなければならないと考えているその「狭さ」をもたらしたものは何なのか、と考えてしまうのだ。
教師が信用できないのは自明のことだ。まず教師になりたいなんて人は、人を支配したがるタイプが圧倒的に多い。もちろん、そうでない人もいる。でも「教室」という特殊な場ではそんな人でも“支配者”になってしまう。大人は1人で、他は子どもだけ、しかも公的な評価権まで持っていて、外からは見えない閉鎖空間では、ふつうの人でも“権力者”になる。そして権力者は必ず堕落する。
ちょっと口の悪い教師が、そのざっくばらんさを売り物にしているうちに、自分が権力者であることを忘れてしまい、自分の“からかい”が、他の生徒のいじめをつくり出していることにさえ無頓着になった、なんてことは大いに、そしてどこの学校でもありうることだ。
運悪く、堕落した権力的な教師に出会ったらどうするか。私なら反抗する。反抗できないなら、従うふりをして内心で反抗することで自分を守る。それもできないなら逃げる。そんな、偶然に組み入れられた特別な空間である教室にいなくてはならない理由はない。自分を殺してまで。
さらに、中学生たちに語ることがあるなら、家庭だって自分を殺してまでいる場所じゃないよ、とも言いたい。家族によって自分が殺されていると感じるなら、自殺したり、家族を殺したりする前に、やはりまず反抗し、内心で反抗し、逃げるべきだ。中学生では一人で働いて生活していくのは難しいだろうが、日本社会は福祉事務所に飛び込めば施設で受け入れてくれる。
介護職に語ることがあるとすれば、いやそれが私の仕事ではないか。介護職よ、自分を殺してまで続けなきゃならない仕事なんかないんだよ。自分が生かされているという実感を得られない職場にあなたがいるなら、まず反抗し、内心で反抗し、それでもダメなら逃げよう。
ちょうど世の中は景気がいいらしく、人手不足なので、すくなくとも都市部では介護の仕事は見つかるはずだ。偶然に就職した介護現場がひどいところで、それが全世界だと思いこむ必要はない。自分がダメになる前に転職しよう。
いい仕事をしているあなたは「私が辞めたらあのおばあさんはどうなるんだろう…?」と心配かもしれない。でもそれは自意識過剰だ。辞めて2週間もして行ってごらん。もうそのおばあさんは忘れているに違いない。忘れてなくても、ちゃんと他のお気に入りを見つけているはずだ。老人はたくましい。だって、たくましいからこそ、老人と呼ばれるまで長生きしたんだから。
人生には苦労はつきもので、苦労した分だけ人間が完成する、なんて考えて今の職場でがまんしていないだろうか? それは誤りだ。老人を見てごらん。苦労した人はひねくれているよ。もっともそのひねくれが人間の味になっているからおもしろ味があるんだけど。
苦労してひねくれていないのは、かつてのNHKの連続ドラマの主人公くらいなものだ。苦労していない人は素直なだけで味はないよね。ひねくれてしまう前に自分の個性を生かせる職場を見つけよう。もし可能なら、そんな職場をつくってしまおう。
「10年で文化はできる」。精神科医の山崎英樹氏はそう言って、デイケア併設の「いずみの杜診療所」を開設した。“文化”とは、老人を患者を支配しないで治療する文化である。権力的にならないでケアする文化だ。さらにそれは管理主義にならない介護組織をつくり上げるという文化である。
小さな組織ならできるかもしれない。しかし、いまや400人ものスタッフを有するグループでそれをやろうというのは壮大な実験である。でも、10年に2年半足りない現在、すでにその文化が実現していることを感じさせてくれるのが『介護道楽・ケア三昧』という本である。
 私は20年以上この仕事を続けて、せいぜいいくつかのコトバをつくり出したくらいだが、山崎英樹氏と清山会のグループはたしかに文化をつくっている。そんな文化をつくることが可能なのなら、介護職よ、自分を生かしていない管理的な職場にいる理由はないよ。それが私が転職をすすめる根拠である。
私は20年以上この仕事を続けて、せいぜいいくつかのコトバをつくり出したくらいだが、山崎英樹氏と清山会のグループはたしかに文化をつくっている。そんな文化をつくることが可能なのなら、介護職よ、自分を生かしていない管理的な職場にいる理由はないよ。それが私が転職をすすめる根拠である。- 2006.11月 介護夜汰話 近代的因果論への静かな異議
『ぼけてもいいよ』~こんな本を書きたかった 福岡市にある「宅老所第2よりあい」代表の村瀬孝生さんの新しい本が出た。『ぼけてもいいよ』。この本の“帯”の表には谷川俊太郎さんの推薦の言葉が、裏には著者の村瀬さんの「あとがき」からの抜粋がある。それをここに引用してみたい。
今日もトメさんはお葬式が始まると言って若い職員を叱りつけている。マサさんは死んだはずの「お婆」を探している。スミエさんはボタンと穴の関係が分からず悪戦苦闘している。テルさんは誰も知らない天皇陛下の秘密をしゃべってまわる。よく分からないものを分からぬままに、あえて立ち入ることなく添い続ける。意味の有る無しにかかわらず、それを受け入れる余白が社会にあること。それが豊かさへとつながるのだろう。
そうだ。こんな本がほしかったのだ。じつは私もこんな本が書きたかった。私は『痴呆論』(雲母書房刊)という本を書かせてもらった。おかげさまで、“差別用語”になりつつある「痴呆」という題をつけたまま(この本も“ぼけ”が使われている)で、“痴呆”ケアの本では一番の売れ行きを続けている。
この本の主調音は、痴呆や問題行動の原因や誘因は生活のなか、あるいは人生のなかにあるはずだ、だからそれを探し出し、生活そのものを変える、もし可能なら人生を変えればどうにかなるかもしれぬ、というものだ。少なくとも、抑制したり、薬で抑えたりしないやり方はある、とその方法論を経験的に提出しているものだ。だから売れているのだと思う。
しかし、この本のなかで私は「お年寄りの混乱した行動の裏には、必ず理由があります」と断言する「バリデーション」には厳しい批判を展開している。これは原因をすべて脳細胞に還元して事足れりとする医療と同じ「個体還元論」である、と。
この世の中は「痴呆」を「認知症」と言い換え、「痴呆」が「脳の病気」であると思い込むことに成功しつつある。私が主張するように「わからないことにとどまる」なんて、あいまいさには現代人は耐えられず、因果論の世界へ逃げるのだ。
だから世の中の痴呆への興味も、脳細胞の萎縮・変性という原因がはっきりしている「アルツハイマー病」や「ピック病」という“若年認知症”にばかり集中している。映画やドラマになるのもそればかりで、痴呆の95%を占める老人性痴呆はむしろ忘れ去られているかのようだ。
因果論、特に原因は個体にあるとする近代的因果論の世界である医療の関係者は、因果論で説明のつかないものは、あってはならないものだと考えてしまう。そこでそんな痴呆は見ないことにする、または薬や抑制で問題行動すらできないようにするのだ。
「バリデーション」の信奉者たちは、原因がわからないのは介護職として未熟だ、と考えて説教をし、もっと研修しろという。問題行動があるのはあなたの「基本的な人間としての価値観と信念」(「8つの原則」の1つ)に問題があるのだ、というのだ。かたや老人を廃人化し、かたや介護職を倫理的に追いつめる。これらは同じ近代的因果論の暴力なのだ。
「私たちが『理由がある』と言えるのは、痴呆老人の問題行動の70%までである」(『痴呆論』第Ⅰ部、第二章「バリデーションの限界と問題点」26頁)と私は書いた。そして、その70%が「便秘」「脱水」「慢性疾患の悪化」などであることを訴えた。
そして、「さらにもう10.20%くらいは、原因はわからずじまいだったけれど、原因が何かと考えながら関わっていくうちに、問題が解決することがある」(同25頁)とし、「さらに残りの10.20%は、どうやってもその理由らしきものはわからぬまま残る」と書いた。
『ぼけてもいいよ』は、この残った30%、さらに10.20%の老人から始まる、エピソードであり、実は方法論なのだ。もちろん「第2よりあい」のような深い痴呆を引き受けている介護現場ではその割合はもっと高いに違いない。
近代的因果論で解決できるものはちゃんと解決すべきだろう。私はそのために『痴呆論』を書いたし、そういう読まれ方をしている。だがその因果論で事が足れると思われては困る。『ぼけてもいいよ』は、因果論の枠に入り切らない老人をあってはならないとする近代に対する静かな異議なのだ。
問題行動の原因が便秘だったとしても、なぜ便秘でそんな行動をするのかまではわからない。「痴呆の原因が脳だ」というのは「人間とは細胞だ」と言っているようなものだ。間違いではないが内容はない。なぜこんな呆け方をするのか、からわかってくることは、人間とは何かということなのだから。
とすれば、村瀬さんのこの本は30%ではなくて100%に通じる方法論なのだ。方法論といっても、ハウツーではない。どう受けとめ、どのように感じて、どう考え、どうつまらないことをしないか、さらにそれをいいことだと思いこんでしたりしないか、が伝わる名著である。
 『ぼけてもいいよ』
『ぼけてもいいよ』
著者:村瀬孝生
発行:西日本新聞社
定価:1,800円+税
体裁:四六判・上製・309頁
- 2006.10月 介護夜汰話 痴呆につきあえる人とは
~「心の闇をめぐって」~ 「心の闇」という表現が使われ始めたのは何年くらい前からだろうか。犯罪が起きた時、その動機がわからない時やわかっていてもちょっと理解しがたいような理由だったりした時によく使われる表現である。「容疑者が抱えていた『心の闇』の解明が今後の課題です」なんて、ワイドショーのレポーターや司会者が常套句のように使っている。
「心の闇」は、暴力団員の殺人事件では使われない。動機がささいなものであったとしても、殺人を起こすことが不思議と思われない人の場合には「心の闇」は必要ないことになる。動機は誰にも見えない「心の闇」ではなくて、誰にも見えているその人そのものにあると思えるからだ。
したがって「心の闇」は、とても犯罪を起こしそうにない“ふつうの人”や児童や思春期の少年少女などの“未成年”の場合に使われることになる。平和で“従順なはず”の“ふつうの人”が犯罪を起こすはずはない、また純粋で無垢な少年少女はこんなことをするはずがないと思われているのだ。
しかし、私が感じていることを直截に言うと、むしろ“ふつうの人”や“児童”“少年少女”のほうこそ「心の闇」をもっているのだ。おそらく、「暴力団員」のほうが「心の闇」は深くないにちがいない。折りにふれ、その「闇」をちゃんと小出しにしているから。
人間はみんな「心の闇」をもっているというのが私の考えだ。「心の闇」とは、人間のなかにあるわけのわからないものだ。非合理的どころか不条理で、無意識的で、他人からはもちろん自分にも見えることのないものだ。その根拠は、人間というより生命そのものの成り立ちに由来していると言ってもいいだろう。
なにしろ生命発生に根拠はない。最新の科学的知見でも「偶然」なのだそうだ。生命が科学によって合理的で意識的につくられたものなら、私たちには「心の闇」はないだろう。そもそも心そのものがないかもしれない。
問題は、人間の心には闇はないと思われるようになったことにある。人間の行動はまったく合理的で理由のあるものでなくてはならない、と見なされるようになったのだ。少しでも不合理なこと、さらに正しくないとされることをすると、それはあってはならないものとして厳しく叱責され禁止されることになった。保育園や小学校で、子ども同士のけんかや乱暴な言葉すら消えつつある。
そうなると、「心の闇」を小出しにしていくことができなくなる。相手に大きな迷惑をかけない範囲、法律にふれない範囲、そして大きな自己嫌悪を感じない範囲で「心の闇」を発現することこそ本当の「心の健康」なのだが、「心の闇」をあってはならないものとして封印し、見えなくすることが「健康」とされているのだ。
少年犯罪の多くは、封印、抑圧された「心の闇」がコントロールを失って一挙に噴出してきたかのように見える。「なんでそんなことをしたんだ?」と聞かれても、おそらく本人にもわからないのだ。
フロイトはその「闇」を“発見”した。彼は、神経症の熱心な治療者だったからこそそれができた。しかし、同じく治療者だったせいでその「闇」を意識化して治療すべき対象にした。精神分析という治療法である。
いわば「闇」は意識という光を照射すべき対象になってしまったのだ。さらに、それは心がコントロール可能なものと思われ、「心の専門家」まで必要とされるに至っている。心まで専門領域化されつつあるのだ。
治療することが悪いのではない。むしろ治療者としてのフロイトにとっては当然のことだろう。しかし、思想としてのフロイトは、「闇」の存在をとおして、その「闇」を内在化していない意識の世界、理性によってつくられる私たちの世界の危うさと欺瞞性を告発していたのだ。そのことこそが重要なのだ。
だって、考えてみるがいい。少年少女による理由のわからない殺人事件のたびに世間は大騒ぎする。しかし一方で、世界で最も民主的制度をもった二大国は理性的な討議を経た国会で人殺し(=戦争)を決議しているではないか。その正義の名による殺人は少年少女の殺人の何千倍、何万倍におよんでいるのだ。「心の闇」を解明するより前に、理性を、正義を解明せねばならないのは明らかではないか。
個々の事件には原因が判明するものもあるだろう。防止が可能なものには私たちの理性を最大限使うべきだろう。しかし、痴呆性老人の問題行動と同じで、どうしても原因のわからないものは何割か残るのだ。
そんな時には下手な「対策」など考えないほうがいい。それは「心の闇」をあってはならないものとして抑圧することになるだけだからだ。私たちにできるのは、人間はときにわけのわからないことをする存在なんだという思いを共有することではないだろうか。
それが共有されている場は、子どもにも優しいし、老いにもちゃんと関われる。さらに「闇」が露呈してくるかのような痴呆にも少しは余裕をもってつきあえるだろう。痴呆になりにくいのは、ハゲているだけではなくて(※)、自分のなかの「闇」をちゃんと見つめている人でもあるのだ。
※「ハゲは呆けにくい」という説については、『痴呆論』(拙著・雲母書房刊)に入っている『きらら通信vol.10』を参照のこと。- 2006年9月 『ユニット・個室』誤りの理由
~ ロシアで考えたこと ~ 
同世代の男性3人で旅行に行ってきた。旅先はロシアのモスクワとセントペテルブルグ。名づけて「ラスコーリニコフ・ツアー」。40年前に読んだドストエフスキーの『罪と罰』(主人公の名がラスコーリニコフ)を再読しての旅行で、3人以外にはツアー客がいないのを幸い、日本語ガイドさんに、モスクワのドストエフスキーの生家、ペテルブルグの没した家と墓まで案内してもらってきた。

驚いたのは、『罪と罰』の始まりの文章が「七月初旬のおそろしく暑い時分のこと」から始まっていたことで、ペテルブルグに夜行列車で着いたのが7月2日の暑い日なのである。なんたる偶然。もちろん、定番の観光案内もついていて、モスクワの赤の広場、そしてペテルブルグの夏の宮殿も見学してきた。
観光の目玉ともいうべきエルミタージュ宮殿と、そこに収集された美術品には圧倒された。でも途中で「ハイハイ、あなたたたちがすごいのはよくわかりました」と言ってやりたくなった。いやあ、ヨーロッパ文明はすごい。しかし、そのヨーロッパ文明にコンプレックスを抱いた奴はもっとすごいことをする、それがペテルブルグとエルミタージュへの私の感想である。
まずペテルブルグという大都会そのものがピョートル大帝の命令でヨーロッパの町並みを真似てつくったのだ。何もない湿原に、である。その労働によって北欧の戦争捕虜が何万人も死んでいる。美術品はエカテリーナ2世を始めとする王室によって全世界から収集された。その陰で農奴は飢えていたのだが。
ヨーロッパに強烈なコンプレックスを抱いたのはロシアとわが日本だろう。明治天皇はピョートル大帝にたとえられることが多い。また農村の惨状を踏み台にして、軍備の近代化に突き進むのもロシアに似ている。かたや革命と社会主義の悲劇として、かたや無謀な開戦によるアジア民衆の大量の死というかたちで破滅へと至るのも共通性がある。
ヨーロッパ近代へのコンプレックス、つまり相手との距離がうまくとれず、自分自身を見失ってしまうことによる悲劇はいまだに続いている。
老人施設の全室個室化もその一つだと言っていい。ヨーロッパ、特に北欧なんかを見学に行ったインテリたちが、全室個室の施設を見てうらやましがり、日本もそうなるべきだと考えたのだ。
私は「近代的個人」という枠内にいる人が生活する場は個室がいいと思う。つまり、自立している人や、身体が不自由でも、自分の意志の発動が可能で、介護者を活用できる主体があるなら個室がいい。しかし、老いも痴呆も、「近代的個人」という枠から大きく外れて、“生きもの”という自然に回帰していくことなのだ。現場の私たちはそのことをよく知っているから、全室個室化なんておかしいということはわかる。しかしインテリたちは違う。なにしろ「自分が入りたくなる老人施設を」なんて平気で言うくらい、自己中心的な人たちなのである。
軽費や養護、それに有料老人ホームなら個室でもいいだろう。しかし、特養ホームなど、どんな人でも、どんなになっても、最後まで介護するつもりの施設なら、個室も2人部屋も4人部屋も必要なのだ。つまり、個室ばかりのグループホームなんてのは、重い人はケアしません、と宣言しているようなものである。実際、呆けが進行した老人が次々と精神病院に送りこまれ、生活を断念させられている。
インテリの近代へのコンプレックスが老人に悲劇をもたらしているのだ。ロシアの農奴のそれとは比べものにはならないが、1人の人間の人生としてみれば等価である。そのことがわからない人は1年でいいから特養ホームで働いてから意見を言ってほしい。働くといっても、施設長や事務長じゃなくて介護職としてだけどね。
情報筋によると厚労省の内部では「ユニット・全室個室」が間違いだった、と言っているそうだ。「ユニット・全室個室」を強制された施設は、多額の建設資金の返済のために経営が難しく、厚労省に「責任をとれ」と突き上げているかららしい。つまり理由は、老人の立場からではなくて、自分たちの立場がなくなったからだ、というのだから情けないではないか。
「ユニット・個室」を推進した張本人でさえ「ハード優先の建築家に惑わされた」なんて言い訳をしながら「やっていけないので『ユニット』に補助金を出せ」なんて言っているというから、厚労省よりもっと情けない話だ。そもそも「ユニット・個室」にすればいいケアができて老人が落ち着くからというのでつくったんだろう?だったら、ユニットでも個室でもない従来の施設のほうが介護は大変なんだから、そちらにこそ補助金を出すべきじゃないのかね?
「全室個室」なんていう、“エカテリーナ2世”がやったに等しい施策を推進したかどうかは、本当の介護を知っているかどうかのリトマス試験紙だったと私は思っている。

追記 ~ロシアで考えたこと2~
「ヨーロッパ文明はすごい。しかしそのヨーロッパ文明にコンプレックスを抱いた奴はもっとすごいことをする」と書いた。あの飽くなき美術品の収集はいったい何だ?という私の疑問に、ツアーで同行した土井新幸さん(ブリコラージュ 2005年7・8月合併号に登場した”寅さん”)がこういうのだ。
「仏教のすごいところは権力者にさえ、無常ということを知らしめたことではないか」と。

そうか、日本人なら途中で虚しくなってやめるだろう。往くだけではなくて、還り道があるのだが、西欧にはそれがない。”神の国”めざして往きっぱなしである。アメリカやイスラエルといった西欧よりもっと”西欧的”な国家のやり方を見ていてもそう思わざるをえない。
エルミタージュ美術館でほっとできたのは印象派のコーナー。それに私の大好きな、スーチンの「自画像」に会えたのは予想外の喜びだ。しかし、スーチンくらいエルミタージュに似合わない画家もいないだろう。

- 2006.7-8月 介護夜汰話 なんて単純なんだろう
かつてマルクス主義という思想があった。思想家マルクスはこれからも残っていくだろう。しかし、資本主義を倒し、社会主義、共産主義社会にしなければ人間は解放されない、というイデオロギーとしてのマルクス主義は過去のものになったと言っていいだろう。
それは、社会主義国家が資本主義に現実に負けてしまったから、というだけではない。そもそもマルクス主義が人間というものの捉え方そのものに失敗してきたからだ、とそのイデオロギーにかつて惹きつけられていた私は思っている。
特にマルクス主義を標榜する国家の指導者たち、つまりスターリンや毛沢東となるとその思想は、思想というのも恥ずかしいくらいに硬直化していった。「下部構造が上部構造を決定する」なんてのがその典型である。
下部構造、つまり具体的な生産の構造が、上部構造つまり人間の意識を決めるというのだ。資本主義という体制は矛盾をきたして社会主義に至るというのは客観的法則なのだから、われわれの意識もその法則を認識し、その歴史の進歩に奉仕しなければならない、なんてものである。
これが、かつての、そして今だに存在している全体主義をつくり上げたのは当然だろう。その法則を把握しているのは「党」であり、人民はその「党」に従うべきだ、となるからだ。「存在が意識を決定する」なんて命題もあった。
マルクス主義は唯物論と言って、現実的な目に見えるものこそ本質であり、人間の意識のような目に見えないものは現実の反映物にすぎないとされたのだ。それじゃ唯物論ではなくて夕ダモノ論ではないか、と言われていたものである。
現在ではこんな単純な論理に魅力を感じる人はいないだろう。それどころか、スターリンや毛沢東、そして金日成親子による人類史上稀な圧制国家の惨状が誰にも知られるようになっている。ところが、その単純なスターリン主義的人間観、世界観が今だに通用するどころか、ますます強まっている領域があるのだ。
日本の医療と介護の世界である。寝たきりなどの要介護度が進行するのは老人の筋力低下だ、と考えて筋力増強をやろうなんて政策はまさしく「スターリン主義」の亡霊のようなものである。筋力が生活を規定するのではない。それは筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーといった特殊な病気の場合だけに言えることだ。
生活的な世界ではどんな生活をしているのかによって、筋力が維持再生するかどうかを決めるのだ。人間関係が豊かで生活空間が広がっている人は筋力も保たれる。しかし、生きていく意欲がなくなって家から出ない、人に会わない人の筋力は低下する。
生活とは意識と身体が不可分な世界である。「筋力」「身体」という『存在』と「心理」「意欲」といった『意識』は相互に規定されているのだ。そして人間が人間であるということは、意識の側からの規定が意味をもつということにある。それが「主体性」と呼ばれるものだろう。
痴呆が脳の病気である、というのも毛沢東の亡霊である。脳力(変な熟語である)トレーニングをすれば呆けを防止できるというのは、何とも呆れた単純な人間観だが、多くの人がそれを信じ込んで、脳トレの本やゲームに殺到している。
脳が生活を規定するのではない。それはアルツハイマー病やピック病といった特殊な病気の場合だけに言えることだ。生活的世界では、どんな生活をしているかによって、脳やその機能が維持、再生できるかどうかを決めるのだ。
生活のなかで強いストレスが続くと脳細胞の再生が困難になる。環境の変化や突然の身体障害、オムツの強制、手足の抑制、などによって、あっという間に痴呆に至るケースはまさしくそのせいである。逆にストレスのない生活づくりによって痴呆が治ることがあるのも、そのことを示している。
寝たきりの原因を筋肉に、痴呆の原因を脳に求めるという“マルクス主義的”発想は「個体還元論」と呼ばれる。病気を身体や心理という個体の特定の臓器に原因を求めるというのが近代西欧医療の方法である。それが目を見張るほどの治療効果を上げたのは言うまでもない。
しかし、ヒステリーはもちろん、精神分裂病(統合失調症)と呼ばれた状態にはこの方法は通用しなかった。寝たきりや痴呆についても通用するはずがないのだが、人々は単純な論理を好むのだろう。専門家もシロウトも。
単純なマルクス主義や「愛国心」を叫ぶナショナリズムを人々が支えてしまう理由がわかる気がしてきた。医学で解けないものは人間学でアプローチしよう。個体に還元できないものは生活のなかに、さらに人生のなかに原因や誘因を求めていこう、それが介護の方向性である。世の中とは逆の。- 2006.6月 介護夜汰話 現場から届いたコトバ
私の本を読んでくれた人からお手紙をいただくことがある。『老人の生活ケア』(医学書院刊)という私の最初の本を読んで手紙をくれたのが下山名月さんだ。それをきっかけにして、当時どこにもなかっだ民間デイサービス「生活リハビリクラブ」が始まった。少々大げさな言い方をさせてもらうと、1本の手紙によって日本のケアが変わったのである。
介護について書かれた手紙だけではなくて、自分の生き方についての相談もよく来る。高校中退、正確には退学処分で逮捕歴も何回かあって、バッイチ(実質上はバツ2)の私なんかに人生相談をもちこんでどうする? と思うが、そんな手紙にはできるだけちゃんとした返事を書くようにしてきた。
でも「入浴拒否の老人に有効なコトバかけがあったら教えてください」なんて手紙には返事しないで放っておく。現場で話し合って、本も読んで、やってみてうまくいかなくて、また話し合って、本を読んで……と繰り返してみるよりないじゃないかと思うからだ。
だいたい、プロなんでしよ。プロ野球の選手がアメリカのイチローに「どうやったらヒットを打てるか教えてください」なんて手紙を書くかね。ましてや、私の打率は2割5分だ。イチローにはとてもかなわない。『痴呆論』を読んでもらうと意味はわかると思うが、1つのアプローチをやってみてうまくいくのは4つに1つぐらいという意味だ。でも1人の人に4つくらいの方法は試してみるけどね。
「いいですねえ、マイナスをゼロに。『美しい言葉はみな嘘に近づいていく。誰も振り向かぬものこそ動かしがたい』という俊太郎さんの言葉の世界も見抜いているし」
こんなファクシミリを送ってくださったのは、野の花診療所(鳥取市)の徳永進先生だ。
ブリコ4月号の「介護夜汰話」への感想である、「俊太郎さん」とは、もちろん詩人の谷川俊太郎さんのこと。いや、ブリコラージュに目を通していただいているだけで恐縮。大阪の「元気の素」が主催した徳永進講演会は大好評だったという。ぜひ東京のブリコラージュセミナーにお呼びしなければ。
最近では、手紙とファクシミリに代わってメールが増えてきた。講演先から帰宅してみると、もうその感想が届いていることもある。同じ4月号の「介護夜汰話」には次のようなメールが届いた。
「ショックでした。『マイナスをゼロに』という文章のなかの以下のところです。「もうこんなプラスのコトバ=幻想に期待し。たりするのはやめにしようよ。期待しては幻滅させられて、今度は次の幻想を探しては……この繰り返しではないか』。この間の私はそのとおりでした。
「痴呆性老人ケアの切り札」と言われたグループホームに期待して就職して見事に幻滅させられ、それでもちゃんとしたところならと期待して同じことの繰り返し。
今度は『小規模多機能』に期待していましたが、それも結局は大規模施設の地域の囲い込みの制度にしかならないことがわかりました。それをズバリ指摘されてガックリしていたら「編集後記」で後追いを受けました。
『行政が10年後についてくるような現実をつくる』仕事をしたいと思っています」
アンリ=ルフェーブルという思想家は『日常生活批判序説』という本のなかで、資本主義を「幻想と幻滅の繰り返し」であるとして批判していた。人々は消費意欲をかきたてるため、より強い刺激を与えられ、いつまでも落ち着くことがない。いまや、福祉や介護の世界までその資本主義の論理に完全に組み込まれたということだろうか。
私たちの「生活リハビリ」や「新しい介護」だって、その「幻想」として消費されていくおそれは十分にある。ただ、私たちの方法論をちゃんと現場でやってみせる人がいっぱいあらわれたおかげで、幻滅から脱出するために飛びついた人が、幻想ではなくて、地に足のついた希望につながることができていると思う。その点は本当に読者に感謝だ。
「私も婦長も医療経験しかないからデイサービスの介護職の言うことが理解できなかったのです。思いつきで言っているとしか思えなかった。彼らはなぜやるのかということは言いませんから。でもこれを読んで、遅まきながら彼らがなぜそれを訴えていたのかがわかってきました。辞めていった若い子もいたので残念ですが、これからは介護職とちゃんとしたコミュニケーションがとれそうです」
これは、親しい医師からのメールである。『実用介護事典』(講談社刊)を読んでの感想だ。私はこの事典で介護職が老人を理解できるよう、老人世代の文化についての項目をたくさんつくった。「のらくろ」「冒険ダン吉」「空襲」「配給」「進駐軍」「君の名は」……etc。
しかし、この事典は医療職や看護職が介護職を理解するためにも役だっていたのだ。この1本のメールだけでも時間をかけてつくりあげた甲斐があったというものだ。- 2006.5月 介護夜汰話 ぬる問題
読者の皆さんにクイズ。 『実用介護事典』をつくりあげる過程で「ぬる問題」というのが発生し、会議まで開かれた。はたして「ぬる問題」とは何だろう。
ヒントその①。 正しくは「ぬる」ではなくて「ぬ」と「る」の問題である。
ヒントその②。 これは多くの事典や用語集を編集する時に必ずといっていいほど生じる問題である。
さあ、それでもわからない人は、実際に事典を引いてみよう。もちろん「ぬ」と「る」の項を。もうおわかりだと思う。「ぬ」と「る」から始まる言葉が少ないのだ。一般の事典でも限られるのに専門的な事典となるとなおのことで、最初はまったく項目がないのだ。
それでは格好がつかないというので頭をしぼることになった。苦労のあとは見ていただければわかると思う。 「ぬた」や「塗り箸」はちょっと苦しいけれど、高齢者の文化として取りあげた。「塗り絵」という項目もほんの少し前なら苦しまぎれと思われたろうが、いま「大人のぬり絵」が大流行で高齢者用のぬり絵も好評である。
「うたうぬりえ帖」(風塵社)は、編集者が私たちの開いている読書会に見本を持って、売れるかどうか意見を聞きにきた。デイサービスや施設に持ち帰って試して、「これなら使える」というので発売に至った。上・中・下巻とそろって売れ続けている。
高齢者用のぬり絵の本は続々出版予定だ。5月には講談社から『名曲のぬり絵』が、雲母書房からは『童謡・唱歌ぬりえ帖』のシリーズが発売される。 『名曲のぬり絵』に私は次のような「推薦の言葉」を寄せた。
「安静」と「リハビリ」は正反対のもののようだが、じつは同じものだ。「安静にしていたらよくなる」「リハビリしてよくなってから」という、未来から現在を見ている。でも介護は違う。現在が一番よいからだ。今日老人を生きいきさせられないなら、明日はもっと難しくなる。
だから、いま、ここから始める。その地平から見ると、安静は「いま、ここ」を奪うものだし、リハビリは、「未来への逃避」だ。老人の「いま、ここ」を支えているのは「未来」よりは「過去」だ。なにしろ、心身の老化、人間関係の喪失、「老い」を内在化していない専門家…etc。
これらに適応して生きてかなければいけないのだから。なつかしい曲を歌いながらぬり絵を描くこの「紙芝居」と共に、「ぬり絵」は私たち介護職が、老人の「いま、ここ」を支えるためのノスタルジーを共有する方法論として掘り起こした日本の文化である。
「ぬ」で私が介護職に読んでほしいのは、「ぬれたオムツ」という項目である。決して無理につくった項目ではない。「オムツ」からはじまる8つの項目と共に、私が介護現場にもっとも訴えたいことである。
「る」にも読んでほしい項目がある。「ルサンチマン」だ。暴力行為だとされ、痴呆による問題行動と思われているものに、この「ルサンチマン」の表現であることが多い。世界を信じられなくて、近づいてくる人を拒んでいるのだ。
考えてもみてほしい。「生命維持」や「栄養補給」の名のもとで鼻から管を入れられ、それを抜こうとすると手を縛られるのだ。「ジジ・バパ体験」でチューブを入れられた人は皆言う。「とても生きていく気がしない」と。鼻、喉への違和感、嘔吐感、ツバを飲み込むたびの痛み。気になって意識は集中しない。聞こえていても’聞こえない。見ていても見えない。
医者や看護婦は全員自分自身に鼻腔チューブを入れて1日その状態で生活してみるべきだろう。そうすれば、これは人間が人間にやるべきことではないとわかるはずだ。していいのは意識を失っている場合だけだと。
自分が同じ目にあってみなければわからないというのは情けない話ではある。老人がチューブを抜こうとして抵抗するのを見ていてわからぬのはなぜだろう。ルサンチマンを理解するのに。同じルサンチマンをもたねぱならないのなら、この世は復讐だらけになってしまう。
専門家と名乗るのなら想像力を使え。人間性があるなら老人の気持ちを想像せよ。 私は「ぬる問題」をも活用して、この事典に自分の思いを込めたつもりである。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
やましさと利己からのケア・介護
~ 講演 最首 悟 ~
§---------------------------------------------------------§- 2006.4月 介護夜汰話 マイナスをゼロに
~ 幻想はもう捨てよう ~ 最首悟さんの話をはじめて聞いた。3月4日の本誌主催「ブリコラージュセミナー」でである。最首さんからは35年も前、彼が東京大学の大学院にいた頃、強烈なメッセージを受けたことがある。それがこうして出会うことになったのは彼が介護家族だからである。
子の一人が重度の障害をもって生まれた。「死んでくれないかなあ、と思うんですよねえ」。満員の会場がシーンとする。でも、彼は穏やかでふつうの口調である。「そう思いながら、一生懸命やるってこともあると思うんです」「殺そうとは思ったことはないですけれど、親子心中は考えますねえ」。
これ、笑顔での発言である。会場は、ああこんなこと言ってもいいんだという、逆に緊張が解けた雰囲気になる。 誤解しないように。これは40kgも体重のある我が子を70歳の介護者がおんぶしてケアする、そんなケアを30年間続けてきた彼が言うことなのだ。
白内障の手術で入院したら、若い医者の練習のために反対の目のレンズまで取られて医療に希望なんかとっくになくしている彼が言うことだ。毎日風呂に入れ、それを障害者団体から「セクハラそのものだ」と糾弾されて、「もう二度としません」と約束して家に帰り、妻から「自分の子どもを風呂に入れて何が悪いのよ」と言われて入浴ケアし続ける彼の発言なのである。
「ケアしたいなんて人はいないでしょう。向こうだって、こんなヤツにケアされたくないと思っているにちがいない」。それでもケアし続けていることの根拠を探して「内発的義務」なんて言葉をつくっていくのだ。
そんな立場から、彼はあまっちょろいボランティアなんか小気味よく批判する。本当は、当日会場の大半を占めていたわれわれプロの介護職にも言いたいことはいっぱいあっただろうと思う。直接の批判も皮肉もなかった。でも私には深いところで届くものがあった。それは、次のような発言に象徴される。
「マイナスをいかにゼロに近づけるかということだと思うんです。決してプラスにはならない。してはいけないんです」。 う~ん。介護の世界のダメなところが見えてきたぞ。 「自分が入りたいと思うような老人施設をつくりたい」なんて言う人がいる。私も言っていたことがある。
しかし、老人施設なんて入りたくて入るものじゃない。自分の家での個別の生活を断念せざるをえなくなって、しかたなく入るものだ。 そこで必要なのは「しかたなく来たけれど、ここでの生活も捨てたもんじゃないな」と思ってもらうようなケアだ。マイナスをゼロに近づけることだ。
ところが「日本一の施設にしたい」なんて言う。それは競争社会の立身出世主義そのものじゃないか。“日本一”じゃなくて、日本中でどんな介護職でもできるようなふつうのケアをちゃんとやって見せることが必要なのだ。
「尊厳を守るケア」なんてのもプラスのコトバだ。呆けや寝たきりになったら人間の尊厳なんかなくなるから筋トレしましょう、なんて風潮を生み出しているだけではないか。「介護予防」もそうだ。
本当に介護予防したければ、ベッドの幅をせめてシングル幅にすることに補助金を出せばいい。介護予防の10分の1の予算で10倍の効果が出るはずだ。 「家庭的ケア」なんてコトバもプラスの雰囲気をもっている。でも考えてみればいい。日本の現在の家庭は、障害児や精神障害者、寝たきり老人たちを施設に送ることで成り立っているではないか。
どおりで「家庭的」を売り物にするグループホームが、ちょっと呆けがすすむと、すぐ精神病院に送り込むという排他性をもっているはずだ。 では「地域」は老いを支えられるだろうか。「地域ケア」なんてコトバもなにやらプラスの雰囲気をもっている。そんなコトバには気をつけたほうがいい。老いを支える地域なんかどこにも残っていないではないか。
今、どんな人でもできるだけ地域で支えようとしている実践は「地域と闘うケア」になっているではないか。特に、都市近郊の住宅地がもっとも差別的だ。高学歴で権利意識のある中産階級の連中がもっとも老人施設に反対し、痴呆老人が歩くことや顔が見えることにさえ文句をつけるのだ。この先、日本中がみんなこんな状態になっていくのだろう。
「グループホーム」も「小規模多機能」も「地域ケア」で「家庭的」だからいいのだそうだ。かつて、「老人保健施設」も「地域」と「家庭」に帰すからいいと言われたものだ。「ユニットケア」も「家庭的」だからいいケアができるのだそうだ。
もうこんなプラスのコトバ=幻想に期待したりするのはやめにしようよ。期待しては幻滅させられて、今度は次の幻想を探しては……、この繰り返しではないか。その典型が「リハビリテーション」だろう。いつまでたっても現実から始めないための「未来への逃避」……。
これだけ多くのコトバと制度が出てきながら、老人のベッドの幅ひとつ広くなっていない。いかにこの世界が地に足をつけていないか、わかろうというものである。 やむなくやっているものとしての介護、という見方は、私たちの人生観とも通底する。
やむなく生きている、生かされている、そして関わりたくもないのに人と関わって生きていかざるをえないということにも。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§ 星子が居る
星子が居る
著者:最首 悟
発行:世織書房
定価:3,600円十税
体裁四六判・上製・446頁
§---------------------------------------------------------§
§------------- Read Me Pleas --------------------------§ ケアの社会倫理学
ケアの社会倫理学
著者:川本隆史
発行:有斐閣
定価:2,000円十税
体裁:四六判・並製・376頁
URL : http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641280975
§---------------------------------------------------------§- 2006年3月 介護夜汰話 異文化としての老い
海外に行って来た。といっても北欧なんかへの視察旅行なんかではない。プライベートな旅で、行き先は北アフリカだ。風景も想像を超えたものだったが、もっと驚いたのはそこでの人々の生活である。迷宮のような街での中世と変わらないような生活、砂漠に行けば今度は古代から続いている生活がそこにあるのだった。
 旅行会社のパックツアーに男ばかりのグループ6人で申し込んだ。30人を超えるツアーのなかで働き盛りの男6人というのは珍しく、残りの大半はすでに定年で仕事を辞めた年代の人たちである。しかも、北アフリカなんかに来るのは、ハワイやヨーロッパにはもう行ったという人が多く、時間にも、経済にも余裕がありそうな人たちである。
旅行会社のパックツアーに男ばかりのグループ6人で申し込んだ。30人を超えるツアーのなかで働き盛りの男6人というのは珍しく、残りの大半はすでに定年で仕事を辞めた年代の人たちである。しかも、北アフリカなんかに来るのは、ハワイやヨーロッパにはもう行ったという人が多く、時間にも、経済にも余裕がありそうな人たちである。

そのなかの男性たちが私には気になった。朝食でテーブルがいっしょになったのだが、会話をする気にならないのだ。「ロクな食べものがない」「クサい」…etc。その言い方が差別的なのだ。日本人の自分の口には合わないというだけではないか。そもそも納豆を食べている民族がよく「クサい」と言えたものだ、と私には思えるのだが。
気に入らないのは食べ物だけではないらしい。ホテルのスタッフの教育がなっていないとか、店員の態度が悪いとか、悪口だらけである。現地のガイドをつかまえて説教をし始めたりする。
旅行、特に海外旅行の楽しみとは何だろうか。日本とは異なる風景を見て感動し、異なる文化に接して驚くことだろう。日本の文化との距離を感じ、その背後にある自然や歴史の大きな違いに思いを馳せ、判断を停止して、あるがままを認めることではないか。いわば自分が相対化されるおもしろさを味わいに行くのだ。
 でも、彼らはそうではないらしい。自分たちの文化の価値観のなかに、相手の文化を組み入れようとするのだ。西欧や近代化された日本は進んでいて、この国は遅れている、と見なしてしまう。だから、けなすか、教育してやろう、となるのだ。相対化するどころか、自分を絶対化してしまうのだ。
でも、彼らはそうではないらしい。自分たちの文化の価値観のなかに、相手の文化を組み入れようとするのだ。西欧や近代化された日本は進んでいて、この国は遅れている、と見なしてしまう。だから、けなすか、教育してやろう、となるのだ。相対化するどころか、自分を絶対化してしまうのだ。
彼らの世代は決して狭い世界にいた訳ではない。実際に、商社マンとして海外生活の長かった人もいるのだ。でも考えてみれば彼らは、その海外でも現地の人たちと交流しようとはせず、日本人だけで、日本の価値観や会社内の序列まで持ち込んでいた人たちなのだ。空間的には広い世界を体験していても、その意識は狭いままだったらしい。
同世代でも女性はちょっと違う。好奇心旺盛でよく笑い、よくしゃべる。男性のほうは表情が乏しい。好奇心もあるのだろうが、カメラのレンズを通してしか向き合おうとはしない。いわば客観的な観察者になることで、異文化の衝撃から自分を守ろうとしているかのようである。
よく似ているなあ、と思った。医師や看護婦、PTやOTといった医療関係者が老人に対する関わり方に、である。彼らは「老い」とか「障害」「痴呆」という「異文化」に出会った時、“判断を停止してあるがままに認める”のではなく、自分たちの価値観のなかに組み入れようとしているのだ。
医学書を開いてみよう。「老人の特性」なんて項には老人の悪口ばかりが書いてある。「体力の低下」「適応力の低下」「刺激に対する反応時間の遅延」etc…。いったい基準になっているのは誰なのだ。若い人ではないか。
パックツアーのおじさんが「自民族中心主義」(レヴィ=ストロースが西欧中心主義を批判してつくったコトバ)なら、医療関係者は「自世代中心主義」である。その“問題だらけ”の老いを教育(=治療)してやろうとして、かつては(今も)点滴潰けにして手足を抑制し、最近では「筋トレ」をしない老人は非国民だと言わんばかりなのだ。
彼らもまた、狭い世界で生きてきた。実社会での経験のないまま専門家になり、コンプライアンス=従順であることを義務づけられた患者ばかりとつき合ってきた人たちだ。「老い」も「痴呆」も従順な訳がない。自分たちに理解できない「老い」や「痴呆」を目の前にして彼らは「冷静な観察者」として振るまい「問題点」を列挙し、治療、リハビリの対象にすることにしたのだ。狭い世界の自分を守るために。
帰国してからの数日、忘れかけていた昔の夢を続けて見た。どうやら無意識が撹拌されているようだ。今回の見聞は、長い時間かけて自分のなかで整理されていくだろうと思う。確かなことは、近代とか医療とかよりも「生活」にこそ普遍性があると考えてきたその「生活」が、よりシンプルなものになっていくだろうということだ。
つまり、ヒトはただ生まれて、食べて、死んでいくのだというところへ。
§------------- Read Me Pleas --------------------------§
 『老人の生活リハビリ』(医学書院刊)のなかで、医学、心理学の老人観を批判しているので、興味のある方は一読を。
『老人の生活リハビリ』(医学書院刊)のなかで、医学、心理学の老人観を批判しているので、興味のある方は一読を。
書籍詳細
§---------------------------------------------------------§

- 2006年2月 介護夜汰話 宅老所「よりあい」が元気だ
福岡の宅老所「よりあい」が元気だ。まず。年2回のバザーの時にしか届かなかった「よりあいだより」が、なんと毎月くるようになった。しかも中身が充実している。老人の人生を通して、社会や世界に迫っていくような主張のあるものだ。
その「よりあい」スタッフ、それに宮崎の人たちの全面協力で、オムツ外し学会の九州版を福岡と宮崎で開いた。新年の3連休なので参加者が殺到、とはいかなかったものの、両会場とも200人もの熱心な人が九州や中国地方からも参加した。
「よりあい」の元気さが地に足の着いたものであることがこの学会でよくわかった。代表の下村恵美子さんに報告をお願いしていたのだが、「よりあい」と「第2よりあい」(代表村瀬孝生さん)の若手のスタッフが2人ずつ、1人の老人への関わりを報告した。
「よりあい」は、制度上の表現では「グループホーム」と「デイサービス」だ。それに「ショートステイ」ということにもなる。しかし、制度で仕事をしているわけではない。ニーズに応えるためにこの活動を始めた。だから最も困っている人とその家族のために、必要なことはできる限りやる。
だから、最初は「デイサービス」だったのがそのうち、夜眠れない家族のために「ショートステイ」を引き受け、それでも限界に達すると「グループホーム」に至った。下村さんたちはこれをそれぞれ、「通い」「泊まり」「暮らす」と呼ぶ。ニーズのためならなんでもするのが本当の「多機能」だ。それを制度にしてどうする。と私は思う。
だから制度ができてから雨後のタケノコどころか、梅雨のカビのように発生してきた「グループホーム」とは本質的に違う。「グループホーム」の大半は軽い痴呆だけを受け入れて、呆けが進行したら出てもらいます、なんて平気で言う。出ていけと言われても現在、介護保険が目玉にした在宅介護は崩壊状態で、特養ホームは100人もの入所待ちという状態だ。そこでグループホームから精神科の病院への入院が続発している。
病院から家庭へ帰すための「中間施設」としてつくられたはずの「老人保健施設」があっという間に、病院から特養ホームへの「中間施設」になって、皮肉なことに、病院から1日たりとも家には帰さないための施設になったように、今やグループホームは、在宅ケアを早期に断念させて抑制と独房閉じ込めの病院へ送り込むためのシステムになり下がりつつある。
この制度ができる時、厚労省に意見を聞かれた下村さんは「せめて3年問、地域の老人をデイサービスで支えて、老人のこともよくわかり、家族に信頼してもらうという経験をした人に『グループホーム』を始める許可を出すようにしたらどうか」と提案したという。しかし「グループホームは介護保険の¨目玉”であり競争でケアの質はよくなる」の一言で押し切られ、大量のグループホームが乱造されることになった。
“目玉¨で政策はつくられるのだ。つまり政治家や官僚の国民への、特に声高な進歩的「市民」に対する人気とりである。老人と家族の切実なニーズに応えようと考えているのではない。ましてや、現場の介護職の主体的条件が整っているかどうかなんて考えもしない。われわれ介護職を単なる介護力だとしか思っていないのだ。
当然ながら、「よりあい」「第2よりあい」の関わりは、老健施設なら「とてもうちではみられません」というだろうし、大半のグループホームは入所すらさせてくれないようなケースを在宅で支えていく報告である。ここの若手職員は特別なスタッフではない。職安、つまりハローワークの求人票を見て面接に来た人も多い。
なにしろ下村さんは。「三好さんの本や「九八歳の妊娠」を読んで感動して『老人が大好きです』なんて言う人は、それだけでは信用しません。理想的なケアが行われているからここで働きたいと言うのでは困るのです。いっしょにつくっていきたいから」と言うのだ。理念から入るのはダメだという。
確かにそうだ。同じ理念をもった人ばかりを集めると一定のレベルの介護をつくりだすことはできる。宗教団体や政治団体、組合や生協が運営するところがそうだ。しかしこれには普遍性がない。ハローワークからやってきた特別ではない人たちが集まってできることでなくては、日本中の老人を元気にはできないではないか。
それとも、日本中が、私たちと同じ理念をもたなければいい介護はできない、とでも言いたいのだろうか。そうだ、そうした宣伝に使うために老人介護をやっているとしか思えないのだ。私が、ブリコラージュの読者ばかりを集めて施設をつくろう、なんて発想にならない理由はここにある。
下村さんは実践報告では司会役だったが、続いての「グループホーム虐待致死事件を考える」ではその思いを熱心に語った。自らも経験している「一人夜勤」の現実からの訴えは「あれは自分ではなかったか」(発行プリコラージュ)。をぜひ読んでほしい。
この本、「週刊現代」の書評で上野千鶴子さんが取り上げてくれて再び話題になっている。私たちもこの問題にはまだまだこだわっていく。2月17日には山口県で高口光子さん、下村さんと3人で、18日には松山市、25日には艮野県で、高口さんとシンポジウムを予定している(情報欄参照のこと)し、来年度も各地で開くつもりだ。声をかけてほしい。
下村さんは熱心さのあまり、1時間のうちの45分間話して、私の時間は15分になった。もちろんこれは想定内である。なにしろ最初に発言をお願いした広島でのオムツ外し学会で、15分の予定を30分以上しゃべり続け、しかもそれが辞めた施設への批判だけだった、というのは今でも語り草だ。
「体力がなくなった」「ひがみっぼくなった」と言うものの、下村さんは相変わらず下村さんだった。ただ、ちゃんと若手が頑張っている。「よりあいだより」も若い人たちがつくって、毎回800人もの人に送っているという。送料だけでも大変だ。定期購読を申し込んであげてほしい。 シンポジウムで私の言いたかったことも書くつもりだったが、また別の稿で。
- 2006年1月-2005年12月 介護夜汰話 「事典」をコミュニケーション・ツールに
「旅行けば、駿河の国に茶の香り……♪」
デイサービスに通っている平山のじいさんの十八番(おはこ)は、浪曲の「森の石松」である。しかし、若い介護職たちは一度も聞いたことがないという。そもそも「浪曲」というものを知らないのだ。だから平山さんが「広沢虎三」をもじって「平沢虎三です」と言っても誰にもウケない。
老人問題というのは、老人に問題がある訳ではない。老いることは生きた結果であって自然過程を経たということだ。問題は、私たちの世代が老いた世代とどう関わっていいかわからないという、世代間のコミュニケーションの問題だ。だとしたら、平山のじいさんとデイサービスのスタッフたちの間にある文化の断絶は、老人問題の現在の課題を象徴しているだろう。
 『実用介護事典』が刊行された。大田仁史先生と私が監修させてもらった。4,150語もの項目のある介護事典は世界では初めてで画期的なものだと思っている。 介護用語、医学用語をわかりやすく解説したのはもちろんだが、私が力を入れたのは、老人との文化の断絶を埋められるような項目を多く取り入れたことだ。
『実用介護事典』が刊行された。大田仁史先生と私が監修させてもらった。4,150語もの項目のある介護事典は世界では初めてで画期的なものだと思っている。 介護用語、医学用語をわかりやすく解説したのはもちろんだが、私が力を入れたのは、老人との文化の断絶を埋められるような項目を多く取り入れたことだ。
のらくろ 1931年に講談社の雑誌「少年倶楽部」で連載が始まった漫画の主人公。作者は田河水泡 (1899~1989)。野良犬だったのらくろ(野良犬黒吉)が連隊に入隊し、二等兵から大尉にまでなる。 戦後は旅館の番頭などを経て、喫茶店を開いて終わる。日本の漫画のキャラクターとしては当時もっとも有名で、老人にとっては戦中、戦後の苫しい時代を共に過ごしてきた特別な思いがある。
京都には、「のらくろ」という名のデイサービスセンターがある。 「のらくろ」だけではない。「冒険ダン吉」も「フクちゃん」もイラスト入りで説明している。[のらくろ]の前には[のと自慢]、少し後には[ノロウイルス]という項目が並んでいるのが、この事典の性格を表しているだろう。
ちなみに、デイサービスセンター「のらくろ」はNPO法人丹後福祉応援団の運営するショッピングセンター内の施設である(本誌2004年12.1月号参照)。 もちろん「実用」と名がついているように、介護の考え方と方法についてはどこにも負けていない。 私たちが、これこそが本当の意味で老人の尊厳を大事にするケアだと考えている排泄ケアでは、「排泄ケア」「排泄ケア(痴呆性老人の場合)」「排泄ケアの環境アセスメント」「排泄ケアの生理学的アプローチ」「排泄最優先の原則」「排泄チェック表」と6つの項目を5ページにわたって詳しく説明している。入浴ケアも5項目、イラストを含め4ページにもわたっている。
しかし、介護現場の人たちにもっともウケてるのは、巻末資料の「流行歌でつづる大正・昭和史年表」と巻末の120年分の干支(えと)の一覧表である。老人との会話のきっかけになるのだという。この事典を世代間コミュニケーションの道具にしたいというねらいが当たった、と私たちは喜んでいる。
時代による用語の意味の変化についても説明している。
たとえば………金婚式[きんこんしき]golden wedding 夫婦が結婚後50年目を迎えたときに行うお祝いの式。かつて平均寿命の短い時代には、夫婦そろって長生きすることは珍しく。大変めでたいとされた。一方、長寿社会となった現在では、離婚することなく50年目を迎えることがむずかしくなっており、やはりめでたいことに変わりはない。といったふうに。
はたして、あなたは「浪曲」や「広沢虎三」を知っていただろうか。「都々逸」や「講談」はどうだろう。「進駐軍」「配給」「空襲」「君の名は」「鐘の嗚る丘」……。老人に関わる人なら知っておかないと老人との共感はつくれないだろう。これらの項目はすべて「事典」に入っている。 売れ行きは順調で発売とほぼ同時に増刷になった。読者のみなさんのおかげである。