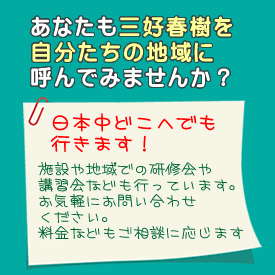●「投降のススメ」
経済優先、いじめ蔓延の日本社会よ / 君たちは包囲されている / 悪業非道を悔いて投降する者は /
経済よりいのち、弱者最優先の / 介護の現場に集合せよ
(三好春樹)
●「武漢日記」より
「一つの国が文明国家であるかどうかの基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である」
(方方)
● 介護夜汰話
介護夜汰話 痴呆論余話 ~禿げは呆けにくい?
介護夜汰話 介護拒否とはなにか
介護職はなぜ辞めるのか?
介護の専門性とはなにか
介護夜汰話 老人介護の現在 ⑨ ユニットケアの退廃 その3 ~対象者の選別~
「一緒に共有する」ツールとしての遊び
ブリコラージュインタビュ『あなたに逢いたかった』
介護夜汰話 老人介護の現在 ⑧ ユニットケアの退廃 その3 ~対象者の選別~
介護夜汰話 老人介護の現在 ⑦ユニットケアの退廃 その1 ~ケアの中身をかたちで乗り切るな~
『死ぬ』と『死ぬる』
介護夜汰話 老人介護の現在 ⑥「現前性」と「先験性」 ~必然性のないケアは堕落する~
介護夜汰話 老人介護の現在 ⑤小さいことはいいことではない ~グループホーム・ユニットケアの問題点
介護夜汰話 老人介護の現在 ④ ISO にはアイソが尽きた
介護夜汰話プラス 介護の社会化の弊害を超えて
「家族か社会か」から「家族も社会も」へ
介護夜汰話 老人介護の現在 ③ 遅れてやってきたCS(顧客満足)
介護夜汰話 老人介護の現在 ②「全室個室」という画一的人間観
介護夜汰話 老人介護の現在 ① 混迷の原因はどこにあるか
特集 【対談】
介護と子育てのアポリア(難関)はどこにあるのか 芹沢俊介×三好春樹
介護夜汰話 「最後の母」としての介護職 ~地下水脈を見つけた~
「介護という暴力」を考えさせる一書
”老いに対して医療が出しゃばりすぎる”
介護夜汰話 痴呆と家族の責任をめぐって ~質問に応えて~
2002・徳島の夏!「寝たきりになら連」阿波踊り!
介護夜汰話 痴呆と家族の責任をめぐって ~質問に応えて~
流行にとらわれず現場から創る管理運営論
介護夜汰話 こんな医者、看護婦は急性期病院へ帰れ!
介護夜汰話 「家庭的」という欺隠 ~こんなグループホームはやめてしまえ~
介護夜汰話 ユニットの強制にどう対応するか
いいケアは自分でつくれ
介護夜汰話 個室の強制にどう対応するか
Mさんよりのメール
介護夜汰話 読んでほしい本がある
介護夜汰話 “筋トレ”ブームをどう思う
- 2003 ~ 2002
-
- 2003年12月 介護夜汰話 痴呆論余話 ~禿げは呆けにくい?~
『痴呆論』は私がずっと書きたかったことである。介護現場に入って以来「どうして人間は呆けるんだろう?」「どうしてこんな呆け方をするんだろう?」と不思議でしかたがなかったから、『痴呆論』のちらしにある「構想29年」というのも決して大げさではない。私か特養ホームに偶然就職したのは今から29年前、24歳のときである。
それから9年後、竹内孝仁先生に呼んでもらって「地域リハビリ研究会」の前夜祭の少人数のシンポジウムで話をさせてもらう機会があった。私は痴呆老人の訴えがメタフア(=隠喩)ではないか、という話を15分ほどした。この話は「Nさんのロシア」という題で『老人の生活ケア』(医学書院刊)という私の最初の本に収録されている。
ちなみにこの本、これまでの私の本のなかで一番いいと言ってくれる人が多い。それでは進歩がない、ということではないか!この本で人生が変わったという人もいる。介護用品のセールスマンに勧められて読んだのは下山名月さん、めったに本を読まないのに本屋で偶然目にして買ったのが小松丈祐さん(「諏訪の苑」施設長)。
このときの私の話をおもしろがる人が何人も現れた。現場でこんな話をしてもみんな興味を示さず、「で、どうしたらいいの?」と言われるくらいだったというのに。世の中には共感してくれる人がいるんだ、その体験が私がフリーになることを後押ししたと思う。
今では現場に共感してくれる人がいっぱいいる。竹内孝仁先生による痴呆の三分類について、日経流通新聞のコピー(2003年6月19日付)を送ってくれたのは倉原一敬さん(神戸「山手さくら苑」施設長)だ。そこには上半期のヒット商品番付が発表されており、不況と先行き不安のなかでの消費動向を分析して、健・再・逃の三文字で表現しているのだ。「健」は健康志向、「再」は再興、「逃」は現実逃避である。
「経済がマヒしていく状況に直面して自信を失ったときに人がとる対応パターンと、痴呆の竹内三分類に共通性がある」と倉原さんは言う。健康な身体になって頑張って乗り切ろうとする人は、それでもうまくいかないときに「葛藤型」に至るのではないか。昔流行ったもののリバイバルがうけるのは、過去のノスタルジーに癒しを求める「回帰型」だろう。現実逃避はもちろん「遊離型」だ。
直面する困難が「不況」から「老化」に代わったときにも、人の対応は同じであるらしい。つまりここに竹内三分類の人間学的根拠がある、という内容だった。う~む、私がやったような「死の受容論」や「障害受容論」を逆行していく心理過程として説明しなくても、こんな身近かなところにその根拠はあったのだ。
しかも、現在の自分の消費動向をチェックすれば、将来どのタイプの呆けになるかまでわかるという優れモノである。兵庫県の東播磨ブロックの老人施設でつくる協議会に呼んでいただいて連続の勉強会をやったその親睦会でのことだ。
現在は特養ホーム「伽の里」のアドバイザーをしている原田正晴さんが、私に近寄ってきてこう言うのだ。「三好さんの主張する痴呆が老いた自分を受け入れられない関係障害だという説は正しいと思いますよ」と。その根拠というのがおもしろい。デイサービスに通ってくる男性の老人を見ていて、ある日原田さんは気がついた。呆けている老人にぱシルバーグレイ”と言えるような髪の毛の豊かな人が多い、というのだ。
そこでさらに注意して観察してみると、逆に頭髪の乏しい人、つまり禿げた人には呆けは少ないように思う、と言うのである。禿げとそうでないことが、なぜ呆ける、呆けないに関係するのかと不審に思う人もいるだろう。しかし私にはすぐにその理由がわかった。
「そうか、禿げは若い頃から少しずつ自分の老いを受け入れて生きてくるよりほかなかったんだ」「そうなんですよ」と原田氏。読者にお願いがある。入所者、通所者のうちの痴呆の男性についてのフィールドワーク(現場調査)をお願いしたい。髪の豊かな大と禿げた人の割合を比べてみるのだ。痴呆でない人も含めた同年代の人のそれぞれの割合がどれくらいかも調べておかねばならない。
果たして、この調査に有意差は出るだろうか。データでどう出るかは別にして、回りの人に聞いてみると「そういえばそうですねえ」なんていう人が多いのだ。私も何人かの痴呆の男性を思い浮かべてみると、髪はもちろん背格好もスマートで若々しい人が多いような気がする。
彼らは老化を実感させられることなく人生を過してきて、ある日突然、老いに直面して対応する術をもっていなかったのだろうか。私の共感を得て原田さんはうれしそうだった。というのも、彼はまだ若いというのに頭髪が前線を離脱しかけているのだった。いわばこの説は彼の我田引水的仮説なのであった。- 2003年11月 介護の専門性とはなにか
 「カ愛不二」とは「愛を持ったカこそ真の強さである」の意で、著者がかって習っていた少林寺拳法で覚えさせられた言葉だという。当時の彼は、将来、老人介護の世界でその言葉を唱えるようになるとは思いもしなかったと言う。
「カ愛不二」とは「愛を持ったカこそ真の強さである」の意で、著者がかって習っていた少林寺拳法で覚えさせられた言葉だという。当時の彼は、将来、老人介護の世界でその言葉を唱えるようになるとは思いもしなかったと言う。
著者、青山幸広はフリーの介護アドバイザーである。老人施設を定期的に訪問して泊まり込み、スタッフに介護を直接指導する仕事だ。介護は誰にでもできるものだと思われてきた。現在でも「介護福祉士」や「2級ヘルパー」といった資格さえ持っていればいいと考えられている。しかし、在宅にも老人施設にも「介護」があるとは言い難い。
特に医療の世界の人たちが介護のことを何にも知ろうとしないでつくった「老人保健施設」がひどい。彼はそんな「老健」に介護長として就職し、医者と看護師との闘いの日々が始まるのだ。
なにしろ彼らはトイレヘ行けない老人にオムツは当り前だと思っている。自立行為が「危険行為」と映るのだ。車いす老人なら機械浴が当然と思い込んでいるし、食欲がなくなれば点滴するのは無条件によいことで、それを外す老人を抑制することに疑いすらもっていない。
医療や看護の専門性が、病気という緊急時にシロウトにはできないことをするものであるのに対して、介護の専門性とは、誰でもできることをちゃんとやる、ということだ。なぜなら介護とは生活の専門家だからだ。
だから青山幸広は、何年もオムツをさせられてきた老人を説得してトイレへ連れていく。立てない人でも、“天ぷら揚げ機”のような機械ではなくて、家庭と同じ個人浴槽で入浴してみせる。食欲がなければ、点滴して手を縛るより、好きなものの出前を取り、外食に出かける。抵抗を受けながらの、そのしつこさには感心させられる。そこまでやる確信はどこにあるのか。
それは保育士と特養スタッフとしての挫折体験、偶然知った「生活リハビリクラブ」でボランティアをするため、津軽を離れて川崎市でのタクシー運転 手、といった人生経験こそが生み出したのだろう。そんな回り道人生を語る文章は軽快でユーモアたっぷり。涙も出そうだ。介護とは何か、ということだけでなく介護が単なる仕事ではなくて人生にまでなっていくことを教えてくれる感激本である。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2003・11 「Bookshelf」 より
●『カ愛不二』
著者: 青山幸広
発行: 雲母書房
定価: 本体1800円+税- 2003年11月 介護夜汰話 介護拒否とはなにか
■熱心な介護者ほど問題行動に
介護拒否は、介護する側にとってはやっかいなものである。客観的に見れば介護の必要な人のケアをやってあげようとしているのに、それを拒否されるのだ。まず、仕事にならない。それだけではなくて、介護者としての自分を否定されているような気になるからだ。
帰宅願望もそうである。客観的には施設にいるより他なかったり、デイサービスにいなければならないのに「家に帰る」と言い張られると、介護職にとっては職場であるこの場を否定されている気がしてしまう。
だから、“精一杯いいケアをしている”と思っている介護者ほど、「介護拒否」と「帰宅願望」は「問題行動」と感じられるはずである。「せっかく頑張ってケアしているのに拒否するなんて…」という感情が働くのだろう。介護家族が痴呆の老人に暴力を加えたり、あるいは老人を制止しようとして結果的に暴力になってしまったヶ-スを調べてみると、この「介護拒否」がきっかけになっていることが多いのもそのことの表れだろう。
■痴呆の本質の表れ
だが、この「介護拒否」と「帰宅願望」は痴呆にとっては本質的な問題の表れなのだ。従ってこの2つにどう対応するのか、は、痴呆老人のケアの本質が問われると言っていい。なぜなら「介護拒否」は、単に入浴とか排泄といった目の前の介助を拒否しているだけではなくて、「介護される自分」の拒否だからだ。
老いた自分自身との関係障害として痴呆が表われていることを知れば、当然のこととして理解できるだろう。従ってそれは、介護関係のなかにいる自分を拒否し、介護関係そのものを拒否することになる。当然我々は、介護者であることそのものを拒否されているのだ。
■「介護される自分」の拒否
帰宅願望もまた、「この場所で介護を受けている自分」や「ここで何もしないでいる自分」の拒否である。もちろん回帰型による見当識の過去へのシフトやアルッハイマー病の見当識の混乱が帰宅願望をもたらしている場合も多いが、私にはむしろ逆に、介護される自分の拒否が、ここにいる訳にはいかないという切迫感になり、その理由として過去の自分の役割を持ち出しているかのように見えてくる。
「乳をやりにいかにゃいかん」「子どもにご飯を用意しておかなきや」と。帰宅願望は、介護関係の場から逃れたがっていることの表現である。だから帰らねばならない「家」は必ずしも現実の家という訳ではない。施設関係者は、老人が「家に帰りたい」と言えば入所前に住んでいた家だと考えがちだが、じつは在宅の老人もまた「家に帰らなきや」といって出ていこうとする。
女性の場合には結婚する前に住んでいた「実家のことだろう」と言う人もいるがそういう訳でもない。養子をもらってずっと実家に住んでいた人でもやはり「家に帰る」と言い張るのだから。どうやら「家」とは、「本来自分のいるべき場」の意味らしい。どこであれ、今のこの場所が自分がいるべき場所だとは感じられない、という訴えなのだ。
■無意識が安らげる条件づくり
それなら私たちは救われる。施設であれ、デイサービス、ショートステイであれ、老人が「ここにいていいんだ」と無意識が安らげる条件をつくればいいのだから。それには、痴呆ケアの7原則のうちの最後の3つを大切にしてほしい。
すなわち、
⑤個性的空間づくり
⑥一人ひとりの役割づくり
⑦一人ひとりの関係づくり
である。
施設のベッド回りやデイサービスのコーナーをその人のために個別化するのだ。さらに「3つの条件」(※)に見合った役割をつくってほしい。もっとも「帰りたい」と言い張っている最中に「役割」をもっていっても、押しつけとしか受け取られないだろう。
※役割の3つの条件
①昔やったことかそれに近いこと
②今の能力でできること
③それを回りから認められること
■介護者として説得するのは逆効果
最後の一人ひとりの関係づくりのポイントは、彼らが介護関係から逃れたがっている、という点である。このことの洞察がないままだと、むしろ私たちは介護者として介護を受け入れるよう、ここに留まるよう説得してしまうことになる。
それは自分の介護者としての立場をますます強調してしまうことになるのだ。じつはそれこそが老人が拒否してしまうものなのに。そこを見事に洞察してみせたのが、竹本匡吾である。
-----------------------------------------------------------------
そのうち井原さんは、夕方になると息子が迎えにくるというのをおぼえていられるようになり、毎日昼ごろからデイの玄関で待つようになった。目を離すと、歩いてどこかに行ってしまいそうで、職員は時折言葉かけをするのだが、なかなかうまくいかない。
「7時ごろに息子さんが迎えに来るから」などとうかつに話すと、「なぜあなたはそれを知っているんですか」と逆に突っ込まれそうな上に、「まだ来られないから中で待ちましょう」などと言っても、「結構です、ほっといてください」と言われるのがオチだった。
井原さんにとっては、我々職員が引き止めるから帰れないのだと思っているフシがあって、帰れないことを職員のせいにして、待っていることの辛さを都合よく他人に転嫁しているところもあった。その日も少しいらいらしながら待っていた井原さんは、そばに寄ってきた私がまたおかしな言葉かけをするかと思ったようなので、私はあえて「日が長くなりましたねー」とまったく無関係な声かけをして遠くを見た。
すると少し驚いたのか戸惑ったように「そうね、ずっと待ってるんだけど(息子が)来ないんよ」と言い、寂しげに笑ったのだった。つまり「息子を待っている」のは井原さん個人であり、私ではないし、ましてや私のせいで待たされているのでもない、という関係がその瞬間二人の間にバチッと確立したのである。
そんなことがあった以後、待つのに飽きると建物に入り、皿拭きを手伝ってくれることもあるようになった。デイに限らず施設の職員は、お年寄りをなんとか説得してそこに適応させようとし、それが上手なことを自慢に思ったりもしている。そこには、「自分は施設の職員で、このお年寄りは利用者だ」という一方的な分断線があるのである。
「家に帰らせて」とせがむお年寄りに、職員という立場から説得という手段で相手をすることは、かえって問題に正面から向き合わず、逃げているだけのように私には思える。その瞬間、介護職であることを忘れてただの一個人、一私人として相手をしないことはむしろ卑怯なことではないだろうか。
職員という立場ではなく、ただの一個人に立場をずらされてしまうと、お年寄りは誰のせいにもできないために「帰れない」という事実をかえって自分の問題として捉え、「本当に帰れないのだ」という現実を、説得されるよりもむしろ短時間で受け入れるのではないかと私は思うのである。
人は自分で結果を悟らないと納得しないものである。(ブリコラージュ9月号「砂丘の憂僻」より)
-----------------------------------------------------------------
■介護関係から逃れろ
そうなのだ。私たち介護者もまた介護関係から逃れなくてはならないのだ。もちろん逃げてばかりいる訳にはいかないから、介護者でありながらそれを超えた自分をもっているということだ。超え方には2通りあると思う。
1つは、より専門性を高めていって超えていくという方法で、「受容の原則」を始めとした、バイスティックの原則が身体に沁みついているような人だ。ソーシャルワーカーや経験豊かな看護師、特に精神科で仕事をしてきた看護師でそうした人がいる。意識的に仕事としてやっているのだけれど、わざとらしさをちっとも感じさせないというタイプである。「困ったときにはあの人がいるから安心」とスタッフからも老人からも思われている人である。
もう1つの超え方がある。それはこの竹本氏のように、ただの“お兄ちゃん”になってしまうやり方である。介護者の立場を降りで通りすがりの人”になるのだ。介護者を降りで人間同士”になってしまう人もいる。たとえば、「宅老所よりあい」の下村恵美子は、利用している老人と、本気にけんかをし、ときにはつかみ合いまでする(『九八歳の妊娠』)。
これも介護関係からの降り方の1つだ。これは専門性を高めていって超えていくのが、上に超えていくのに対して、横超(おうちょう)、つまり、横に超えていく方法だと言えよう。しかし、私のような凡人にはどちらも難しそうである。しかし残念に思わなくてもいい。介護関係を超えた関係は、介護職ではない人たちによってこそつくられるからだ。
■年配ボランティアの役割
デイサービスにボランティアで来てくれているTさんは70歳の男性。定年退職後、44年間勣めた企業とはまったく違う世界である介護の世界に興味をもち。デイサービスにほば毎日通っている。エプロンをつけて食事介助もするし、通院介助で運転手もするが、彼の役割は、介護スタッフとはちょっと違った立場から老人に関われることだ。
老人の言うデイサービスの悪口やスタッフの陰口にときには共感しつつ話をしている。スタッフではない人が混じっていることで、老人たちは介護関係とは違った関係に入り込めるようで、Tさんは貴重な存在である。
■制服も白衣もなくなった
老人同士の関係も、介護関係から逃れられる関係である。このデイサービスには「帰りたいクラブ」と呼ばれる3~4人のグループがある。帰宅願望の強い女性が玄関の長イスに座って互いに「帰らなきゃならんのに」「私もだよ」と言い合っている。だが玄関だから人の出入りが多く、誰かが通る度に「あれは誰か」と話題が変わり、なんとか半日くらいはもつのだ。
スタッフが用があって車で出かけるときには声をかけ、何人かを乗せてドライブに出かける。手が空けば散歩に誘う。こうして夕方まで持ちこたえている。経験を通して介護関係から“降りる”ことで、介護拒否や帰宅願望が少なくなることがわかってくるにつれ、まず若い男のスタッフが白っぽい制服をやめて私服で仕事をするようになり、やがてその“効果”が誰の目にむあきらかになるにつれ、1人、また1人と私服が増えた。
ついには看護職も白衣を着なくなった。白衣では介護関係からは降りにくい。そして、いつの間にか「帰りたいクラブ」も自然消滅したのだった。- 2003年10月 介護夜汰話 老人介護の現在
⑨ ユニットケアの退廃 その3 ~対象者の選別~ 【ユニットケアの退廃 その①】
ケアの中身が問われているのをかたちで乗り切ろうとしていること〈前々号〉。
【ユニットケアの退廃 その②】
ユニットケアと称した、施設内アパルトヘイトが始まっていること。〈前号〉
【ユニットケアの退廃 その③】
ユニットケアに合う老人を探すという対象者選別が始まっていること。〈今号〉
私は医療批判の急先鋒のように思われているけれど、福祉なんかよりははるかに医療のほうを信用している。何より医療は具体的方法論をもっている。人間を個体としか見ないという限界はあるけれど。それに、どんなに重症の人にも逃げないで関わる。
救急車でたらい回しにされたなんて話もあるが、目の前に困っている人がいればとりあえず立ち向かうという姿勢を医療はもっているではないか。特養ホームがそれなりに社会から認められ「もっと特養を」なんて市民団体が訴えたりしているのはなぜだろうか。
それは、寝たきりや痴呆で最も困っている人をちゃんと引き受けてきたからである。そして、どんなに呆けてもケアを継続し、さらに地方の特養を中心にしてターミナルケアまで実践してきたことによる。ずっと生活させてくれない老人保健施設が社会から支持されることはなかったし、あれほどジャーナリストが絶賛したグループホームも急速に評価を落としている。
なにしろ、「家庭的雰囲気を守れないようになったら出てもらいます」なんて平気で言うし、入所したその日の夜に寝なかった、というので退所させられたなんて話が続出している。痴呆老人が環境が変わった日の夜に熟睡するかね。それに家庭的雰囲気を守れる人なら、デイとショートステイを使って在宅でケアできるじゃないか。
グループホームは重い痴呆は入所させないどころか、軽い痴呆さえ入所させてくれないし、老人保健施設も、重い寝たきりや呆けは入所させてくれないところが多かった。「うちはリハビリの可能性のある人しか対象にしませんから」なんて理由でだ。
“リハビリ”は困難なケースから逃れるための言い訳なのか。特養に比べれば、老人保健施設は医師、看護婦、PTやOTが揃っているくせに、深刻なニーズに応えないのだ。入所者を選別するということは、入所している人に変化が出たら追い出すということだ。それが「環境を変えるな」「人間関係を変えるな」という痴呆ケアの原則に反することは言うまでもない。
にもかかわらず、特養ホームが「ユニットケア」を理由にして入所者を選別しようとする動きが出てきた。「ユニットケアにはどんな老人が適応するのか」を研究するのだという。おいおい、そりゃ話が逆だろう。果たして「ユニットケア」が重い障害老人や痴呆老人に適応しているのかどうかをチェックするというのがほんとうではないか。
ユニットケアのメリットは「家庭的雰囲気」だそうだから、グループホームと同じように家庭的雰囲気を乱す人は「適応外」ということになるのがオチだろう。こうやって、一番困っている人のニーズに応えてきたがゆえに認知されてきた特養もまた、入所者を選別し、途中で追い出す施設になっていくのだろうか。そうならないことを願うばかりだ。
ブームだからとか、それでないと認可しないと言われて「ユニット」に走る人たちに問いたい。職場に無用の混乱をもち込んでまで行うユニットによってどんなケアがしたいのか、と。
ユニットによって、機械に頼らない生活的な入浴ケアができるのか、工場の作業のような分業による入浴介助をやめて、相性の合う人とのマンツーマンのケアができるのか、と。
ユニットによって、トイレに通うという当たり前の排泄ケアができるようになるのか、吸収力があるからといって1日4回しかオムツ交換しませんなんていう“後始末”をしてたんじゃしょうがないじゃないか、と。
ユニットによって、食欲がないとすぐにチューブや胃ろうにしてしまって抑制するなんてことがなくなるのか、と。
好きなものを出前したり、そば屋に外食してみたりといったケアが可能になるのか、と。そして、それらは、ユニットにしなけりゃできないのか、と。介護の中身が問われているというのに、ユニットというかたちに逃げてはいないのか、と。- 2003年10月 「一緒に共有する」ツールとしての遊び
 老人介護現場で行われているレクリエーションやゲームを見て、「幼稚だ」とか「子どもだまし」と言う人たちがいる。私は「現場を知らない人だな」と思う。少なくとも、深い痴呆(私は“重い"と言わずに“深い”と表現している)の人にかかわったことがないか、ひょっとするとそうした人は「人間」だと思っていないのかもしれない。
老人介護現場で行われているレクリエーションやゲームを見て、「幼稚だ」とか「子どもだまし」と言う人たちがいる。私は「現場を知らない人だな」と思う。少なくとも、深い痴呆(私は“重い"と言わずに“深い”と表現している)の人にかかわったことがないか、ひょっとするとそうした人は「人間」だと思っていないのかもしれない。
特養の全室個室化を主張する人たちが、プライバシーを求めるような近代的自我を持った者だけが「人間」だと考えていて、毎夜のように体をくっつけてやっと落ち着く痴呆老人がいることなど考えもしないように、私たちが「遊びリテーション」と呼んでいるアプローチで生き返った老人がいることを知らないのだろう。
今田トクさん(91歳)は、誰が声をかけても反応せず、独り言を繰り返す、竹内孝仁氏による痴呆3分類の「遊離型」の典型といっていい老人だった。自分で自分の名を呼んで自分で返事をし、一人で笑っているという人だ。
この人を私が担当していた「遊びリテーション」の「風船バレー」に連れてきた。すると、目の前を赤い風船が動くと、視線が動き、手が出るではないか。風船を打てば周りが喜ぶのがわかると、約45分間、風船を追い続けたのだ。
その夜、変化が生まれた。独語が消えたのではなくて、その内容が変わったのだ。一晩中「あの風船叩きは面白い」と繰り返したのだ。翌日、私が「今日も風船叩き行きませんか?」と声をかけると「おお、行こう」とトクさん。現実的な会話の世界への復帰だった。
同じ痴呆でも「葛藤型」には「風船バレー」は逆効果だろう。「俺を馬鹿にしているのか」と言われるに違いない。しかしトクさんのような「遊離型」や、子どもの時代に戻っている「回帰型」には、どんな“療養”なんかよりはるかに効果的である。
『遊びリテーション大事典』は、すでに『極楽遊びリテーション』(雲母書房)を世に出し、老人レク界の第一人者である坂本宗久氏の実践の集大成ともいうべき本だ。彼はほぼ同時に『介護職人スーパーテキスト』(オフィスエム)も主著者として出版するという精力的な活動ぶりだ。
老人ケアの武器を手に入れたい人、現場感覚に触れたい人のための一冊。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2003・10 「Bookshelf」 より
●『遊びリテーション大事典』
著者: 坂本宗久
発行: 関西看護出版
定価: 本体2,310円+税- 2003年10月 ブリコラージュインタビュ『あなたに逢いたかった』
今回の三好春樹の対談相手は大田仁史先生です
~終末期リハビリテーションを担う中心は介護です~
リハビリテーションとはなにか
――リハビリテーションというと機能回復訓練と思ってしまいますが、先生がおっしゃっているリハビリテーションは違うように思われます。
リハビリテーションの“ハビリス”が重要な意味をもっていると思いますね。ハビリスは、「適している」という意味の形容詞ですが、「何に適しているの?」ということになります。 主体的に生きていることに適しているという考え方なのか。
これまでのリハビリテーションの流れのなかで重視されてきた意識性、すなわち「自分で自分の存在をきちんと認識できて、自分の意思を表示できる意識レベル」に適しているのがリハビリテーションだとしたら、痴呆の人はどうなるのか、植物人間になってしまった人たちをどうするのかということになってしまうんです。
だから、僕はもっともっと幅を広げていって、そういう人たちも「人間の姿としてふさわしい状態」にすることをリハビリテーションといっていいと思うんです。治りえない重度の障害をもつ子どもたちも含めて。僕はそれを「終末期リハビリテーション」と言っているのです。
――終末期といっても、いわゆるガンの末期などに使われるターミナルとは違うのですね。
確かに「終末期」ということばは子どもには向かないとは思っています。ここで終末期というのは生きている人間の人間らしい姿形のことです。
自分を認識するという意識性はなくなっても「身体としての人間らしさ」というのがあるでしょう。そう考えればご遺体が人間らしいかどうかまできちゃいますからね、最後は。だから勝負はご遺体。評価はご遺体がすればいいんです。
床ずれがいっぱいできているようなご遺体は、エンドオブライフのケアが悪かったということになるし、骨が曲がっていて棺に入らないから折るみたいなことは、やはりプロセスが悪いんだということになって、明快じゃありませんか。
終末期リハビリテーションと介護
――そうすると、リハビリテーションは介護と深く関わっているというように思いますが。
介護の世界が中心なんですよ。終末期リハビリテーションではPTやOTがやるよりも介護の世界のほうがはるかに比重が大きくかかってくる。
そこに、身体として非人間的な状態をつくらないという思想があれば、介護の技術がもう少しリハビリテーション的になるんじゃないかと思う。それが予防的介護。 介護を受ける人がもっと安楽になるような介護です。
もうちょっと前の段階が生活リハビリですよ。生活をしていると思えない人がいっぱいいるじゃないですか、たとえば植物状態の人。その人たちはどうするのかということです。
――そのためには、介護の世界がリハビリテーションの考え方やその手法をもっと取り入れるべきだということでしょうか。
リハビリテーションには手法があります。リハビリテーションの歴史のなかで十分にでき上がった手法があるから、リハビリテーションの側はそれを介護の世界に移入すべきだ。介護の世界はそれをとるべきだ。で、どこまでオーバーラップするのかを明確にしたほうがいいんじゃないかということを提言しているのです。
そのためには「終末期リハビリテーション」という言葉をつくっておいたほうが、リハビリの連中を引きづり込んでいくためにはいいんじゃないか。地域リハビリ、生活リハビリと同じ手法です。現場で働く介護職の人たちも、そういうことをやることが大事なんだ。それがリハビリテーションなんだって考えてほしい。
――リハビリテーションと介護との協働とすみわけ。それはどういうかたちになるのでしょうか。
リハビリテーションの側に言っていることのひとつは「きちんと技術を開発しなさい」。もうひとつは「リハビリテーションの技術を移入するために、介護に対してこれはリハビリテーションの手法を使えば完全にできるということを明確にしなさい」。それから「一般の人が賢くなるように教育しなさい」と。
介護という領域があるんだから、そこでお年寄りがレ・ミゼラブルな姿形にならないために、安楽に介護ができるような技術を導入しなさいということです。オムツをするのにも、普段から股関節を柔らかくしておけば、一人で短い時間にできるじゃないですか。
それが「予防的な介護」で、時間を節約し、労力を節約し、本人が安楽になるような、そういう介護手法を確立しなさいということです。そのために既存のPT・OTたちのもっている技術のなかで、どこを導入すればいいかということをきちんと勉強しなさいと言っているんです。
医療の光と陰、陰の部分をどうするか
――「終末期リハビリテーション」というご本をお書きになりました。それは、やはり、そのことを今、訴えなければならないという強い思いがあったということだと思います。
僕が勤務する茨城県立医療大学付属病院には子どものベッドもあります。医療が進歩して、今は300gくらいの赤ん坊でも助かるのです。
医療の光の部分と陰の部分だから仕方がないけれど、そうして助かった命の4分の1の子は障害をもっています。そういう障害のある子を、光が当たってすくすく育った子たちは背負っていくべきだというのが、僕の主張なんですよ。お互いに一生懸命やっていかなければならないと思うんですが、やってないです。救命救急ばっかり進んでる。
――医療の光と陰の部分。その陰の部分は陰のままという、そういう現状に対する危機感なのでしょうか。
在宅での生活をどう組み立てるのか。そのために病院で何をやらなければいけないのかというのが、僕の基本的なスタンスなんです。
医療というのは病気が発生して、それを治して帰すという上からの流れとしてありますね。急性期があって慢性期があって、リハビリで言えば維持期というのだけれど、介護はその最後にあるわけでしょう。その介護側からみて医療は役立っているのか? そういう視点です。
急性期医療は命を助けなければいけません。それですら、助けた命がどうあるべきかということに関心をもってほしいということを問いかけている。それは子どもたちを見ているとわかります。助けていただいた命は大変ありがたいけれども、その命がどうなっていくのかということにも、助けた人は関心をもってほしい。手を出さなくてもいいから…そういう思いが僕にはあります。
――いわば川下にある介護、それはエンドオブライフと関わる部分と言っていいと思いますが、そこが手薄になっているということですね。その部分に医療が十分に関わっていない?
病院でやるのと違う、在宅だとか素人の立場でできる、そういう立場に立って素人を賢くしなければいけないし、役に立たなくちゃならない。それは川下から川上に向って求められていることでしょう。でも、医療は川下をちゃんとしていないから、川下は洪水です。
リハビリテーションだって、急性期、回復期、ときて、川上のほうの流れはよくなりました。でも維持期に入ると在宅だったらPT・OTが行く頻度だけを見てもすとんと落ちています。病院からソフトランディングなんて冗談じゃない、蹴飛ばして突き落とすみたいな、ハードランディングもいいところ。
訓練してADLが少しよくなって家に帰っても、からだソコソコ心ウツウツといっているわけでしょ。気持ちの問題だとか、うつ傾向、そんなのは全然よくなっていない。だから閉じこもり傾向は進む。
オムツは「高齢者の尊厳」そのもの
――ところで、厚生労働省の高齢者介護研究会から「2015年の高齢者介護」という報告書が出たようですが、その大目標が「高齢者の尊厳を支えるケアの確立」です。高齢者の尊厳とはなんでしょうか。
そんな難しいこと言わないで、もうちょっと具体的なことを言ってくださいと言いたいですね。高齢者の一番の尊厳はオムツですよ。オムツを当てるくらい尊厳を傷つけることはありません。
「高齢者の尊厳を支えるケアの確立」ではなくて「高齢者にオムツを当てないケアの確立」と具体的に言えばいいと思うんですけどね。 僕の母親は95歳になるんですが、絶対にオムツはいやだって、夜中でも家族がトイレに連れて行っているわけ。
あるとき、トイレに行けないと言うから、姉がオムツを当てたの。そしたらおしっこが出ないと言う。僕が「どんな具合?」って姉に聞いたら「少しは出てるようよ」って言うのです。
「何時間出ないんだ?」って聞いたら、朝の6時から夕方の6時まで。「それは出てるんではなくて、おしっこが漏れてるんだよ。看護師さんに連絡して導尿してもらわないとパンクしちゃうよ」。
で、「おかあさん、今から看護婦さんにきてもらって管を入れるからね」って言ったら、母親はびっくりして管はいやだ、どうしてもトイレに行くって2人がかりでトイレに連れて行ったら、すごい勢いで出て、それからすぐ普通の生活に戻りました。オムツぐらい人の尊厳を傷つけるものはないと思うね。
自立できなくてもいい
――この報告書にも多々出てきますし、われわれも高齢者の自立、自立した生活など、自立という言葉をよく使いますが、リハビリテーションはそれを目指すものではないのでしょうか。
それを否定はしないんだけれど、僕は、自立をあんまり強調してくれるなと言っている。自立を強調すると、自立しえない人を切り捨てることになる。これは非常に危険だと思っているんですよ。自立しえなくてもいいんだということを認めるような社会をつくらなければいけない。
南雲直二っていう心理学者が「2つの苦しみ」ということを言っています。1つの苦しみは、障害があったり、身体が不自由だったりして「自らが自分を苦しめる苦しみ」。
だけど、ハンセン病などで見るように「社会が苦しめる苦しみ」もあるわけです。いくら努力したってしょうがないことはあります。でも、本人にばっかり努力を強いている。
障害の受容なんてそうですね。本人が受容するよう努力しなければいけない。それは大事だけれど、余計なお節介。心の問題だからね。
――問題は、そういう人々を社会が受け止めているかどうかということですね。
自立は大事だけれど、できない人にどうするかが問われているのです。僕は「総支えの思想」をもつべきだと思うんです。子どもの教育だってそうだ。子どもが社会のなかに入っていけるようなところまで、体勢を整えてきちんとやるということ。それは社会も変えなさいということです。そこまで行かないといけないと思うんですね。
お年寄りの場合は、もう先がないんだから、死ぬまできちんと総支えですよ。どんな姿形になっても。介護が支える部分がある。家族が支える部分がある。そういう人たちがきちんとできなくちゃいけない。
国民皆3級ヘルパーを提案したい
――国民全員がヘルパー3級をとろうとおっしゃっていますが、それも「総支え」というお考えからのことですか。
ヘルパーが足りない、介護福祉士も足りない。日本が急激に高齢化を迎えたということが、事実として現れている。でも守りきらなければならない。問題だ、問題だと言ってても解決にはならない。それで国民全員がヘルパー3級をとろうじゃないかと提案しているのです。
介護を学んでいると介護されるほうもされやすい。そういう介護を勉強することで「介護予防」を学んでもらう。それは大事なことですよね。そういう状態にならないようにね。もしそういう状態になっても介護ができるし、介護が受けやすくなる、そういう状態をつくる。第一、人のことをお世話すると、人が優しくなるって僕は言っているんです。
『新しい介護』出版の意味
――このたび、三好春樹さんと『新しい介護』をお書きになりました。
『新しい介護』は、実はあれが進んでいくと「終末期」になる。介護というのはどちらかというとそちらに近いから。急性期、回復期、維持期ときたら、終末期。あれ自体、全体がそうだ。
お年寄りに限定して言えば、人生の最後を迎えつつある人に対するリハビリテーションを介護という切り口でいけばああなりますよ。終末期のことを少し書いておきましたが、足りないのは意識のない人をどうするかという部分でしょうか。いわゆる植物人間のような人の介護を完璧にするにはどうすればいいのかというようなね。
ああいう本がこれまでなかったというのが不思議だね。大手の出版社(講談社)が目をつけるということは、ますます介護が必要になってくるということですね。
「寝たきりになら連」
――さて、大田先生は、失語症をもつ人の海外旅行への同行、徳島の阿波踊り、松山の野球拳踊り、青森ねぶた祭りなどの「寝たきりになら連」はじめ、当事者を直接支援する活動を長くされておられますが、それには、どんな思いが込められているのでしょうか。
海外旅行は、STの遠藤尚志君が主催する失語症の人たちのもので、医者がいないからっていうので僕は付いて行っただけ。そこから学んだことはいっぱいあるけどね。
阿波踊りに「ねたきりになら連」が参加するようになったきっかけは、三好君と一緒に徳島に行ったとき、阿南市の石川富士郎さんというお医者さんに、「徳島に阿波踊りがあるのに、年寄りが出られんというのはおかしいんじゃないか。そういうのをつくってあげたら」と言ったら、石川先生が計画してくれて、始まったのです。
もう11年になります。 松山野球拳踊りはその翌年から。それが青森のねぶたにも繋がって、ほかにも尾道とかいろんなところに広がっていきました。
先ほども「2つの苦しみ」の話をしましたが、その「社会が苦しめる苦しみ」は社会が変わらなければ取り除けません。その社会が変わっていくプロセスが社会や地域のリハビリテーションということになるのです。僕は地域リハビリテーションと言っていますが、「寝たきりになら連」もそうなのです。
――毎回、たくさんのボランティアの方が参加されていますね。その方たちにとって、ここに参加することとはどういうことなんでしょうか。
何か学ぶべきことがないとね。単にお手伝いするとか、お祭りだから行って楽しめばいいとかいうレベルでは、みんなお金出してくるのがいやになってしまう。何かを得ているはずなんだけれど、それを認識できているのかどうか心配ですね。
イベントというのはわかりやすいんですよ。お年寄りや自分一人では何もできない人がいて、その方たちのお世話をさせてもらって、感動したり興奮したりする。それが、お年寄りの存在をどう考えるかということなんです。
車いすを押していると、車いすに乗っている人のことを考えるんです、そのときは不思議に。ふだん、自分のことしか考えていない人でも純粋に他人のことを考えられるというのがあるということを発見してほしいですね。
――いわばイベントいう非日常のなかで得たものを、介護現場でのお年寄りとの日常的な関わりのなかに生かしていくということにもなりますね。
自分一人では何もできない人、いろんな人がいて、死んでも悲しんでくれる人がいないような人もいっぱいいるわけでしょう。それに関わる人が、関わり方のなかで状況や関係性をつくり上げる。そのなかで自分が心を動かせるのかどうか。そういうことをつくれるのかどうかということが、日常に引き寄せたときのプロの感性でしょうね。
だって、毎日毎日の仕事が楽しいわけはないでしょう。そんななかで、ときどきでいいから自分の心が動くようなことを体験してほしいんです。99回いやなことがあったって1回いいことがあったら困難なことにならない。そういうことを学んでほしい。
――介護職の人たちにアドバイス、あるいはエールをお願いします。
感性のみにとらわれてはいけません。感性のみだったら、それをもたない人は介護ができないことになります。天性のものをもっている人もいますが、そんな人はそれほど多くはない。技術は環境と学習で習得できるものです。人に対する技術だって同じです。勉強しましょう。
介護は発展途上。医療、リハビリその他からいろいろなものを取り入れて完成させていくことが必要。そのためには「介護とは何か」という議論をもっとしていくべきです。
介護職は誇りをもてと言いたい。終末期を中心的に担うのは介護なのですから。- 2003年09月 介護夜汰話 老人介護の現在
⑧ ユニットケアの退廃 その2 ~施設内アパルトヘイト~ 私は『完全図解新しい介護』(講談社)のなかで、「痴呆のケア7原則」を提案している(第5部15章)。
その①が「環境を変えない」
②は「生活習慣を変えない」
③が「人間関係を変えない」
である。引っ越しをして子どもの家に引き取られた老人に痴呆の発生率が高いことはよく知られている。これは、環境と生活習慣と人間関係が一挙に変化してしまったことによる。
もし痴呆が脳の病気だというのなら、引っ越しした人にだけ住みつくウィルスでもいるのだろうか、と竹内孝仁先生はその著書のなかで皮肉っている。老いていく自分になんとか適応しつつ生きているのが老人である。
老いていく自分に適応できなくて混乱しているのが痴呆の症状であり、そんな危機に直面したときに人がとりうる3つの態度が、①葛藤、②回帰、③遊離という竹内の痴呆3分類に対応している。となると、老人はもちろんだが、特に呆け始めたときや呆けが進んだときにこそ、環境や生活習慣、人間関係を変えてはいけないことになる。
なぜなら、老人たちは、自分の老いだけでなく、新しい環境、新しい生活習慣、新しい人間関係にまで自分を適応させていかねばならなくなるからだ。それは老人を呆けに追いやるに等しいと言っていいだろう。ところがそれを「ユニットケア」の名のもとに行おうというのだから驚いてしまうではないか。
ある特別養護老人ホームは60人の定員を4つのユニットに分けることにした。最初は、なんとか家庭に近い生活的雰囲気にしたい、という思いだったのだが、一年もするうちにとんでもない方に向かっていってしまう。
4つのユニットを老人の機能によって分類したのである。曰く、①最重度痴呆ユニット、②軽度痴呆ユニット、③重度障害ユニット、④軽度障害ユニットの4つにである。そのほうがより専門的なケアができて効率的だから、というのである。
しかし、これはもう「ユニットケア」と言うべきではない。「ケアなきユニット」である。さらに私はこれを「施設内アパルトヘイト」と呼びたい。アパルトヘイト、つまり人種隔離政策である。かつての南アフリカ政府は、有色人種を一定の地区に囲いこんでここから出ることを禁じていた。
その特養ホームでは重度痴呆性老人は1つのユニットに押し込められ、他のユニットに行くことを禁じられている。障害ユニットとの間は鍵つきの扉で完全に仕切られていて往き来できないし、軽度痴呆ユニットとの問には鍵はないものの、入り込むと「あなたのいるところは向こうだから」と追い返されるという。
障害はあるが痴呆のない老人たちの間では「あそこに行ったらおしまいだ」と言われているという。「あそこ」とはもちろん痴呆ユニットのことである。しかしその「おしまい」の恐怖が現実のものなのだ。なにしろ呆けてくるとそこに入れられるのだから。実際に何人かの老人が、呆け症状が出たからと痴呆ユニットに移されているし、痴呆が進んだからと軽度痴呆ユニットから重度痴呆ユニットに移動させられている。これを「ユニットの適正化」というのだそうだ。
しかし私に言わせればこれは「スターリンの民族強制移住」である。かつてのソ連は、政府に従順ではない民族をまるごとシベリアに移住させたりということを平気でやった。ある朝突然兵士に銃をつきつけられて貨車に乗せられたのだ。無茶苦茶である。
だが痴呆性老人にとっての「ユニットの適正化」はそれ以上に無茶苦茶ではないか。ある日突然、環境も人間関係も変わってしまうのだ。呆けが出始めたり、進行したときにやってはいけないことをやるのでは、その呆けをつくり出す機能を果たしているだけではないか。そんなときこそ、生活空間も人間関係も変えてはいけないのに。
しかし、かつての老人保健施設が「4か月で退所してもらう」なんていって追い出すものの、老人は家には帰れず他の施設を転々とさせられて痴呆をつくり出したように、また今でも「市民」が後押しして梅雨のカビのように生まれてくるグループホームの多くが「呆けたら出ていってもらいます」と平気で言っているように、老人政策こそが痴呆老人をつくり出しているのである。
ユニットを推進する人たちの目標は施設の家庭化であり地域化であるという。しかし「家庭」や「地域」の実態を見てみるがいい。精神障害者や障害児を「専門家の手に委ねる」という美名のもとで「家庭」と「地域」から追い出してきたのではなかったか。
そういう意味では「家庭的雰囲気を守れない人には出てもらいます」というグループホームはまさしく「家庭」に近づいたのだし、「ユニットの適正化」を行う施設は私たちの地域のミニチュア版をつくったのである。推進するのは「ユニット」ではなくて「ケア」のほうである。
めざすのは、どこにもない「家庭」や「地域」という理想のイメージではなくて、現実の閉鎖的な家庭でもアパルトヘイト的地域でもない新しい共同性の創出なのである。私はそれを「新しい介護」のなかの7原則の最後に、「受容より相性」「専門性より母性」「共感できる仲間」という表現でイメージしたつもりである。もちろんそれは各地の介護現場に現実に創り出されているものだ。- 2003年07-08月 介護夜汰話 老人介護の現在
⑦ユニットケアの退廃 その1 ~ケアの中身をかたちで乗り切るな~ 現場の必然性と自発性によってではなく、厚労省の強制とブームに引きずられて行われるユニットケアは、ユニットケアがめざしたものとは別の結果、それも深刻な退廃を、ケアの現場にもたらしつつある。以後、3点について、その退廃を指摘していくことにする。
⟨ユニットケアの退廃その①⟩
ケアの中身が問われているのをかたちで乗りきろうとしている。
⟨ユニットケアの退廃その②⟩
ユニットケアと称した、施設内アパルトヘイトが始まっていること。
⟨ユニットケアの退廃その③⟩
ユニットケアに合う老人を探すという対象者選別が始まっていること。
老人施設を少人数のグループに分けてケアしていこうという発想は、かつて「民間デイサービス」といわれた小さなデイや宅老所の実践に、施設関係者が大きな刺激を受けたことから生まれてきた。「民間デイ」の草分け的存在ともいうべき「生活リハビリクラブ」(神奈川県川崎市)が始めたケアの中身への驚きを、私自身が「民間デイの七不思議」という文章にしている(老人介護問題発言」雲母吉房刊)。
ちなみに七不思議とは、
①いっしょに食事している
②排池ケアがない(かのように見える)
③入浴ケアがない(かのように見える)
④呆け老人がいない(かのように見える)
⑤記録をちゃんととっている
⑥自立している
⑦エロス的な関係がある、
の7つである。
この文章を私は「施設や地域は、その斬新なケアの内容をこそ取り入れていくべきではないかと考えているのです」と締めくくっている。そうだ。民間デイのケアが革命的なのは、いいケアをしたいという思いがあり、その具体的方法論を手に入れていたからなのだ。
ところが厚労省は、小規模で、あることがいいケアの理由だと考え、「ユニット」の強制をやり始めたのである。たしかに、民間デイのケアは、施設に比べれば小規模である。しかし、それは、金も人手もなくて小規模にしか始められなかったからだし、自分たちのやりたいケアを考えると必然的に対象人数を限定するよりなかったのだ。
つまり、ケアというソフトがあって、それが規模というかたちを決定したのである。逆、つまり、規模がケアを決める訳ではないのだ。
にもかかわらず現実には、小規模で、さえあればいいケアになると考えているため、小規模のもたらす弊害を克服する気がないために、前述のように“施設の在宅化"、つまり、老人の閉じ込めと介護者の孤立をもたらしているのである。しかし、もっと深刻なのは、小規模とかユニットというかたちをつくることが目的化され、肝心のケアをよくすることに手をつけていないことである。
“家庭的ケア"と言いながら、老人の生活習慣を断念させるような人体洗浄機や特殊浴槽といった機械浴を使っているのはおかしいじゃないか。施設空間を壁で、仕切って無理にユニットにするよりも、家庭浴槽の設置こそが先ではないか。
夏場、食欲がなくなった老人に、すぐに点滴や胃ろうをつくって、手足を縛ってしまうようなやり方が、果たして“家庭的"だろうか。“家庭的"というなら、まずその老人の好きなものの出前をとるとか、外食に行くとか、好きな人といっしょに宴会してみるべきなのである。それができないような管理的な施設は、ユニットなんかにすべきではないし、小規模のグループホームやデイサービスに手を出して“地域密着"なんかしてもらっては困るのだ。
在宅も同じである。出前も外食もさせていないような在宅ケアなら、在宅にいる意昧はないといっていい。家にいるという、せっかくの利点を活かしきっていないならば、まだ生活的な施設のほうがいいのだから。
小規模で、あることで評価すべきではない。もちろん、ユニットであることで評価すべきでもない。そこでどんなケアがなされているかが問題なのだ。そこでは、安易にチューブにしない食事ケアが行われているだろうか。機械浴にしない入浴ケアが行われているだろうか。オムツにしない排池ケアが行われているだろうか。答えはノーである。ユニットに取り組む施設の多くはその問題意識もないし、方法論も知っていない。
ちゃんとやっている施設は、ユニットでなくても、ユニットにする前でもやっているのだ。たとえば、rf同室・ユニットケア読本実践編」という本がある。全室個室、ユニットで有名な特養ホーム「風の村」の本である。この木によると、排池ケアのウリは「おむつ交換はトイレでなされている」ことなのである。
トイレでオムツ交換するぐらいなら、出る前にトイレに連れていけよ、と言いたくなるではないか。本誌4月号の「あじさい荘」(東京都北区)の実践を読めば特にそう思う。オムツ使用を前提とされては困るのだ。同じ4月号の私の「尿便意のアセスメント」に目を通してほしい。
「風の村」のケアレベルは高いと思う。オムツ使用者の割合も乙の本ではわからないのだが、どうしても気になることがある。「排油介助の労力よりコミュニケーションの時間を優先する」iワーカーが1日おむつ交換で仕事が終わるというのも何か悲しいものを感じる。今しなくてはならないものは入居者とのコミュニケーションではないか」といった文章である。
排油よりもコミュニケーションのほうが大事だというような“市民的"な人間観こそが老人問題をっくり出してきたのである(拙著『関係障害論」(雲母書房刊)のマズロ一心理学批判で詳しく述べたつもりである)。@ケアワーカーは“ウンコ、シッコに関わってナンボ"である。もちろん、オムツ交換という後始末ではなくて、生理学的排油ケアによって関わるのはいうまでもない。- 2003年7月 『死ぬ』と『死ぬる』
~老人介護の完結とは何か~
 現場で身を投げ出すようにして老人を介護している人たちは、文章なんか書かない人が多い。私のように介護の本をたくさん書いている者は、そうした介護職に比べると、老人とちょっと距離を置いた、冷静で客観的に観察している人、ということになる。それは、冷ややかで他人事として見ているということだ。
現場で身を投げ出すようにして老人を介護している人たちは、文章なんか書かない人が多い。私のように介護の本をたくさん書いている者は、そうした介護職に比べると、老人とちょっと距離を置いた、冷静で客観的に観察している人、ということになる。それは、冷ややかで他人事として見ているということだ。
距離なんか置かず、ときには一心同体になり共感的にかかわれる介護職にとっては、目の前の老人の現実こそがすべてで、それを言語で表すことには興味がなさそうである。それは健全なことだ。
著者である中矢暁美さんも、そんな健全な人である。だから彼女の実践がこうして活字になって私たちを唸らせるに至るには、彼女の不思議なパワーに引き込まれて何回も松山まで足を運び、話を聴いて文章化した編集者の存在が必要だった。その編集者が最も大変だったというのが、中矢さんの伊予弁だという。「編集と翻訳を同時にやった」そうだ。
看護職だというのに自らヘルパーをやっていたという彼女が始めた託老所は、築100年の古屋敷である。段差だらけだが彼女は気にしない。「みんなそんな家で生きてきたんやから」と。
託老所の名前の「あんき」は「のんびり」とか「楽に」といった意味の伊予弁。「のんき」とは少しニュアンスが違う。彼女の口ぐせがある。「あんたも死ぬるところを作っとかんと」。この「死ぬる」が編集者には新鮮だったという。彼女と同じ文化圏である広島で育った私には違和感はない。
標準語なら「死ぬ」で「死ぬる」とは言わない。「死ぬ」が「生まれる」に対応しているのに対して「死ぬる」は「生きる」に対応しているコトバである。
「死ぬ」は一瞬だが、「死ぬる」は時間に幅がある。
「死ぬ」は客観的だが「死ぬる」は関係的だ。
「死ぬ」が生物学的なのに対して「死ぬる」には人の意思が感じられる。
おそらく古語が残っていると思われる方言の「死ぬる」に、「死ぬ」にはない豊かさを感じるのは私だけではないようだ。この本の最初から最後まで、標準語と都会が失った、その豊かさが溢れている。
あなたはどう“死ぬる”か。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2003・07 「Bookshelf」 より
●『老いを支える古屋敷』
~託老所 あんき物語~
著者: 中矢暁美
発行: 雲母書房
定価: 本体1,600円+税- 2003年06月 介護夜汰話 老人介護の現在
⑥「現前性」と「先験性」 ~必然性のないケアは堕落する~ 次のような質問が私のところに届いた。以下その内容と私の返事を紹介する。
 三好さんは「富山型」についてどう思っているのですか。
三好さんは「富山型」についてどう思っているのですか。
下村恵美子さんが『九八歳の妊娠』のなかで富山型への批判を書いていて、それに対して、惣万佳代子さん(富山市「このゆびとーまれ」代表)がずいぶん怒っているという話ですが、三好さんは下村さんとはもちろん、惣万さんや阪井由佳子さん(「にぎやか」代表)ともつきあっておられますよね。
私のいる県でも、行政が「富山型」を押し進めようとしているのですが、三好さんの見解はどうでしょう?
 「富山型」というのは、惣万佳代子さんが「このゆびとーまれ」で始め、「にぎやか」などに受け継がれている、老人だけじゃなくて、障害児や障害者もみんな受け入れていこうという宅老所のことです。「混合型」なんて呼ぶ人もいます。
「富山型」というのは、惣万佳代子さんが「このゆびとーまれ」で始め、「にぎやか」などに受け継がれている、老人だけじゃなくて、障害児や障害者もみんな受け入れていこうという宅老所のことです。「混合型」なんて呼ぶ人もいます。
結論から言うと、私は惣万さんや阪井さんのやっていることを大変評価しています。しかし、「富山型」は評価しないというのが私の立場です。
「でも、惣万さんや阪井さんのやってるのが富山型じゃないですか」と言われそうですが、私か彼女たちを評価するのはその「現前性」なんです。あらかじめ「こうあるべきだ」と決めてしまわないで、目の前に困っている人がいれば何とかしようという、ケアの基本といってもいいでしょう。
惣万さんは老人とその家族を支えようとして「このゆびとーまれ」を始めたのですが、最初老人の利用申し込みはなく、障害児を抱えるお母さんからの依頼が利用第1号だったのは、彼女の講演でよく語られる話です。私が評価するのはこういう現前性です。
新潟でいっしょに講演をさせてもらった、グループホーム「からし種の家」の山崎ハコネさんという女性の牧師さんもこの現前性に動かされた人でした。なにしろ、ケアハウスの施設長をしていたときに、退園を迫られた一人の老人といっしょに施設を辞めて、その人を支えるために部屋を借りていっしょに住んだというのですから。
つまり、彼女たちにはそうなる必然性があったのです。目の前に困った人がいるという外的必然性とそれを放っておけないと感じた内的必然性があったのです。現前性に対するコトバは、ちょっと難しくなりますが「先験性」でしょうか。つまり、なすべき正しいことは先に決まっているという立場です。
「富山型」はこの「先験性」として登場していると思います。つまり何ら必然性のない人たちまで「そうすべきだ」という理念だけで、障害児や障害者を集めようとしているように思えます。「富山型をしたい」という人がいたので、「精神障害者とつきあったことがあるんですか」と尋ねると、まったくないとのことでした。
惣万さんや阪井さんの話がすごいのは、「富山型」に至ったその現前性なのです。それを語るのはいいけど、「富山型が正しいからやれ」と言われると「おいおい、よせやい」と言いたくなります。必然性のないものはダメなんです。
先験性だけで始めるのももちろん、行政がそれなら認めるから、なんて理由で始めたところは「富山型」というかたちをつくるだけですから、「うちには小さな子どもがいるので、こんな問題行動だらけの老人は引き受けられません」なんて言いだすに決まっているんです。県がなんと言おうが、学者たちが「富山型こそ新しい福祉だ」なんてもちあげようと、自分かやりたいのは何なのか、必然性があるのかどうかで決めてください。
それが、じつは老人のニーズにも応えることになると思います。なぜなら、老人のニーズは多様で、いろんなタイプのデイが必要だからです。子どもが好きな老人もいますが、自分の孫だけが好きという人も多いですし、子どもの声で血圧が上がると嫌う人もいます。
混合型が「正しいのだから」というスタッフの側の満足感のために子どもぎらいの老人に我慢をさせているかもしれないぐらいのことは思っていたほうがいいですね。老人は私たちに合わせてくれますからね。子ども好きの人は子どものいるところへ、子どもぎらいの人は老人だけのところへ、グルメ老人は食事の旨いところへ、と選択できるようになるのがいいんです。
さて、ユニットケアについて書こうとして先月号の「砂丘の憂鬱 --竹本×伊藤対談--」に巻き込まれたことへの補足説明の必要を感じていたため、富山型についての文章になってしまった。
言いたいことは同じである。最初に施設をユニットにしてケアを始めた人たちにはその必然性があった。私の知るかぎり「ユニット」なんて名乗らないが、その最初は大阪市生野区にある特養ホームあじさいの里だ。それは何より目の前の老人のニーズという現前性から始まった。
しかし、それがないのに「流行だから」とか行政による強制によって始められる「ユニット」は「かたち」だけになるのではなくて、深刻な堕落に陥ることとなる。必然性のないものはダメなのだ。だから「富山型」にせよ、「ユニット」にせよ、権力が強制し始めた途端、「待った!」と言わねばならないのである。
権力のやるべきことは、余計な規制をせず選択の幅を増やし、現場の決定に委ねることなのだ。「規制」を別の「正しい規制」に置き換えることではない。
このことは私か50年余り生きてきて、最低限人生から学んだ大事なことだと思っているのだが、どうしていいケアを実践してきたはずの人が、そうした権力とくっついて「正しい規制」に加担してしまうのか、私は首を捻らざるをえない。そこは彼らと私の生き方というレベルでの決定的な違いなのだと思っている。- 2003年05月 介護夜汰話 老人介護の現在
老人介護の現在 ⑤小さいことはいいことではない ~グループホーム・ユニットケアの問題点 特別養護老人ホームの経験8年の主任寮母は疲れ切っていた。 「からだが疲れるのはもう慣れてるんですけどね。精神的余裕がなくなってしまって…」 元気な介護職として評価され、若いのに主任に抜てきされてきた彼女が疲れ果ててしまうその“転機”は半年前のユニットケアの導入である。
施設長がユニットケアの導入を決定し、若干の改修工事を経て、定員90人を3つのユニットに分けることになった。職員も各ユニットごとに3つに分けられた。 問題は夜勤である。施設長はユニットを厳格に分けないと意味がなし、と考えているという。“なじみの関係”をつくるには夜勤といえどもスタッフはユニットの担当でなくてはならない、と言い、それまで全体を3人で見ていたのを、各ユニットそれぞれを1人ずつでケアすることになった。
「介護されてる家族の話を聞くことがあるじゃないですか。どんなに大変でつらいかというのを涙ながらに話す家族がいるでしよ。正直言って私、あれよくわからなかったんですよ。大変ったって家族は1人みてるだけでしよ。こっちはプロではあるけど、何十人もみてるんだから、なんて思ってたんです。でも“1人夜勤”やってから、あの介護してる家族の気持ちがよくわかるんですよ」
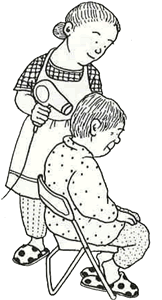 実際に彼女は話しながら泣くのである。 「淋しいんですよ。こんな淋しいとは思いもしませんでした。老人の状況、夜の間に何があったかというのを、自分以外に知っている人がいないんです。誰も気持ちを共有してくれる人がないという孤独感、ああ、これが家族の大変さなんだと思いましたね」 彼女は退職も考えているという。
実際に彼女は話しながら泣くのである。 「淋しいんですよ。こんな淋しいとは思いもしませんでした。老人の状況、夜の間に何があったかというのを、自分以外に知っている人がいないんです。誰も気持ちを共有してくれる人がないという孤独感、ああ、これが家族の大変さなんだと思いましたね」 彼女は退職も考えているという。
“1人夜勤”の問題はじつはもっと深刻である。介護する側より、介護される側にとってである。老人保健施設の職員研修に呼んでもらったときのことである。施設内を自由に見てくれ、と言われ、併設のデイケア、さらにグループホームで時間をつぶしながら雰囲気を感じとっていた。グループホームの日勤者の勤務が終わり、夜勤(正式には宿直だが)への引き継ぎが終わって、その夜勤のスタッフがフロアに入ってきたとき、集まっていた7~8人の老人が、ピーンと緊張したのである。
そのときの目に見えないが、確かに老人の表情や態度、空気が変わったのを、今でも私はリアルに覚えている。おそらく、入所している老人にとっては、この緊張が一晩続くのだろう。スタッフの名前も覚えていない人が多いのだが、彼らの無意識とからだは、ちゃんと他の職員と識別しているのである。
老人たちを一瞬にして緊張させる職員は、声の大きい、一見すると元気で陽気な人である。老人にもよく声をかけているが、よく見てみると、老人を本当は見ていないんじゃないかと感じられるタイプである。
1クラス25人にすればいい教育ができる、と言う人がいる。私はそうは思わない。 25人だと担任の目が一人ひとりに届くだろう。すると、担任と合わない子は2年間地獄である。 50人で担任が2人ならそんな心配はぐっと少なくなる。2人と合わないなんてことはまずないからだ。
問題は少人数かどうかではない。関係が閉じているか、開かれているかなのだ。学級は「担任帝国主義」と呼ばれている。担任がどんなことをしていようと、たとえ体罰が横行していても、隣りのクラスの先生が口をはさむことはない。治外法権なのだ。
担任という大人が1人で、あとはみな子どもという関係が閉鎖的になってしまうことが問題を生じさせるのだ。もちろん、介護職1人で、あとは痴呆性老人という関係が閉じることも同じ問題をつくり出す。チェックする人がいなくなったとき、人は堕落してしまうからだ。
2人の担任なら、互いに堕落をチェックする役割をすることになる。同じように「2人夜勤」なら、手を抜いたりすることもできなくなる。もちろん、孤独からも解放される。ただし、寮母長が勤務表をつくるときに、決して組んではならない組み合わせさえつくらなければ、という条件付きだけど。
だから私は「小さいことがいいことだ」とは決して思わない。グループホームでも宅老所でも、2人夜勤が可能なくらいの規模のぽうがいいと考えている。もちろん、老人施設を無理にユニット化レて、同じ屋根の下にいるのに“1人夜勤”を強いるのは、あきらかにユニットのやり過ぎだ。それは、長年、老人施設が培ってきた『家庭にはない施設のよさ』を自ら投げ出すものではないか。
いわば『施設の在宅化』でしかない。「在宅化」とは介護者の孤独と老人の閉じこめに他ならない。 大家族が核家族化することは、ある種の解放であったろう。だがそれが新たな問題をかかえることになったことは言うまでもない。ユニット化や小規模施設はちょうど核家族が直面した問題に、2周くらい遅れて出遇っているのである。- 2003年04月 介護夜汰話 老人介護の現在
④ ISO にはアイソが尽きた 前近代的で遅れている介護の世界を近代化しよう、という試みが、いずれもピント外れであり、別の新たな問題をつくり出すことでしかないことを、ここ3回ほど書いてきた。
「全室個室化」は、大部屋の問題点は解消するものの、プライバシーを大切にする近代的自我をもった者こそ人間的なのだ、という近代的人間観の枠のなかに、老人たちを押し込めることだった。じつはそうした人間観こそが痴呆性老人への偏見と差別をつくり、老人問題を生み出しているのだと言ってもいい。
老人を大事にしようというCS(顧客満足)もまた、老人を、消費者=金を払う主体として大切に扱うだけであって、むしろその画一的人間観が老人の個別性を台なしにしてしまうことも述べてきた。これまで、消費者としてすら扱ってこなかったのだからまずそれをすべきではないか、という主張はわからないではない。
しかし、目の前の老人、特に痴呆性老人が、消費者として扱われることを切実に望んでいるとはとても思えないではないか。私たちは「顧客」なんて人間観よりもっと先へ行かねばならないのだ。
それらに比べてみると、介護している我々の側に狭い人間観を押しつけるのがISOだということになろうか。ISOとは「International Organization for Standardization」の略で、世界標準機構と訳される。会社の宣伝で「ISO認証取得」なんて書かれているのを最近よく見かけるだろう。
ISO 14000シリーズは環境管理についての認証で、有害物やゴミを出さずに、リサイクルに協力している工場やオフィスに与えられるもの。一部の人が老人介護の世界に導入しようとしているのは、ISO 9000シリーズで、製造業やサービス業で、業務内容のマニュアル化、手順書の作成、マニュアル徹底のための教育の実施、マニュアルが守られているかのチェック体制ができているかどうかをチェックされる。
「ISOにはアイソが尽きました」というオヤジギャグで私に相談に来たのは、寮母長歴20年の女性である。民間企業からやってきた施設長がISO取得をめざして熱心に働くのだそうだ。それまでの役場からの天下りのやる気も何もない施設長にうんざりしていた彼女は、その熱意に惚れ込んで慣れないISOの勉強をして協力してきたという。
食事、排泄、入浴の手順は細かくマニュアル化され、そのとおりになされたかどうかをチェック表で毎日点検することになった。そして、マニュアル通りでないと叱責されることになった。しかし彼女から見ればマニュアル通りにしなかったのには一つずつ理由があるのだ。
Tさんの入浴の順番が最後になって入浴時間が大幅に遅れてしまったのは、Tさんがなかなかその気にならず、説得に時間をかけたからだった。その日はたまたまデイサービスに手伝いに行っていたTさん好みの男性ワーカーを呼びに行って説得してもらって、やっと入浴に至ったのだ。
Nさんの決められていた夜間のトイレ誘導をしなかったのは、夜勤の寮母がサボった訳ではなくて、その日は寝つくのが遅くて、ちょうどトイレ誘導時に深く寝入っていたからだったのだ。しかし、ISO認証が目的化している施設長にはこれが許せないのだ。
もともとISOは製造業で商品の品質を高めるためにつくられたものだ。従って、何をなすべきかは、予め決まっており、それをマニュアル化して実施すればいいことになる。しかし介護は、何をなすべきか予め決まっていないのだ。
たしかにケアプランを立て、食事、排泄、入浴の手順も決められてはいる。しかし老人は一人ひとり違う。マニュアルがそのまま通用する人なんていないといっていい。老人はその時、その時で違う。介護職は、今、目の前にいるこの老人が何を求めているのか、老人の表情を見るなどして情報を集め、考え、判断し、行動しなければならない。
決めたとおりでいいのか、それとも若干修正すべきなのか、それともしないほうがいいのか、と。予めなすべきことが決まっているなら、そんなことはしなくていい。顔色を見なくてもいい。そのかわり、マニュアルを見ればいい。考えたり判断しなくてもいい。作業をするロボットになればいいのだ。いや、最近のロボットはちゃんと考え判断するから、ロボット以下になれ、と言われているように彼女は感じたという。
高口光子さんは「施設介護学セミナー」のなかの「職員管理の原則」のなかでこう言う。「最終判断は現場に任せろ」と。「現場を信じられない管理者は現場からも信じてもらえない」とも言う。「マニュアルを決めてもいいけど、『ただし、最終判断は老人を目の前にした介護職が行う』とつけ加えたらいいのにね」と私が言うと、彼女は「そうよねえ、でもそんなファジーなことじゃISOの認証はくれないでしょう」と笑った。
私は彼女に拙者を1冊贈呈した。『男と女の老いかた講座』(ビジネス社)である。読んでほしいのは次の部分だ。
 時にこうした女性集団の非公式介護のあまりのファジーぶりに、「介護の客観化を」なんて言って介入じたがる人がいる。前項で登場した”事務局長”のようなタイプの男性である。役場とか、銀行といった企業を定年退職して特養の施設長や事務長になった人が、それまでやってきたような職場の合理化、近代化を推し進めるのである。
時にこうした女性集団の非公式介護のあまりのファジーぶりに、「介護の客観化を」なんて言って介入じたがる人がいる。前項で登場した”事務局長”のようなタイプの男性である。役場とか、銀行といった企業を定年退職して特養の施設長や事務長になった人が、それまでやってきたような職場の合理化、近代化を推し進めるのである。
なにしろ彼らの目には介護の世界は10年も20年も遅れた前近代的世界に見える。これを変えるのが自分の役割だと使命感に燃えているのだ。周りの介護職は白けているのだが、何も知らない介護の世界にやってきた事務長や施設長が初めて見つけた生きがいだから、むげに反対するわけにもいかない。「ま、これも老人介護のうちか」なんて言って、付き合ってはくれるのである。
かくして老人ホームには近代的なケアプラン作成システムなるものが出来上がり、介護方針や経過が項目ごとにちゃんと記録されていくのだが、実際の老人ケアなんて、その日の朝、老人と顔を見合わせてその顔色を見て決まっていくという世界だから、それらは”建て前”にすぎず、実際には相も変わらず、非公式でファジーなケアが続いているのである。
それどころか、公式な「ケース会議」に対して「裏ケース会議」というものまであって、こちらで本音で語られているから、公式版はますます形式化していくのである。つまり、女の世界に介入する近代的で合理的な男の論理は、現場の二重構造を作り出してややこしくするばかりで、合理化どころかかえって現場に非効率化をもたらすばかりなのだ。
それどころか、こうした二重構造が、変えるべき前近代性の存在を見えなくさせてしまう役割さえ果たしてしまう。こうして一人の男性の生きがいのために膨大な時間と労力を使って作られた近代的システムは、ある日突然、終焉する。
彼が退職したときである。もともと空虚なシステムだから、ある日突然終わっても誰も困らないし、現場が混乱することもない。こうした現実に、明治以降の日本の近代化なるものの本質を見た、というのはちょっと大げさだろうか。
(第1章 P.48~P.50)
- 2003年04月 介護夜汰話プラス 介護の社会化の弊害を超えて
「家族か社会か」から「家族も社会も」へ 本誌に竹本匡吾さんが連載している「砂丘の憂鬱」への反響を続けて2人から聞いた。
1人は、ケアマネジャーで、11月号の内容に「ドキッとした」そうだ。『せっかく静かに暮らしていたのに、危険だからとヘルパー、デイ、ショートステイと割り振りしていくうち、なんとか保っていたその人の能力を日常のなかで溶解させてしまうのだ』といった文章に自分のやってきたことを重ねてしまったのだという。
「『介護の社会化』を実現しようと思ってやればやるほど家族が老人から疎遠になってしまって、結局施設に入らざるをえなくなったケースがたくさんあるんですよ」。同じように「ドキッとした」と言ったのはグループホームのスタッフである。こちらは2月号の内容に対してである。
宅老所の“感動的”なターミナルケアの報告に皮肉を言う著者らしき(その名も竹本ならぬ梅本という)人物が登場する文章を読者は覚えているだろう。こちらは、介護職が介護の前面に出てくるあまり、家族との関係を疎遠にしてはいないか、という警告である。
介護保険を始める際の『介護の社会化』というスローガンを叫んだ人たちには、介護は介護力であるとしか思わなかった。だから簡単に「社会化」などと言うのである。彼らは「家族」と「社会」を別々のもの、さらに対立するものとしてとらえ、介護は「家族」ではなく「社会」がすべきものだと主張した。
もちろん、介護によって自分を犠牲にせざるをえなかった人にとっては「社会化」は救いだと映ったのだろう。だが、それでも私は介護は、「家族か、社会か」という二者択一ではなくて、「家族も社会も」だと言うべきだと考えている。「介護の社会化」ではなくて「介護の町内化」と言ってきたのは、この家族と社会が互いに協力しあう場のイメージなのである。
この協力には次のような分業が好ましい。介護力は社会の側が、介護関係は家族の側が扱うといったかたちである。家族がいなかったり、協力がない場合は私たち介護職という「社会」の側が介護関係まで引き受けることはもちろんあるけれど、本来はそれは家族の役割なのである。
2月にNHK教育テレビ「ETV2003」で福岡の「よりあい」が取り上げられた。タイトルは「2人でいっしよに暮らしたい」。これは、まさしく竹本さんの問題提起やそれを読んで「ドキッとした」現場の人たちに応える内容だった。
ご承知のように、「よりあい」は特養ホームに勤めていた下村、中島、永末の3人娘(?)がお寺の一室から始めた宅老所である。私は開設前からのつきあいだが、彼女らの嗅覚の鋭さには一目も二目も置いている。収容型の施設ケアを批判して宅老所を始めたのだが、小規模のケアをやるうち、その問題点に気づいていくのだ。
そして、世間が「小さいことはいいことだ」と「ユニット」と言い始めるころには、「小規模では人間関係が煮詰まってしまう。 50人のうちの1人でいられるのがいい老人もいるはず」と流行をたしなめるのである。さらに、少人数でなじみの関係になってくると、痴呆の老人がスタッフを「娘」や「孫」だと言い始めることに対してもこう言うのだ。
「最初はお年寄りが家族だと思ってくれるのはここが家庭的雰囲気がある証拠だと喜んでいたんです。でもある日、お年寄りはそうでも思わなければここにはいられないからじゃないか、と思い始めたんです」と。ここから宅老所のケアは転換を始める。
お年寄りがターミナルになったら、家に帰り、家族に看とってもらう。自分たちはその応援に回ろう、というのだ。もちろん、家族の協力が必要だから実現した例はまだ少ないけれど、家族との介護関係を保ち、より強いものにしていく介護に向かっていこうとしているのだ。これは、まさしく”媒介”の介である。
「ETV2003」では、「よりあい」に住んでいる83歳の女性が、週に1日、一人暮らしの88歳の夫のアパートに帰るところが紹介されている。女性は、夫と2人になるとわがままになる。やはり、家族との関係で自分を出せるのだ。
介護力は私たちが引き受けよう。そして、介護の“おいしいところ”は家族に登場してもらおう。ターミナルケアが“おいしいところ”と言うと、ひんしゅくを買うかもしれない。
じゃ、言い換えよう。一番意味のあるところ、であり、看とる家族の人生や未来に影響を与えるところだと。
- 2003年03月 介護夜汰話 老人介護の現在③
遅れてやってきたCS(顧客満足) 時代遅れのCS
介護保険がやってくるというので、介護関係者は浮き足立っていた。なにしろ、どんなケアをしようが国から金が払い込まれる措置制度がなくなり、契約の時代になるのだ。評判が悪ければ淘汰されてしまう、という、社会ではとっくに当たり前になっている原理が、遅ればせながらこの世界にもやってきたのだ。
そこで多くの関係者が採った方法もまた、社会の側ではとっくに時代遅れとなったものだった。その典型がCSという方法論である。CとはCustomer=顧客、SはSatisfaction=満足で、CSとは顧客満足のことである。白分たちのなすべきサービスを顧客が満足しているかどうかで決めていこうというのだ。
そもそも老人をCustomerとして捉えようというのが医療や介護の世界では画期的であった。それまでは治療や介護をしてあげる対象でしかなかったのが、我々のサービスを選択し消費する主体として捉えるのである。もっともそれが画期的だというのは、それだけ医療や介護が常識から外れていたからである。
「様付け呼称」の人間観
CSという考え方は、まず市場原理にさらされた医療の世界で、そして遅れて介護界にも入ってきた。敬語の強制や「様付け呼称」もその一つである。 病院の待合室にいると「三好様」と呼ばれるようになった。そんなにていねいな呼び方をしてくれるくらいなら、待合室の固い椅子で1時間以上も待たせるのをどうにかしてほしいと思うのだが。
つまり、“様を付けて呼べば喜ぶに違いない”というのが彼らの顧客像だということだ。ずいぶん皮相な顧客像だとは思わないか。ついでに院長以下、白衣の医師がズラリと玄関に並んで「いらっしゃいませ」と頭を下げてみたらどうだろう。
近代的契約関係と介護
個室の場合と同じく、私は様をつけて呼ぶことが悪いと言っているのではない。そういう場合はある。しかし特別なケ-スだと言っていいだろう。 銀行やデパートで行員や店員が「○○様」と呼ぶのは特別ではない。そこでは客ぱ”消費する主体”として扱われている。資本主義的契約関係のなかの主体なのである。
しかし、介護関係に、果たしてこうした近代的契約関係が当てはまるだろうか。 老人が“自立した主体”として登場しているうちはいい。老いや痴呆という自然へと回帰していくに従って、介護関係は、近代的契約関係からはみ出さざるをえないのである。なにしろ、老人の求めている関係が“契約関係”などではないからである。
痴呆性老人が「消費する主体」として遇されたいと思っているなどと言えば現場の人は一笑に付すだろう。彼らが切実に求めているのは過去の人間関係だったりし、自分の子どもの小さかった頃だったり、最後には「母」を求めるに至る。小さな子どもや母を求めているというのに「○○様」と呼んだりしたら、それはちっともニーズに応えていないことではないか。
近代的契約関係が通用するのは老人介護の一部でしかない。介護関係は近代的関係より巾が広く本質的なのだ。
介護現場に社会が追いつくのだ
私はかつてブリコラージュの誌上で、読者の質問に答えて次のような文章を書いたことがある(『老人介護問題発言』雲母書房刊・第1章所収)。少し長くなるが引用したい。
------------------------------------------
6事なかれ主義になるなかれ一老人介護Q&A
 特養ホームの指導員です。私は寮母たちに、老人には敬語を使うように指導しています。でも、三好さんが『正義の味方につける薬』や『関係障害論』の後書きで書かれていることも、大変よくわかるのです。矛盾してますよね。でも、放っておくとどんどん馴れ馴れしくなってしまうので、しかたなくそう言うんです。三好さんならどうしますか。
特養ホームの指導員です。私は寮母たちに、老人には敬語を使うように指導しています。でも、三好さんが『正義の味方につける薬』や『関係障害論』の後書きで書かれていることも、大変よくわかるのです。矛盾してますよね。でも、放っておくとどんどん馴れ馴れしくなってしまうので、しかたなくそう言うんです。三好さんならどうしますか。
 その気持ちはよくわかります。何人かの人からそんな声を聞きました。
その気持ちはよくわかります。何人かの人からそんな声を聞きました。
ある町のケースワーカーも、「今度来られたヘルパーさんが母に馴れ馴れしいコトバを使うのでどうにかしてくれ」という苦情を家族から受けることがあるそうです。
研修会に行けば、偉い先生が「老人の人権を大切にJ「老人には敬語を」なんて言いますし、家族からのクレームもないほうがいいですから、「敬語を使え」と指導する気持ちもわからないではありません。なかには「○○様」なんて呼ばせてるところもありますからね。
ケース報告で“患者様”つて言ってるのを聞いたことがありますよ。“様”をつけるくらいなら“患者”つていう呼び方のほうを変えたほうがいいと思うんですがね。急性期ならともかく、憲った者、というのはその人の一面でしかないんですから。
でもちょっと考えてみてください。こうした指導方法は、“事なかれ主義”ではないでしょうか。なぜなら問題は、それほど近しい関係になってもいないのに親しそうなコトバを使ったことにあるからです。つまり、その人の状況判断がまちかっているのです。
特養ホームの4人部屋を思い出してみます。入って右側のベッドの中田さんを私は「中田のバッちゃん」と呼んでいました。本人も自分のことを“バッちゃん”と言うんです。そう呼ばれると一番うれしそうでした。
でも、ちょっと真面目な話をするときや、誕生会みたいな“公式の場”では「中田さん」と呼んでいました。一度、「中田のバッちゃん元気かア」と言いながら部屋に入っていったら、家族が面会に来られていてあわてて謝りました。家族の前では「中田さん」ですよね。
もっともこの家族の方は「こんな大変な婆さんをそんなに親身にしていただいて、“バッちゃん”でちっともかまいません」と言ってくれました。確かに大変な人でしたけどね。
もちろん家族は施設に対して弱い立場ですから、異議は唱えにくいということもあるでしょう。ですから、こうしたコトバを全て真に受けるようでは困りますが、この家族に関してはそうではなかったと思いますね。それはわかりますよ。気になるなら誰か施設外の人、例えばボランティアとか福祉事務所の人から本心を聞いてもらうといいと思います。
右の窓側の熊田トキさんは、私も他の職員も一貫して「熊田さん」と呼んでいました。でも寮母さんで一人だけ「トキさん」と呼ぶ人がいました。若い寮母さんで、熊田さんは彼女のことを孫娘に重ねて見ているようで、それが許されるちょっと特別な関係でした。
左の窓側の、かなり深い呆けのあった武田さんは「センセー」と呼んでいました。元学校の先生でした。私のことぱ教え子”だったり介護職だったりしました。
左手前の山田マキエさんは化粧を欠かさない社交的な人でした。この方は、もう一人山田さんがいたので「山田マキエさん」とか「マキエさん」と呼んでいました。ときどき冷やかすときには[マキエちゃん]で、そう呼ぶと少女みたいに恥ずかしかって「やめんさい」と言いましたが、満更でもないようすで、後でアメ玉を2~3個、握らせたりしました。
つまり、親し気に呼んでいい人間関係と、呼んではいけない人間関係があるのです。なぜなら私たちは、単一の“アイデンティティ”なんてものを持っているのではなくて、いろんな人間関係の中の“関係の束”として存在しているからです。
親し気に呼んでいい場面と、呼んではいけない場面があるのです。なぜなら、私たちはいろんな場面で自分を使い分けている多面的存在だからです。
もし、現場の人たちを指導しなければならないとしたら、こうした関係の場面をちゃんと判断して、コトバを使いこなせるような指導でなければならないと思います。 「馴れ馴れしいコトバを使うな」ではなくて、「あなたと○○さんの人間関係はまだそれほど親しくないのだから、もう少していねいな言葉のほうがいいと思うよ」という具合にです。
コトバを統一してしまう画一的な事なかれ主義では、私たちの状況判断能力はますます退化していくばかりですから。さて、CSを取り入れた企業の側には反省が起こる。いくら顧客満足といっても、肝心の顧客の捉え方が皮相では顧客のニーズはつかめないからである。
アンケートなんかやってみても、アンケートの項目そのものが皮相な顧客のイメージの枠内から出ていなければ話にならないのだ。 そこでCSは古くなり、新たに主張されたのがPSである。PとはPersonal、つまり、PSとは「個客満足」である。皮相で画一的な「顧客」ではなく、一人ひとりニーズの違う「個客」として捉えようというのだ。
先の文章を思い出してほしい。文では私が主体となっているが、一人ひとり、さらにその日の老人の状態によって呼び方を変えていたのは現場の“おばちゃん寮母”たちであった。私はそれを真似たのだ。つまり、現代資本主義の最前線が、二十数年前のシロウト介護職の無意識なPSにやっと追いついたのである。
近代は誇大妄想の時代か
さて、様をつけて呼んだほうがいいのはどんなときだろうか。芦屋や田園調布のデイサービスなら、○○様が似合うかもしれない。しかし田舎の特養ホームで「OO様」なんて呼ばれたら老人は気味悪がるだろう。だってそれまでの人生で様と呼んで近づいてくるのは人をだまそうとする奴だったからである。
私も病院で「三好様」と言われると「この病院はよほど後ろめたいことをしているに違いない」と思う。「三好さん」のほうが看護婦の呼び方も自然でよほど満足度は高い。 かつて寮母たちが「様」で呼んでいた老人がいただろうか。いた。誇大妄想気味の老人に対してだけは様付けだった。
近代人の病気は自意識過剰だと私は思っている。「様付け呼称」は、様をつければ喜ぶだろうという、医療の側の皮相な人間観の表れだとするならば、近代の申し子たる医療の専門家の自意識過剰は誇大妄想の域にまで達したということではないか。「先生」と呼ばれなければ機嫌が悪くなるという自己像が「顧客」にも投射されているのである。
------------------------------------------
- 2003年02月 介護夜汰話 老人介護の現在②
「全室個室」という画一的人間観 科学より常識
戦後、アメリカから“科学的育児”なるものが日本に入ってきた。大和魂や天皇神話といった非科学的なものでひどい目に遭ったこともあって、多くの日本人がこの“科学的育児”に飛びついた。
「人工乳のほうが母乳より栄養価が高い」とか「赤ん坊が泣いていても決められた時間以外に乳を与えるべきではない」「泣いてすぐにあやしたりすると自立的な子どもに育たない」「赤ん坊のときから個室で育てることで自立した個人に育つ」…etc。
こういったことが、専門家によって科学的根拠があるとして語られたのだ。
「そんなこと言われたってねえ」と、日本の母親たちは、赤ん坊が泣けば抱いてあやし、乳首を口にふくませた。個室を与えようにもそんな住環境ではなく、日本人の伝統どおりに親子が“川”の字になって寝ていたからよかった。
なにしろ、何十年か経って厚生省があれはまちがっていたと事実上認めるに至るのだから。専門家が何と言おうと、実感と常識のそばから離れないという生活者のあり方こそ確かだということを教えてくれる一例である。
それは老人ヶアの世界も同じだ。専門的に正しいとされることは、10年いや5年も経つとまちがいだったとされたりするのだ。生活者の常識は5年や10年で変わることはない。長い時間をかけて、生活者の実感というフィルターで検証されたものが常識として定着しているからである。
二度めの喜劇が始まった
しかし、「科学」や「専門家」に弱いインテリの母親はこれに飛びついた。人工乳はバストのスタイルを崩さないためにも好都合だったし、個室を与える経済的余裕もあったからだ。インテリの子に問題が多いのはそれが理由に違いない、と私はにらんでいる。
一定の年齢になれば個室はほしくなる。それは近代的自我をもった人間のニーズだろう。“科学的育児”の誤りは、その近代的自我に基づくニーズを赤ん坊にまで押しつけたことである。 いま、子どもに個室を与えることが必ずしもよいことばかりではないことに皆が気づき始め、住宅メーカーも小さく独立した子ども部屋をやめてコーナー化したり、リビングを経由しなければ2階に行けないように階段を部屋のなかに付けるようにし始めた。
子どもを一人の個人として大切にするということと、個室を与えることとは何の関係もないということがわかってきたのだ。そんな時代になったころに、特別養護老人ホームの全室個室という方針が出てきたのである。二度めの喜劇が始まったのである。近代的自我をもった人間のニーズを、老人、特に痴呆性老人に押し付けようというのである。
画一的人間観
私は何度も繰り返しているように、個室があることに反対はしない。また、大部屋がいいとも言っていない。個室か大部屋かという二者択一的発想からくる「全室個室」という画一的人間観に異議を唱えているのだ。
これらについては、この連載の2001年11月号「全室個室こそ人権無視である」と、2002年3月号「個室の強制にどう対応するか」の2回にわたって述べているのでここでは述べないが、赤ん坊がそうであるように、老人、特に痴呆性老人は必ずしも「個室」を求めてはいないということは、現場の介護職なら当然のことのはずである。
個室がいい人もいれば、大部屋で雑魚寝で落ち着く人もいる。ふすまや障子で区切られている空間がいい人もいる。ある人が、いつもは個室だが、ときどきは添い寝でないと眠れないなんてこともある。
どうしてそうした人間の多様性や多面性を認めようとしないのだろうか。全室個室をよいものと信じて疑わない人たちのその貧弱で画一的な人間観に比べれば、われわれ介護現場の人間観ははるかに多様で豊かである。
押し付けの背後の近代人の恐怖
それにしてもなぜ彼らは、自分たちのニーズを平気で子どもに、ついで老人に押し付けるのだろうか。権力とまでくっついて押し付けようとするのは、正しいことだから押し付けてもいいという過剰な正義感からだけだろうか。
私には彼らの恐怖が見てとれるのだ。彼らが老人に個室を押し付けるのは、老いに対する恐怖からではあるまいか。 つまり、近代的自我を失って生きものへと回帰していくことへの恐怖である。だから、目の前で近代的自我から脱出していく老人たちの姿を認めるわけにはいかないのだろう。
夜になると、人の声や灯りを求めて部屋から出てくる痴呆老人たちを「個室」に閉じ込めようとするのは、じつは狭い近代的自我という枠のなかに人間を閉じ込めておきたいという彼ら自身のニーズなのである。
育児の場合と同じように厚生労働省が「あれはまちがいだった」と認めるのに十数年もかかるのだろうか。
- 2003年1月 「介護という暴力」を考えさせる一書
~誰が『母』を引き受けるのか~
 この本の題名は「母という暴力」であって、「母の暴力」つまり、母による虐待のことではな い。母という存在そのものが孕む暴力という意味なのだ。
この本の題名は「母という暴力」であって、「母の暴力」つまり、母による虐待のことではな い。母という存在そのものが孕む暴力という意味なのだ。
その根源は、子どもを一方的に産んだということにあるのだ、と著者はいう。子どもの側からいえば、「頼みもしないのに生みやがって」ということだ。この根源的受動性を著者はイノセンスと呼び、それが暴力を孕んでいるという。いわば、母という暴力ヘの対抗暴力である。
泣いたり、すねたり、わがままを言い張ったりするのはこうした対抗暴力の発現であり、それらは、〈母〉によって受け止められることで解消する、というのが著者が『現代子ども暴力論』 (春秋社)以来展開しているイノセンス論である。それが受け止められないことが少年犯罪に結びついているとの著者の指摘は、いつも具体的例証を伴って説得的である。
とすると、「介護という暴力」ということが成り立つはずではないか。それはもちろん、介護者の暴力ではなく、介護することそのものが孕む暴力のことである。
なぜなら、老いと深い痴呆は、いわば“最終的受動性”だからである。多くの老人はそれに耐えられず暴力を孕むに至る。
介護拒否、暴力行為、そして介護者、それも熱心な介護者ほど「泥棒」呼ばわりされるのは、介護という暴力に対する対抗暴力だと考えれば納得できるではないか。
痴呆性老人が最後に求めるのは〈母〉である。嫁やヘルパーを「母ちゃん」と呼んだりする。
なぜだろう。痴呆は、自分が誰か、ここがどこかも判らない悲惨な世界だと思われている。しかしそれは赤ん坊のときと同じである。
赤ん坊のとき、泣けば応えてくれる〈母〉さえいれば、決して悲惨ではなかったはずである。ならば、痴呆性老人が〈母〉を求めるのは当然だろう。
介護者は〈最後の母〉なのだ。だから”母という暴力”をも孕む。 〈母〉と母親は違う。「母親は〈母〉の第1候補」だと著者はいう。その母親が〈母〉から降りようとしている、とも。
介護者はもちろん、母親ではありえない。しかし〈母〉の第2候補にはなり得るだろう。
各地で第3候補の若い男性介護職が老人の〈母〉を引き受けようとしているのをみると、日本も捨てたものではない、と私は思う。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2003・01「Bookshelf」より
●『母という暴力 』
著者: 芹沢俊介
発行: 春秋社
定価: 本体1,680円+税- 2003年01月 2002年12月 介護夜汰話 老人介護の現在①
混迷の原因はどこにあるか 介護の中身が問われているのに
施設ケアを始めとした老人ケアは今大きな転機に立たされている。きっかけとなったのは介護保険である。措置から契約へという制度の変更はもちろんだが、介護の社会化というスローガンが叫ばれるなかで、社会の側からの介護に対する要求や発言が増え、特に老人施設への視線がこれまでになく厳しくなった。
閉鎖的だった老人施設が社会に開かれ、情報が公開されていくことはもちろんよいことで、むしろ遅すぎたくらいだと言っていいのだが、施設関係者はこの時代の変化に対応しきれず、あせりのあまり混迷へと至りつつあるように見える。
多くの施設経営者がやったことといえば、「措置から契約に変わるのだから」と職員に意識変革を要求することだった。しかし、言葉だけで意識を変えろ、と言われても、職員は空疎な説教をされているとしか思えず、結局は措置時代の古い倫理主義がむし返されるのが関の山であった。
問われているのは介護の中身を変えていくことなのである。食事ケアをどうするのか、排泄ケアをどうやるのか、入浴ケアをどう変えるのか、痴呆への関わりをどうするのか、という方法論が求められているのである。
しかし、介護の中身まで語れる経営者は皆無といってよいだろう。介護は具体的な方法論の創造ではなくて単なる介護力でしかない、せいぜい介護カプラス倫理観ぐらいにしか考えていない人が大半なのだ。
近代化は問題を解決しない
具体的な方法論を現場の介護職と共に創造していこうという能力も気持ちもない施設関係者は、その課題から逃げるように、安易な、しかし介護現場をより混乱させる方法に飛びつきつつある。それは”近代化”である。新聞を代表とするジャーナリストや進歩主義的な評論家たちが一貫して主張しているのは、一言で言うと「施設は前近代的だ。もっと近代化しろ」ということである。
「人権を守っていない、プライバシーがない、集団として扱われ、個人として尊重されていない…etc」が彼ら“近代主義者”の施設への批判である。そしてこの“近代主義”とは現代の日本人にとっても当然というべき考え方である。
皮肉屋の私から見れば、日本人全体が特定のイデオロギーにマインドコントロールされているかに見えるが、彼らは国民の意見を代表した”正しい”主張であると信じて疑っていないようである。前近代的な施設が近代的になるのはいいことではないかと、読者も思うかもしれない。しかし、こうした近代化は介護をよくするものではないという理由を、2点挙げたいと思う。
近代化を求めて行われていることは、次のようなものである。今後、これら一つひとつの問題点を具体的に挙げていくつもりである。
・契約にふさわしい顧客満足度(C.S)という考え方の導入
(接客態度の研修、敬語の使用、様づけ呼称etc)
・ISO (国際標準化の機構) の導入
・施設の全室個室化
・施設のユニット化
・グループホームの大量開設
中身から形へ逃げている
これらが問題を解決しない理由の一つは、こうした方法は介護のハードや形、あるいは形式を変えようとしているにすぎない、という点である。全室が個室化しユニット化されれば、建物が変われるのだから、見た目にはたしかに変わって見える。しかし、そこでどんな介護が行われているか、はまったく別問題なのである。
「ハードのもつ介護力」などと言われているが、介護の質を高めるためには、全室個室化はまったく誤った方法論だし(特に深い痴呆性老人のケアには)ユニット化も、現場から始まった実践は画期的なものと評価できるが、権力と土建屋と結託してユニット化を強制、半強制(事実、県庁の役人がユニットでなければ新築、改築を許可しないという“行政指導”を行っている)するようになるや、弊害のほうがはるかに多くなっている(後に詳しく述べる)。
老人に近代を押しつけるな
理由の二つめは、もっと根本的なことである。生老病死に関わる介護はそもそも近代的思考や方法論の枠の内に入り切らないのである。生まれて以来、畳や布団で生活してきた老人がある日、病気で倒れる。気がつくと近代的な病院のベッドの上に寝ている。意識が完全に戻っていない老人はいつものフトンのつもりでマットの上で立ちあがろうとする。
病院スタッフは、危ないからと抑制し、一時的な病気や軽いマヒの老人があっという間に廃人となる。日本のあらゆる病院でこんなことが起きた。しかし、病院の専門家は自分たちが老人をダメにしているとは考えもしなかった。
なにしろ老人に“近代”を恵んでいるのだから。日本の家屋の畳や布団は前近代的空間であり、病院のベッドは近代の象徴である。その近代に適応できない老人のほうが問題なのだ。そもそも入院することができて、医療という近代の恩恵を受けられること自体が幸せだった時代が長くあったのだ。だが、誰もがその恩恵を受けられるようになった途端、近代は老人たちの最大の弊害となっているのだ。
近代への信仰の薄い、田舎の診療所の医者とおばさん看護婦たちだけが、ベッドを納戸にしまいこんで、布団を敷き、そこに老人たちを寝かせていた。だが、それ以外は特養の資格もないシロウトの、だが母性的な寮母たちの出現を待つより他に「老人の側に私たちが適応する」という発想は生まれてこなかったのである。
近代を老人に押しつけて恥じない医療とその同じ誤ちを今や介護がやろうとしているのではないか、というのが私の見た老人介護の現在である。 「歴史は繰り返す、ただし一度は悲劇として、二度目は喜劇として」と言ったのは、かつての大思想家だったか。
(つづく)
- 2002年11月 特集 【対談】
介護と子育てのアポリア(難関)はどこにあるのか
芹沢俊介×三好春樹 【社会の許容量がどんどん狭くなっている】

三好 芹沢さんのイノセンス論では「生まれてきたことには責任がないんだ」というのが子どもの言い分で、老人は「年とったことに自分の責任があるわけではないのではないか」ということですが、最近どうも「年とったのは自分の責任だよ」という風潮ではないですか?
「リハビリテーションをやれ」と言うのが、まさにそれでしょう。発病後3か月や4か月の時期ならともかく、発病から5年も10年も経っている人に「今のあんたはダメだからもっとよくなれ。死ぬまでリハビリやれ」と言うのは「おまえの責任だぜ。年をとることに個人が責任をもつべきだ」と言われている感じがします。
子どももそういう傾向かありませんか。
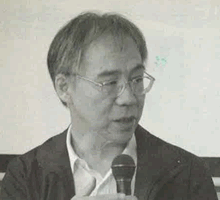 芹沢俊介(せりざわしゅんすけ)
芹沢俊介(せりざわしゅんすけ)
1942年東京生まれ。上智大学経済学部卒業。評論家。
著書に『子ども問題』「主題としての吉本隆明」(春秋社)「眠らぬ都市の現象学」『オウム現象の解読』(筑摩書房)など多数
芹沢 ええ、その傾向はますます強くなってきている気がしますね。きっかけは97年の「サカキバラ事件」だったなあと思います。あの事件がきっかけで少年法の改正へ向かって火蓋が切られ、それで変わってしまったわけです。その基本姿勢は子どもたちの勝手を許すなという風潮です。
三好 少年の凶悪犯罪はけっして増えてはいないのです。世界の中でも日本は一番少ないレベルで、昔に比べて少年の殺人事件は確実に減っているんです。しかし、あれほど大騒ぎをして少年法の改正になるというのは、皆がそれだけ問題視しているということです。
「そういうこともあるかもしれない」ではなくて、「あってはならない」ということが先走っている。吉本隆明さんは、あれは逆だと言います。要するに、「彼らはまだ大人になっていないからあんな犯罪をするので、少年法の年齢を引き上げるべきだ」と言っています。
芹沢 少し付け加えますと、日本はとても特殊な国なんですね。法務省の殺人事件(未遂、予備を含む)の統計を読むと、1997年では一番起こしているのが40代、次に50代、その次に30代、60代、70代ときて、最後に10代という順なのです。
しかし他の国々では、そういった激烈な事件をもっとも起こしやすい年齢というのはだいたい20代と相場が決まっているのです。日木も戦後しばらくの間はそうだったのですが、65年代頃からはそれが変わって、中年以降の世代がそういう事件を起こす主役になってきたのです。そういうデータをお役所は把握しているのに表に出さない。とても奇妙な国なのです。
三好 10代の子どもの犯罪が、諸外国に比べて少ないというのは何なのでしょう?管理的になっているということでしょうか。
芹沢 ひとつの理由はそういうことでしょうね。子どもがたった1,2歳なのにもうその頃から「良い子」を求める風潮が強くなってきています。しかも「教育ママ」の時代は終わり、最近ものすごい勢いで出てきているのが「しつけママ」です。
「しつけママ」は、ほとんど虐待とボーダーのところにある感じがしますから、ちょっと怖いです。しつけが早期教育とセットになっているんです。死ぬまでずっとリハビリをしなくてはいけないという風潮と早期教育は、どこか対応している感じがしています。
三好 胎教でクラシック音楽を聞かせることと死ぬまでリハビリをすることが、極限のところで一緒になっているのですね。 僕は上の子が3年生で、下の子はまだ幼稚園の年中さんです。最近のお母さんを見ていて気になることがあります。まず「しつけ」なんです。正しい子でなければいけないんです。
 三好春樹(みよしはるき)
三好春樹(みよしはるき)
芹沢俊介氏の最初の評論集「宿命と表現」(1970)以来の熱心な読者。
「自分が対談者になろうとは思わなかった」
暴力を振るってはいけない、それから差別用語を使ってはいけないと言う。子どもに説教してますね。だけど、子どもって差別するものですよ。暴力も振るうものです。傷つけ合いながら、結果として、そういうことはいけないことだということを自分の実感で獲得していくものですが、実感より先に正しい情報を入れてしまうのです。私はそれが気になってしょうがないのです。
差別用語や汚い言葉を使うのを聞き逃せなくなっているのは、お母さんというより社会全体なんでしょうね。社会がそうだからお母さんがより神経質になっているという気がします。人間の幅がすごく狭くなっているという気がします。
芹沢 その狭くなった人問の幅に我が子を適応させようと母親がやっきになっているというのが現状です。
【家庭が安全な場でなくなっている】
三好 老人ケアの世界、特に最近のグループホームで、よく「家庭的」という言われ方をします。私はこの「家庭的」という形でなされるケアにすごく抵抗があります。なぜかと言うと、ほとんどのグループホームは痴呆の軽い人しか入れてくれません。痴呆が重くなったらどうするかというと「出ていただきます」と言うのです。
呆けたときに環境を変えることは一番呆けを進行させることですから、どんなに重くなっても死ぬまでみるという覚悟がないのなら最初から引き受けるべきではないと私は思います。 障害児は施設に、老人は老人ホームへ、病人は病院へ入れてというように、異物を排除したところで成り立っているのが「家庭的」なのではないかという皮肉も言いたくなるのですが、子どもを巡っての家庭は今どうなのですか。
芹沢 2、3か月前に埼玉で、不登校の女の子をお母さんが殺してしまう事件がありました。最初はいじめがきっかけで不登校になった。学校を変えれば不登校はなくなるだろうと考え、父親が住んでいる町へ行かせたのです。しかしそこでもまた学校へ行かなくなりました。それで、娘さんはまた元の母親のところに帰ってきた。母と子の間で学校へ行けの行かないのという争いをして、結局は家庭内暴力が出たからという理由で殺してしまった事件でした。
すごく象徴的な事件だと思います。まず、子どもがいじめられて学校へ行けなくなってしまったことに対して、親がその子のつらさに添った共感を示していません。その子の苦しさを真っ正面から受け止めて、学校へ行って抗議するなり問題解決に向けた態度をとることをしていない。ひたすら登校のことしか関心がない。
つまり、我が子の条件が学校へ行くことになってしまっている。だから、いじめのある学校に行けないなら、いじめのない学校へというように対応したように見えるのですね。学校へ行けるわけないですよ。学校という場での対人関係に傷ついているのですから。子どもがものすごい不安状態に追いやられているのに安心を与えていない。安全も安定性の感覚が崩されたままなのに、すぐに学校へやってしまう。そういう状況の中で起きた事件だと思います。
【正しい子なら愛してあげる】
芹沢 僕は「権力線」とか「限界線」という言葉を使いますが、家族が子どもに対してここまでやらなければうちの子ではないという線を引いてしまっている。これは「しつけママ」の大量発生とも対応している。挨拶がきちんとできる子にしたいという強い要望のように、何かがきちんとできることが我が子であることの条件になっているのです。家庭が子どもの丸ごとの場になっていない。安心できる場や安全で安定的な場になっていないのですね。
三好 千葉県で子どもが暴力を振るって親を殺したという事件がありましたが、事件現場の映像を見て私は「ああ、まただ」と思いました。非常にモダンで、最新型のきれいな出窓が付いているカラフルなショートケーキみたいな家なのです。家庭というのはこうあるべきだというイメージに合わせて、子どもがたぶん家具みたいなものになっているのです。
そして、そのイメージから子どもが外れるともうダメ。おそらくそういうきれいな家のかわいい子どもを演じろという圧力を受けながら子どもは育ったのだろう、そしてその最初の反抗が暴力だったのだろうと思います。家の中で息が詰まったのだろうという気がします。
「家庭」というイメージが先行していて実体がどこにもない。そのイメージに振り回されている。その最大の犠牲者が子どもだという気がしてなりません。
【老い方レッスン 私たちは果たして依存できるだろうか?】
芹沢 先ほどの、いつまでもリハビリをやっていなくてはいけないという話に関連しますが、僕も中高年や高齢者の自殺を調べたり書いたりしてきました。 100年前にデュルケムという人が『自殺論』を書いています。その中に「温かい家庭の中にお年寄りがいれば自殺は起こらない」という文章があります。
ところが、日本の高齢者の自殺は非常に多いのです。それもどう見ても幸せとしか思えないような家庭でお年寄りが自殺しています。
三好 三世代同居の老人が一番自殺率が高いですよね。一人暮らしは自殺率が低いはずです。
芹沢 何だろうと考えたことがあります。実はリハビリと関係があるのですが。つまり「自立」という要請です。生産的な貢献が生きていることの至上命題になっている。しかも、それはいまや不可能である。だとすればせめて自立していなければという思いです。家族に、とりわけ嫁に世話をかけないこと。
ところがもうしばらくしたら家庭の中で迷惑をかける存在になってしまう、という状況が見えてくる。そうしたときにどうも亡くなっているのです。
三好 50代の自殺を見ると男性の自殺率が女性の約3倍くらいですね。女はしぶといですね(笑)。男は社会的に地位が高くなり、それが止まったときがダメみたいですね。下り坂に弱い。高く上がった人ほど着地が難しいのでしょうね。女は順調におばあさんと呼ばれるのがふさわしい感じになって、最後は順調に魔法使いになっていきますね(笑)。
芹沢 自殺が男性に多く女性に少ないのは、男性が生産型人間で女性が再生産型人間であることと関係しているのではないかと思っています。それで僕は順調にいけば、平均寿命あたりまでは生きるだろうと思っているのですが、同年齢の人と話をしていて2つの不安が出てきました。
1つは死が実感ではなく、イメージとして襲ってくるという感じです。これはかなり怖いです。死が向こうからやって来る感じがして「ああ、あと20年ぐらいか…」とか、「やだなあ、どうなっていくんだろう…」といったような不安と怯えが自分の中に出てきています。
2つめは、どこかの時点で自分を他者に委ねるというか、誰かに介護をしてもらわなければならないということが起きてくるという想定が生じてきたことです。それが果たして自分の中でできるだろうか、すんなりと自分を他者に委ねることができるだろうかということです。どちらもとても中途半端なリアリティーなんですよ。
三好 僕たちが年をとっていくにあたって最大の課題は、介助されることを受け入れられることだと思うけれど、それは一般に言われているような「近代的な市民意識をもった契約関係なのだから」とはちょっと違うような気がします。
「これは権利で、君たちヘルパーは制度で雇われているのだから」みたいな言い方をする人は逆に何か後ろめたさがあるから権利という言葉を使うので、卑屈になるか横柄になるかといった二者択一しかない世界なのです。卑屈にもならず、横柄にもならず、ちゃんと介護関係をとれるために必要なものは、近代的な市民意識ではないような気がしています。
他人に迷惑をかけてはいけないというのが日本人の遺伝子に染みついているのでしょうが、子どものときや病気のときは人に依存するのが当たり前で、いつでも依存できるという安心感があるから自立できていると思うのです。当たり前に依存できるというのは子どもの頃の経験が大きいのではないかという気がします。
依存してもいいのだということを母から認められた経験がある人はそこに還って行けるけれど、そこで失敗している人はもう一度最後の老いでつまずくのではないでしょうか。これは実証できるわけではないので何とも言えませんが、理論的には言えそうな気がしています。
芹沢 60代は、そういうリアリティのあるような、ないような追いつめられ方が起きてくる年代だという感じがします。これからどうやって行こうかということをなるべく考えないようにしようと思っていたのに、こういうところに座っている(笑)。
遅まきながら死について気になって考えなければならないという思いもしてきています。現状だけでなく、10年20年先に自分に起きるであろうことを必死に考えなくてはならなくなっているという妙な現在の僕自身の位置があります。
【老い方レッスン セルフイメージは軽やかに】
三好 私もどうなるかわかりませんが、介護をやっている者の強みはたくさんのケースを見ていることですね。世の中の人は、介護は大変な仕事で給料も高そうではないし臭いし汚いと思って、産廃業者と同じようなイメージをもっているけれど、介護の世界の人は職場は結構辞めるけれど、介護職は続けますね。
なぜかというと「一度入ってしまうとこんなにおもしろい仕事はない」と言うわけです。その理由はいろいろあるでしょうが、それなりにみんな、哲学者になってしまう。あと現実的な魅力で言うと自分の老い方のレッスンができる点でしょう。「あんな婆さんにはなりたくないなあ」と思える人が何人かいて、ときどき「ああいうふうに年をとっていけばいいんだ」という人もいるのです。
村上セツというおばあさんがいました。インテリのおばあさんで、いつも世の中を皮肉な目で見ている方でした。この方はなんとか押し車を押して普通のお風呂に入っていました。私が特養ホームで働いていた当時は、入居者の半数くらいの方がストレッチャーで運ばれて特浴に入られていました。私はその介助をやっていたのですが、村上さんはそれを見ながら「あんなになってまで生きとうないのう」と言うのです。
太っていた彼女は膝をやられて歩けなくなって普通のお風呂が無理になり、ストレッチャーで特浴に行かなければならなくなりました。プライドの高い彼女に特浴が苦痛であることは明らかでしたから、誰がそれを言いに行くか、誰が猫の首に鈴をつけるかということで話しあった末、結局風呂の担当ということで私が行きました。
「膝が治ったら普通の風呂に入れるけど、しばらくの間はこの船(ストレッチャーのこと)に乗って行こう」と言ったら、意外にも「うん」と言ったのです。「あれ、構えがなくなっちゃって呆けたかな?」と思いました。
そして、特浴初体験の日、全介助のお風呂から帰ってきたら「こんなええ風呂は初めて入った。極楽、極楽」って村上さんが言ったのです。それまでは自分を叱咤激励する意味で「あんなにはなりとうない」と言っていたんですね。だけど、そうなってしまったとたんにパッとそれを引き受けて、こっちがそれを気にしているということまで気遣って「ええ風呂じゃった」と言うのです。見事なもんだと思いました。
そういういい加減さというか融通無碍と言いましょうか、「そうなったらなったときのことよ」みたいにそれまで言ってきたことを、コロツと転換してしまうことができればよいのかなあと思っています。断固としたセルフイメージをもっていることは、老いにとってはすごく障害になるんだろうと思います。
芹沢 僕は竹内孝仁さんの分類(編集部注①)でいくと葛藤型かなあ。そうするとなかなか大変だろうなあ。こっちはそうなってしまえばしめたもんだと思いますが(笑)、介護する人は大変だろうな。
三好 ちゃんとイノセンスを受け止められる介護職を今のうちにつくっておかないと、変人扱いされてしまうことになりますね(笑)。

写真挿入熱心に聴き入る参加者
【引きこもりには意味がある】
芹沢 引きこもりについての本を書きました(編集部注②)。引きこもりは親御さんにとっては登校拒否よりもショックなことのようです。僕が話を聞いた引きこもりの人の中で一番長い人が13年くらい、10年くらい引きこもっている人にも3、4人会いました。
恐るべきことは世の中にはそういう人たちを外に引き出してこようとする人たちがいるんです。僕はこの本の中で2人の引き出し人を批判したのですが、そういう人たちには共通した発想があります。
それは「引きこもりという状態は社会的な損害が何十億円にもなるのだ」という発想です。「引きこもりは社会の無駄遣いだ」ということになります。これらの発想はどうも人間は自身として存在しているのだという認識以前に社会的存在、社会的資源だと見ているふしがあります。あるいは人生の効率主義ですね。
今日使った言葉で言えば、つき詰めていけば人間は何かを「する存在」と見ています。でも、その前に人間は「ある」のではないでしょうか?「あるというのが基底ではないか」という視点が全然ないのです。「あなたたちが引きこもっているために我々社会は何十億円の損失をしています」という、非常に強迫的な社会経済ファシズム的な発想で引きこもっている人たちを引き出そうとしています。これはちょっと怖い人たちだなあと思います。
単に無神経な人たちというより、この人たちは何を背負ってこういうことをやっているのだろうかと思います。社会や国家を背負っているということなのでしょうが、やっていることはとっても善意なのです。困っている家族のためにとか、困っている本人のためにやるわけですが、そういう善意の道は地獄に通じている感じがします。
三好 引きこもりの人が後から書いた本や実体などを見ると、あれは何にもしていない訳ではないですね。「出て行かない」ということを一生懸命やっているのですね。荒廃とは違うのです。「人に会わないぞ。出て行かないぞ。しゃべらないぞ」をすごく意志的にやっているという気がしました。
この芹沢さんの本の『引きこもるという情熱』という題は、引きこもるといっているけど非常に情熱的です。情熱的に自分を確認しているのではないかという気がすごくします。
【自己との関係を取り直すための引きこもり】
三好 私は人前でこうやってしゃべるのが仕事ですから意外だと思われがちなのですが、すごくオタクです。人前でしゃべった分と同じ時間だけ、一人で閉じこもって本読んだり音楽を聴いたりしないとバランスがとれない。そういう意味では、引きこもりを部分的に断片的にやっているタイプです。
芹沢 さみだれ型ってやつですね(笑)。
三好 引きこもりと社会に出ていくことを分散してやっているから、病理的にはならないというだけで、基本的に僕は引きこもっている気がすごくするのです。「あまり外へ出過ぎたからしばらく何年間かは引きこもっているよ」と考えればいいのではないかという気がするんです。
芹沢 対人関係や社会関係でくたびれたというのが、今までの社会的な引きこもりのイメージですね。だけどそれだけでは引きこもりを語り尽くせない。三好さんも「自己間関係」ということを言われますが、僕もそれがとても大事だと思っています。
何をもって人間の成熟と見なすかということをずっと突き詰めて考えたことがあります。一つだけこれならばという答えが出ました。それは、自分が自分を受け止める「自己受け止め」ができるようになったとき、その人は成熟したと言えるのではないかと思ったのです。
我々はなかなか自己受け止めができにくい構造になっています。つまり根源的受動性という形で僕らは生を得ているわけです。あらゆるものを強制的に贈与されているという点で、責任がないということ自体が構造化されている。
何か起きたときに、責任がないという位置へ逃げ込むようにつくられているからです。そのようにつくられている自分だけど、一歩踏みとどまって、これはことによったら自分の責任なのかもしれない、と自己受け止めができたなら成熟したと言える。少なくとも自己受け止めという観点を欠いた成熟論、責任論は成り立たないのではないかというように思ってきました。
そして自己受け止めは他者による受け止められ体験をベースにはじめて可能になると考えてきました。 引きこもりの問題を考えていると、確かに社会間関係や対人関係で病んでいる。でも対人関係については引きこもってしまえば強迫感はなくなるはずです。しかし、彼らは引きこもった状態でもなお葛藤しているのです。
何を葛藤しているのかというと自分と自分との関係性で葛藤しているのです。こうでなくてはならないという規範を組み込んできた社会的自己と、それがつらいよという自己が闘っている。社会的自己から逃れ、社会的自己を相対化するための滞在期を十分にすごせたとき、引きこもりが終わるのではないかと考えて、僕はそれを「正しい引きこもり」と言っています。
【老人の引きこもりと子どもの引きこもりは同じか?】
芹沢 僕は養護施設の人たちを中心メンバーにする「養育を語る」という勉強会の会員の1人なんです。そのメンバーの一人である師康晴さん(編集部注③)から、老人の引きこもりと若者の引きこもりには違いがあるのではないかという質問を投げかけられたことがありました。
僕は単純に違うとは言えないような気がするのですが、そこを突き抜ける論理がまだ見つかっていません。でも、まず引きこもっていることそのこと自体を受け止めて承認しようということは共通するのではないでしょうか。
つまり、引きこもっていること自体がその人の現在だということを認めよう、というのは基本ではないかという議論をしたことがあります。
三好 ブリコラージュにその質問が来て、7.8月号の「介護夜汰話」に書いたのですが、介護の世界では寝たきりのお年寄りは「閉じこもり症候群」と呼ばれています。私たちはその方々をデイサービスへ引っ張り出して来る「引き出し」をやっているわけですが、お年寄りの閉じこもりと引きこもりはどう違うのかというのがブリコラージュに来た質問でした。
社会的にがんばってやってきた人が、今障害を負って閉じこもっているというのは、好きで閉じこもっている訳ではないので、芹沢さんのお話に出てくる「引きこもり」とはやはり違うところがあります。では、基本的な共通点はどこかというと、「出て行っても傷つくだけだから出ていかないよ」という点です。
ですから、僕らが出ておいでと閉じこもりの人を引っぱり出すのは、出て行って自分のいる場所があるよという居場所や関係をつくろうという意味であり、ただ引っぱり出してくればいいということとは全然違うのです。そういう意味では違いもあるし、同じところもあるよという回答をさせていただきました。
【介護は受け止め手である】
三好 芹沢さんの話で私が一番おもしろかつたのは、「介護は受け止め手である」ということです。介護していると、こちらが相手に何かを「与えている」というイメージが強いのですが、本質的には受け止めることができるかどうかだということです。
哲学者の鷲田清一さんも『「聴く」ことの力』という本のなかで「介護は相手の話を聞くことが基本だ」と言われています。 この鷲田さんの言われていることを私の言葉で言いかえると、「よい介護職は老人に振り回される」となります。
私は「痴呆性老人に、もっと振り回されようよ」と言ってきました。これはお医者さんや優秀な看護婦さんにはできないことですね。問題行動には原因があるはずだから診断をして治療方針と看護計画を立てて、それに基づいて動くのが専門職であるから、老人に振り回されるのは専門職にあるまじきことだと専門職は言うのです。
痴呆老人の言う通りにやってみるとか、「赤子が泣いとる」と言ったら車イスに乗せて一緒に探すとか、徘徊していたら一緒に徘徊してみるとか、ナースコールに一晩中呼ばれるとか。よく夜勤明けの寮母が「夕べ柏原さんは4時に寝るまでナースコールを38回鳴らしました」とか報告していましたが、鳴らしたほうも鳴らしたほうですが数えたほうも数えたほうでしょ。すごいですね。“正”の字を書いて数えたわけですから(笑)。
でも、それだけナースコールを鳴らせたということは、逆に言うと薬を盛りませんでしたよ、ナースコールを引き抜きませんでしたよということでしょう。これはすごいことですよね。振り回される快感を他の職種も覚えたほうがよいという気が私はすごくするのです。
「受け止め手としてどれだけいられるか」というのは、非常に示唆に富むことばです。 訪問看護婦をやっていた人の話です。呆けがかなり進行している人でしたが、訪問した時だけでもトイレに誘導しようと、その人の両手をもって廊下を歩いていたのだそうです。そのおじいさんが突然立ち止まったから何だろうと手を離したら、両手でパッとオッパイをつかまれた。
あれ!?と思って見たら、その人は子どもの顔をしていたそうです。訪問看護婦さんは「ああ、私をお母さんだと思っている」と全部了解したというのです。パッとオッパイをつかまれたときに相手の目を見て「ああ、子どもの目をしている」と考えられる人はすごい介護職です。そういう許容量がどうも最近なくなってきていると思いますね。
【振り回し、振り回される関係を築こう】
芹沢 受け止め手とは母なんですね。振り回されるということに関していうと、ブリコラージュで「べてるの家」を特集していましたね(編集部注④)。あそこは精神障害者たちが医療者たちを振り回しています。お互いに振り回し、振り回されながら、何か自分の「丸ごとある」というものを見つけていった20年だったのかなと思っています。
僕も一度行ってみたいと思う魅力を伝えてくるブリコラージュの特集でしたね。
 三好 『べてるの家の非援助論』(編集部注⑤)というおもしろい本があります。べてるでは、年に1回総会をやるのですが、そのとき「幻覚幻聴発表会」が行われるのです。そして、一番すごい発表をした人が表彰されるのです(笑)。
三好 『べてるの家の非援助論』(編集部注⑤)というおもしろい本があります。べてるでは、年に1回総会をやるのですが、そのとき「幻覚幻聴発表会」が行われるのです。そして、一番すごい発表をした人が表彰されるのです(笑)。
先日「べてるの家」のソーシャルワーカーの向谷地さんが東京に一緒に連れてきた人が今年の新人賞をもらった人でした。その人は、発作が爆発して家に火をつけて措置入院になったという危ない人でしたが、「人はいかにして爆発するか」という発表をしたそうです(笑)。
私は、精神障害や分裂症についてはR・D・レインの本などですごく学んだ気がしていましたが、「べてるの家」の障害者自身が病気について書いているほうがはるかにリアルでおもしろいですね。分裂症なんていう名前など全然気にしていないですよ。
「精神パラパラ病の早坂です」なんて自己紹介するのですからね。 幻覚や幻聴に対しても「幻聴さん」と呼んでつきあって行くわけです。僕は痴呆老人のケアなどは本当にそこから学ぶべきだという気がしました。 子どもの領域、それから精神の領域、いろいろなところで共通した地下水脈が見えてきたという気がしています。またこういう機会を一緒にもちたいと思います。
芹沢さん、今日はありがとうございました。
(2002年8月31日、東京カタログハウスセミナーホールで開催された「ブリコラージュセミナー」より編集)
※お薦め書籍
芹沢俊介『母という暴力』
「介護という暴力」を考えさせる一書 解説:三好春樹
編集部注①
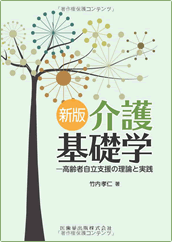 竹内孝仁氏はその著書「介護基礎学」(医歯薬出版・2,200円十税)の中で痴呆匪老人の症状類型を「葛藤型」「遊離型」「回帰型」の3つに分類している。
竹内孝仁氏はその著書「介護基礎学」(医歯薬出版・2,200円十税)の中で痴呆匪老人の症状類型を「葛藤型」「遊離型」「回帰型」の3つに分類している。
編集部注②
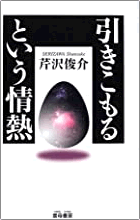 『引きこもるという情熱』
『引きこもるという情熱』
◇著者 芹沢俊介
◇判型 四六判/上製/192頁
◇発行 雲母書房
◇定価 1,600円十税
編集部注③
 師康晴さんは、神奈川県横浜市にある「セルフ杜」の施設長。
師康晴さんは、神奈川県横浜市にある「セルフ杜」の施設長。
本誌5月号のブリコラージュ★インタビューにご登場いただいている。
編集部注④
 ブリコラージュ2002年4月号特集
ブリコラージュ2002年4月号特集
★浦河べてるの家に学ぶ
~介護が自前の老人観をもつための最大のヒントがここにある
編集部注⑤
 『べてるの家の非援助論 そのままでいいと思える25章』
『べてるの家の非援助論 そのままでいいと思える25章』
◇著者・・浦河べてるの家
◇判型‥A5判/並製/256頁
◇発行…医学書院
◇定価・・・2,000円十税
- 2002年10月 ”老いに対して医療が出しゃばりすぎる”
~人々の生活に分け入り、在宅ケアに取り組む医師からの提言~
 医者にはなんであんなに威張っている人が多いのか。もっている権限や地位に比べて中身が乏しいのを埋め合わせるためだろう、と私は思っている。
医者にはなんであんなに威張っている人が多いのか。もっている権限や地位に比べて中身が乏しいのを埋め合わせるためだろう、と私は思っている。
何しろ、人間を「人体」として見る目はあっても、「主体」とか「生活者」として見る日はもち合わせていないようだし(ケアマネジヤーも大変な権限をもっている。果たして中身はどうだろう。ケアを知っているからといってケアマネジメントができるとは限らない。しかし、ケアをまったく知らないケアマネジヤーが大量に生まれてしまって、他人事ながら私は心配している。今のところは、保険の見積りやら給付管理みたいなものだからいいけれど、言葉本来の意味でのケアマネジメントが問われるようになったらどうするのだろうか、と)。
でも、私にも大好きな医者はいるのである。決して威張らないで、率直に“中身”で勝負する医者である。
病院長を辞めて、村営住宅を改造した診療所の所長とな り、ヘルパーとともに浴槽を家に運びこんで在宅ケアを始めた医者がいる。
この本の著者である矢嶋嶺氏、村の名は信州の武石村(たけしむら)である。村中を駆け巡る診療活動のなかで、寝たきりや呆けの老人と家族の実態を肌で感じた先生は、2年間の診療所の黒字を背景に、村長にデイサービスセンターの設立を提案する。
こうして県下で初めての通所施設が完成し、往診とデイサービスによって在宅死亡率は3割から7割に上昇する。当時の先駆的実践は、1993年に銀河書房から『家で生きる』と題して出版され、全国にデイサービス、デイケア、 在宅介護を急速に広めることとなる(この本は絶版となっていたが、今回、本書とともに『たかね先生の在宅介護論』として加筆再版された)。
氏は生活の場から次のように訴える。「老いに対して医療が出しゃばりすぎる」と。医者はケアマネジャーには向いていない、とも書いている。そして、老人施設で「血圧が高いから入浴は中止」などと言う医師や看護婦には「余計なお世話」と批判する。そりゃそうだ。生活の場でいちいち血圧測定して風呂に入る人はいないだろう。
だから、現場で介護する我々はたかね先生に拍手喝采する。文中に頚椎症で入院した先生を追っかけて入院してくる リウマチ患者さんがいたが、介護職の間でも先生の講演会に押しかける“追っかけ”が出現しているのも納得である。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2002・12「ケアマネジャーの本棚」より
●『たかね先生の地域医療論 』
著者: 矢嶋 嶺
発行: 雲母書房
定価: 本体1,800円+税- 2002年9月 介護夜汰話 痴呆と家族の責任をめぐって
~質問に応えて~ 客人 前回に続いて、読者からの質問に答えてもらうかたちで進めよう。
「金子満雄先生と呆け老人を支える家族の会の論争についてどう思いますか?」という質問が来ているんだけど。
金子先生というのは「浜松方式」で有名な医者で、彼が、“家族が呆けの原因をつくっていることが多い”といった発言をしたらしい。それに対して家族の会は、“痴呆は病気であって原因を家族のせいにするな”と反論しているというのが「論争」なんだけど。
三好 家族の会は「病気論」にどんどん傾いているように見えるね。「アルツハイマーデイ」を大々的に取り上げるようになったのもその一例だね。 老人性痴呆とアルッハイマー病とは似て非なるものだし、「アルツハイマー型」といった分類も意味があるものとは思えない。今回の論争でその傾向に拍車がかかるんじゃないかな。
客人 家族が「病気論」にいくのはわかる気がするよね。ただでさえ家族は罪悪感をもっていてケアで疲れ果てているわけだから、自分たちのせいじゃない、というのは、前向きになれる前提だというんだ。
三好 だからといって痴呆を病気だと決めつけるのはおかしいよね。自分たちの立場のために痴呆を定義するんじゃ、今はすたれたイデオロギーも真っ青じゃないか。 金子氏がどんなニュアンスで言ってるのかは知らないけれど、家族が呆けさせてるケースはいくらでもあるじゃないか。
客人 じゃ、君は金子派かね?
三好 とんでもない。 家族が呆けさせてるケースはいくらでもあるが、病院が呆けさせてるケースはその何十倍もある。金子氏が家族について注文つけるなら、その何倍も医者と看護婦について文句を言わなきゃならんはずだ。まして片や家族、片やプロじゃないか。
 客人 なるほど。金子先生についての君の見解はいつもおもしろいな。 「かな拾いテスト」についてもそうだったけど(『ブリコラージュとしての介護』のなかの「“呆け予防”に悩む保健婦との会話」を参照)、部分的には真実だけど、全体的には根底的に批判的なんだよね。
客人 なるほど。金子先生についての君の見解はいつもおもしろいな。 「かな拾いテスト」についてもそうだったけど(『ブリコラージュとしての介護』のなかの「“呆け予防”に悩む保健婦との会話」を参照)、部分的には真実だけど、全体的には根底的に批判的なんだよね。
三好 医者も家族の会の人たちも、痴呆とは何かと定義したがりすぎるよね。「病気か病気じゃないか」というのもあまり意味のある論争じゃないよね。病気だとしても今度はどんな病気なのかが問題になるわけだから。
まだ何もわかってないよ、という立場にちゃんと踏みとどまることが大事なんだよね。それに、家族も医者も看護婦も、もちろん介護職も、ひょっとしたら自分の関わりが呆けをつくっているかなという罪悪感をもっているべきだと思う。それが大事な気がするね。専門職だから痴呆は扱えるなんて厚かましく思っていて、罪悪感とは無縁という連中は論外。
「病気論」で罪悪感から逃れようという家族の気持ちはわからんでもないけどちょっと違うよ、という感じだな。
客人 じゃ、痴呆になった原因はみんなにあるというのが君の立場かい?
三好 いや違うよ。個々のケースではいろんな人がそのきっかけになっているかもしれないけれど、“原因”というのとは違うね。 もし原因があるとしたらそれは、私たちが意識というものをもって生き物から人間になってしまったことにある、と僕は思うね。
客人 人間になったことが痴呆の原因だと?
三好 そう。ペットの犬や猫も呆けるというけど、犬や猫は「こんなからだになってしまって情けない。昔は俺も立派だったのに…」なんて思ったりはしないものな(笑)。 痴呆を、老いを巡る関係障害、特に自分自身との関係障害として捉えると。そうなるんだよ。もっともその定義だけで痴呆がすべて捉えられるなんて思ってないけどね。
客人 でも、「脳血管型」「アルッハイマー型」という病理学レベルの分類にばかり頼っているのに比べれば、別のもっと人間学的レベルの定義の提出になっていると思うね。そういうふうに捉えれば、ちゃんと痴呆性老人が落ち着くアプローチが出てくるものな。
三好 竹内孝仁先生の「葛藤型」「回帰型」「遊離型」という生活というレベルでの分類の提案もあるしね(『介護基礎学』参照)。これはすごい定義だと老うよ。「脳血管型」「アルッハイマー型」という古典的分類から早く自由になったほうがいいよね。
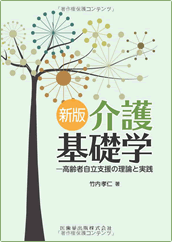 家族の方たちに最後に一言。 私は金子氏のように家族に原因があるなんて思いません。真の原因は「人間」になったことだと思うからです。でも、痴呆性老人が心身ともにちゃんと落ち着いて笑顔まで出て生活するために一番大きな力をもっているのは家族だと思っています。私たち介護職もその力を見習ってやっていこうと思っているのです。
家族の方たちに最後に一言。 私は金子氏のように家族に原因があるなんて思いません。真の原因は「人間」になったことだと思うからです。でも、痴呆性老人が心身ともにちゃんと落ち着いて笑顔まで出て生活するために一番大きな力をもっているのは家族だと思っています。私たち介護職もその力を見習ってやっていこうと思っているのです。
客人 ああ、質問1つでページが終わってしまった。次号も続けるか思案中。読者からの質問を待っています。
●『介護基礎学』
著者…竹内孝仁
判型…B5判/280頁
定価…2,200円十税
発行…医歯薬出版株式会社
● 「プリコラージュとしての介護」
著者・‥三好春樹
判型…四六判/248頁
定価…1.600円十税
発行…雲母書房
- 2002年8月 2002・徳島の夏!「寝たきりになら連」阿波踊り!
~身も心も動いてしまいました~ (リハ研事務局 発)
思い・執念・感動って伝染するものですね。 「なら連」の方々の晴れ晴れとした笑顔が、 リハ研事務局および腰痛もちの僕の身も心も元気にしてくれました。

手つきが結構サマになっているよね!
 踊り終了後、すみやかに入浴・食事を済ませたにもかかわらず、夜遅くまで盛り上がっていました。
踊り終了後、すみやかに入浴・食事を済ませたにもかかわらず、夜遅くまで盛り上がっていました。
ちなみに僕も寝たのは3時過ぎぐらい…
 翌朝、みんなスッキリした顔をしてました!
翌朝、みんなスッキリした顔をしてました!
来年の夏になればまた踊れる、 みんなに会えると思うだけでわくわくしてくるような感動が起こりました。
「なら連」、なにわ老人ケア研究会の皆さん、そして参加された多くのボランティアの皆さん!ご苦労様でした。 元気をありがとう! ( 担当N.S )- 2002年7~8月 介護夜汰話 遊びリテーションは子どもだましか?
~質問に応えて~ 客人 今回は読者から来ている三好さんへの質問に答えてもらおうと思います。何人までいけるかなあ。最初は老健の介護職からです。「大阪で阪井由佳子さんの話とビデオを見て感激しました。
話のなかで『老人ばかりで風船バレーしてるのは変じゃないですか』という発言があって、それもそうだなあ、と納得してしまったのですが、「遊びリテーション」の創始者の三好さんとしてはどう思いますか?私も施設で「遊びリテーションやってるんですけど、やっぱり「子どもだまし」なんでしょうか?」というものです。
三好 学者やジャーナリストが施設で行われているゲームやレクリエーションを「老人を子ども扱いしている」と言って批判することが多いですよね。宅老所を紹介している加藤仁氏の『介護を創る人びと』という本でも、前書きでわざわざ触れています。でも私はまったくそうは思いませんね。
長い間の一人暮らしで、民生委員が心配してやっと説得して特養ホームに入ってきたIさん(88歳)は、職員や同室の老人がいくら話しかけても、何の反応もない人でした。そのかわり、自分で自分の名を呼んで自分で返事をし、一人で笑っている、という自分の世界に閉じこもっている人でした。
そのIさんを風船バレーに連れてきたんですよ。私はこんな人が来てもなあ、と思ってたんだけど、ゲームが始まって2~3分だつと、独り言を言ってたIさんが、風船を目で追い始めたんですよ。そして目の前に来た風船に手を出したんです。 でもゲームに参加している気はなくて一人で風船を突こうとしてるんだけど、そのうちネットの向こうに打つんだということがわかってきてチームの一員になるんですね。
終わってからも「おもしろいの~」と言い続けてその夜は興奮して寝なかったんですけどね。つまり、閉じこもっていたIさんが現実の関係的世界に再登場するきっかけが風船バレーだったんです。 ゲームやレクリエーションを“子ども扱いしている”なんて批判する人たちは、表情もコトバもないような老人にどうやったら笑顔が出てくるか、コトバが出てくるかということをやったことのない人たちなんですよ。
客人 そうか。じゃ阪井さんの言ってることはどういう意味なの?
三好 阪井さんのやってる「デイケアハウスにぎやか」は笑顔やコトバを引き出す武器を他にもってるんですよ。子どももいるし犬もいるし、わざわざ「遊びリテーション」なんかやらなくてもそれができるんです。もっとも家も狭くてそんなことやろうにもできないんだけどね。
客人 僕は「にぎやか」は知らないけど福岡の「よりあい」には行ったことがある。あの狭さはいいよね。何もしないで一緒にいるんだけど互いが相手の“社会資源”になってる感じ。
三好 でも施設じゃ何もしないでいると、閉じこもりをますます進行させるだけになってしまう。だから意図的にレクリエーションやゲームをやらないといけなくなるんだよね。
客人 なるほど。でも老人を子ども扱いしているレクリエーションやゲームも多いよね。
三好 あるね。やるんなら本気でやらなきや。風船バレーだってベンチサッカーだって、職員も本気でやらなきや老人に負けるくらいのものなんだけどね。スタッフも楽しめるし、閉じこもりの人の手も出るという、奥行きのある方法論だということを、現場のちゃんとした介護職は知ってるはずだよ。
 客人 だから外から何と言われようと全国に広がって続けられてるんだよな。そういえば君の『元気がでる介護術』(岩波アクティブ新書)のなかに、「父を子ども扱いしている」と怒ってやってきた娘さんが、その様子を見て納得するという章があったな。あれはジャーナリストや学者向けに書いたんじゃないの?(笑)
客人 だから外から何と言われようと全国に広がって続けられてるんだよな。そういえば君の『元気がでる介護術』(岩波アクティブ新書)のなかに、「父を子ども扱いしている」と怒ってやってきた娘さんが、その様子を見て納得するという章があったな。あれはジャーナリストや学者向けに書いたんじゃないの?(笑)
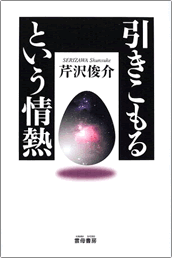 “閉じこもり”に関連して2つめの質問に移ろう。東京のOTさんから。「芹沢俊介さんの子ども論に惹きつけられています。最新刊の『引きこもるという情熱』もうなずきながら読みました。芹沢さんは子どもの「引きこもり」を意味あるものとして肯定し、“引き出じする人を批判しています。三好さんが老人の「閉じこもり」を引っぱり出そうとしているのとは反対のようにも思えますがどうなんでしょう」というものです。
“閉じこもり”に関連して2つめの質問に移ろう。東京のOTさんから。「芹沢俊介さんの子ども論に惹きつけられています。最新刊の『引きこもるという情熱』もうなずきながら読みました。芹沢さんは子どもの「引きこもり」を意味あるものとして肯定し、“引き出じする人を批判しています。三好さんが老人の「閉じこもり」を引っぱり出そうとしているのとは反対のようにも思えますがどうなんでしょう」というものです。
三好 子どもの“引きこもり”と老人の“閉じこもり”は違いますね。私も芹沢さんの言うように、子どもの“引きこもり”は内的世界を充実させ、外的世界に出かけていくために必要なことだと思っています。
でも老人の“閉じこもり”は違います。みんな社会のなかに出て人間関係をもってきた人たちです。その人たちが閉じこもっているのは決して本意だとは思えません。私たちぱ閉じこもり”をただ引っぱり出そうとしているのではなくて、出ていきたいと思えるような関係的世界をつくろうよ、と言ってきたはずです。
それにしてもこの本での芹沢さんの「引き出し人」に対する憎悪はすごいですね。「前向きで友だちを多くつくって明るく生きる」なんていう生き方を正しいと思い込んで子どもに強制することへの憎しみですね。じつはそうした画一的な人間観こそが子どもに“引きこもり”を必要と感じさせ、障害老人を“閉じこもり”に追い込んでいるんですけどね。
● 「元気がでる介護術」
著者…三好春樹
判型…新書判/188頁
定価…700円十税
発行…岩波書店
● 「引きこもるという情熱」
著者…芹沢俊介
判型…四六判/上製/192頁
定価…1,600円十税
発行…雲母書房
- 2002年7月 流行にとらわれず現場から創る管理運営論
 高口光子女史の講演を開いたことがあるだろうか。会場は最初、シーンとしている。こんなきわどい冗談に笑っていいものだろうか、と戸惑っているのだが、やがて苦笑が爆笑に変わる。彼女の「本音ワールド」に引きずり込まれるのだ。
高口光子女史の講演を開いたことがあるだろうか。会場は最初、シーンとしている。こんなきわどい冗談に笑っていいものだろうか、と戸惑っているのだが、やがて苦笑が爆笑に変わる。彼女の「本音ワールド」に引きずり込まれるのだ。
あまりに辛らつな看護職への批判に、途中で怒って帰る人を私は何回か見たことがあるが、最近では、ターミナルケア、それもケアプランの中にそれを位置づけての実践報告 に、海千山千(と言っては失礼か)の婦長連中を泣かせるほどに“芸”が上達している。
その高口さんが本を出した。前著『いきいきザ老人ケア』 (医学書院)も、すごい衝撃だった。訓練室で老人が、障害や境遇など、どちらが不幸かを競い合うようすを描いた「不幸くらべ」に大笑いした。彼女はその後、病院のPT科長の職を捨て、介護の世界に入る。特養ホームの寮母長を経てデイサービスセンター長も経験する。
その畑違いの分野を見事に自分の領域にしてしまったのが今回の本である。題名とは違って、きわめてまっとうな施設の介護論である。特に、婦長、寮母長、主任といった中間管理職にとっては、これまでどこにもなかった共感のできる運営管理論になろう。
介護保険の開始に伴って、施設の運営は盤石のものになっ たかに見える。しかし施設介護の現場は逆に自信を喪失しつつあるように思える。「ユニットケア」なんていう流行に飛びつくこともその自信の無さの表れだろう。
「ユニットケア」にすることでいったいどんなケアをしたいのか、という肝心の中身が見えてこないのだ。個別ケア?それはユニットケアでなくてもできるんじゃないの。むしろ、人間関係の個別化は、無数の組み合わせの可能な非ユニットのほうが可能ではないのか。
家庭的ケア?「家庭的雰囲気を壊すから」と重い呆けを追い出すグループホームを見ていれば、「家庭的」がいかにギマン的か判りそうなものじゃないか。
施設スタッフがこれまで経験してきたことをこそ大切にし て、新たな介護管理論を創り出そうとする著者の姿勢はそんな流行を吹き飛ばす。デイやショートの運営についても語られており、施設はもちろん、地域のケアマネジヤーにも必読の書。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2002・07「ケアマネジャーの本棚」より
●『仕事としての老人ケアの気合 』
著者: 高口光子
発行: 医歯薬出版
定価: 本体2400円+税- 2002年6月 介護夜汰話 こんな医者、看護婦は急性期病院へ帰れ!
客人 とうとううちの親父も寝たきり老人になってしまったよ。でも介護体制をつくるゴタゴタでいろんなことを学んだよ。
三好 寝たきりになった過程は?
客人 最初は風邪だったらしい。いつまでも治らないので病院に行ったところ、肺炎と診断されて入院することになった。そこからはお定まりのコースで寝たきりだ。お前がいつも言ってるとおり、病人とはいえ、ちゃんと歩いて入院したのに、高いベッドで足が降ろせず、マット幅も狭いので上を向いて寝ているだけになった。
三好 そして食欲がなくなってチューブになり、それを抜くというので抑制され…。
客人 まったくそのとおり。おまけにMRSAまでうつされる始末。あわてて実家に帰り、母親や親類を説き伏せて反対する医者をあきらめさせて家に連れて帰った。
三好 家に帰った途端に元気になっただろう。
客人 それもいつもお前が言ってるとおりだったのには驚いたけど、家で看ていくには今では大きな難関があるんだ。
三好 何?
客人 介護保険という制度だ。一応介護の仕事に関わってるし、お前の本も読んでるから寝たきりにしない介護をやろうと思ったんだけど、介護保険が邪魔するんだ。 まずやってきたケアマネジャーが、お尻に小さな床ずれがあるからというので勧めたのがベッドとエアマットのレンタルだ。すぐに申し込もうとする母親を俺が止めてたんだけど、往診を頼んだ開業医と看護婦まで「すぐにエアマットを」と言うんで母親は抵抗しきれなくなったらしい。
三好 床ずれができてしまった原因である寝たきり状態という生活を変えないで、結果である床ずれをどうにかしようというのはとても科学的対応とは思えないよ。
客人 しかもケアマネジャーが紹介した業者がもってきたのは狭いベッドで、おまけにエアマットの上に寝てると身動きもとれない。
三好 床ずれの予防の治療の第①は寝たきりをやめて座る生活をつくること。座って食事をし、座って排泄し、普通の風呂に入ること。
第②はペッドの上でゴツゴツできる条件をつくること。なぜなら、私たちが一晩中寝ていても床ずれができないのは、無意識にゴソゴソしているからだ。
そして第③は笑顔が出るような体験をしてもらうことだ。 エアマットは、起き上がりはもちろん、ベッドから足を垂らして座ることも難しくするし、床反力がないからゴツゴツすることすらできなくなってしまう。
客人 医者や看護婦にエアマットの適応や副作用についてちゃんと教育してくれないものかなあ。
三好 エアマットはどうやって外したんだい?
客人「ベッドの幅が狭い」といって私が怒って、一番広いものに変えてくれるよう要求したんだ。ちゃんと100cm幅のレンタルがあるんだよ。ところが幅広のベッドに合うエアマットがないものだからベッドの上に段差ができてしまう。「これじゃ広いベッドの意味がないから」とエアマットを引き取らせたんだ。
三好 医者から怒られなかったかい?
 客人 次の日やってきた医者と看護婦は半ばあきれていたそうだが、エアマットを外すことに不安だった母親がその夜、興奮して電話をかけてきたよ。「お父さんが自分一人で寝返りした」というんだ。最初は何が起きたかわからなかったらしい(笑)。でもパタンと右横を向いて、続いて左側にも向いたらしい。母親が喜んで父に話しかけたが、父親はもう寝ていたそうだ。半ば無意識に動いたらしい。
客人 次の日やってきた医者と看護婦は半ばあきれていたそうだが、エアマットを外すことに不安だった母親がその夜、興奮して電話をかけてきたよ。「お父さんが自分一人で寝返りした」というんだ。最初は何が起きたかわからなかったらしい(笑)。でもパタンと右横を向いて、続いて左側にも向いたらしい。母親が喜んで父に話しかけたが、父親はもう寝ていたそうだ。半ば無意識に動いたらしい。
三好 エアマットを外してベッドを広くする、といってもシングル幅だから広くはないんだけど、普通の生活と同じ条件をつくるだけで無意識の主体性をちゃんと引き出せるんだよ。狭いペッドにエアマットじゃ、床ずれを治すためといいながら、床ずれができる条件をつくっているだけなんだ。
客人 どうして頭のいいはずの医者にそんなことがわからないんだろうな。
三好 エアマットの適応があるのは、四肢の完全マヒで動けない人か、意識を失っていて無意識にもゴソゴソできない重度障害者か重い急病人だけなんだ。病院でそんな人ばかり見てきた医者や看護婦が、頭を切り換えないまま在宅介護に関わってるからこんなことになる。
客人 これじゃ「介護の社会化」じゃなくて’「介護の医療化」じゃないか、とつくづく思ったね。
三好 「地域の病院化」と言ってもいいね。イリイチが『脱病院化社会』を書いて久しいけれど、介護保険がますます「病院化社会」を進めているとしか思えないな。 ところでチューブはどうなった?
客人 ちゃんと外して口から食べてる。病院の医者は「一生口から食べられない」と言ったがあれは何だったんだろう(笑)。
三好 介護は医療の後始末をするものだとしか考えてないから、病院でダメなものが介護でよくなるとは夢にも思ってないんだよ。もっともそんなちゃんとした介護も存在しなくなってるけどね。
今回の結論。 床ずれにエアマットを指示するような医者、看護婦は介護の勉強をし直せ。さもなくば急性期病院へ帰れ。もっともそんな応用力に乏しい専門職じゃ急性期の患者も迷惑だけどね。
※ [介護夜汰話]のテーマを、「看護師」とせず、あえて「看護婦」とした。法律ではなくて生活者の習慣のほうに従いたいからだ。(三好)
- 2002年5月 介護夜汰話 「家庭的」という欺隠
~こんなグループホームはやめてしまえ~ 客人 『元気がでる介護術』がずいぶん売れているそうじゃないか。
三好 おかげさまで早くも増刷になった。自分としては力をぬいて書いたんだが、それが売れるというのも不思議な感じだ。
客人 「介護をめぐる11の物語」風の読みものになっているから読みやすいけれど、特養の全室個室化反対の主張も入っているし、世間の大がよいものと信じている「介護の社会化」や「グループホーム」への批判も入った辛口の本だというところが売れる理由だと思うよ。
三好 そう言えば、講演の後の質疑応答で「グループホームをつくりたいのですが、アドバイスを」と言われたので「やめなさい」と応えたら、会場中の大が不審そうな顔をしていたなあ。
客人 その会場には俺もいたよ。みんな、グループホームは少人数で家庭的なケアのできるいいものだと思いこんでいるから、おまえが批判的だとは思ってもいなかったらしい。
三好 収容所も顔負けするような老人施設に比べて”まし”だというものが“いいもの”のはずがないじゃないか。そんなものに飛びつくのは、罪悪感を感じないで支配欲、管理欲を満たしたいという奴にちがいないね。
客人 おいおい、知人、友人のなかにグループホームをやっている人もいっぱいいるじゃないか。そこまで言うかね。
三好 彼らはちがうさ。「グループホーム」をやりたかったわけじゃない。病院でしばられてたり、施設で個室に閉じ込められている痴呆性老人を少しでもましな条件でケアしたいと思った人だ。深い呆けで困っている本人と家族の二ーズに応えたいと思った。そのために「グループホーム」という制度を活用しようと考えた。そこが大きなちがいだ。
客人 制度があるからやるんじゃない。ニーズに応えるためにやるんだ、ということだな。
三好 そう。ニーズに応えることを基本にしていれば「グループホーム」の大半がやっているような「呆けが重い人は入れない」とか「呆けがひどくなったら出てもらう」なんてことは決して言えないはずなんだ。むしろ逆だろう?重い人ほど入れるべきだし、呆けが重くなったときほど同じ環境で同じケアを続けるべきじゃないか。
客人 でも、グループホームでは重い人をケアするほど金はもらってないと主張しているぜ。
三好 福岡の「宅老所よりあい」はトレーナーを売ったり、セミナーを開いたりして不足分を補っているじゃないか。いま流行のワークシェアリング、つまり給料は安くていいからスタッフを増やすことで乗り切っているところもあるんだ。
客人 でもそこまではできないから、やっぱり要介護度が4になったら追い出すより他にない、制度の不備なんだからと言い訳しているぜ。
 三好 それじゃ、やらなきゃいいんだよ。こうしたやり方は老人を痴呆に追いやり、介護職を堕落させるという犯罪的なものなんだ。
三好 それじゃ、やらなきゃいいんだよ。こうしたやり方は老人を痴呆に追いやり、介護職を堕落させるという犯罪的なものなんだ。
まず、第一に、環境や人間関係の変化が呆けをつくり出すということはよく知られている。環境と関係をできるだけ変えるなというのは、老人ケアの原則だと言ってもいい。まして、呆けが進行したときに、出て行けと言って特養ホームなんかに移すなんてのは老人を呆けさせているようなものだ。
第二に、ちゃんとした介護職なら、長い間ケアしてきた老人を呆けが進んだからといって追い出そうとは思わないはずだ。『情が移ってないのかねえ』というのは『元気がでる介護術』の最終章に出てくるベテラン寮母によるグループホームへの嘆きだ。制度のせいにして、介護職の思いを封じ込める。これが介護を堕落させるのだ。
客人 中国地方で開かれたグループホームの大会で、会場の家族からこんな切実な質問があった。「重くなってもみてもらえるんですか」。地元のグループホームのスタッフが「うちでは、要介護度4でも5でもちゃんと住み続けてもらっています」と答えたそうだ。
三好 立派なもんじゃないか。
客人 ところが東京からやってきたというグループホームのスタッフがこう言って怒ったというんだ。『そんなのはグループホームとは言えない。家庭的雰囲気を守るためには4や5の人には出て行ってもらうべきだ』と。
三好 やれやれ。“家庭”ってそんなにいいものかよと言いたくなってしまうなあ。
客人 そんな家庭的雰囲気を乱さないような人なら家庭でケアできるはずじゃないかと思うね。「家庭的」を免罪符にして、軽い呆けまで家庭から追い出す役割をしているのが「グループホーム」じゃないかと思えてきたよ。「家庭的」というのは、家族と同じくらい親身にケアするということジやないのかね。白分たちの技倆のなさを棚に上げて老人のせいにするとはあきれたものだ。
三好 現代の日本の「家庭」がいかに異質なものを排除して成り立っているかということがよくわかるじゃないか。老いも、身体障害も、精神障害も家庭から排除されてきた。一見「家庭的」な家族も、子どものなかにある異質な部分を抑圧して成り立っているなんてことは、芹沢俊介氏の著作を読むまでもなく、ありふれたことになっている。そういう意味では、重い呆けを排除しようとするグループホームは、まさしく「家庭的」なんだよ。
客人 グループホームという制度を使いながら、どんなに呆けても、寝たきりになっても最期までケアしようよ、みんな。
- 2002年4月 介護夜汰話 ユニットの強制にどう対応するか
三好 しかし、毎月の勉強会でミッシェル・フーコーを読んできてよかった、とつくづく思うね。個室なんていう施設の近代化が、問題を解決するどころじゃなくて、権力の完成の姿だということ、そして近代化を押し進めるヒューマニストたちが、じつは「牧人権力」(『ブリコラージュとしての介護』参照)という権力の最後のかたちであることがよくわかるよ。
 客人 そういえば「ユニットケア」を推進する人たちまで行政権力とくっついて、新型特養に強制するところも彼らの権力性の表れでしょうね。
客人 そういえば「ユニットケア」を推進する人たちまで行政権力とくっついて、新型特養に強制するところも彼らの権力性の表れでしょうね。
三好 私は施設のケアに疑問を感じて「ユニットケア」を始めた人たちの実践を評価したいと思う。大阪市生野区の「あじさいの里」なんかは「ユニット」という名前のない頃からやっていて、ちょっと他では感じられないいい雰囲気だった。
また、武田和典さんたちがユニットを始めたのも、やむにやまれぬ気持ちからだったことはよく理解できる。でも「ユニットケア」がうまくいくためには「ケア」がちゃんとしていることが前提なんだ。
客人「ケア」じゃなくて「ユニット」というかたちを先行させてしまえ、というのが行政や「ユニット」に飛びつく施設のやり方だよね。 かたちからケアの中身が生まれてくるということはないかね?
三好 まずないと思う。 「ユニットケア」は管理的な施設をますます管理的にするだけだ。残念ながら現存の施設の9割は管理的だから、管理主義を推進する役目にしかならないだろう。
客人 でも少人数で家庭的雰囲気でケアするのが目的だと言ってるぜ。
三好 家庭がそんなにいいものかねえ(笑)。現在の核家族が子どもにとって息苦しい管理の空間になっていることを考えてみればいいじゃないか。少人数の閉じられた関係が病理を生むことは戦後の日本の家庭が教えていることじゃないか。
教育を良くするために、1クラス25人にしろ、という人たちがいるけど、とんでもない意見だよ。俺たちの頃の小学校は1クラス58人もいた。よかったよ、先生の目が届かなくて(笑)。 25人だと担任と相性が合わない子どもにとっては2年間は地獄だよ。 50人で担任を2人にするべきだね。さらに言うと「学級」という閉じられた関係をいかに開くかを考えるべきなんだ。
客人 たしかにあれは、大人1人に他が子どもという“担任帝国主義”だもんな。隣の担任は互いに“内政不干渉”だし。
三好 つまり「ユニット」を強制された介護現場のやるべきことは、担当スタッフと老人という閉じられた関係を開くことだと思う。他のユニットの老人のことは関与しない、なんていうことでは困る。老人の側から言うと、十数人の職員と50人の老人のなかで気に入った人が1人ずつでもいれば落ち着けるんだけれど、ユニットはその選択の幅を狭めているんだよね。
客人 専門家なんだから誰でも受容できなきゃ、というのは建て前だものね。三好さんの言うように「受容より相性」(『老人ケアが上手くなる10ヶ条』)だものね。
三好 そういう意味じゃ、彼らが目指すという“家庭的”の家庭こそ、その選択の幅がいっさいない閉じられた関係の場なんだよね。施設は、“家庭"に近づこうとするんじゃなくて、近代的家庭のもち得ない関係の多楡陛と選択性を生かすべきなんだ。ユニットはその良い点を自ら手放してないかい?
客人 実際、隣のユニットに老人が行くことを禁止している施設もあるもんな。ひどいもんだ。
三好 さらに、ユニットごとに施設の外にどこまで開かれているかがこれまで以上に問われると思う。一人ひとりの老人に会いに来てくれるボランティアをつくっていくこと、そのボランティアと狭いユニットから外へ出ていく機会をつくること。それができないならユニットじゃない方がいい。だってユニットじゃない方が関係性も豊かだし世界も広いじゃないか。
客人 10人くらいのユニットだと人間関係は難しいね。 1人の問題老人でユニット全体がイライラしてしまう。三好さんが『ブリコラージュとしての介護』のなかで、「生きいきの里」のことを書いてますよね。広い食堂にみんな集まってくるんだけど、自然発生的にいくつかのグループに分かれていて、問題老人もそのなかでちゃんと居場所があるっていう、あれ。あれこそほんとうのユニットじゃないかと思うんですよ。自発的で流動的なユニット。それを大事にすべきだと思うよね。
三好 問題老人でうまくいかないユニットに、10人を1か所に集めないで別の空間に別のグループをつくればいいとアドバイスしたんですよ。すると若いスタッフが「それじゃ、スタッフの人数が少ないので見守れないんです」と言う。「見てなくていいじゃない」と言うと「そんな!」と驚くんですよ。
老人を全部見てなきゃいけないと思ってるのね。見えない空間があること、見られない時間があること、見て見ないふりをすること、それこそ介護の課題なんだけどね。
客人 職員がいなかったら、老人同士でけっこううまくつき合う知恵が出てきたりするんだよね(笑)。
『ブリコラージュとしての介護』
三好春樹 著
四六判・並製・248頁
発行 雲母書房
定価 1,600円十税
- 2002年4月 いいケアは自分でつくれ
~地に足をつけた仕事をするために~
 私は『老人の生活リハビリ講座』を18年間開いてきた。「生活づくりの介護」「関係づくりの介護」などをテーマにした、A~Eまでのそれぞれ2日間のセミナーである。
私は『老人の生活リハビリ講座』を18年間開いてきた。「生活づくりの介護」「関係づくりの介護」などをテーマにした、A~Eまでのそれぞれ2日間のセミナーである。
開催日は土・日の2日間だ。職場からの出張でなくても個人で参加できるようにしている。実際、受講者の大半は、自分の休みを使い、決して安くはない受講料を自分の金で払ってやってくる熱心な人たちである。
「熱心さのあまり職場では浮いている人が多いでしょう」と 私が言うと、爆笑する人や苦笑する人がたくさんいる。
「でも“浮いてる”と思っちゃダメですよ。周りが沈んでるんだと思って頑張らなきゃ」と言うと、こんどは明るい笑いが返ってくる。
そんな受講者のなかには、病院や施設勤めを辞めて、自分で事業を始める人がたくさんいる。東京で受講した下山名月(なつき) さんは、川崎市で生協の協力を得て「生活リハビリクラブ」 というデイサービスを始めたし、大阪会場まで通っていた五藤万里代さんは、愛知県一宮市の借屋で「お達者くらぶ」を 始めた。いずれも、老人や家族から利用料をもらっての苦しい運営だった。
私は介護保険という制度にも運用にも多くの批判をもっている。しかし最大のよい点は、民家を借りたり、自分の家を使ってのデイサービスにも報酬が支払われるようになったことである。
お寺の敷地内の築60年の借屋で始められた福岡の「宅老所よりあい」は、昨年末、10周年集会を開いた。記念に出版さ れた『九八歳の妊娠』(下村恵美子著・雲母書房)は、「日本の痴呆性老人のケアの神髄がここにある」と話題になっている。
下村さんたちもまた、管理的な施設に見切りをつけて辞め、 自ら事業を起こし、日本の老人ケアを変えるに至ったのだ。 「職場でいい介護ができないのなら、自分で職場をつくればいいのですよ。つくり方はこの本に書いてありますから」言うと、受講者の表情が変わる。この本とは、『あなたが始め るデイサービス』だ。本屋でもよく売れているらしい。
本誌の読者で、職場だけでなく、介護保険という情況下で浮いている人がいないだろうか。そんな人には、足が地に着いた仕事へ向かうきっかけになるだろうと思う。
『ケアマネジャー』(中央法規出版)
2002・04「Bookshelf」より
●『あなたが始めるデイサービス 』
著者: いらはら診療所+日本生活介護 共著
発行: 雲母書房
定価: 本体1,800円+税- 2002年3月 介護夜汰話 個室の強制にどう対応するか
客人 「新型特養ホーム」の設計段階で、県の担当者の頭が固くて困っている。ユニットを厳格に分けろと言うし、個室も引き戸で開くのはダメで完全な個室にしろとか。
三好 かつて痴呆性老人の施設を、老人が徘徊しやすいように回廊式にしろ、なんて強制してましたよね。今じゃ、誰もそんなものつくろうとしないでしよ。だって、痴呆性老人のニーズは自由に徘徊したいということじゃないですものね。ユニットも個室も、10年経ったら「なんであんなバカなことをしたんだ」と言われるようになるのは目に見えてますね。
客人 三好さんの予想はよく当たるものなあ。かつて「MDSなんてすぐすたれる。誰がこんなものを現場に押しつけようとしたか覚えておこう」なんて書いてましたよね。そのとおりになった。
三好 もうMDSなんて言っても何のことか誰も覚えていないんじゃないの(笑)。
客人 でもその「全室個室」を押しつけられている側はどうすればいいんでしょうね。
三好 個室というのは、近代的自我に対応しているんですよね。みんな近代的自我を確立しなきゃいけないっていうんで、子どもに個室を与えたでしよ。で、どうなったっかっていうと、反省が起こっているんですよ。子育てで失敗したことを、1回りも2回りも遅れて介護の世界でやろうとしているんです。
老いは、近代的自我が崩壊していく世界です。痴呆となると、自我が消えて、自然に回帰していく世界です。そんな人たちにまで、近代個人主義というイデオロギーを押しつけようというのが「全室個室」です。 人恋しくて夜中に個室から出てくる人、互いに添い寝をして落ち着ける人たちのために、そんなコーナーを予め用意しておくべきですね。スタッフ室の近くに、畳でも置けるようなコーナーをね。
また、何室かに1室、個室にしては広い部屋をつくっておくとかね。そこにベッド3台ぐらい入れて、痴呆性老人のニーズに応えるんです。広い理由は何とでもつけられるでしょう。
客人 なんだか正規のケアに対して、ゲリラ戦みたいなケアですね(笑)
三好 そうそう。それでも、近代主義者たちはザコ寝させてるなんて、老人の「人権を尊重していない」なんてケチをつけるだろうけど、現場で老人のニーズの多様性を身体で知っていない人たちは放っておけばいいんです。
客人 たしかに個室がいい人もいるし、大部屋で落ち着く人もいる。フスマや障子で区切られているくらいがちょうどいい人もいますもんね。
三好 同じ人でも、個室がいい状態のときとみんなと一緒にいたいときが交互にくる人だってあるし…。
客人 近代主義者って発想が画一的ですよね。
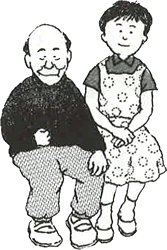 三好 そう。そもそも近代というのが画一的なんです。「人権」なんていう抽象的レベルでしか人間を捉えないから、人間がみんな同じに見えてしまう。実際には、人間は多種雑多だし、若い人と老人はちがうんです。痴呆性老人はもっとちがうのにね。
三好 そう。そもそも近代というのが画一的なんです。「人権」なんていう抽象的レベルでしか人間を捉えないから、人間がみんな同じに見えてしまう。実際には、人間は多種雑多だし、若い人と老人はちがうんです。痴呆性老人はもっとちがうのにね。
客人 「1万人委員会」で活動している女性と議論したことがあるんですよ。彼女の実母は痴呆で特養ホームにいるんです。それで介護に興味をもったっていうんですけどね。当然、特養の全室個室化には賛成なんです。私が、現場のいろんな老人の話をして反論すると、最後には本音を言ったですね。
『たしかに、母はぼけていて(母が)個室がいいなんて言った訳じゃない。しかし、特養に預けている私としては、大部屋の施設に入れてるより、個室に入っているほうがいい』つて言うんです。 つまり、老人のニーズではなくて、自分の側のニーズだということなんですよ。
三好 特養ホームに入れていることへの罪悪感とか世間体のための個室なんですよ。特に、戦後の生まれで近代個人主義を信じて育った団塊の世代の自己満足だと思いますね。
客人 だから「介護を知らない1万人委員会」なんて現場から揶揄されるんですよ。
三好 えっ、そう言われてるの?
客人 そう。「高齢者介護から逃げたい女性の会」とかね。彼らの「全室個室化」の主張は間違っているだけじゃなくて、それを行政権力と結びついて現場に強制するのがもっとひどいと思うね。
三好 介護現場に影響力をもっていないから、権力と結びつくんだよね。行政のやるべきことは選択の幅を広げることですよ。何を選ぶかは、介護保険料を払っている人たちが決めればいいんです。でも、この人たちは大衆をバカにしているから、自分たちが“正しいこと”を強制してやらなきゃと思っているんですよ。
客人 家族主義を強制する古い権力と、近代個人主義を強制するちょっと新しい権力という構図ですね。
三好 現場はどっちにも加担しないこと。幻想なんかもたないこと。それが大切。個室化に代表される近代化は、新たな問題のはじまりにすぎないのだから。
客人 ユニットケアの強制については、また次号で語ってもらいましょう。- 2002年2月 Mさんよりのメール
昨年11月 三好春樹の主宰する生活とリハビリ研究所の介護施設研修ツアーに参加しました。
 北海道、東京、広島から募集されたメンバーが広島に集まり、広島誠和園にバス2台で向かいました。三好春樹を信奉し、その理論を取り入れた介護を実践している村上園長さんの楽しさのあふれ出る語り口はちょっと福祉的な篤志家のそれとはまるっきり違った弾むような流れ方がありました。
北海道、東京、広島から募集されたメンバーが広島に集まり、広島誠和園にバス2台で向かいました。三好春樹を信奉し、その理論を取り入れた介護を実践している村上園長さんの楽しさのあふれ出る語り口はちょっと福祉的な篤志家のそれとはまるっきり違った弾むような流れ方がありました。
古い建物の活用やそれを吹き飛ばすような職員さんの元気いっぱいの挨拶(ちょいと元気すぎ?)、新しいグループホームの建物、設備の目を見張る豪華さ。玄関からはこれが施設? まるでちょっとした料亭のようなたたずまいでした。管理しやすいようにこの1点に立てばすべてが見渡せる・・なんていう場所はまったくありませんでした。
最後に参加メンバーで記念写真・・となったのですが、園長さんの軽妙な撮影で全国から集まった者が一体になったように感じました。ちなみに村上園長さんのお年寄りを撮った写真集は一見の価値があります。この写真集だけで施設(利用者)に対する前向きさが伺えるように思います。
2日目 福岡に移動し、宅老所「よりあい」の10周年記念セミナー「ぼけても普通に暮らしたい」
 ○よりあい主宰の下村恵美子さんの情熱あふれる10年の回顧録
○よりあい主宰の下村恵美子さんの情熱あふれる10年の回顧録
○相変わらずの三好春樹の愉快で活力あふれるトーク
○対談「老いて出会う、いのち」森崎和江&谷川俊太郎 進行役三好春樹
学生時代にちびっとかじった森崎さんの本とはまた印象が違い、不思議な新鮮さでした。いろいろと考えさせられた対談でした。
○詩とピアノのセッション 谷川俊太郎&賢作(親子)
初めて息子さんのピアノを聞きました。わあっもうちょっと聞きたいと思いましたが、残念ながらここはジャズライブショーではなかったのでした。本当にもりだくさんのライブショーでした。
3日目 その宅老所「よりあい」の見学です。昨日の下村さんの話の中にあった「ゆったり」が実践されている空間です。古い日本家屋の中で職員もそのお年寄りの側にあって一体化していました。何か我々見学者がドシドシと見学してまわるのが悪い気がするほどでした。(いや ホント申し訳ありませんでした。)しかし 私がやりたいグループホームはこの古い日本家屋です。
 バリアフリーな最新設備も良いかもしれませんが、私は古いものに落ち着きや安心感を・・・・(今は)そのことが優先されるべきだと思っています。俊太郎さん作詞の「よりあいのうた」の一節「いまはむかしで むかしはいまで」のまんまの生活感が実現できれば最高・・ではないでしょうか?
バリアフリーな最新設備も良いかもしれませんが、私は古いものに落ち着きや安心感を・・・・(今は)そのことが優先されるべきだと思っています。俊太郎さん作詞の「よりあいのうた」の一節「いまはむかしで むかしはいまで」のまんまの生活感が実現できれば最高・・ではないでしょうか?
しかし このようなツアーは初めての経験でした。
広島からの移動の新幹線の中で、たまたま隣り合わせた女性と話していたら、私などよりもずっと三好春樹について詳しくて、いろいろと教えてもらいながら、私の想いを話していました。博多に着く頃になって「実は私の夫は県知事なんです・・・・」と言われてビックリ。すっかり 親身に話しておりました。だからどうじゃ・・と言われて構えてしまうのは我が身のつたなさかもしれませんが、その後もすっかり相談など聞いてもらいました。このことも大きな経験でした。
10周年記念セミナーの昼食は近くの公園で食べたのですが、アフリカの太鼓を抱えたご夫婦のようなカップルが犬と戯れながら、練習というか、ただ遊んでなのか、たたく太鼓の音が静かにとても気持ちよく、響いていたのが印象的でした。
何だかバラバラで参加し、最後もバラバラで解散し、博多駅に向かいました。
後ろ髪を引かれながら、もっといろいろ話したかった・・・
某県知事夫人を始め、福井から参加の方、名古屋からの方、あの人たちは・・などと
思いをはせながら
さあて 明日から頑張るド・・・と日常に戻る覚悟を・・・
しながら帰路についたのでした- 2002年2月 介護夜汰話 読んでほしい本がある
新年早々、岩波書店から『元気がでる介護術』が出た。新聞社や大手の雑誌からの原稿依頼も次々に来る。発言の機会が増えるのは有難いことだが、広く一般の人たち向けに発言することには、いつも少し躊躇がある。
というのも、私が一番最初に訴えたいのは現場の介護職だからである。特にブリコラージュの読者に伝えたいからだ。 そこで、この間、新聞と他の雑誌に書いたもののうち、特に読者にも読んでほしいものを2本、“介護夜汰話"でとりあげることにした。
正月呆けで原稿が書けなかったので苦肉の策、という訳ではないので念のため。読みたいと思ったらすぐBBCへ。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
『おしっこの放物線』
『九八歳の妊娠』
家庭の育児力が低下している、といわれている。親による子への虐待が社会問題化している。しかし、では育児ロボットをつくればいいじゃないか、と言う人は一人もいない。育児の本質は人と人との関係だということをみんな知っているからだ。
ところが、老人介護についてはどうだろう。介護力が足りないなら、介護ロボットをつくればいい、と平気で言ったりする。介護は介護力の問題だとしか思われていないからだ。そんな考え方こそが「老人問題」を生み出してきたのだと私は考えている。老人問題は、老人世代に私たちの世代がどう関わったらよいのかという関係の問題なのだと私は思う。
老いとの関わりを学びたければ北欧に行くより日本のケアの実践から学べ、と私は主張してきた。自立した個人を価値あるものとする北欧や西欧と相互依存文化の日本とでは、老人から求められる関わり方が違っているからだ。
特に、近代的自我を前提とする北欧の方法論は、痴呆性老人のケアには向いていないように思う。 なぜなら、痴呆とは近代的自我が解体されて「生き物」という自然に回帰していくことなのだから。 私はかねてから「痴呆ケアを学びたいなら福岡へ行け」と言ってきた。
 今年10周年を迎えた「宅老所よりあい」と「第2よりあい」の実践から学ぶべきだ、と。「よりあい」は、通って泊まれて住める老人施設である。施設といっても福岡市の住宅街の一角にある借家である。
今年10周年を迎えた「宅老所よりあい」と「第2よりあい」の実践から学ぶべきだ、と。「よりあい」は、通って泊まれて住める老人施設である。施設といっても福岡市の住宅街の一角にある借家である。
第2よりあい代表の村瀬孝生さんは、利用者の女性(74歳)をめぐって同僚と張り合っている。そこへ風格のある元副社長の利用者が現れ、三角関係が四角関係に…という小説風のエピソードから始まるのが、村瀬さんが書いた『おしっこの放物線 老いと折り合う居場所づくり』(雲母書房)である。
 「私のおなかに、どうも赤ちゃんかおるごたる。産んでもよかろうか」と、入所者の女性から相談を受けたのは、よりあい代表の下村恵美子さん。これは下村さんが書いた『九八歳の妊娠』(同)のタイトルになったエピソード。下村さんはまじめな顔で「父親はだれ」とおばあちゃんに問いただすのだ。さて、どうなるか…。
「私のおなかに、どうも赤ちゃんかおるごたる。産んでもよかろうか」と、入所者の女性から相談を受けたのは、よりあい代表の下村恵美子さん。これは下村さんが書いた『九八歳の妊娠』(同)のタイトルになったエピソード。下村さんはまじめな顔で「父親はだれ」とおばあちゃんに問いただすのだ。さて、どうなるか…。
ここでは痴呆性老人は介護される対象ではなくてエロス的関係の主体であり、客体である。エロスとは男と女が互いを求めることだけではなくて、母と子が、さらには人間と人間が互いのことを求める人間関係の基本である。
老人ケアはエロス的世界の行為でもあるのだと私は思う。そのことが介護の現場からイキイキと表現される時代が来た。最近出版された2冊の本には日本の老人ケアを変えるヒントがある。【12月14日、西日本新聞に掲載】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
『〈母〉の根源を求めて』
「女性と聖なるもの」を副題及び原題としたこの本は、世界的知性をもった2人の女性の往復書簡である。難解でないはずがない。まして日本人である私にはキリスト教的伝統と文化に対する知識がないから、2人が何を巡って対立しているのかもよくわからない、といった始末である。
 しかし、もの凄いことを言っているのだということはわかる。なにしろクリステヴァは、手術のために入院するわが子に冷静でいられず、「一人の女性にとって、子どもの命よりも神聖なものはもはや何もない」という、母である自分と、哲学者である自分とを同時に語ろうとしているのである。
しかし、もの凄いことを言っているのだということはわかる。なにしろクリステヴァは、手術のために入院するわが子に冷静でいられず、「一人の女性にとって、子どもの命よりも神聖なものはもはや何もない」という、母である自分と、哲学者である自分とを同時に語ろうとしているのである。
こんなことは男の哲学者にはもちろん、フェミニストにもできないことだ。彼女らはフェミニズムの硬直性を批判し、「平等」を「概念において非常に男性的なものだ」とも言っている。 手紙はクレマンがアフリカで体験した、カトリックのミサの光景から始まる。そのミサの最中、黒人の女性信者が、次々とトランス状態に入り悲鳴をあげて倒れるのだ。
「女性の身体は社会の基準に完全には従わないのだ」とクレマンは言う。そしてヘーゲルが「女性は共同体社会のアイロニーである」と否定的に見たそれを、逆に女性のもつ聖なるものへと転化してみせるのである。 その聖なるものは、時にはキリスト教という共同体社会のなかでのマリア信仰として、時には魔女狩りの対象とされてきた。
その聖なるものから見た現代社会は、生命を最高の価値としながらも、「生命それ自体の生命」「問いの存在しない生命」を価値だと言っているにすぎない、と映るのだ。 ここで私は思うのだ。看護婦たちは戦略を間違えたのだと。男の医者に象徴される近代科学という共同体社会に、同じ近代科学で抵抗しようとしているのではないか、と。
その点、介護職は上手い。彼女らは「かわいそうじゃない」という科学にならない母性や、トランスに近い感情の世界で老人に関わる。聖なるものの強みを知っているのだJ 介護も人生も女にはかなわないと思う。そんな思いを拙著『男と女の老いかた講座』(ビジネス社)に書いた。
こちらは難解ではない。おっと自分の宣伝になった。この自己中心性は女性から学んだ。いや、、女性のは正確には母子中心性というべきだ。それが人類を生存させてきた愛というよりは愛着という聖なるものなのだ。
【『ケアマネジャー』(中央法規出版)2001年8月号に掲載】
『おしっこの放物線』
村瀬孝生著
雲母書房発行
定価 1,600円十税
『九八歳の妊娠』
下村恵美子[著]十谷川俊太郎[詩]
雲母書房発行
定価 1,800円十税
「〈母〉の根源を求めて」
ジュリア・クリステヴア/ カトリーヌ・クレマン 著
永田共子訳
光芒社 発行
定価 2,800円十税- 2002年1月 介護夜汰話 “筋トレ”ブームをどう思う
【2001年12月】を参照ください