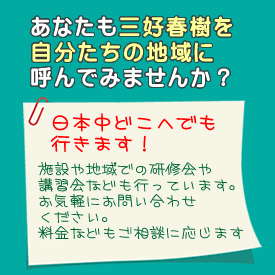●「投降のススメ」
経済優先、いじめ蔓延の日本社会よ / 君たちは包囲されている / 悪業非道を悔いて投降する者は /
経済よりいのち、弱者最優先の / 介護の現場に集合せよ
(三好春樹)
●「武漢日記」より
「一つの国が文明国家であるかどうかの基準は、高層ビルが多いとか、クルマが疾走しているとか、武器が進んでいるとか、軍隊が強いとか、科学技術が発達しているとか、芸術が多彩とか、さらに、派手なイベントができるとか、花火が豪華絢爛とか、おカネの力で世界を豪遊し、世界中のものを買いあさるとか、決してそうしたことがすべてではない。基準はただ一つしかない、それは弱者に接する態度である」
(方方)
● 介護夜汰話
- List
地下水脈 “かわいい”とは何か
芹沢俊介 VS 三好養樹 子どもの暴力・老人のボケ
地下水脈 「評価法」に老人を閉じこめるな
地下水脈 つくづく老人は強いと思った ~車イス阿波踊り参加記~
三好春樹 VS 木問富士雄(元湧愛園生活指導員)「年をとったら湧愛国へ行く」と言われるケア
地下水脈 倒錯から逃れるために ~「まごの手」の3周年によせて~
地下水脈 恥を知れ!
地下水脈 写真は現場の開きなおり
地下水脈 現場のリアリズム
三好春樹 自著を語る ~遠くまで行くんだ
『関係障害論』を解剖する 芹沢俊介 ~老いの尊厳を奪回する強靭な処方~
地下水脈 事なかれ主義になるなかれ ~老人介護Q&A~
医療の場と生活の場 [高口光子&三好春樹]
地下水脈 不思議なインフルエンザ報道 ~マスコミはやっと「特養」を発見したらしい~
地下水脈 僕らは人間をリアルに見ているだろうか ~『関係障害論』を書いたわけ~
地下水脈 あえて死こついて語らないわけ
地下水脈 介護計画賛成、MDS反対
- 1997 ~ 1996
-
- 1997.12月 “かわいい”とは何か
若い人が老人のことを「かわいい」なんて言い方をする風潮を“問題”だとする論調の新聞記事があった。この“かわいい”は介護職から広まったと私は思っている。
24歳で特養ホームに就職した23年前、すでに若い寮母が特定の老人や老人の言動、しぐさを“かわいい”と表現して、寮母長から注意されていた。経験豊かな人生の先輩に対しでかわいい”とはなんですか、という訳だ。ところが「寮母長さんのそういう生真面目なところが、かわいいですね」なんて言われて、寮母長ががく然としていたものである。
ま、感じるな、というのが無理な話ではある。実際私も、この“かわいい”はよく判るのである。これは老人介護の現場にいる人にとっては共通の感覚ではなかろうか。ところが、この“かわいい”を説明するのがむずかしい。ファンシーショップで若い人のセンスに合ったアクセサリーを“かわいい”なんて言ってるのとはちょっと違う。
なにしろ“かわいい”と言われてる老人は、ヨダレをたらしている小汚い爺さんだったり、施設で最も長谷川式痴呆スケールの点数の低いボケ婆さんだったりするのである。
◇
9月15日の「老人介護塾」で芹沢俊介氏の講演を聞いた。芹沢さんといえば私は、最初の評論集「宿命と表現」以来のファンで、家庭内暴力やオウム事件など、そう簡単には解けそうにない現代社会の問題に、深層から発言してくれる数少ない1人だと思っている。
「ある人が老いたな、と感じるのはどういうことだろうと考えると」と氏は言う。「それは“構え”がなくなった、ということのような気がするんです」と。老いの定義を身体や心理の客観的変化としてばかり習っている私たちには、こうした生活的な印象というところから老いを言語化する方法そのものが新鮮なのだが、私はそれを聞いて、あっと判ったことがあった。
ひとつは、オバタリアンとは何かということである。あれは、老いを待たずしで“構え”を手放してしまったということのようである。男のほうが社会的に“構え”を要求されることが多いために、オバタリアン的にはなりにくいということだろうか。
もうひとつが、あの“かわいい”とは何か、ということだ。構えが必要なときや場所でのそれは、たとえば、常識とか礼儀とか言われるようなものだろう。だがそれが過剰になると、私たちはそこに、何かの「意図」を感じたり、何かから強制されているような不自然さを感じとることになる。
老人や老人の言動を“かわいい”と言うのはこの意図や、何かから強制されているという感じがないことを言うのではないだろうか。つまりそれは、構えがなくなった状態であり、それが自然であると感じられることだ。
がしかし、である。男性のTさんは元銀行員で、誰に対しても、丁重な言葉使いを崩さなかった。つまり、“構え”を手放していないどころか、完全にパターン化さえしているのだが、若い寮母ぱ”かわいい”と言うのである。これはどうしてか。
構えそのものが長い時間たってその人の“自然”にまでなってしまった場合、それも“かわいい”と感じられるようである。それは意図や規範からの強制が習慣化され、Tさんに血肉化したかのようである。こうなると確かに“かわいい”のだ。
◇
構えを失って、だらしないと感じられるのが、オバタリアン。構えがなくなって、自然だと感じられるのが、かわいい老人。すると子どもがかわいいのは、まだ構えをもっていないからということになろうか。確かに、大人の表情をうかがいはじめ、構えができてくると、かわいくはなくなってくる。
◇
老いて構えを失ったときに、だらしないと回りに見えるか、それとも自然だと写るか、どちらに行くかを決めるものは果して何だろうか。私は、構えが既製品だったか手づくりだったかではないか、なんて考えている。既製品でもその人にピッタリだったらマルである。Tさんみたいに。
◇
「年をとってまで回りから“かわいい”と言われる老人にならねばならないとは」。これはある新聞での識者の嘆きのコメントである。大丈夫、回りから“かわいい”と言ってもらいたいなんて意図をもっているような人は決しで“かわいい”とは呼ばれないから。
- 1997.12月 芹沢俊介 VS 三好養樹 子どもの暴力・老人のボケ
9月15日、東京カンダパンセホールで老人介護塾が開催されました。 セミナーは芹沢俊介さん、三好春樹のそれぞれの講演に加えて福岡の宅老所よりあいの下村恵美子さんからの実践報告という濃い濃い内容でした。このセミナーの最後を飾った芹沢俊介・三好春樹対談を誌上再現バージョンでお届けします。
●司会(三井)芹沢さんのお話を三好さんにまとめていただいて、副題にもありますように「子どもと老人を通底する地下水脈」ということで、ここからは少しアンダーグラウンドの領域に入って話を進めていきたいと思います。
【質の問題が数量化される世界】
●三好 芹沢さんから、家族の変遷についてお話をうかがって、あっそうか、と思うことがいくつかありました。そのひとつが、どんな家族を形成するのかという選択の自由が拡がってきてるんだという言い方です。
農業社会に適応した多世代同居家族、そして工業社会に適応した単世代同居家族、さらに消費社会型ともいうべき個別同居家族というふうに芹沢さんから整理されて、個別同居では封建的な家からだけでなく、「性」からも自由になって、男と女というよりは個性と個性の組み合わせなんだ、したがって男と男も、女と女も、人とペットという組み合わせだって家族になりうるんだという話でした。
ああ、それが吉本ばななの世界なんだなと私は思いました。ばななさんの小説の登場人物って性的存在じゃないんですよ。『キッチン』の女装したお父さんが象徴的なんだけど、で、それは私には判らなかったんだけど、あ、自分の感覚はまだ消費社会まで行ってないんだ、工業社会にとどまっているんだろうなと思ったんです。
と同時に、これまで私たちは、老人ホーム入所とか、今日実践報告してもらった「宅老所よりあい」のようなグループホームというのは、家族が崩壊してやむなくそうなっているという捉え方をしてきたのですが、そうじゃなくて、これもひとつの選択すべき家族のあり方なんだということを教えてもらったように思います。
で、ここからが芹沢さんへの質問なんですけれど、封建制からも性からも自由になっていったのはすごくいいことだと思うんですよ。でも、自由になってきたという気はするのですけれども、ただその分人開が抽象的になっていないかという気がすごくするんです。
自分の個別性を侵犯されないように生きていけるようになったのはいいけれども、その個別性というのも個性と呼ぶには恥ずかしいようなちょっとした差異だったりね、ダッチが好きか、イブ・サンローランが好きかみたいなブランドが違うぐらいの差異でしかないんじゃないか。
性から自由になったということが、「男である」「女である」という生々しい具体性を失ってしまって、漂白されたみたいな気がしてあまり楽天的になれないんです。 老人介護の現場でも、かかわり方までマニュアル化していくみたいな世界がある。
たとえばケアプランなんてそうですね。「○○さん、戸外散歩」と方針を決めると伝票が下りてきて散歩の仕方までマニュアルになっているのですよ。 80m行って体調を聞くとか(笑い)、全部書いてあるみたいな世界とどうも対応してるような気がするのです。
そういう解放感のない自由みたいなものをどうしたらいいのだろう?ということを芹沢さんにお聞きしてみたいと思いました。
 芹沢俊介(せりざわしゅんすけ)
芹沢俊介(せりざわしゅんすけ)
1942年生まれの気鋭の評論家。犯罪や風俗への批評や分析をとおして、現代社会の病巣をえぐり、「人間」の暗部を透視するスリリングな評論を書き続けている。「「オウム現象」の解読』(筑摩書房)「「イエスの方舟」論』(筑摩文庫)『子ども問題』『現代〈子ども〉暴力論』(新版、春秋社)「いじめ時代の子どもたちへ」(共著、新潮社)このほか著書多数。
●芹沢 個別性というのは本来は量的な差異ではなくて質的な差異として捉えるのが筋だと思うのですね。「数値化されたこれがあなたです」と表わされた自分と自分自身が感じている自分の差異が出てきて、数値化された「これがあなただ」という言われ方に対して強い抵抗感が出てきていると思うのです。
それは、子ども問題で言えば登校拒否の子どもたちです。登校拒否は飛躍的な増え方をしていて、もう登校拒否をマイナスの視点で見ることはむずかしくなっています。 登校拒否の子どもたちというのは、量的な差異のなかに押し込められる息苦しさに対して、NOだ!、イヤだ!ということを言おうとしているような気がするんですね。
本来の質的な差異が量的な差異にいつのまにか置き換えられてしまっている。目指すべきは質的な差異なんだということなのではないでしょうか。
●三好 質を量にしてしまうといえば、老人ケアの世界だとADL評価、教育なら偏差値ですよね。僕は、偏差値そのものにはそんなに批判的ではないのです。成績なんていうものはもともとおかしなもので、数学の点数と国語の点数と音楽の点数と体育の点数をたして平均値を出すなんて何の意味もないじゃないですか。
でもまあ何か成績というものをつけなくてはいけないから、しょうがなくてそういうものを全部一緒にして偏差値を出している。僕はある種の合理的なやり方だと思うのです。先生の主観が入ったり、エコひいきが入ったりするのに比べればはるかに客観的な基準でスッキリしていると思う。
だけど、他にもいっぱいものさしがあるうちのこれは1本ですよということも同時に言わなければいけないと思う。
 三好春樹(みよしはるき)
三好春樹(みよしはるき)
老人ケアの世界でもたとえば、「宅老所よりあい」の下村恵美子さんたちの実践報告のように、個別の、自分がどう感じて、どういうドラマがあって…と、その物語をちゃんと語ることで聞いている人に感動を呼び起こすことができるのに、全部データにしたがる現実もあるわけです。
あるいはどういう介護をやったらいいのかマニュアルを示してくれ、と現場が求めてくるという側面がありますよね。 なんでヒトはそんなものを求めたがるんでしょうね?
【日常性から革命が起こっている】
●芹沢 一つはわれわれの社会が情報化されてきていると言いますかね、情報を抜きにしては社会が成り立っていかないというのが背景にあると思うのです。 いま三好さんの言われた偏差値も2つの方向で問題があると思います。点数がこうなっているということだけを言えばいいものを「だからおまえはここしか受けられないよ」と、それをベースにして指導されていっちゃう。
つまり指導の材料になることが問題の一つなんです。「どこを受験してもいいけれど、この点数だからそうとう気をつけないとあぶないよ」という言い方が正しいと思うのですが、そうじゃなくて「だからおまえはこっちはやめとけ」という指導の仕方になる。
あるいは、おれはとてもここは受からないからこのあたりにしておこうという自己規制として出てくる。そして、それがやがて学校間差別、偏差値差別みたいなものを生み出す。 もう一つの問題は、たとえば点数ばかりじゃということで「こころの教育」というのをやり始めたことです(笑い)。
ボランティアなどをやり始めるのですけれども、それも点数化されていくわけですよ。点数のなかに組み込まれていく。こころまで点数化されちゃう。学校の先生が主導してやっているとは思っていないのですよ。先ほどシステムと言いましたけれども、一方向に向かってある力が働いているわけですね。
これが権力なのですけれども、システムとしての権力が大きなところで左右しているのだと思います。 いま、偏差値をやめたら、今度は生徒も教員も不安になっちゃうでしょう。ほんとうは、その不安というのが大事な変化のきっかけになるはずなのですが、不安だから元へ戻せという流れが出てくる。
本来ならば質的な違いとして見えてくるものが全部量的な違いに変えられていく。量的な差異をある段階で差別化していく勣きがわれわれを含めて大衆を巻き込んで起きているような気がするんですよ。
●三好 老人介護の世界は、一人ひとりの関係ですから「質」の問題だと言われてQOLなどというコトバを医療の世界が使い始めたじゃないですか。すると、QOLを点数にするPTがいるのですよ。せっかく量じゃないよ、質だよと言っているのに「社会性を確保していると何点」とか言ってね。
いまの芹沢さんの話では、これは資本主義の必然だと言うのですけれども、資本主義をやめなくてはしょうがないのですかね。
●芹沢 このごろ不登校についてずっと考えています。うちも末の子が不登校になったのですが、学校をやめてものすごく元気になりました。 そういう現実を経験すると、子どもたちがシステムの外へ出始めた。システムに乗っていると、この道をまっすぐと黙々と歩いて行けばあそこへ到達するというのが分かるわけですね。それも数値として分かるわけですよね。
●三好 だいたい年収何百万のところへいけるとか…。
●芹沢 そう(笑い)。
●三好 不安もないけど希望もない。
●芹沢 希望もない。だから、すごく閉塞感があって息苦しい。学校へ行かなくなると、後は24時間は自分の時間ですからそれをどう使うかということから考え始めるわけですよ。とりあえず昼夜交代しようかとですね(笑い)。そういうステップを踏みながら自分なりのタイムスケジュールをつくり始めるのです。先行きの見えないことの良さというのか、自分で手にしたものしか確かなものはないのだという感覚を手にしていくのです。
不登校を見ていると、一つのきっかけ、家族自身がシステムのなかに組み込まれているあり方から変わっていくきっかけを登校拒否の子どもたちがつくっている。そういう意味ではとても革命的じゃないかという思いがしているのです。始まっているなと僕は感じるのです。
●三好 いろいろなところから革命が始まっている。日常的諸関係のなかから実は起っているということですか。
●芹沢 ええ、始まっている。
【幸福の条件と無条件】
●三好 私は、この歳でやっと子どもができていま3歳なのです。公園で、同世代の子どもと遊んでいたのですが、だんだん子どもがこなくなるのです。聞くと塾へ行っているという。日本語もしゃべれないくせに英語の塾に行くんですよ(笑い)。
教育環境が悪いからお父さんだけ残して自分たちはどこかへ移るという人までいるのです。夫婦仲良くしているのが一番いいじゃないか、子どもは遊ばせておけばいいじゃないかというのが僕らの常識なんだけれども、そういう常識がなくなっているんですね。
僕は、老人介護でも「専門性より常識、専門性と常識が対立した時はもう躊躇なく常識につけ」と言います。専門性は5年で変わる。10年で残っているものはほとんどない(笑い)。常識は、長い間の歴史で残ってきたのだから絶対確かだと言ってきたのだけれども、常識が残っていないとしたら、後はマニュアルしか頼るものはないなという、敗北感みたいなものを子どもを見てて思いましたね。
 三井ひろみ(みついひろみ)
三井ひろみ(みついひろみ)
1961年、宮城県生まれ。明治学院大学フランス文学科卒業後、文芸出版作品社に勤務。出産とともにフリー編集者。1994年、作家向井承子さんと出会い臓器移植問題を考え始め、現在は医療、いのち、こどものテーマに取り組む。
●司会(三井)むかしはお父さんが心臓発作で倒れたりすると、一家の大黒柱を失って家庭がガタガタッと崩れることがありました。いまはお父さんが倒れても保険があるから大丈夫とか、お父さんが単身赴任してもお母さんがいるから家庭の平和は維持できるとか、家庭の幸福の条件がむかしみたいなかたちでは崩れることがない。
そのことと子どもたちの無気力や家庭内暴力は関係があるのでしょうか? 老人は、暴力というかたちでは表面化しないで無気力・消極的な自殺になって病院へと、つまり家庭の外側に出ていっている。家庭の幸福の条件、幸福の価値観のもち方って何なのでしょうか?
●三好 私は、20数年前から老人介護の現場にいるですが、当時の老人は明治生まればかりでした。明治の人は強いと言いますがあれは嘘、すごい人ばかりが生き残っているからすごく見えただけで、まあほんとうにすごかったです。荒れる人は、明治の老人が消失すると共にいなくなりました。
最近の老人は自分自身との関係を失っているという気がしますね。むかしは怒る自分がいましたよ。自分は悪くない、周りが悪いと怒っている自分がいたのだけれども、いまは自分に自信を失っていて自分との関係を喪失して目がトロンとしてきてボケに至るというケースが膨大に増えてきましたね。
時代の価値観みたいなものとすごく関係があるという気がしますね。大正生まれの人は、戦後の価値観の転換をなんとか受け入れてきた人たちですね。子どもが親をみるのは当り前と思っていたのが裏切られたというので明治の人はワアーと怒ったのですけれども、大正以降の人は怒る対象がないのですね。
自分も個人主義でやってきたから怒りようがなくて、自閉してボケているというんじゃないかなという気がちょっとしているのです。 外に向かうべき暴力が老人の場合は内側、自分の側に向いている気がしてならない。だから子どもがまだ暴力を振るっているというのはまだそこに主体があるという感じがするのですけれども。
●芹沢 1960年代の後半から1970年代の前半にかけて教育家族と呼ばれる家族像が一般化したんですね。教育家族とは、一言で言えば子どもに高学歴を授けたいということが家族の唯一のテーマになった家族のあり方を言います。そうすると、現在の家庭をひっくるめてほとんどが教育家族なんですが、その条件は少しづつ変わってきています。
1980年に金属バット殺人事件がありました。彼が金属バットを振るった時点の良い子の条件は従順であること、成績が良いこと、良い学校に入ることだったのです。ところがこの間、東大出のお父さんが息子さんを金属バットで殺すという事件がありましたが(1996年11月)、この時点になると良い子の条件が変わってきているのです。
良い成績、良い学校というのはなくなって、登校と、従順さと、進学が良い子の3点セットなんです。 これだけ膨大に不登校が増えてきた現実のなかで、良い子そのものの期待が裏切られていく。 1960年代末から1970年代前半にかけて出現した教育家族が終わろうとしているのです。
つまり、わが子に高学歴を授けたいという発想は、内側から崩れる可能性をもうもっているのですね。
●司会(三井)良い老人の条件というのはあったのかしら?(笑い)。かつての家族は老人を邪魔にしながらも受け入れていたけれども、いまは受け入れるスペースが住居的にも精神的にもない。子どもと同じで、はじき出しているような気がする。そのあたりはどうなのでしょうか?
●三好 僕は最初から特別養護老人ホームという、世の中から見れば、吹き溜まり、人生の果て、うば捨て山みたいな世界にポツと入ったのですよ。そこで自分がやっている排泄ケア、入浴ケアの意味を単に社会の厄介者、家族が大変だから代わりにみてあげていますという消極的な位置づけではなくて、何か意味があるのだと思おうと思ったら条件がつけられないわけですよ。
もう、すごいじいさん、ばあさんがいるわけですから。僕は、老人というものは人間が完成していて、介助してもらったら手を合わせて「ありがとうございます」とか言って、お経を読んでいると思っていたのですよ(笑い)。エライ違いですからね。個性が煮つまっていくという世界ですよね(笑い)。もういるだけでいいという世界です。子どもにも、そういう「いるだけいい」という考えが必要だろうと思うのです。
●司会(三井)そうですね。どうですか、芹沢さん?「子ども論」のなかに、子どもって何だというと、つまり口をふさいで目の前にいる子を指差せばそれは子どもだっていうのが一つありますね。
●芹沢 子どもって何だと問われたときに、コトバとして答えるのは大変ですから、とりあえず口をつぐんで、ウロチョロしている子どもを指さして「あれが子どもだ」と言うのが一つの答えだと思うのです。 誰もがそこを通ったという意味で子どもというものを捉える視点が、一つあったなという感じがしています。
僕は「イノセンス」というコトバを与えているのです。どういうことかと言うと、つまり子どもというものは自分の生命、身体、性、家族、親から遺伝子まで全部ひっくるめて自己選択の余地がないのです。すべてのものを強制的に贈与されちゃったという、子どもの側からすれば全部が受動性だということです。
【存在そのもののもつ暴力性】
●芹沢 それは老いに対しても言えると思うのです。僕らは老いを望んでいるか。まあ望んでいる人もいるかもしれませんが、身体が不自由になっていくとか、痴呆になっていくとか、少しずつ記憶が虫喰い始めてということを僕は望んでいないと思うのです。
本人が希望する、希望しないにかかわらずやってくるものですから、老いもまた受動性であって、子どもと同じに老いもイノセンス、根源的な受動性というコトバで捉えることができるという気がするのです。ただ子どもは少しずつ根源的な受動性の段階を離れていきます。
あたかも自分が選んだかのように自分の身体や性や親やさまざまな与えられたものを引き受けていくということができるようになっていくわけですが、老いはそうではなくて自分自身を限りなく引き受けられなくなっていく。つまりどんどん受動性を深めていくのが老いの姿だと思えるのです。
●三好 子どもというのは純粋・無垢で、それがだんだん社会に交わっていくうちに悪くなるというのではなくて、もともと人間は暴力を内在しているということですか。
●芹沢 イノセンスという考え方は無垢という面ともう一つ、子どもは遺伝子から全部決められて書き込まれてきちゃいますから全くの無垢ではありえないわけです。無垢じゃないけれども、自分で選んでいないという意味ではやっぱり無垢なのだという捉え方を僕はしています。
だから子どもは無垢だと言われるとそうだと言いますし、子どもは無垢じゃないと言われてもそうだと僕は答えるのです。
●三好 そうか。僕らは老いとか障害は向こうから不可避的にやってくるものだという言い方をしてきたのですが、人間そのものが向こうからやってきたのですね。
●芹沢 はい。
●三好 それは暴力性を孕まざるえない。
●芹沢 はい。
●三好 それじゃあ、老人が荒れるのは当り前なんだ。
●芹沢 そう思います。最初は暴力で始まるみたいなことはあると思うのです。暴力というのは殴りかかるとかいった意味ではなくて、存在そのものが暴力的であるわけです。
●三好 親なんてそうですよね。それは実感としてよく分かる。
●芹沢 お互いがお互いを暴力だと見なす関係性というのは諸発の段階としてはものすごくノーマルだけれども、じゃあそのままでいいのかというとそうではないと思うのです。 どこかで折り合う地点を探し出していく。そういうことを少しずつ積み重ねることで、尊重すべき1個の他者として見ることができるようになる。それができれば良いかなと思うのですけれども。
●三好 いまのお話、他者との関係というよりも自分自身との関係というところに引きつけて聞いていました。こういう自分、こういう身体でこういう顔で、親の財産がこのくらいの家に生まれてという自分が現としている。思春期の頃、それを受け入れるのに、僕はかなり危うい橋をわたったという気がするのです。
男の子って大変だと思いません?女の子の方がサッーと自然に通っているような気がするのです。
●芹沢 女性は女性で危うい場所を通っていますよ。

●司会(三井)自分の身体の変化のときが一番危うかったですね。どういう家に生まれたとか、階級がどうのとかいう以前に母親の生き方と自分を重ね合わせたときに同じ女としての性(さが)つていうのかな?性的なことを否定したり、潔癖症になったり、または離人症の回復過程期みたいにいろんな人と関係を結ぶとか、そういう危うさを女の子は自分の身体で接して通っていくと思うのです。
●三好 女性は肉体のほうが先に反応しちゃうんだ。精神の問題を肉体で乗り切っていくという感じですね(爆笑)。
●芹沢 拒食・過食っていう問題はそうだと思う。
●三好 思春期の自分の引き受け方が、年をとった時にもう一回問われるという気が僕はものすごくするのです。向こうからやってきた老いに対してどうやって自分があきらめて引き受けていくのか、思春期にやったことを再生産しているような気がしているのです。
【「あきらめるよりないですよ」】
●芹沢 僕は整形というのにとても関心があって、一時期よく考えていたのですけれども(笑い)。たとえば、いま整形することに対して若い人たちはなんでもないですよね。 家庭内暴力の子どもたちは、自分の身体を受け入れられないんです。顔とか身長とか自分のあらゆるところに関心が向いている。
いまは美容整形もスンナリとできるわけで、ちょっと顔の部分をいじったりする、その程度で自分の身体とか顔を受け入れていくことができるんですね。それで何とかなっちゃうのだったらそれも悪くはないのではないか。赤塚不二夫の『天才バカボン』にものすごくいじわるな看護婦さんが出てくるのですが、整形するとすごく優しくなる(笑い)。
だけど、老いに関してはどうなんでしょうか。三好さんの言われる生活障害とか関係障害がもたらしたものだったらそれを外せば解決するかもしれないけれど、老いは自らの障害を押し進めていくという側面ももっていますね。その暴力性に対してはどうしていったらいいのかなとやはり思うのです。
その暴力性はどこから来るかははっきりしていて、誕生と同じところですよね。裏返せば、死の方から来るわけですけれども、その暴力性に対してどうやって逃れようか、どうやったらなるべくそこへ近づかないですむだろうかみたなことを考えている自分に気づくわけです。逃げたい。
●三好 リハビリの世界には「障害受容論」というものがあります。障害をどう受容していくか。最初はショック期、それから否認期、混乱期、それから受容期。最後に受容することによって価値観の変換が起きるというのです。つまり足を失ったことぐらいで自分の価値がなくなるわけではない、という新しい人間的な価値観に目覚める過程を障害受容論と言いまして、この障害受容過程を促進しなければいけないと言うのです。
だけどね、障害を負った人だけがより新しい人間的な価値観にめざめなければいけないというのはおかしな話でしょう。 僕は最初は障害受容論っておもしろいなと思ったのですが実体は全然違います。実際はあきらめるのです。「障害受容過程」なんてそんな美しいものではないです。あきらめなきゃいけないですよ、芹沢さん(笑い)。

●芹沢 自分は年をとらないんじゃないか、死なないんじゃないかと思う時ってあったんですね。でもある時そうじゃないということに気がついて愕然とするということがありました。でも、あきらめるかというとそうじゃないですね。そこまで自分のなかで捨て切っていないんです。もしそういう段階があるとすると何回も繰り返すだろうなという感じだったんです。
●三好 可逆的過程ですね。しょっちゅう戻るのです。ただ、固い人は老いに弱いと思います。狭い人間観をもっている人はキツイと思います。 村上セツというおばあさんがいました。いつも和歌をつくっているインテリでした。ストレッチャーに乗って風呂に行く老人を見て「あんなにだけはなりとうない」と言い続けていた人でした。
膝が痛くなってふつうの風呂に入れなくなりましたが、誰もストレッチャーで特殊浴槽に行こうとは言えないのです。私が「良くなればふつうのお風呂に入れると思うけれどもまだ膝が痛いから、あの風呂で我慢してくれませんか」と言うと、「いいよ」とスッと入るのです。
しかも、帰りには歌を歌いながら「こんないい風呂に初めて入った」と帰ってくるのです。たいしたものだなと思いました。それまでは自分を叱咤激励するつもりであんな風呂には入りたくないと言っていたのです。ところが状況が変わった、自分が歩けないとなったとたんそれをちゃんと受け入れましたね。受け入れたどころかこっちが気にしているのを知っていて気をつかってそういう言い方をしてくれたのです。
向こうからやってきた老いや障害とかに応じて、別の自分がパッと出現するような、変化しうる自分がいて、いまはこの若さがあってこういう状況で家族もいて、だから自分はこういう生活習慣でやっているけれども、状況が変わればまた形を変えますよみたいな可遡性がポイントだと僕は思うのです。自分というものの広さと柔らかさみたいなものでなんとか乗り切っていけないかなと思います。
【「何かをしない」という関わり方】
●司会(三井)子どもの問題、老人の問題、それから彼らを社会の突出者として暴力と感じている中間層だってかなりユラユラしていますよね。人と人との関係性、そういうところはいかがでしょうか。
●芹沢 僕はいま何かするということのなかに「何かをしない」ということを組み入れていかないといけない時期にきていると思うのです。つまりほっとけよ、ほっといたほうがいいんだ、という観点がどこかにないとすごくおっかないのですよ。
世の中が倫理、死生観をひっくるめて根本的な動揺期に入っていて、ことによったらわれわれが資本主義と考えていた時代が終わるかも知れないのです。一つの例として不登校の問題を出しましたけれども、たとえば、登校拒否の対策というのは、これまではなんとか学校へやらなくてはならないという考え方でやってきました。
でも、その子は家のなかでは自由にしていたのに、両親と話もできていたのに、登校させようと思って働きかけを始めると閉じこもって、家庭内暴力が起ってというふうになるわけです。これは対処をしたことによって悪くなったということなのですね。
三好さんのチューブを外しちゃえ、オムツを外しちゃえも同じだと思うのです。近代医療の専門家は問題を見つけて対処をしたわけですね。だけど、対処したことがさらに悪い状況をつくりだしている現状があらゆる場面で見えてきている。
地殻変動のなかで起きていることだから、既成の対処じゃ対応できなくなってきているのです。やみくもに対処していくというやり方は基本的にダメだと思うのです。
●三好「こころの教育」なんてまさしくそうですね。いま必要なのは「こころの教育」ではなくて教育の自己限定だと思うのです。むしろ手をひくことではないのか。教育のやるべき領域をもっと狭くするということを自らやることではないか。これは医療もいっしょです。
どうも私は子どもから老人介護の世界に至るまで無意識の世界がなくなっているというのかな、無意識が荒れている、そのツケがドンドン出てきているような気がしています。近代は、すべてのものに光をあてていきました。病気が治るようになったということもそういうことですね。
たいへんけっこうなことなんだけれども光が強烈な分、影も強いのです。光に眩惑されているものですから、僕らは暗いところが見えなくなっている気がしています。老いとか障害を見ないように見ないようにしてきた。もう光はいいのではないか。むしろ僕らの目を暗順応させていく。
暗いところに入ったら、最初は見えないけれどもその暗さに馴れるとだんだん見えるようになる、そういう目に僕らの目を変えていかなくてはいけないのではないか、という気がしています。 私は14歳の頃に『罪と罰』を読み、主人公のラスコーリニコフにすごく共感したのですが、象徴的に言うとラスコーリニコフにとってのソーニャが世の中から消えているような気がすごくするんです。
そういう意味では、老人介護の世界というのはソーニャがいっぱいいるおもしろい世界だという気がします。ソーニャが天使ではなく娼婦であったみたいに、俗っぽい天使みたいなのが、人間くさい天使がいっぱいいる世界だなという気がしています。
- 1997.11月 「評価法」に老人を閉じこめるな
拝復
Aさん。『生活障害論』のさっそくの感想、ありがとうございました。『関係障害論』に続いての刊行のため、私の健康への気遣いまでいただき恐縮です。 でも、6月には土日の生活リハ講座以外は仕事を入れない態勢を組みましたし、10年以上もしゃべり続けてきた内容でもあり、夜9時にはベッドに入るという日常生活を変えることなく原稿を書き終えました。
◇
『生活障害論』の前半の生活評価法で私が訴えたかったことは、Aさんに「徹底した個別性」と評価していただいたことに尽きます。各項目の評価を自由な記述式にしようという提案も、一人ひとりの生活の個別性を、評価する私たちの側の貧しい生活観のなかに閉じこめてしまわないためなのです。
多くの「生活評価法」が提案されていますが、そのほとんどが項目の数をどんどん増やし、その項目ごとに、どこかに○印をつけるという形式です。たとえば、本のなかで私が批判しているように、本来ADLの項目ではない「移動」が項目として登場します。そして、独歩、杖歩行、歩行器、車イスなどのどれか1つに○印をつけろ、というのです。
しかし、考えてもみればいいのです。ほんの少しでも在宅老人に関わったことのある人なら気がつかないはずがありません。私たちが関わらねばならないようなケ-スほど、こうした選択肢のどれにも当てはまらないということを。 たとえば、「いざり動作」なんてのが移動の項目の選択肢に入っていたのを見たことがありません。「四つ這い」も「膝歩き」もです。どこにも○をつけられないのです。
ところが、これまた私が批判していることですが、多くの評価法がそれを数量化することを目的にしているため、どこかに○をつけないと困ってしまうのだそうです。そこで彼らは無理やり、「いざり動作」を「車イス」に“匹敵”させてしまうというのです。おいおい、これじゃ“でっちあげ”じゃないの。
◇
やらねばならないのは逆のことです。どんなによくできた評価法であろうと、あるがままの老人の個別の生活を表現するために、評価法そのものを変えてしまえばいいのです。 食事、排泄、入浴という共通したADL項目に、その人だけにとって大切なものを“項目化”してしまおうという、「個別項目」なる空欄もそのひとつです。
さらに、月1回の入浴サービスという生活実態を、「全介助で行っている」ではなくて、「行っていない」の上に勝手に“月1回しか”と書き加えて○をする、なんてのもその一例です。
◇
それにしても、生活を評価するための評価法なのに、その評価法そのものが目的化され、かえってあるがままの生活が見えなくなるという倒錯はどうして起こるのでしょうか。 また、とうてい数字という一本の価値観に還元できるはずのない生々しい生活を、数量化せねばならぬと考える人がこんなに多いのはどういうことなんでしょうか。
人は、たとえば、立体を多方面から認知することの困難さから逃れるために、無理やり平面にしてみたり、さらには線分にまで倭小化して安心したいのでしょうか。だとすれば、数え切れないほどの「評価法」は、そうした私たちのどうにもダメな部分にお墨付きを与えるために生まれてきているとさえ思えてきます。
◇
ですから、この本のなかで提案した私の「ADL評価法」(無断複製歓迎)も、その形よりは、なぜその形なのかという根拠の方をこそ伝えたいのです。さらに、その形を個別の老いの生活の側が突き崩していく回路をこそつくりたいと思っているのです。
したがって、『生活障害論』の後半部分の、食事、排泄、入浴についての介護法の提起もまた、その方法論そのものよりは、なぜそうなのかを伝えたいと思っています。「評価法」と「生活実態」との関係は、「方法論」と「現場実践」にもそのまま当てはまるからです。
◇
さて、本のなかに出てくる“福田和子”は、出版の1ヵ月前に、時の人となりましたが、果たして何年後まで人々の記憶に残っているでしょうか。何しろこの本は、10年や15年は売れ続けるだろうとおこがましくも自負しているので、その点だけが心配です。
◇
私ぱいつまでも若々しくなんて思っていませんので、ちゃんと「年相応」に生活しています。どうか身体の心配はなさらぬよう。それよりも、老人のニーズに突き動かされるようにエネルギッシュに動きまわっておられるAさんこそどうかご自愛くださいますよう。
1997年秋、十勝にて 敬具
- 1997.10月 つくづく老人は強いと思った ~車イス阿波踊り参加記~
私ぱ“雨男”らしい。かつて、月に一度、訪問活動に伺っていた広島県沼隈町でも、その日はだいたい雨。でなければ、記録的寒さの日だったりして訪問活動を終えて福祉会館にたどり着くや、トイレに駆け込むなんてことが多かった。
北海道や九州で初めてセミナーを開催したときも、天変地異に見舞われるといった具合である。 徳島のケア付き阿波踊り「寝たきりになら連」も、これまでの4回のうち私が参加した2回が大雨。特に昨年は台風の真っただ中、雨のなかを車イスで行進し、その直後に大会自体が中止になったほどである。
それにもこりず、「今年も行きたい」と言いだしたのが、大阪市生野区在住の地木さん、89歳。それならということで、今年も「なにわ老人ケア研」のスタッフが大阪港からのツアーを組むことになった。車イスの老人4人を含む総勢11人のツアーである。
大阪港に見送りに来られた地木さんの娘さんは「去年より元気ですから今年はもっと踊れると思いますよ」とおっしゃる。う~ん、89歳になって“去年より元気”か…。しかし、私がもし家族だったら、これはどの状態の人を見も知らぬボランティアに託す勇気があるだろうか。
同じ生野区からは、84歳の石橋さんという女性も参加。こちらは訪問看護婦さん同行だが、もし私が担当だったらこのおばあさんを阿波踊りに誘う勇気があるだろうか。 あとの2人は、尼崎の特養ホーム園田苑からの樋口さん(86歳、女性)鶴田さん(76歳、男性)。う~む、私が施設長だったら、よりによってこの2人を徳島まで1泊2日の旅に出す勇気があるだろうか。
なにしろ、ハードな日程である。午前10時に大阪港を出港し昼に徳島着。実行委の人たちの迎えの車に分乗して、四国電力が提供してくれている“よんでんプラザ”で昼食、阿波踊りの受付を済ませ、ボランティアに手伝ってもらって着替え。全国からの参加者が集まって簡単に自己紹介した後、踊りの練習。さらに「新のんき連」の踊りを見学。
軽く腹ごしらえをして、いよいよ市役所前の演舞場へ。車イス43台、総勢150人近い“寝たきりになら連”は、見物客の拍手を浴びてさらに次の会場へ……! 夜の8時半から着替え、宿舎に着いて入浴。夕食は10時過ぎから始まり、舞台でまたひと踊り(!)して、日程終了は11時半である。
私は4人の老人たちが気になってしょうがないのだが、彼らはいたって元気である。そういえば、昼食・軽食・そして宴会のときも4人ともよく食べていた。これくらいでないと長生きできないよなあ。 そういえば、最初に参加したとき、雨のなかボランティアがバタバタ倒れた。ひどい下痢なのだ。昨夜食べたものの何かにあたったらしい。
“正露丸”を回し飲みして本番をもちこたえたのだが、同じものを食べたはずの車イスの老人たちはなんともないのである。いや、恐れ入った。 世間にはこうした老人たちを、患者だとか弱者だとかいって安静を強要したり、ただ自分の博愛主義の対象にしてしまう人たちがいっぱいいるが、一度でもこの“車イス阿波踊り”に出てくればそんな老人観は吹き飛んでしまうにちがいない。
今回は、遠路東京から15人、鹿児島からも4人参加した。もっと全国の大勢の人に体験してもらいたいと思うのだが、受け入れ体制にも限界がある。なにしろ一度来た人が“常連”になってしまうのだから。 今年の阿波踊り大会実行委員長の石川富士郎先生の言語機能の大幅な回復に驚かされたのも大きな喜びだった。
雨がほんの小雨だったことも。 来年こそは!と思う人は、早めに現地にお申込みを。
★「ねたきりになら連」事務局
徳島県阿南市新野町西馬場3-3
富士医院 事務長、久米秀昭さんへ
0884-36-2024
◇
「三好さんは外国に行かない主義じゃなかったんですか?」と何回か尋ねられた。 10月のカナダ・アメリカツアーのちらしを見た人からである。私は、北欧のような恵まれたところを見なきゃいけないのは政治家だと思っている。現場の人間は恵まれたところを見てもしかたがない。むしろシビアな条件のもとで、それでもこんなにやっているというところを見ればすぐに役立つではないか。
というわけで、日本国内のツアーばかりを呼びかけてきた。今回はクリスチャンが自発的にグループホームをつくり、そこに州政府から補助金をつけさせているという実践を見にゆく。それなら“民間デイ”と同じ発想でないか、というわけだ。 金と時間のある人はご一緒に。もちろん、東京と札幌発の「誠和園・よりあいツアー」もよろしく。
- 1997.10月 三好春樹 VS 木問富士雄(元湧愛園生活指導員)
「年をとったら湧愛国へ行く」と言われるケア 三好◆ まず木間さんの経歴から教えていただけますか。
木間◆ 中学を出てすぐ酪農をやりました。酪農で食えなくなって、建設会社に働きに出て、特養ホームの建築現場に行ったんです。事務長になる人が現場監督で来ていて、「福祉の道に入ったらどうだ、口をきいてやるから」と言われまして、それが特養に勤めるきっかけでした。
三好◆ 湧愛園ではないんですよね。
木間◆ 近くの町の特養ホームでした。そこで6年と2ヵ月お世話になりました。
三好◆ それで、自分の町に特養ができるので、そちらに移ろうと。そのとき、前のところが反面教師になったということですが…。
木間◆ そのホームは病院併設の特養でした。ですから、健康管理というと、看護婦が主体になるわけです。そんなことで、納得のいくケアができなかった、ということがありましたね。
三好◆ 医療的な管理主義ではない施設をつくろうと決意されて行かれたということですか。
木間◆ そうですね。遠藤さんという初代の園長になられる方が準備室長でした。特養に対する考え方が、私と共通するものがありました。具体的には網走管内でいちばんお年寄りの住みやすい施設をつくろうということでした。
三好◆ その発想はどこからきたのでしょうか。
木間◆ 職員は全部素人、平均年齢は40歳代。50歳代の人もいるんです。全職員が同じ方向にむかって協力しあっていける言葉が「お年寄りが住みやすいように」ということだったんですね。
【「立場かなくなる」なんてぱかなことは言わない】
三好◆ 関川夏央さんの『よい病院とはなにか』に出ていましたが、寮母さんの間では「鬼の指導員」と呼ばれたそうですね。
木間◆ いやア……。自分では仏のつもりでいますけれど(笑)。お年寄りが生活しやすい施設づくりが目標ですから、どうしてもお年寄り主体に考えます。そのためには妥協はしなかったですね。それが“鬼”になったのかな…。
三好◆ 職員とどういうことで意見が対立したんでしょうか。
木間◆ たとえば食事。私か廊下を歩いていたら下膳しているところだったのですが、見ると、味噌汁に手がついていないのす。本人がいらないといったから下げようとしていたんですね。「ほんとうにその人はほしくなかったのか」とか、そういうところは厳しかったですね。
三好◆ 生活の場にしていこうと思うと、もうひとつ、専門職の看護婦さんともむずかしかったでしょう。
木間◆ そうですね、3年で6人くらい代わりましたかね。
三好◆ 木間さんが辞めさせたというウワサもありますが(笑)。

木間◆ 特養では寮母が主体です。看護婦は寮母がどういう考え方でその人に接しているかということを理解して、専門的な立場からアドバイスしてもらわなければ困るということを、採用時に必ず話します。そのときは「わかりました」といってもらえるのですが、やはり……。
5時から引き継ぎなのですが、いつも30分くらい延びるのです。看護婦は配膳車の横を通って引き継ぎの場所に行って、10分も15分も待っているのです。看護婦としての仕事は終えて、また引き継ぎの時間も過ぎているわけですから、それについては何も言わないのですが、だけど、寮母が一生懸命食べさせて、下膳をしているところを素通りしてしまう神経。私は納得できないから、「どうしてそこを素通りして10分待ったのか、書いてください」と言っていました。
三好◆ で、そういうことが2回くらい続くと辞めていくと。
木間◆ だいたい辞めていきます(笑)。
三好◆ 看護士の木戸由幸さんが入ってきたのは何年目ですか。
木間◆ 4年目です。彼は精神病院にいたのですが、1年くらいかけて話をして引っ張ってきました。 彼は寮母とのつきあい方がうまいんですよ。それぞれの立場での主張がありますから、寮母代表と看護幟とでやりあっても平行線ですけれど、彼の場合は、その人の命に関わるわけではないからいいじゃないか、というような感じですね。
 ◆湧愛園の看護士、 木戸由幸さん
◆湧愛園の看護士、 木戸由幸さん
精神科にかかっている人がいました。その人に安定剤や眠剤を飲んでもらうのですが、そうするとぽ一つとしてしまうでしょう。それで寮母が、看護婦にも話をしないで薬をとめていて、10日も過ぎてから白状したということがありました。
そのとき、木戸さんは「あなたたちがそう考えてやったことであれば、それでいいだろう。ほんとうはそのほうがいいのだから」と言いましたね。自分の立場がなくなるなどというばかげたことは言わなかったですね。

三好◆ 寮母さん自身が判断して自立的にやる領域が増えていく、いざというときのために看護職がいればいいわけで、そういう意味では、木戸さんの対応は立派だと思いますね。そういうことって、ちょっとできないですよ。
【食事にストしスをもたせない】
三好◆ 私は洞爺湖での大会で木間さん、木戸さんに出会いました。当時の私は、リハビリより何より、まずベッドの足を切れと言っていたのですが、「うちは最初から切っている」と言うのです。これは一度行ってみなきゃと思って、それ以来毎年のようにお邪魔していますが、行くたびに発見があります。
湧愛園では食堂には5、6人くらいしか出ていなくて、他の人たちは部屋で丸いテーブルを囲んで食べているのです。真ん中にお櫃があって、味噌汁があって……と、そういう風景を見ると、かえって50人全員集まって食べているほうが収容所みたいで、部屋で食べているほうがはるかに自然な感じがしました。老人ホームでの職員とのトラブルというと、食事に関することが多いですね。
木間◆ そうです。食事に不満をもたせて、オムツのことを考えたり、行事のことを考えてもだめだと思うんです。 食事にストレスをもたせないということが、その他のことに大きく影響するような気がしてならないですね。
三好◆ 配膳や下膳など、調理の人も栄養士さんも、事務の人まで全員でやっていますよね。ご飯を食べられないときは、好きなものを買ってくるということを聞きましたけれど。
木間◆ その前に、ほんとうに食べないのか、その人に食べさせられる人がいるのか、いないのかを考えます。気にいった寮母だったら、食べさせることができたりしますから。
【夕/1コの制限こ芒始末書モノ】
三好◆ 湧愛園のベッドは低くて、柵がほとんどないですね。物をぶら下げるために柵があるということはあるけれど、降りる側にはペッド柵がない。落ちませんかと聞かれるでしょう?
木間◆ はい。落ちますけど下はカーペットですし、それで危なければキャスターをとったり、台だけにしたり、畳だけにしたりしています。
三好◆ 湧愛園のベッドの高さだとお尻から落ちますから危なくない。ベッドが低い、柵がないというだけでなく、古いベッドですよね。ギャッジなんてほとんど外れていますけれど、電動ベッドはないんですか。
木間◆ 1台もないです。半分くらいがギャッジ、あとは上げ下げできないベッドです。電動ベッド、エアマットもひとつもありません。機能的に片マヒであっても、座位をとって車イスに乗って食事ができれば、ギャッジで起こす必要もないですね。
三好◆ バアさんがベッドから降りて、ごそごそっと這って廊下に出てきて、ぱっとお尻をあげて廊下のソファーに座ってタバコを吸っているでしょう。ソファーの下は焼け焦げだらけ。他の施設の職員なら、始末書を書かされると言うでしょうね。
木間◆ 寝タバコ、布団の上だけはだめですが。でも、始末書というのは、焦げ跡にとるのではなく、3本吸っていたのを1本に減らした人から取るべきものだと思うんです。
三好◆ えっ? どういうことかな。
木間◆ 3本タバコを吸いたいというお年寄りに1本しか与えないという人に始末書を書いてもらうのであって、3本吸ってそれで焦げ跡をつくったからといって、始末書を書いてもらうことはないと思うんですね。 紋別のリハビリセンターから来た田中さんはタバコは吸ってはだめと言われていたんです。うちにきたら、タバコは吸うわ、晩酌もする。2年半で体重が十数kg増えました。(笑)
三好◆ 管理的な圧力はなかったですか。
木間◆ いろいろありました。公立の場合は、一職員がやろうとしてもなかなかできないですね。何かの力を借りないといけない。うちの場合は家族会の存在が大きかったですね。
自分の家族の状態が入所する前よりよくなったら、いちばんわかってくれるのは本人と家族です。 三好さんに湧愛園に来てもらったとき、初めて職員が「私たちのやってきたことはまちがいじゃなかったんだ」と言ってくれました。職員がそういう気になっだのと、家族会が認めてくれたので、管理社会での効率ということはわりとクリアできました。

◇木間富士雄(このまふじお)
お金がなかったのと、10人家族の生計維持のため進学を断念。中学卒業と同時に酪農業に従事する。農民運動(?)で第一次産業のしくみを知り失望。35歳のとき離農し、建築人夫として働く。2年後、縁あって法人施設に機能訓練員として就職。
福祉への夢は、開拓に打ち込んだ祖父母や、父との生活のなかから膨らんでいったのかもしれない。在任中は、「くやしかったら仕事で見返せ!」が口ぐせ。現在は、町社協理事。趣味の書道に専念している。
【記録の誤字・脱字OK!】
三好◆ ツアーに参加した寮母さんが、「湧愛園では洗腸したことがないんだそうです。便秘の人がいないんだって」と言うのです。私もびっくりしました。 便秘をしないというのは心身ともに落ちついていることだし、遠慮なく排泄介助をお願いできるということです。ぼけ老人の問題行動の原因のほとんどは便秘ですから、それがないというのはすごいな。
木間◆ 便秘がちな老人をつくると担当寮母の恥、というのかな。どうしようもないという場合は1日おきとか、3日おきに薬が出ますが、担当寮母が、自分の勤務に出るのにあわせて使います。自分がいるときにちゃんと排泄があるように、ということですね。
でも、リンゴをすって毎日食べさせる。バナナを食べさせる。冷たい牛乳をのませる。毎日腹部マッサージをやる。そういうことをしたから便が出るというものでもなくて、三好さんが言われるように便秘は精神的なものに負うところが大きいと思います。
三好◆ ケース会議を開いて、この人のニーズは何かというようなやり方はしているんですか。
木間◆ 3ヵ月を基本として、寮母の担当替えをしています。その3ヵ月ごとの目標しか設定しません。その時々にあわせていく、というのでしょうか。たとえば、医者はタバコを禁止したけれども、本人は吸いたがっている。そうしたら、どうすればタバコを吸わせてあげられるかということが目標になります。
食欲が落ちたとき、カロリーがどうこうではなく、どんなものなら好んで食べてくれるだろうかを考える、それでいいんです。 そして、そのことについて記録もするわけです。観察・記録することで自分が高まっていくと思っています。お年寄り一人ひとりについてちゃんと書くこと。記録を書きづらい人、書かなくてもいい人もあるのですが、でも、1人の人に対して1週間も10日も記録しないということはなかったですね。
三好◆ 当時は、「字を書かなくていいと思って寮母になったのに」なんて人もいました。よく書かせましたね。
木間◆ 誤字脱字、文章の長い・短いなど、直したことはないです。言わんとしていることがわかればいいんです。
【指導員日誌はいらない】
三好◆ 指導員は何年やっていたのですか。
木間◆ 12年くらいでしょうか。
三好◆ 講演での木間語録に、「おれは指導員を十何年やっているけれど、一度も指導員日誌を書いたことがねえ」というのがありますね。老人のことは全部頭のなかに入っているということでしたが、ある意味で新鮮なショックでした。
木間◆ 必要がないと思うんです。行動記録を書いたって、どうにもなりませんよ。
三好◆ 監査でひっかかるでしょう。
木間◆ 寮母の関わりに対して調理はどう関わっているか、看護士はどういうアドバイスをしているか、全部知って調整してます。それが指導貝の仕事だから、寮母日誌や委員会の記録簿に書き込むときはあります。それが指導員日誌に代わるものである。それでずっとつっぱり通しましたね。
三好◆ 現場の人が書いたもののなかに指導員の指導が反映されているはずということですね。 人員の確保に関しては、町が協力してくれているという話を聞きますが。
木間◆ うちは北海道で2番目くらいに恵まれています。

三好◆ 朝食から夕食終わるまで、日勤者を8人は確保できているでしょう。でも、それは公的に決められた数に何人かパートを雇えばいいというくらいですよね。それはどの金額になっていないし、東京や横浜なんかだったら都や市の定員増でそれくらいはいるはずです。
職員が大変だから人数を増やそうというかたちで補助するから、人数が増えたってお茶をのんでいるとか、あるいは何とか療法という役にたたないことをやる職員が増えるだけで、肝心の生活支援は全然変わらない。 湧愛園は、朝食から夕食の間は職員を8人確保してくれ、だったらいいケアをするというとても具体的な形で人員を確保してきてるんですね。そういうかたちで人を増やしているから意味があるんですね。
木間◆ 15年間、オムツ使用者が20%を超えたことはないです。オムツ代、水道料、ベッド代、エアマット代など、そういうものを人件費に回せます。代替要員も確保できます。予算がよけいついているから代替要員を確保できるというのではなく、そういう経営努力もしているから維持していける、ということになると思うのです。
三好◆ 上湧別町の高齢者に対するアンケートで「将来身体が不自由になったらどうするか」という質問に対して、「湧愛園に入る」という回答が60%以上あったそうですね。ふつう3%ぐらいですよ。
木間◆ いろいろなことがあったけれども、町民の60%以上の人が、「年をとったら湧愛園に行きたい」と認めてくださった。うれしかったですね。
三好◆ 新しい施設は最初の1年間くらい、木間さんを指導員として呼ぶと、施設がちがってくると思いますね。
今日はどうもありがとうございました。
- 1997.8-9月 倒錯から逃れるために
~「まごの手」の3周年によせて~ 「専門家のいっぱいいる病院で寝たきりをつくってきたのだから、生活の場でシロウトが寝たきり脱出の仕事をしようじゃないか」。
12年前から開催してきた「生活リハビリ講座」の受講者に対して、私はそうしゃべってきた。“煽っている”といわれるのも無理ないが、むしろ、「治療モデル」に対抗して「生活モデル」を創りあげたいと考えていた自分自身へのアジテーションだったのだと思う。
ところが、実際にそんな場をつくりたい、という人が続々現れてきた。私自身は、それができるにしても、5年先、10年先のこと、くらいに考えていたのだが、こともあろうに、私の話を真に受けて、“宅老所”をつくろうというのである。
「生活リハビリクラブ」(川崎)を始めた下山名月さん、金田由美子さん、「宅老所よりあい」(福岡)の下村恵美子さん、そして「まごの手」のスタッフもまた、そうした、“とんでもない人々”である。
もちろんこれは“煽られて”始められるものではない。ましてや続けられるものではない。私のような、コトバだけの人間と違って、彼らは大胆に、かつ着実に、老人を寝たきりから脱出させ、ボケ老人を落ち着かせ、イキイキさせる実践を積み重ねてきた。
なぜやれるのか、なぜ続けられるのか。それは、この仕事そのもの、老人にこうした場で関わることそのものがじつにおもしろいからだ、と思う。 社会を変えるため、とか制度・政策をよくするために、なんて目的のためではあるまい。そうした目的のため、となると、老人ケアという仕事や、老人そのものが、“手段”にされてしまう恐れがあるからだ。
私たちにとってはあくまで、目の前の1人の老人こそが目的で、制度・政策の方が手段なのだから。たとえ不備で不完全な制度・政策であったとしても。 じつは、そうした実践こそが、制度や政策をよく動かすのである。行政が補助金を出す例も増えてきたし、大阪では府や市の議員さんたちがこうした民間デイに注目し、全府下に創り出そうという構想すらあるという。
それらは「ゴールドプラン」だの「介護保険」なんかに、“乗っかかろう”なんていう受け身で虫のいいやり方とはまったく別の、生活の場のニーズに応えるという実践のなかから生まれてきた”生きた制度・政策”になるにちがいない。 “制度・政策を創り出す実践”こそが生き続ける。
“制度・政策があるからやる”という仕事は、じつは最初から「死産」させられているのである。 制度・政策を使うな、と言っているのではない。その制度・政策をちゃんと目の前の一人ひとりの老人と家族のニーズに応えていくために役立てているか、と問いたいのだ。目的と手段が逆立ちしてはいないか、と。
制度・政策に恵まれていない、「まごの手」のような民間デイこそが、こうした倒錯から逃れられるのだとしたら、人間というのはどうにも仕方のないものではないか。
- 1997.8-9月 恥を知れ!
5月15日、「エキスパートナース」誌と共催で、看護学会の日程と場所に合わせる形で「看護と介護」をテーマにしたシンポジウムを神戸で開催した。私はいつもと同じようにケース報告をし持論を述べたつもりだが、看護婦を中心とした参加者からはかなり不評をかってしまった。
ま、看護協会の総会なんかにやってくるような“体制派”の婦長連中が中心だから、不評なのも当然かも知れないが、シンポジストの1人が川島みどりさんだったこともあって、私としては、もう少し頭の柔らかい人たちが集まるのではないかと考えていた。
当然ながら、私自身も、大きな違和を感じざるをえなかった。まずこれは以前から気になっていることなのだが、一人ひとりの看護婦さんとなると、じつにいい仕事をしていて、話だって通じ合うのだが、「看護婦」という集合名詞として自分たちを語るやいなや、きわめて自己保身的になるのはいったいどういうことなのだろうか。
たとえば、看護婦の世界の内側ではその体質に対して痛烈に批判している人でも、同じ批判が外からなされた途端、“看護婦共同幻想”の側について弁護をはじめるのである。「ほんとうの看護はそうじゃない」なんてムキになって言い返してくる。
どこにあるのかわからない“ほんとうの看護”なんかじゃなくて、現実の個別の看護について語っているだけなんだけどなあ。もちろん、1つの職種に属しているときにその“共同幻想”に自分を一体化して排他的になってしまう心理はわからぬではない。
医者だってPTだってOTだって同じようなものだろうが、看護婦ほどひどくはない。シンポジウムに同席していた高口光子さんも私も、他職種からのPT批判は大好きだ。だって、いろいろな考えのPTがいて、内部で論争しているなんてのは、外部からもとっくにお見通しなのだから、内部の情報を公開してしまえばいいのである。
だいたい、同じ批判を内部の者がしたら、「そうだ、そうだ」と言っておいて、外部から言うと、「それはちがう」と弁護する神経が理解できないよ。もう1つ、私に違和を感じさせたのは、彼女らの医者に対する対抗心の強さである。自分たちは医者による被抑圧者だという意識の強烈さである。
私は、医者の理不尽な権力性や、非合理性としか言いようのない医療界の“身分差別”については当然批判してきたし、それを是正しようとする運動に異をはさむつもりはまったくない。しかし、医者を権力者、そして自分たちをその被害者というふうにだけ位置づけてしまうことには、私は大いなる違和と危険性を感じざるをえない。そうした発言が会場でウケるからこそ危険だと思う。
こうした、自分たちを“被害者”“被抑圧者”として位置づけてしまうことと、先の排他的共同幻想がいっしょになると、自分たちは人に喜ばれる大変いい仕事をしており、外から批判されるようなこと、たとえば手足を抑制したり、オムツを強要したりしていることは、すべて医者が悪いのだ、という自己中心的心性となって表れてしまうのである。いや、ほんとうにそういう雰囲気そのものだったのだ。
ここで私は、本誌の前々号のインタビューで語った自分のコトバを思い出していた。たとえ社会最下層で差別と抑圧を受けている階級といえども、自分たちを被抑圧者だ、と規定したところから、じつはそれさえ強力な権力に転化してしまうんです。うーむ、まったくこの通りではないか。
シンポジウムで川島みどりさんは、「医者が看護婦に対してやってきたことを、再び介護職に対してするのではないかと心配している」旨のことをおっしゃっていたが、なんのことはない、現場では、看護婦が他の職種に対して、医者がやってきたとおりの権力的対応をしているのである。
たとえば、それは当日の会場からの発言にもみられた。「病院から訪問看護に出てみたら、“資格のないヘルパー”が床ずれの処置までしているのを見て、唖然とした」なんて発言である。おいおい、いまごろやっと地域に初めて出てきてその言いぐさはなんだ。私たちはずーつと、医者が診てもくれず、訪問看護なんて望めもしなかったころから、やむなく家族と共に床ずれの手当だって、何だってやってきたのだ。
自分たち“資格のある者”が目もくれなかったくせしてよく言えるものである。“資格のないヘルパー”が、やらねばならぬ状況に自分たちが追い込んでいたことを反省して、「よく頑張ってきましたねえ、大変だったでしょう」と一言言えないのか!
そう言えない体質こそ、看護の側か批判してきた、資格をカサに着た医者の体質とそっくり同じではないか。私は過去への反省もこめて言うが、反権力もまた権力なのである。上一下という人間関係に必要以上にこだわっているという点では、権力側よりも権力的だと言っていい。
川島先生。私はこう思うんですよ。権力を無力化するのは権力に対抗することからは生まれないと。必要なのは、権力の有無という上下関係をズラすことなのだ。その関係にとらわれてしまわないことなのだ。さもないと、反権力の側は権力に似てしまう。だって、上下関係にとらわれ、そのなかでしか自分というものを規定できないのだから当然である。
だから、他職種のヘルパーや寮母との関係も上下関係としてしか反応できなくなっているのである。口では「横の関係」と言ってもである。他職種との付き合い方の一番下手な職種は何か、という話題では、いつも看護婦が筆頭にあげられる。ま、看護婦は数も多いしどんなチームにも必ず参加して大切な役割をもっているから目立つのかもしれないけれど。
医者も下手だ。おそらく看護婦が集まって同じテーマで話せば、医者が一番下手、ということになるだろうが、じつは多くの職種は、ちょうど看護婦が医者を見るように、看護婦を見ているのだということは知っておいたほうがいい。
という状況にもかかわらず、介護保険や“ケアプラン”をめぐって、これに乗っかかって自分たちの職種の権力性を維持、拡大しようとする醜い動きがある。医師の一部の人たちは、市町村のケアプランの立案を、医師会にやらせるようにと訴えている。やってみるがいい。ケアの何たるかも知らないし、知ろうともしない医者が他の職種に恥をさらすだけだから。
看護婦のなかにも、「ケアプランは看護婦こそが」と言う人がいる。考えてもみよ、“体位変換”は知っていても「寝返り介助」ひとつできない安静看護婦が、どれだけ老人を生活の主体にするケアを邪魔してきたか。いま、ケアを担える職種も資格もどこにもありはしない。
無資格だが経験を積み重ねている介護職や、資格はあってもやっと最近ケアの世界に入ってきた専門職らが、ワイワイ、ガヤガヤいっしょに試行錯誤するなかで、かろうじて“ケア”と言えるものが出現するかしないか、いまのところ日本のどこでもそんなものである。
それを「医師に」とか「看護婦に」とか、「介護福祉士に」なんて言う連中にはただ、「恥を知れ」とだけ言えばいい。彼らの頭には老人のことより自分たちの職益しかないらしい。あさましいことだ。私たちは、自分たちの地位や権限を高めようなんて思わない。もちろん、結果として認められることはそれでいいのだが、地位と権限のために何かしようとは思わない。
その理由の1つは、「自分たちの地位向上→老人(患者)の利益」という2段論法はウソであることがわかったからだ。医師会も看護協会もその他あらゆる圧力団体がそういう論理を使ってきたが、「老人(患者)の利益」が、自分たちの利益のための方便であることは明白である。
もう1つの理由は、老いと関わってきたからである。地位も名誉も権限も、障害や老いの現場からは何の意昧もないかのように思われる。いやむしろ、老いや障害を生きるのに邪魔なのではないか、と私たちは現場で毎日感じているからだ。
私たちは、老人に関わることで、職種エゴやセコいプライドにこだわるあさましい人たちとは、はるかに遠いところに来ているのである。シンポジストの1人だった徳永進さんはこう言われた。「威張った方の負け、なんですよ」と。いいコトバである。
- 1997.7月 写真は現場の開きなおり
5月11日、岡山で「口から食べるから元気になる」をテーマにした研修会が開かれた。参加者は全国から集まり、会場に入りきれずホールにモニターが設けられ、当日参加はお断わりという状態だった。本誌の読者は当日行ってもどうにかなると思っている人が多いから、入れなかった人もあるのではないか。
参加者の大半が歯科医と歯科衛生士さん。聞いてみれば、多くの人が老人施設はもちろん、在宅の老人の歯科医療と口腔ケア、さらには終末のケアにまで参加しているという。しかも当日の私以外の講師が、在宅老人の口腔ケアに関しては名の知れた人ばかりだったから、多くの人がつめかけるのも道理なのである。
まず歯科医の岡崎好秀氏(本誌55号の講演録参照)が“尊師”と呼ぶ、横浜の歯科医、加藤武彦氏、茅ヶ崎で在宅歯科診療をすすめている黒岩恭子氏、そして、山梨で活動する歯科衛生士の牛山京子氏である。牛山さんの発表は、口腔ケアの道具まで、その場の工夫で手づくりしてしまうという、文字どおりの“ブリコラージュ”であった。
[綿棒なんか使わないで歯ブラシで]と訴える彼女の実践は、「口腔安静ケア」を「口腔生活ケア」に転換しようとするもののように思えた。歯科の世界では、論文でも学会の発表でも、数値だけでなく、実際の口腔の様子を写真で見せることがよく行われている。歯や歯ぐきの様子を実際に見てもらって、その変化を示そうというものである。
だが、加藤先生や黒岩先生の写真は口の中だけにとどまらない。食事の姿勢はもちろん、表情、家のなかの様子、人間関係までスライドで写し出す。私たちが、学会でのデータばかりの発表に対抗して、老人の表情を写して発表しはじめたのは十数年前である。だって、いくらいい実践でも、データになんかならないのだから、これはもう現場の開きなおりである。
病院から岡山県庁に入ったばかりのPTの安永道生さんを広島に呼んでの講演会だったと思う。当時、地域に入り込んだばかりで、新鮮な驚きとやる気に溢れていただろう彼は、今のようなホロリとさせる話ではなく、すごいエネルギーと気迫で実践報告を始めた。
家のなかに閉じこもっていた障害老人が機能訓練教室に出てきてどう変わっていったかを、スライドで見せるのである。「ほら、こんなに笑顔が出るようになって!」と説明してくれるのだが、なにしろ、35ミリレンズで遠くから撮っているので顔なんか見えやしないのである。でも、みんなうなずき、共感して聞いたものである。だって説明する人がほんとにうれしそうなんだもの。
それを、歯科医や歯科衛生士がやっているのである。虫歯治療や入れ歯づくりという技術でちゃんと通用する人たちが、一文にもならない、生活の治癒や笑顔づくり、人間関係づくりにまで関わっているのだ。うれしくなってしまう。
ケース報告では、適切な入れ歯や口腔のケアによって、歩行が可能になったケースまであった。口の機能が下肢の機能を良くしたわけではない。もちろん、奥歯でかみしめることが筋力やバランスに影響することはあるにせよ、これはそうした直接の効果ではないだろう。
私たちは、老人は身体の障害で寝たきりになるのではなく、関係障害、それも自分自身との関係の障害によって寝たきりになるのだと訴えてきた。こんな自分が生きていてもつまらない、と思ってしまうのである。だから、こんなマヒした身体でもう一度生きていこう、という気持ちになれば、手や足の廃用性が原因の機能低下はすぐにでも良くなるはずだ。
私たちはそういう主体の再建の仕事を、食事、排泄、入浴という生活ケアをとおして行おうとしてきた。特に、ときに、やり方によってはあっという間に主体を崩壊させてしまう排泄ケアについては「オムツ外し学会」を開くなどして新しい排泄ケアを提案してきた。
下の口だけでなく、上の口のほうも、やり方によっては、あっという間に主体を崩壊させてしまう。入院すると「口にしますか、胃にしますか」といきなり経管栄養を前提にした話を始めるような介護がそれである。こうした“口から食べる”という最も基本的な人間の社会性を根こそぎ奪ってしまうことに抗議して始めたのが「チューブ外し学会」だった。
そしてこれに共感してくれたのが、栄養士さんや歯科医師、歯科衛生士の人たちだった。寮母は下から、彼(女)らは上から、PTは手足から、それぞれ入口は違うが、みんなそこから入って老人の主体の再建という共通の目的に向かう。すでに「第2回チューブ外し学会」の日程も決まった(1月25日、福岡市)。そこでまた、“上”と“下”の合流をしましょう。
- 1997.6月 現場のリアリズム
ブリコラージュの別冊に『生活ケア13人の発言』という本がある。広島での第2回オムツ外し学会の演題発表をまとめたものだ。そのなかに、保健婦とヘルパーの連名で発表されたものがある。北海道の端野町の2人が、かけ合い漫才のように語った実践報告である。
そのヘルパーの山本政子さんが亡くなった。昨年末のことである。 52歳、ガンだったという。一昨年、端野町で「オムツ外し学会・北海道版」を開く、と言いだし、講師の人選や諸準備を中心になってこなしていた。昨年9月の学会は大成功で、私たちは東京からの「湧愛園ツアー」の人たちと共に、バスの窓から手を振ったのだが、それが終の別れとなった。
聞けば、学会の終わった数日後、倒れるようにして入院したという。学会を仕切っている彼女はハツラツとしていて、とても痛みに耐えているようには思えなかった。懇親会では“南京玉すだれ”を演じてみせ、会場を沸かせたが、あれは、どんなに面白くないことがあっても、老人の前に出るとそれを見せないで笑顔になる、“介護職精神”だったのかもしれない、と思う。
山形の宅老所“あべさん家”にカンパするために販売していた手づくりのリースも、痛みで眠れない夜につくったものだともお聞きした。いま思うと、彼女は、自分の寿命を知っていたかのように、生き急いでいた。彼女のホームヘルパー歴は18年、私はその後半にお付き合いさせていただいた。
初めて北海道で開いたセミナーに、5月の連休だというのに峠が雪で通行不能になるなかを遠路札幌まで、車で来てくれたのが最初の出会いだった。以降、金曜の夜の夜行バスで、保健婦の菊池恭子さんと2人でビールを飲みつつ札幌に出、生活リハビリ講座のAからDまでを全て受講してもらった。帰りもまたビール付きの夜行バスで、月曜からそのまま仕事なんてこともあったらしい。
講座での彼女は印象的だった。受講後は必ず、ケースの相談に来た。「受講料と交通費のモトを取らなきや」と言っていた。そう、彼女はリアリストだった。習ったことは町に帰って月曜からすぐに実践するほどだった。「閉じこもり症候群のままで老人を元気にさせようとしても無理、まず散歩に出よう」と言えば、さっそく老人を散歩に連れだした。
だが、歩行器も車イスも雪にめりこんで動かない。そこで、手づくりのソリを取りつける。先日、雪祭りに行くと、運営本部に、車イスがズラリと用意されていた。前輪に不要になったスキー板の前の部分を取り付けたものだ。いまではあたりまえになっているが山本さんは、雪のなかに障害老人を連れ出すという実践のさきがけだった。
「座ってふんばるから排便できる」と講義すれば、さっそく、自慢のご主人が手づくりした穴あきイスを家にもちこんで試してみる。『言われたとおりにやったら、いっぱい便が出ました。写真取って送りましょうか』との電話は、さすがにお断りしたが、東京での実践報告では、イスに座った老人の肛門から太い便がまさに出つつある後ろ姿のスライドがスクリーンに映し出され、科学的で上品にまとまった発表しか見たことのない都会の参加者のド肝を抜いた。
後ろ姿とはいえ、排泄中の老人の写真を撮らせてくれ、なんて頼むのは非常識だと思うのがふつうだが、家族も本人も笑って許してくれるような雰囲気を、彼女は確かにもっていた。訓練教室のメンバーのバス旅行での話だ。リウマチの女性が小用を催した。ヒザが曲がらず洋式の便器にしか座れない人だ。
だが行った先の施設には和式のトイレしかない。何か代用品はないかと探したが、そんなものはまわりにあるはずもない。やむなく山本さんは、自分が和式トイレに中腰でしゃがみこみ、そのヒザの上に座ってもらって、目的を達したという。名づけで“人間便座”。
予算がない、人手が足りないと嘆くより前に、山本さんは、介護のやり方を変えることで2人分も3人分もの仕事をした。厚生省が悪い、社会資源が少ないと訴えるより前に、山本さんは、まず自分自身を“社会資源”にした。これこそ現場の姿勢、現場の論理だと、私は思う。
それは「政治の問題」だとか「資本主義の矛盾」などと、したり顔で語って、現場の“いま、ここ”にはなにも提起できない“正義派”の人たちとは対極にあるものだ。私自身も、「近代の問題だ」などと分析することでいい気になってしまっていることがときたまあるが、そうした自分の観念性への歯止めとしても、彼女を永く記憶のなかにとどめておきたいと思う。
- 1997.6月 三好春樹 自著を語る ~遠くまで行くんだ
◆いよいよ、三好さんの「生活リハビリ講座」の内容が、ビデオと本で出されることになりました。その第一弾が、『関係障害論』ですが、シリーズの最初にこれをもってきたのはどうしてでしょう。
●一見難解そうな題の本からはじめたのは、一つは自分自身に対する“気合い”のようなものですね。もう一つは、介護現場がこうした関係論を切実に求めているはずだ、という確信です。
5年前なら無理だったと思うんですが、いろんな分野でいろんな人が老いにかかわるようになって、いろんな体験をし、発見をしていると思うんですけれど、それらの意味づけのためには、どうしても必要で、どこにもなかったものが「関係障害論」という視点だろうと思います。
◆読んでびっくりしました。三好春樹は現場の人にこんなことをしゃべってるのかと。
●むずかしいですか?
◆いやむずかしくはないんです。でもいきなり自分の留置場体験に、哲学者フーコーの権力論ですからね。驚きますよ。
●僕自身、この本を書いていくなかでフーコーにもう一度触れて、やっと長年のマルクス的思考から自由になれたという気がしています。 老人介護の置かれている社会的状況や、介護そのものを捉えるときに、一部の人たちや新聞をはじめとするジャーナリストのなかに、マルクス的思考が抜き難くあるんです。
それは、権力というものが我々の外にあって、それが悪の根源だから、これを批判したり、倒さなければ老人介護は良くならないという根強い信仰みたいなものです。 この人たちはたとえば、痴呆性老人からちょっと抵抗されたのに対して介護職が暴力をふるったことさえ、厚生省の決めた人員規準のせいだ、なんて言うんですよ。冗談じゃない。でも古い思考の枠だとそうなるんですね。
それに対してフーコーは、権力は外側にあるんじゃない、と言いました。私たちがいつでも権力になるんです。そして、権力は必ず堕落するんです。だれもこの権力のアミの目からは逃れられないんです。
たとえ社会最下層で差別と抑圧を受けている階級といえども、自分たちを被抑圧者だ、と規定したところから、じつはそれさえ強力な権力に転化してしまうんです。だからこそ、“被差別者の側に立っている”と自称するジャーナリストの文章も態度もあんなに強迫的になるんです。
それに対して、いい医療職や、いい介護職というのは、目の前の老人に対して、自分をいかに権力的にしないか、堕落しないか、ということを態度としてやってきました。それが「いい医者」とか「いいヘルパーさん」というふうに評価されてきているんですけれど、どうもそれが、人格とか人間性の問題としてしか語られていないんです。
で、人格や人間性の素晴らしい人はそれでいいとして、私のように人格はひずんでいるし、人間性も怪しいという者でも、少しはそうなれる、つまり、権力的にできるだけならないで、堕落しない方法をつくれないかと思ったんですよ。
◆そうか。それが最後の「関係づくりのリハビリ」という章に結論的に出てくる、老人にとって私たちが、“自然”であるかのように感じられるようなかかわり方が理想じゃないか、ということになる訳ですね。
●それが結論かと言われると、なんだそんなことか、ということになるんだけど、“自然”という表現で言おうとしたことは、逆に“不自然なもの”をどれだけ私たちが抱えこんでいるかということで、それから自分自身を脱却させるというか、解毒していく具体的な作業がいるんだということなんですよね。
たとえばそれは、専門職に不可欠といわれる「客観的で冷静に観察する」なんていうかかわり方のもっている問題点を明らかにすることでなくちゃならないんです。これは、この本ではまだ十分じゃなくて、次回の「生活障害学」でもう少し詳しくやろうと思っています。
さらに、ケースワークの原則といわれている「受容の原則」とか「非審判的態度」なんてのは一見、権力的でなくかかわることのように見えるんだけど、じつは、ほんとうはすごく権力的じゃないのかっていう疑いを私はもっているんですよ。
東大出の進歩主義者のお父さんが、心理療法士に言われたとおりに、子の暴力に対して無抵抗で耐えた挙げ句に我が子を殺しちゃった事件がありましたね。マスコミは父親に同情的だけど、私はむしろ、子のほうが耐えられなかっ5ただろうな、と思いますね。ああいう親の態度というのは、一番隠れた形のとんでもない権力じゃないか、と思うんです。
◆まだ、なぐり返したりする方が、よほどそこに人間同士の共感があるんじゃないかと思いますよね。なぐりゃいいってもんじゃないけど。
●そうした、優しさみたいなものに隠された権力というのを、じつはフーコーは最後の権力だというふうに言っているように思うんです。フーコーは「福祉国家」というのを同じ理由で批判しているんです。それは、“優しい看守のいる監獄”じゃないか、と言っている気がするんですね。
私たちは、私たちが考えている以上に遠くまで行こうとしているんだと思います。「福祉」を超えてね。
- 1997.6月 『関係障害論』を解剖する 芹沢俊介
~老いの尊厳を奪回する強靭な処方~ 人間は関係の産物である。したがって関係が損なわれれば、その人の人間性に多かれ少なかれマイナスの結果が表れる。ところで吉本隆明の言い方を借りると、老いればみな身障者になる。つまり関係が損なわれる。
三好春樹はこの関係が損なわれる事態を関係障害という言葉でとらえている。だれもが老いを避けられないとすれば、関係障害もまた不可避である。だとすれば問題はどの程度の関係障害を負っているかということになる。適切にも関係障害の深さという言葉を三好春樹は使っている。
話は突如飛躍するが、50代も半ばに達すると怖いものがなくなると思っていた。ところが現実にはまったく逆で怖いものだらけになった。たぶん生きるということのすべてにわたって、無心ではいられなくなってきたからに違いない。
無心でいられなくなった理由を問われると言葉に詰まるが、あえて答を探せば、若いときには無縁に映っていた老いの姿が思いがけないほど身近にちらつき出したからというところに落ち着く。自分を意味あるもの、有償的なものに向かわせようという動機は迫りくる老いに対する一種の武装なのであり、同時に老いそのものの現れだということに気づいたのはごく最近のことである。
だが老いはだれにも例外なく訪れる自然過程である以上、武装は無効でもある。したがってまた当然ながら老いはその人の責任ではない。では寝たきり、オムツ、呆け、ベッドへの縛りつけといった状態もまた老いの自然過程がもたらすものなのだろうか。言い換えれば老い行くことの必然的な結果なのであろうか。
私たちが老いに否定的にならざるをえないのは老いのこういう姿をイメージしているからである。もし必然であるなら老いを嫌悪し、恐れ、目を背けたくなるのも無理はないであろう。たとえだれもがそうなりうる老いの姿であるにしてもだ。
三好春樹のこの本は、老いに対するこうした貧しいそれゆえに根暗い考え方を関係障害という観点から根底的に覆す論理をじつに朗らかに軽やかに展開する。以下にポイントを摘記してみる。
第1に寝たきり、呆け、オムツ、ベッドへの縛りつけといった私たちが判断しての屈辱的な事態が、老い(身障者)の必然などでは決してなく、老いにとっても同様の屈辱的な事態であること。
第2にこの屈辱的な事態は関係障害によってつくり出されたものであること。
第3にそうした屈辱的な事態に反発したり適応したりしつつ、さらに屈辱的な事態であることを自覚できないという屈辱的な事態に陥つて行く場合 --- オムツをさせられた老人は尿意を感じなくなり、尿が出たか否かもわからなくなる --- 関係の障害がさらに深まっているというふうに認識すべきであること。
第4にこのような関係障害の深まりには、老いと接する人すべてが関与している可能性があると考えていくべきであること。とりわけこれまで第三者とみなされ、免罪されてきた病院や老人ホームのあり方、医者や看護婦、介護者、リハビリのセラピストなどの専門家すべてが、その権力性によって関係障害の深まりに関与している可能性が高いこと。
第5に老いの自然過程として現れた関係障害、つまり第一次的な関係障害は復元不可能である場合がほとんどであること、したがって老いにかかわる人が成すべきことはこの復元不可能性を踏まえて、それ以上の関係障害の深まりを生み出さないように注意しつつ、これまでその人を支えていた関係に代わりうるその人にとって肯定的な関係を新たに構築することを全力でもって援助すること。
これが三好春樹の老いの関係障害論の構想である。見事である。なぜ見事であるかといえば、老いの尊厳ある生活の復活に、だれかの犠牲を求めていないからである。こうした関係障害の認識から新たな関係性の構築までの過程に、老いの人間としての尊厳の取り戻しからはじまり、家族、地域社会の再生、老いにかかわる人たちや施設、制度の再生にいたる基本的かつ実践的な処方がこめられているからである。
主に専門家に付随する権力性の解体を求めるのは、それが老いを悲惨で屈辱的な状態に縛りつけている最大の要因の一つを形成している事実がある以上当然である。私たちがいくらか言及してきた子ども問題に三好の関係障害論を引き寄せてみる。
たとえば登校拒否は、学校という社会のもたらした関係障害、教育家族(家庭の唯一の主題が子どもの高学歴化であるような家族。この家族の教育家族化は我が国において1960年代後半から70年代前半にかけて成立した)がもたらした関係障害が、子どもにとって処理不能になった状態であり、こうした危機に子どもたちが自己(自己関係性)を守るために取ったノーマルな反応であるという理解が可能になるだろう。
だとすればここからごく自然に家庭内暴力やひきこもりは、寝たきりや呆けやオムツ、ベッドへの縛りつけなどの老いの関係障害の深まりに対応しているという理解が得られよう。すなわち家族、病院などの権力性が老いに加える関係の解体(暴力)の生み出した必然的な反応は、登校拒否の二次反応、つまり登校拒否というその子にとっての関係障害の必然性を承認できない親や学校や周囲の権力性が加える有形無形の登校刺激(暴力)のつくり出した必然的な関係障害の深まりであるというように。
三好春樹の提唱する関係障害論は、私たちが苦闘してきた権力問題、暴力問題の解体にも強力な援軍になってくれることが確認できる。
芹沢俊介 せりざわしゅんすけ
1942年生まれの気鋭の評論家。
犯罪や風俗への批評や分析をとおして、現代社会の病巣をえぐり、「人間」の暗部を透視するスリリングな評論を書き続けている。『「オウム現象」の解読』(筑摩書房)『「イエスの方舟」論』(筑摩文庫)『子ども問題』『現代<子ども>暴力論』(新版、春秋社)『いじめ時代の子どもたちへ』(共著、新潮社)このほか著書多数。
- 1997.5月 事なかれ主義になるなかれ ~老人介護Q&A~
【Q】 特養ホームの指導員です。私は寮母たちに、老人には敬語を使うように指導しています。でも、三好さんが「正義の味方につける薬」や「関係障害論」の後書きで書かれていることも、大変良く判るのです。矛盾してますよね。でも、放っておくとどんどん馴れ馴れしくなってしまうので、しかたなくそう言うんです。三好さんならどうしますか。
【A】 その気持ちはよく判ります。今号の高口光子さんとの対談でもそんな話が出ましたし、何人かの人からそんな声を聞きました。 ある町のケースワーカーも、「今度来られたヘルパーさんが母に慣れ慣れしいコトバを使うのでどうにかしてくれ」という苦情を家族から受けることがあるそうです。
研修会に行けば、偉い先生が「老人の人権を大切に」「老人には敬語を」なんて言いますし、家族からのクレームもないほうがいいですから、「敬語を使え」と指導する気持ちも判らないではありません。なかには「○○様」なんて呼ばせてるところもありますからね。
ケース報告で「患者様」って言ってるのを聞いたことがありますよ。「様」をつけるくらいなら「患者」っていう呼び方のほうを変えたほうがいいと思うんですがね。急性期ならともかく、患(わずら)った者、というのはその人の一面でしかないんですから。
でもちょっと考えてみてください。こうした指導方法は、「事なかれ主義」ではないでしょうか。なぜなら問題は、それほど近しい関係になってもいないのに親しそうなコトバを使ったことにあるからです。つまり、その人の状況判断がまちがっているのです。
特養ホームの4人部屋を思い出してみます。人って右側のベッドの中田さんを私は「中田のバッちゃん」と呼んでいました。本人も自分のことを『バッちゃん』と言うんです。そう呼ばれると一番うれしそうでした。でも、ちょっと真面目な話をするときや、誕生会みたいな「公式の場」では「中田さん」と呼んでいました。
一度、「中田のバッちゃん元気かア」と言いながら部屋に入っていったら、家族が面会に来られていてあわてて謝りました。家族の前では「中田さん」ですよね。 もっともこの家族の方は「こんな大変な婆さんをそんなに親身にしていただいて、「バッちゃん」でちっともかまいません」と言ってくれましたけどね。確かに大変な人でしたけどね。
もちろん家族は施設に対して弱い立場ですから異議は唱えにくいということが多いですから、こうしたコトバを全て真に受けるようでは困りますが、この家族に関してはそうではなかったと思いますね。それは判りますよ。気になるなら誰か施設外の人、例えばボランティアとか福祉事務所の人から本心を聞いてもらうといいと思います。
右の窓側の熊田トキさんは、私も他の職員も一貫して「熊田さん」と呼んでいました。でも寮母さんで1人だけ「トキさん」と呼ぶ人がいました。若い寮母さんで、熊田さんは彼女のことを孫娘に重ねて見ているようで、それが許されるちょっと特別な関係でした。
左の窓側の、かなり深い呆けのあった武田さんは「センセー」と呼んでいました。元学校の先生でした。私のことは「教え子」だったり介護職だったりしました。左手前の山田マキエさんは化粧を欠かさない社交的な人でした。この方は、もう1人山田さんがいたので「山田マキエさん」とか「マキエさん」と呼んでいました。
ときどき冷やかすときには「マキちゃん」で、そう呼ぶと少女みたいに恥ずかしがって「やめんさい」と言いましたが、満更でもないようすで、後でアメ玉を2~3個、握らせたりしました。つまり、親し気に呼んでいい人間関係と、呼んではいけない人間関係があるのです。なぜなら私たちは、単一の『アイデンティティ』なんてものを持っているのではなくて、いろんな人間関係の中の「関係の束(たば)」として存在しているからです。
親し気に呼んでいい場面と、呼んではいけない場面があるのです。なぜなら、私たちはいろんな場面で自分を使い分けている多面的存在だからです。もし、現場の人たちを指導しなければならないとしたら、こうした関係の場面をちゃんと判断して、コトバを使いこなせるような指導でなければならないと思います。
「馴れ馴れしいコトバを使うな」ではなくて、「あなたと○○さんの人間関係はまだそれほど親しくないのだから、もう少していねいな言葉のほうがいいと思うよ」という具合にです。コトバを統一してしまう画一的な事なかれ主義では、私たちの状況判断能力はますます退化していくばかりですから。
- 1997.5月 医療の場と生活の場 [高口光子&三好春樹]
◆三好 高口光子さんは、1995年に病院のPT科長からシルバー日吉の寮母長に転身されたわけですが、病院という場と、ぼくらが生活の場と呼んでいる特別養護老人ホーム(あるいは在宅や老健も)では、相当雰囲気が違うと思うんです。そのへんで感じたことはありますか。
◆高口 病院では、「~ねばならない」という意識が、いわゆるプロ意識が高いといわれる人ほど強いんですね。 たとえば点滴でも、患者さんがすごく嫌がって外す、仕方がないからしばる。本来、点滴というものは患者さんを元気にするものだったはずなのに、嫌がる患者さんに点滴しつづけることによって、結局は患者さんの元気をなくしてしまった。
でも、そこを「医師の処方なのだから」「これが私の仕事なのよ」というところで折り合いをつけないと、どうしようもない。ほんとうは「患者さんのため」「家族のため」というはずだったのに、真面目になればなるほど、「~ねばならない」になってしまう。
◆三好 老人ホームに来るとどうですか。「~ねばならない」はない?
◆高口 ないですね(笑)。 もちろん、けがをさせてはいけないとか、失礼なことはしちゃいけないということはあります。でも、それはケアだからということではなくて、常識ですから。 疾患を治癒させるという絶対的使命があるときは、たしかに行き当たりばったりは困るでしょうね。
症状を観察し、過去にどういう経緯があって、いまどうなのだということを知っておかないといけない。それは医療人として必要な態度だと思うんです。 だけど、このお年寄りに今日一日気楽に過ごしてもらいたいというとき、行き当たりばったり以外何もないじゃないか、というのかな。
いま対座している私が見て、私が触れて、その私がすること、それしかないというのか……。 ただ、気をつけなければいけないのは、仕事だから、時間も人数も限られているわけで、一般的な業務としての効率化ということはどこかで意識しておかないと、寮母たちの言葉でいえば「回りきれない」ということはあるんですね。そこはある程度調整はいると思う。
【テンポのちがいを受け入れる土壌】
◆高口 仕事のリズム、テンポがバラバラなんです。シャカシャカと仕事をこなしていく寮母もいるし、あちこちにひっかかっている寮母もいる。家族との話を切れずに30分も立ち話をしているとか、だいたい毎回言うことは決まっているお年寄りに、やっぱり同じように毎回ひっかかっているとか、病院なら許されないことです。

でも、寮母は平気でひっかかります。それをまた、まわりも受け入れている。食事どきの大変さはみんな知ってるのに、まったく別個のことをしている人がいる。また、他の寮母もそれに対して腹がたつとか、注意しようとか、それを変えようということはないのね。
◆三好 同じ職種というよりも、人間みな個性が違うのだからというほうが強いのかな。
◆高口 そう、そう。さぼりというとらえ方を基本的にしていないんです。
◆三好 病院ではマイナス部分と見られていることをむしろプラスだと思っている。これはおもしろいですね。 だけど、他の特養が全部そうかというと、決してそうじゃない。シルバー日吉は特殊だと思うんです。
◆高口 私は、一般的な特養がどうかということはわかりませんが、ただ、病院でやりたくてもやらせてもらえなかったことに、生きいきとして取り組んでいる自分が、いまはありますね。そういうこと以外に、やはり施設長の方針だとか、お年寄りがつくる雰囲気だとか、なにより一人ひとりの職員の思いの総体的なかたちがシルバー日吉をつくっているんでしょうね…。
【ことばは関係のなかで発せられる】
◆三好 病院との違いに話を戻すと、言葉づかいなどもだいぶ違うでしょう。
◆高口 違います、びっくりしましたね。お年寄りに向かっで“エツちゃん"“しのリン”ですからね(笑)。それも大きい声で。 もっとびっくりしたのは、それを受け入れる雰囲気があることです。私は“エツちゃん"“しのリン”が決していいとは思いません。
私が呼んでも雰囲気にそぐわないし、お年寄りも受け入れないと思うから、私は呼べないのです。でも、そう呼べる寮母がいる。雰囲気にもあっていて、お年寄りも受け入れているんです。

◆三好“しのリン”といわれたジイさんはどうしてる?
◆高ロ ニヤニヤッとしたり、ヘラヘラしたりする(笑)。でも、きっと私か呼んでも彼はヘラヘラしたり、ニヤニヤッとすることはないでしょう。
◆三好 けっこう悪口とか、きずつけるようなことを言うでしょう、本人の目の前で。
◆高ロ ハハハ(笑)。言いますね。 たとえば、むちゃくちゃ忙しいときに、ウンコを失敗されたりすると、「どうせウンコするんなら、もうちょっとあとからしてくれりゃ、いいのに」「なんでこんなことするん?!」とか言いますね。病院ではそんなことは、ナイチングール精神からして決して言っちゃいけない(笑)。
だけど、お年寄りも、「ウンコもらしたら怒られて当然」というのが、どこかにあるわけです。そこを寮母が、「大変でございましたわね。汚されてしまいましたねエ。お片付けしましょうね」と言うほうがおかしいですよ。「まあ、きたなかー」というほうが、お年寄りも「すまんじゃったな」とか、受け入れているんですね。
あとで、お年寄りが私のほうに怒ってきたりすることももちろんあります。あの寮母は、わしがおもらししたときに文句を言いながら替えた。けしからん、と言われたときは対応しないといけない。それで寮母に、おもらしは誰よりも本人が気にしているのだから、あまり言うてやるなと言いますよね。そうすると、まわりにいる寮母が、「そりゃあ、腹たつわ。なんか一言いうちゃらんな」というわけです(笑)。
◆三好 それって、職員じゃなくて、ほとんど嫁さんだよね。
◆高口 ただ、それは、軽率に対応しているということと、紙一重ですよね。 お年寄りがそれで恥をかかされたと思えば、それはプロとしてハズレなんですよ。そこは、ちゃんと気づいてもらわないといけないと考えています。 紙一重の“紙”がはがれてしまうと、私有物になってくるわけです。
かわいいマスコットとか、何を言ってもいいジイさんとか、やつ当たりの道具になってはいけないわけで、たとえば世話女房が、「稼ぎの少ない亭主がいまごろ帰ってきやがって」とかいうでしょう。そのとき、姑さんが、「あんまり言いすぎると男は働かなくなるよ」とちょっと言うことで、微妙にバランスをとる役目というのかな(笑)。
◆三好 ほう、高口姑説!いや、世話女房という表現はおもしろいですね。介護現場のそういう猥雑さを外から見て批判する人は多いんですよ。人権意識が低い、敬語を使えとかいう。それに対してぼくはずっと反発してきたんです。 介護現場のその猥雑さをどこで擁護するかというと、いまの高口さんの言葉がすごくヒントになりますね。
たとえば、専門的でなければいけないとか、福祉の心がなければいけないという考え方は、老人とケアする私たちの関係はあくまで社会的関係なのだというところから出発しているわけです。社会的関係というのは、最初の話でいえば「~ねばならない」ということですよ。
ぼくも社会的関係だと思います。だって、家族関係ではないもの。直接ではないけれども金をもらって、契約をしている関係だから社会的関係なのだけれど、それだけでかかわっ-ていたら、老人は生きいきしないよね。
【社会的関係を超える「能力」】
◆三好 いいケアをやっているところは社会的関係を越えてしまって、ほとんど身内みたいな、馴れ馴れしい世界に入っていくんですね。高口さんは、世話女房という言い方をしたけれど、これは疑似家族じゃないかという気がするんです。
社会的関係であることはまちがいないんです。それは基本的に変えられないけれど、社会的関係という枠をもっと広げて、家族的領域みたいなところまで入り込んでいっちゃう。だから、言葉もぞんざいになるし、悪口もいう。人間関係が近しくなって、生活を共有していくと、そこへ入り込んでいくものだと思うんです。
◆高口 病院では処方を超えることをしてはいけないわけです。時間内で精一杯患者さんとつきあうことは認められるのだけれど、時間外、たとえば帰りがけに家まで薬を届けるとか、外来の患者さんを出勤時にお連れするとかは、許されないという雰囲気です。
でも、特養はそういうことはあまりないんですね。秋田県の萬生苑で、自分の仕事が終わって、お年寄りと一杯飲みにいくという話を聞きました。それは、仕事のあと一杯飲みにいく相手がたまたまお年寄りだったということだから、支払いはワリカン。それは一見、職業を越えているようであり、職業を内包しているようである。
 ○高口光子(たかぐちみつこ)
○高口光子(たかぐちみつこ)
PT。熊本市の特養シルバー日吉の生活ケア主任。老人病院のPT科長だった彼女がなにを血迷ったか、寮母に転職し介護の世界へ。講演でのエキセントリックな言葉が彼女の持ち味だが、じつはとても倫理観のある真面目なひとなのかもしれない。良妻賢母といううわさもある。正月の朝日新聞に紹介されたことで年齢が明らかにされてしまったと、くやしがっている
私は、なぜか素直にそういうことができにくいんですよ。私は、自宅にお年寄りの家族から電話がかかってきたりするのも苦手なんですが、彼女たちは抵抗がないですね。私と彼女たちの決定的なちがいだと感じました。
◆三好 ぼくも、そういう能力はあまりないと思っています。だけど、それが老人を生きいきさせるということはあるんですね。さきほど疑似家族と言いましたが、家族であるかのような関係にまで入りこんでいける、これは「能力」だと思うんです。 社会的関係なのだけれど、家族的関係にまで入り込んでしまう能力、相手にのめりこんでしまう能力、というのかな。
◆高口 ぽんと相手の懐に入り込める能力、これは訓練や教育を越えてあるものなのかな。少なくとも自分としては、意識しないとできないような気がしますね。
◆三好 意識してやってもダメなんだと思う。相手は受け入れない。たとえば痴呆性老人はそうでしょう。こちらが「~ねばならない」というかたちでかかわっていたら、絶対表情がゆるまないものね。アドリブ的にその場で、その人のニーズが直感的にわかって動いたときには、うまくいくということはあるけれども、「今日あの人はこうだから、こういうことしてやろう」なんて思ってかかわったら、まずダメですよね。たぶんそういうことだと思う。
◆高口 そこですごくうまくいったという職員に「なぜそうしたの? その根拠はなに?その方法論の裏付けは?」と聞いても、言えないんですね。そういう方法論の整理なんていうことは、全く別個の人たちの仕事なのだろうと思いますね。
【ファインプレーを喜ぶ特養、嫌がる病院】
◆高口 そういう行き当たりばったり的なことが、医療の世界ではなかったかというと、そうでもないような気がするんです。たとえば、チューブをしている患者さんに、「経口摂取してみよう」とか言い出す看護婦さんはいるわけです。たまたま経口摂取したら食べた。だから、これからは経口摂取しよう。そこからの展開はものすごく的確です。
何をいつ食べたか、それが便としてどう排泄されたかというようなことは明確にされていくんです。 でも、症例検討会などで、なぜその人に食べさせようと思ったのかと質問しても、答がないんです。 2人になったときに「ほんとのとこ、どうなんですか」と聞いてみると、「食べたそうな気がしたのよ」(笑)。
ファインプレーは、練習してできるものじゃないでしょう。体力をつくったり、日頃の練習があったり、たくさんの試合経験があるなかで、ぽんと出てくるものだと思うんです。
◆三好 それが試合の流れを変えたり、人の運命を変えたりするんだよね。
◆高口 医療の現場は、ファインプレーをきらうでしょう。いわゆるスタンドプレーとしてとられがちで、否定されやすい。 特養の場合は、そういうファインプレーをまわりがすごく喜ぶのね。「あたった!」「いけた!」とか(笑)。「なんだったのよ?」「腹すいてると思ったもん、わたし」。なんか盛り上がるのね、すごく。
【内に往き、外に往き…】
◆高ロ ライフワークというと大仰なのだけれど、いま介護を仕事とする現場にいて、お年寄りの笑顔がほしいと思えば自分も笑顔でいる、相手の信頼を得たいと思えば自分から信頼する、老人の主体性がほしいと思ったとき、勝負できるのは寮母たちの主体性しかないということを痛切に感じています。
主体性というと仰々しいけれど、こんなことをしてみたい、一緒に感じてみたいということが、私たちがやりたい仕事にとって大事だというとき、彼女たちの主体性を傷つけるものやつぶしてしまうものが、いまの私の敵みたいな気がするんです。
それは給与体系だったり、仕事の圧倒的な量だったり、体調不良だったり、人事待遇だったりするんですが、でも、それだけではないような気もするんです。……なにかわかります?
たとえば、夕焼けがきれいで「ばあちゃん、一緒に見にいこうや」という気持ちになる日と、ならない日がある。同じお年寄りを目の前にしていても、一緒に花見に行こうねと思う自分もあれば、「そこそこ仕事しておけばいいんだ」という自分もある。これは何なんでしょうね。それさえつかめれば、けっこうなところにいけそうな気がするんですけれど。

◆三好 与えられた仕事はそうなるじゃないですか。それが、「自分がやっている仕事なのだ」となっていくためには、いったい何が必要なのか、ということですね。逆にいうと、いくら給料が高かろうが、処遇がよかろうが、やっぱりそうなるでしょうね。
いま求められているのは、「外」からもちゃんと見られるし、「内」にも入り込めるという、両方往復できる能力なんです。それを1人の人間がもっていればいいのだけれど、たとえば生活指導員は「内」にもいるし、「外」にいるというおもしろい位置にいたんですよ。
いく人かの指導員はそうだった。それが、現場の狼雑さ、乱雑な言葉がもっているプラスの意味を全然知らないで、お説教をするような指導員ばかりになっちゃった。
【ケアプランは寮母の主体性次第】
◆高口 たとえばね、寮母が「わたし、もう老人にやさしくなれなくなっちゃった……」と、ぽつんと言ったときに私はどうしたらいいのか、という事なんです。どうして私が、彼女たちの主体性にこだわるかというと、シルバー日吉のケアプランは、彼女たちの老人へのまなざしや、「やってみたい」ということだけが頼りなんです。それがなくなったら、シルバー日吉のケアプランはありえないわけです。
◆三好 現場の直感でやるのが基本なんだけど、継続していくには何かコトバとか論理とかがいるんですよ。つまり「外」からの意味づけね。高口さんが、「外」からの役割をしなくてはいけなくなったとき、既成の理念からではなくて、個別のひとりの老人をとおしてどれだけ「外」を語れるかだろうね。
特別のひとりの老人に対して、一般論ではなく「こういう生活歴の人に対してはこうだ」ということが、「外」からどれだけ定義できるかということじゃないかな。
◆高口 私はこんな寮母長でいいんですかね、三好さん。
◆三好 どうなんでしょうね(笑)。 私は、すごい人物が介護の世界に入ってきたなという気がしてるんです。介護の独特の世界をちゃんと認めて語れる人をこちらにひきずりこんだな、という気がしています。直接的には、シルバー日吉の施設長補佐である森上さんがひきずりこんだのですが、その背後には熊本老人ケア研の経験があったり、ぼくらとのつきあいがあったりしたわけで、うれしいですね。
12月には、浜松で「新しい施設ケアセミナー」を、高口さんの講演をメインにしてやろうと計画しています。今日、話した高口さんの課題の答が聞けるかも知れませんね。楽しみにしています。
- 1997.4月 不思議なインフルエンザ報道
~マスコミはやっと「特養」を発見したらしい~ 私は、新しく出版する「関係障害論」を脱稿した。といっても、2日間の講座を録音したテープを起こしたものに手を入れていくので、最初から文章を書いたわけではない。
しかし、あいまいな記憶でしゃべっていることもあって、生活リハビリ講座・プログラムC<関係障害論>で取りあげる参考文献、「アヴェロンの野生児」や『狼に育てられた子』をはじめ、レヴィ=ストロースやM・フーコーの本まで目を通さなくてはならず、大変だけどおもしろい年末だった。
その知的な興奮のようなものがまだ残っている正月の3日間に、わが家のFAXに、新聞記事が次々と送られてきた。私が新聞をとってないことを知っている知人が、何か関連した記事があると送ってくれるのだが、正月からご苦労なことだ。
まず元日の朝日新聞の2面ぶち抜いての新連載で、熊本のシルバー日吉のケアの話が載つている。事前に聞いてはいたが、大新聞が元日から人が死ぬ話を載せるような時代になったということだけでも大変なことである。 涙が出てくるようなドラマチックな文章だが、岡山でのブリコラージュセミナーでの高口光子さんの語りとそっくりの表現が多くて、記者が彼女のしゃべりに圧倒されて記事を書いたのだろう、と苦笑したりもした。
毎日新聞には、これまた大きな連載の第1回目が中田光彦さんの紹介である。若い記者の老人ケア同行記はなかなか率直で、こちらもいい記事だ。 だが私は、こうした連載を、それぞれの新聞が最後にどうまとめていくのか気になった。
どうせジャーナリズムのいつものやり方どおり、制度・政策が悪い、専門家が足りないという結論にもっていいくために、現場の具体的な実践が材料にされるだけではないのか、という思いがあって、いくぶん皮肉な気持ちで連載を読んでいたのだが、両紙ともそうはならず、具体的なままで終わったのはまずまず。老人問題が、制度・政策といったレベルで語られるものではないことに、少しは気づいたのだろうか。
埼玉新聞も1面を使って三恵苑デイサービスの遊びリテーションの大紹介。一昔前なら正月の新聞には皇族の写真が出ていたものだが、指導員の小松さんの顔が登場しているんだから時代は変わりつつあるよ。うん。 一方で、新聞、テレビが「特養ホームでインフルエンザで○人死亡」なんて大々的に二ユースにしているのは、ありや~一体何だ?
ニュースショーで例によって評論家が、「特養には医者が充分でないから」なんてしゃべっているけれど、ピント外れもいいところである。 特養で死んでりや、老人病院ではもっと死んでいるはずだ。一般病院でも、老人の数が少ないから見えにくいだけで、比率からいえばもっと死亡者は出ているだろう。
だいたい、インフルエンザが流行しようがしまいが、毎冬老人は風邪をひいて肺炎、気管支炎に至り、最後には「心不全」と診断書に記載されて亡くなっているのである。なぜ今年だけ、それも特養ホームだけ、大ニュースとして取りあげるのだろうか? ヒトが死んではいけないとでも言いたいのか? もっと不思議なのは、毎日新聞が「消極的安楽死」などといって特養などでの終末ケアのあり方を、これまた大きく問題として取りあげている点である。
介護の不在によって経管栄養とされ、チューブを抜くからといっ手足を縛られて死に至らしめられている従来の方法に対して疑問を感じて、最後まで口から食べてもらい、手足を縛ったりしないで生を全うしてもらおうという実践は、これまた在宅でも特養でも、さらには病院でもいくらでも行われてきたはずだ。
それを今年に入って突然、問題だとして一面トップに取りあげる意図は一体何なのだろうか。 自分が知らない世界のことについて書かれた記事を、私たちは事実だとしてと受け入れて読んできた。だが一度でも自分の知っている世界について、新聞やテレビが取りあげると、それがいかに実情を知らないピント外れな報道になっているかに気づいて、愕然としてしまう。
つまり、これまでに読んできた記事だって、当事者にしてみればみんなピント外れだったに違いないのだ。 新聞やテレビは、昨年末からの厚生省の不祥事でやっと「特別養護老人ホーム」を発見したらしい。特養ホームや老人介護に目を向けるのはいいが、“インフルエンザ”や“消極的安楽死”報道は、私たちの側から見れば、マスコミは何も知ってはいないし、そのあげく老いや特養ホームへの人々の偏見を煽るだけでしかないことがよく分かるではないか。
私か新聞をとらない理由も、介護現場の自前の表現媒体としてのブリコラージュの発刊にこだわる理由もここにある。 マスコミがわずかながら変わりつつあるという表層と、本質的にはそんなものに頼っていては私たちが愚かになるだけだという深層の2つを同時に見せてくれた新年であった。
- 1997.3月 僕らは人間をリアルに見ているだろうか
~『関係障害論』を書いたわけ~ 『関係障害論』は、老人が縛られないため、私たち老人にかかわる者が老人を縛らないための、関係についての試論である。 なぜ私が、老人を縛らない、という目的のために、人権意識の啓蒙という手段に向かわなかったのかという理由を記しておきたいと思う。
これまでの医療の、身体をメスと化学物質の対象としか見ないという人間観に対しては、さまざまな批判がなされてきた。たとえば、医療に対して批判的であることの多い福祉の側や、医療内部の良心的な人たちは、「人権」を声高に訴えている。
だが私は、こうした「人権」という崇高な理念を声高に叫ぶことでは、現実はちっともよくならないと感じている。 まず、医療関係者の人権意識が低いから老人を縛っているわけではない。むしろ、「人権」という理念は、老人を抑制するという行為を擁護さえしてきた。
『ベッドから落ちて骨折したらこの人の人権はどうなるんですか』『栄養が足りなくて死に至ることこそ人権を軽んじてることになるんじゃないですか』etc。 こうした、身体とか生命という目の前の現実性の前に、理念としての「人権」は有効に反論などできないのである。
『お年寄りを呼ぶときは○○さん、と固有名詞で。“おばあさん”なんてとんでもない』とか『敬語を使え』と、うるさく指導する施設長や指導員がいる。もちろん私は、人を呼ぶときには、苗字に、“さん”をつけるのがふつうだから、それでいいと思っている。
しかし、それでは返事をしない老人がいるのだ。 山本スエさんは、「山本さん」と呼べば、「なんかいの」と答えていた。しかし、そのうち「山本さん」では反応しなくなった。その代わり「伊藤さん」と呼ぶと「なんかいの」と言うのだ。旧姓に戻ったのである。 さらに数年たつと、旧姓でも返事をしなくなり、小さい時から年をとるまでずっと村で呼ばれていた「スエさん」という呼びかけにのみ答えるようになった。
なら「スエさん」でいいではないか。ところがそれでも「山本さん」と呼べというのである。「スエさん」なんて呼ぶのは人権意識が低いのだそうだ。『ボランティアや家族が聞いたらどう思われるか』とまで言う。 ふーん、人権意識が高いわりには、世間体ばかり気にするんだな、と皮肉のひとつも言いたくなるではないか。 もちろん「スエさん」でいいのだ。
自分を孫だと思ってる人には「ばあちゃん」と呼びかけていい。周りが誤解したら、ちゃんと説明すればいい。周りの人の目を気にするより、老人の表情をこそ見なければならないのだ。 彼らの「人権」とは、どこかの抽象的人権でしかない。目の前の爺さんや婆さんの人権じゃないのだ。
自分が呼ばれたことさえわからぬ呼称で呼ばれる山本スエさんの人権はどうなるのか。彼らが大事にしたいのは、目の前の具体的な老人の人権ではなく、彼ら自身の理念でしかないのは明白である。 こんな抽象的できれいごとの「人権」が臨床という具体性をもった医療の世界を批判できるはずがないではないか。
そうした福祉の世界に比べれば、なにより具体的でリアルに思える医療の世界もまた、人間を抽象的にしか見ていない、と私は思う。 なぜなら、人は、医療がリアルだと思っている個体の疾病によって生きたり死んだりもするが、そうした病気という特殊な時期を別にすれば、人は関係のなかで、関係によって、生きたり死んだりするのである。
したがって、関係から切り離してとらえられた身体は、じつはちっともリアルではなく、抽象的にならざるを得ないのだ。たとえ「全人的医療」なんて言ってみても、である。 つまり、ヒトを、関係から切り離した個体の論理で見ているという点では、医療も、人権を訴える側も変わらないのである。
人権という概念も、医療の人間観も、共に近代個人主義という、抽象的人間観を前提としているのだ。「人権」を訴えることの無力さの根拠はここにある。 この本が、私たちと老人を、こうした抽象的存在から、そこで私たちがイキイキし、そこで私たちが崩壊するに至ることさえある関係的で、だからこそほんとうに現実的で具体的な存在を取り戻すために役立つことを願っている。『関係障害論』は、3月に雲母書房より刊行されます。この文章はそのあとがきとして収録されるものです。
- 1997.1-2月 あえて死こついて語らないわけ
前号の「地下水脈」で、夜と昼について語った。夜、つまり睡眠を、昼間の活動と切り離して論ずると、方法論は“小手先”になっていく、と。 50号の特集号で、湖山病院の大和田医師から、批判というか注文があった。前号から続くこの文章は、それに対する返答のつもりでもある。
大和田先生は、その経歴も異色ながら、医者というより思想家といったタイプの方で、そこで「幸福とは何か」なんて表現が出てきたりするのだろう。私は、人生を「生きもの」なんてところまで還元してしまうタイプである。つまり「生きているだけでいい」という風に。
だから「幸福」とか「人生の意味」なんて、アクセサリーくらいにしか思えないところかあるのだが、そこは、寝たきりや呆けにかかわってきた私と、若いアル中の愚者さんたちに興味をおもちの大和田先生との、いわば対象領域の違いであろう。
さて、氏は「死の受容を見つめる目が伴っていないように思える」と書かれた。そして「そのため人間の個別性と共通性への理解か浅くなっている」とも。私は、あえてそこには踏み込まないつもりでいる。つまり、「夜」を「昼」との関係で捉えたように、「死」も「生」との関係で捉えるべきだと考えているからだ。
夜の熟睡が昼間の活動的生活によって作られるように、死もまた、生によって決められていくように私には想われる。もっとも私の知っている死は高齢者の死で、若くして死と直面した人とのかかわりの経験はないから、老人の場合に限定してということになるけれど。
死についての個別性と共通性といえば、キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』を思い浮かべるだろう。彼女は死への遇程を(①否認、②怒り、③取り引き、④抑うつ、⑤受容の5つに段階づけて見せ、大きな反響を呼んだ。 しかし、リハビリ関係者にとっては、この過程は決して目新しいものではなかった。
というのも、障害受容過程の研究で、ほほ同じような段階がすでに語られていたからである。それは、①ショック期、②否認期、③混乱期、④受容期の4段階〔論者によっては5段階〕で、ロスの②③④の3つの段階が、混乱期として1つにまとめられ、代わりに、生物的防衛というべき、現実感を喪失したショック期が付け加わるというものである。
この障害受容過程論については、私はかつて批判的に論じたことがある。(『教師はなぜ呆けるのか』参照)それは、障害受容が「価値観の転換」といった風な、倫理主義として捉えられていることへの違和感であった。
じつはロスの説に対しても似たような違和感をもったのたが、それ以上に思ったのは、この、死に至る心理的、現実的遇程は、実は私たちが、自分の生に対する心理的、現実的過程と同じではないか、ということである。
思春期から青年期にかけて、私たちは、現実の自分と向き合った時、ときに否認し、怒り、取引し、抑鬱におちいる。 現実の自分は、金持ちの子息でもないし天才でもないし異性にとって魅力的でもない。だか結局はそんな自分を受容していった。いやほんとうに受容できている?
こうした、青年期を過ぎても、どこか心の内で再生産し続ける“受容過程”の、最後の緩り返しが、ロスの言う「死の受容過程」なのではあるまいか。 だとすると、死に向き合ったときうまく受容に至れるとするなら、その条件は、これまでの生き方、特に思春期以降の、自分という現実との付き合い方にかかっているのだということになる。
ならば、介護にかかわる私たちの仕事は、老いと障害をもった自分とつき合うという困難な課題に立ち向かっている老人の生をつくり出すことではないか。そのことこそ、老人の死をつくり出していることになるだろう。
昼と夜の場合と同じように、死についての知識や技術も“小手先”だと言ってしまうには、あまりにも死は重い。だが、誤解を恐れずそう言ってもいいくらい、介護は老人の生そのものに入り込んでいると思いたい。
尊厳死なんてことばがよく語られている。だか私は、尊厳死と言うくらいなら、尊厳生を作り出す“いま、こご”の具体的仕事をやろうよと、どうしても言いたくなってしまうのだ。
- 1997.1-2月 介護計画賛成、MDS反対
私は、現在、厚生省や行政や専門家の一部の人たちが、強引に押し進めている、いわゆる「ケアプラン」に対して、以下の3点について批判したいと思っている。
①動機が不純である。
私は、ケアプランそのものには反対ではない。ケアプラン、つまり介護計画を立てるなんてことは、むしろ当たり前のことである。いま、「ケアプラン」と騒ぎ立てている人たちは、これまで、一人ひとりの老人の介護方針さえ検討しないで仕事をしてきたのだろうか。
そもそも私たちが、他の職種と集まってケアプランを練るのは、ひとりの老人の運命が気になるからである。私たちのかかわり方ひとつで寝たきりのままの人生を送るのか、それとも、もう一度その人らしさを取り戻すのかが決まったりするのだから、とても無関心ではいられない。だからみんなで相談し、役割を分担し、よい結果が出れば喜び合い、うまくいかなければ、もう一度考え直すのである。
なのに、いまの「ケアプラン」はどうか。金になるからやる、とか、県からの指導がうるさいからやるのだそうだ。そんな動機ではじめても、決して老人のためにはならない。それより、スタッフのなかからひとりでもいいから、老人の運命に関心をもつ人を作り出すことからはじめてはどうか。
②MDSでなければならぬ根拠がない
従って、ちゃんとした介護現場なら、必然的、かつ自発的に、自分たちのケアプランのやり方を作ってきたはずである。私のいた特養ホームでは、処遇会議と呼ばれており、月に一度、2~3人のケースが話し合われて、記録用紙にそれが書かれ、全職員に回覧されていた。
記録形式は、いくつかの項目に分けて散文で記述されるもので、いくつかの形式を試してみて、もっともシンプルなものに落ち着いた。というのも、いくら詳細な項目に分けてみても、一人ひとりのケースは実に個別的で、結局、散文で自由に表現するほかなくなってしまうのである。
だから私は、ケアプランの方式は、現場の数だけあっていいと考えている。厚生省さえも、MDS(Minimum Data Set)は、ケアプランの一例にすぎない、と言っているにもかかわらず、「MDSでなければダメ」なんて言ってる行政関係者がいる。これはちょうど、「介護用ベッドはフランスベッドでなきやダメ」と、行政が言っているようなものである。
どのベッドを使うかは現場が決めることだ。行政はいくつかのケアプランの方式を、例として示すまではやってもいいが、そのうちのひとつを現場に押しつけるなんてことはすべきではない。北海道庁の担当者、あなたのことですよ。
たとえば、日本医科大学の竹内孝仁先生の「ケアマネージメント」(医歯薬出版)で示されたやり方ではどうしていけないのか。また、私が生活リハビリ講座で提案してきた、生活の場のADL評価表を使った介護計画ではなぜダメなのか。
はたまた、特養ホーム、シルバー日吉の高口寮母長が各地で発表して歩いている「○○さんと温泉に行って一杯やりたい」という願いをケアプランにしていくという「目標指向型システム」ではなぜいけないのか、MDSを強要する人たちは説明する必要があろう。返答をお待ちしている。
③MDSはケアのプランにはならない
さらにそのMDSそのものも、ケアプランの一例として挙げるのにさえ問題のある代物である。細かく分類された項目を一見しただけでわかるとおり、こうした方法の規準になっているのは、問題点指向システム(POS)でしかない。
POSは、急性期にこそ有効だが、生活期へのアプローチに関しては。むしろ弊害の方が多いことはよく知られている事実である。問題点は知っておいたうえで、老人のもっている良い点にこそアプローチしなければならないのだ。それこそ、介護が、看護、それも安静看護の真似から脱却して、独自の領域を作ってきた最大のポイントなのである。
見てみるがいい。MDSを強要しようとしている人たちが、病院の医療や看護はやったことがあっても、生活の場での生活期のケアの経験などろくにもってはいないことを。彼らは、意識的にか無意識的にか知らないが、介護の世界が自立していくことに対して苛立ち、介護をもう一度、医療的世界に引きとめようとしているかのようである。
だが必要なのは逆のことだ。医療や看護を介護のなかに、つまり生活のなかに位置づけ直すことなのである。 現場で県の役人や金ほしさの事務長からMDSを強要されている皆さん。心配はいらない。MDSなんてすぐにすたれる。そのとき、誰が、上の指示に権威主義的に従って、「MDS」と叫んでいたか。ちゃんと覚えておこう。そういう人たちこそ、現場に何より必要な自発生と創造性の敵なのだから。